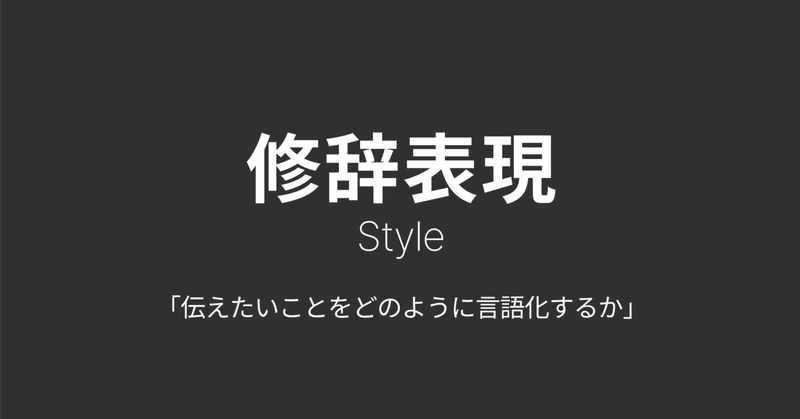
レトリック・カノン③:修辞表現-前編-
レトリック・カノンの第3段階は、話し手が伝えたいことを、どんな言葉で言語化するか決定する工程だ。この工程は、話し手が一番自由にかつ思いのままに考えることができ、自由である反面、その表現次第でプラスにもマイナスにも働く諸刃の要素を含んでいる。

前編では、古代の偉人が、この修辞表現についてどのように考えていたかを述べつつ、修辞技法の1パターンを例にとり今後のまとめ方を考察する。
言葉にとって大切なことは何か?
修辞技法の前に、この言葉について考えてみたい。
日常会話の中で、言葉巧みにユニークな表現をする人もいれば、CMなどで耳に残るキャッチな言葉が流れることもある。
どうやら人の胸を刺す良い言葉と、そうでない言葉があるのはなんとなくわかる。上にも書いたが、話し手を引き立たせ、武器となる言葉の条件にはどんなものがあるのか。
そのためには、この言葉にとって大切なことは何かを知る必要がある。
クインティリアヌスの主張はこうだ。
巧みな文飾・修辞を重ねても、そもそも自分が伝えたいことを正しく言語化できていない限り意味をなさない。言葉には明晰さが備わっていなければならない。
著書、弁論家の教育の中で、明晰について語られているポイントを1枚にまとめると、次のような図式になる。

措辞(=そじと読む)という言葉は、僕が40年以上生きてきて初めて目にした言葉だが、言葉づかいや言いまわしのこと。明晰さとは言葉がもつ最も基本的な特性であり、次の3つの要素いずれかが欠けても良い言葉にはならない。
話し手として主張があるとき、
その主張のためにどんな言葉を選ぶか?
その主張を通すための明瞭かつ適切な構成をとっているか?
必要以上に冗長な表現になっていないか?
繰り返しになるが、修辞前の言葉を選定するときに、以上のポイントに従って何度もチェックすることが必要不可欠だ。
保有した語彙数によっても話が変わる
修辞の前の明晰な言葉選び。
自分の主張を包含した完全な言葉というものを、どうやって選び出すか。
これはもはや、その人が保有した語彙数によってだいぶ違いが生まれると感じている。例えば、言葉の獲得途上にある子供が、自分の主張を訴えるために、限られた語彙の中から言葉を選んで話をしてくることもある。それはとても愛らしい。
一方、僕が古典レトリックとしてまとめている内容は、この技術を使ってビジネスや交渉を意図する方向に導くためのノウハウとして書いている。
子どものままの幼稚な表現がいつまでも許されるわけもなく、受け手にも理解される適度な抽象度で言葉を選ぶ必要がある。
語彙数の話を書いていて、ふと三島由紀夫のことを思い出した。
彼は創作活動の中で、辞書を引くではなく、辞書を読む(=そして覚える)ということを繰り返していたらしい。小説こそ、書き手の主張を持って人の心を動かす集大成なわけで、言葉選びの最たる例だ。
また、古代中国の科挙という試験。
科挙では論語、易経、左伝などの歴史書を丸暗記して試験に望む。
その文字数40万字以上というから驚きを隠せない。
漢字は1字1字に意味がある文字であり、説客として言葉を知っていることは当たり前だったのかもしれない。
言葉を知る者と知らない者とでは、選定される言葉に違いが出るのは明らかだ。
僕もそうだが、気がつけばスマホ片手にだらだらした移動時間を過ごすことが多い。読書をする機会は減る一方だ。自分の語彙数を高める努力を怠ってはならない。
修辞技法(比喩)

以上のことからも、元の語彙数の違いから明晰さの違いは生まれてしまうかもしれない。それでも言葉選びが終わったと仮定して、次はいよいよ修辞表現だ。
修辞技法を調べようといくつか書籍を読んでみたが、どれも共通していえることは、文字の説明が長く、瞬間的に概要を掴むことができないということ。
極力文字を使わない方法で、1つの技法を1枚の絵にできないものかと思い、ノートに書き溜めたものの作図を試みた。
今回紹介するものは「比喩」だが、これについては次の言葉が真をついている気がする。
語ないし表現に関しての、本来の意味から別の意味への卓越した変換
直喩
ある事柄Aを、〜のようなという言葉を使い、別の事柄Bに変えて表現する。
両者の類似点を想起させ、受け手を刺激する技法。

隠喩
ある事柄Aを、別の事柄Bで説明する。
受け手が両者を比較した時、その類似点を暗に示すことで強調させる。

提喩
上位概念Aの部分を使って、下位概念Bの全体を表現する。
説明に工程を経ることで、アイデアやイメージの共有を強化する。

換喩
ある事柄Aと近接する別の事柄Bがある。両者の関連度合い、近似の強さを使って、受け手に奥に潜む意味を示唆し、感情的な反応をもたらす。

それぞれの技法には、上のイメージで描いたような関係図が成り立つ。後編では、同様の形で他の技法についてまとめていく。※修辞表現の具体的な文章、サンプルは、検索するとたくさんでてくるので割愛する。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
