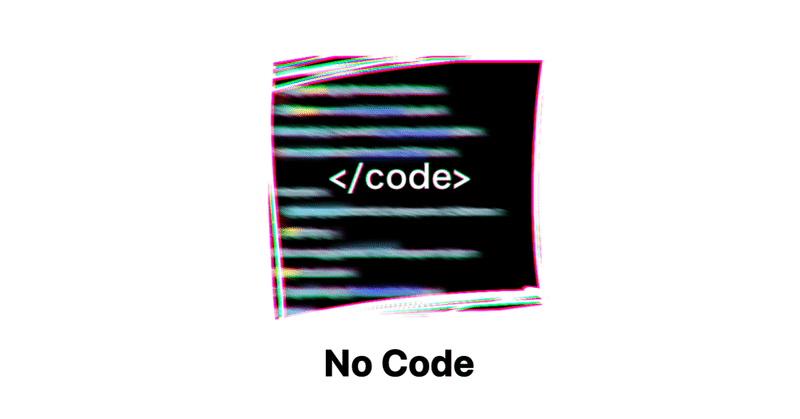
失敗を学びに繋げるMVP失敗事例【NoCode Summitイベントレポ】
NoCode Summit 2021 A/Wが、2021年12月3日に開催されました。当イベントは、国内最大規模のノーコードコミュニティを運営する一般社団法人ノーコーダーズ・ジャパン協会と、一般社団法人スタートアップスタジオ協会の共催イベントです。
今回は、大盛況に終えた当イベントの様子を一部お届けします。
■「失敗を学びに繋げるMVP失敗事例‐スタートアップスタジオ協会理事パネルディスカッション‐」
スタートアップスタジオそれぞれ育成手段/支援手法が異なる中で、どのようにノーコードを使って検証しているのかをテーマに行われたセッションです。
・モデレーター:永野 祐輔 氏(Creww株式会社 スタートアップスタジオ責任者)
・パネリスト:佐々木 喜徳 氏(株式会社ガイアックス スタートアップスタジオ責任者)
:坂東 龍 氏 (株式会社デライト・ベンチャーズ プリンシパル)
:及部 智仁 氏 (株式会社quantum 代表取締役副社長)
Q.1 新規事業立ち上げにおいてNoCodeツール利用の目的や理由は?
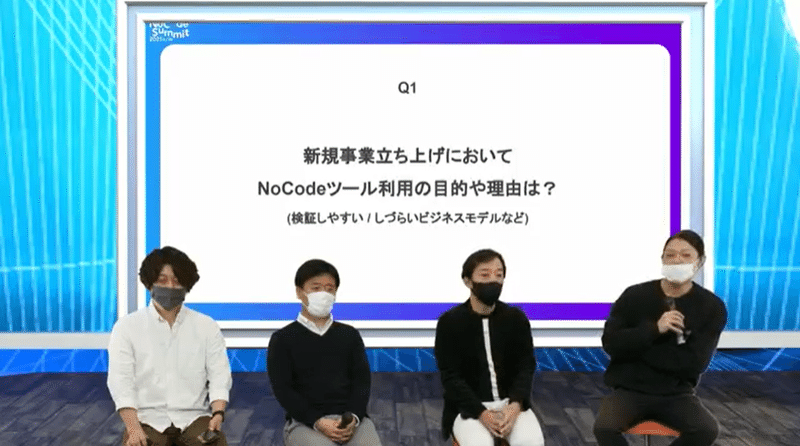
「ビジネスモデルの価値提供を見定める」
永野氏:新規事業立ち上げにおいて、ノーコードツールのメリットはなんでしょうか?
佐々木氏:自分の場合、コロナになってオンライン飲み会のビジネスをつくるのにノーコードツールを使ったのが最初でした。3~4日でMVP作って検証できたのはメリットだったと思います。ただ、リボン型でマッチングさせるところまでは簡単なんですけど、さらにテクノロジーを使うようなMVP作ろうと思うとめちゃくちゃ難しいんですよ。
永野氏:「テクノロジー使う」とは、例えばどんなものがあるんですか?
佐々木氏:Zoomのように、お互いに画面を共有して音声繋げてアクティビティするといったものですね。それが(オンアイン飲み会サービスの検証では)提供できなかったのが負けポイントだと思います。
坂東氏:自分の場合、ノーコードツールを利用する目的は早く検証ができるというところ。マーケティングのランディングページを作るのに重宝しています。
マーケティングテストなので、toCやスモールビジネスのtoBだと検証しやすいですが、エンタープライズの場合は検証しづらいので、パワポに落として営業していくのが適していると思います。
永野氏:LPを短縮できた後に、どのような形でノーコードを事業検証に使っていますか?
坂東氏:このビジネスモデルやサービス案が、価値提供できるかどうかを確かめます。サービスのニーズを確かめる最初の手段としては非常に有益なツールだと思います。
それから、それだけじゃなくてサービス案を磨くのにも使用しています。ユーザーを集める為に一回ランディングページを出し、事前登録のような形でユーザーを集めてディープヒアリングする等ですね。
佐々木氏:仮説検証するときは「いかにお金を払って使ってもらえるか」の検証が一番重要なので、そのためにカジュアルにEC系のサービスを使う事は多いです。
及部氏:自分の場合は、用途としては、PoCとPoBに特化しています。本開発に使用することは今のところはないです。
プロトタイプの開発に関しても、大手企業との共同事業の場合など、基本的にセキュリティが厳しいので、ノーコードは使用していません。ハードウェアと絡むにしても、いろんな失敗を繰り返して、暗中模索の中で使っているのが実情です。
永野氏:Crewwでは、まずチャレンジの敷居を下げるということをやっています。ノーコードツールを使って、出来ない理由をなるべく減らし、(サービス案やビジネスモデルに)手触り感がなければやめるということをしていますね。
Q.2 NoCodeツールの活用によって早期に撤退判断をすることができた事例は?
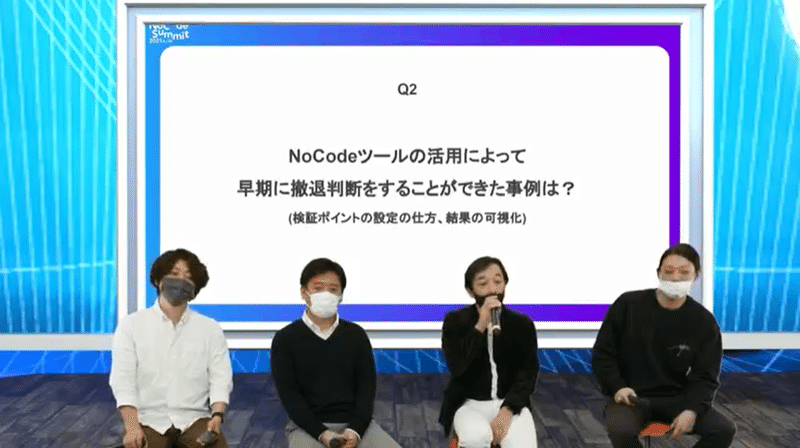
「MSPで顧客の本音を聞き出して、即時判断ができる」
永野氏:ノーコードでは、検証ポイントをどう設定されていますか?
及部氏:もともと、MVPで(ユーザーが)お金を払わなくて検証するのと、実際にMSPにして検証することには温度感の差があります。MVPでは評価が高くても、MSPにした瞬間にユーザーにボロカスに言われることは多いです。
その点、NoCodeはいきなりMSPが出来ます。なので、ノーコードの場合、初期にユーザーからかなり辛辣なコメントを頂いて、撤退を早めに防止したり、ピボットしたりできるケースは多いです。例えば、QAL startupsという動物医療のベンチャーがあるんですが、これはかなりニッチな分野なのでどこにあたりそうかをNoCodeを使ってMSPしながらやっていて、加速しました。
<用語説明>
MVP:Minimum Viable Productの略称で、ユーザーに必要最小限の価値を提供できるプロダクトのこと。
MSP:Minimum Sellable Productの略称で、必要最低限の価値で売れるプロダクトのこと。
坂東氏:2年前からNoCodeを使うようになったんですが、そのきっかけが、ある起業家候補がギグワーカー向けのtoCスモールBのようなサービスの事業案を考えて、一日足らずでランディングページを作ったことだったんですね。
その時はデジマ(デジタル・マーケティング)をかけたんですが、思ったより人が来ず、当時の事業リーダーが早期に「やめます」といってやめる判断をしました(笑)。すぐに諦めるというよりは、ピボットできる、早期判断ができるのがいいところだと思っています。
佐々木氏:ちょっと変わった事例ですが、中高生に起業ゼミをしている中で、優秀な2~3人くらいをピックアップしてMVP検証をするんです。その中で、ノーコードを使うと起業家(候補)自身のポテンシャルを見極められるんですね。MVPを作った後、起業家がどう動くのかを見るのにも最適だと思います。
Q.3 NoCodeツール活用時に特に注意している点は?
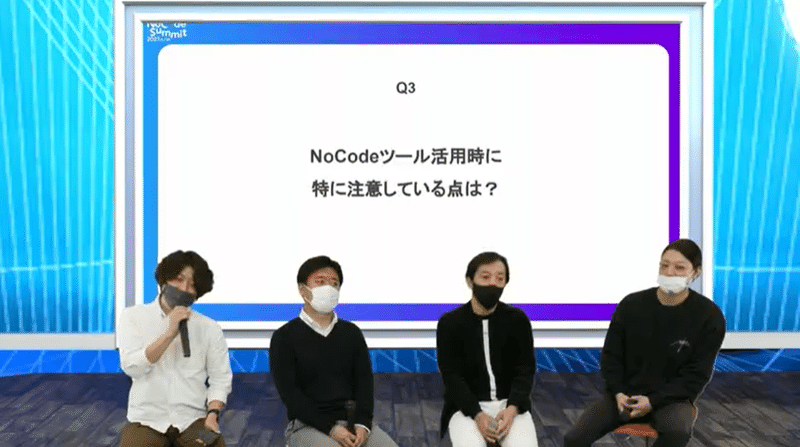
永野氏:最後の質問ですが、ノーコードツールを使う時に注意している点はなんでしょうか?
佐々木氏:恥ずかしい話、それなりの数のノーコード検証をしているので、この前セキュリティインシデントを発生させてしまって...。
ノーコードは、プラットフォーム側がセキュリティ対策をしているので、初心者がセキュリティに弱い状態のサービスをローンチできるんですね。なので今は、セキュリティ面のガイドライン作りに取り組んでいます。
永野氏:セキュリティは、スピードと反比例しますからね。
坂東氏:ノーコードは早期判断ができるんですが、判断を拙速にしすぎるのも良くないと思っています。最初の判断が悪くても、繰り返し検証してチューニングしていくうちに10倍くらいの効果がでるということは実際にあります。
及部氏:そうですね、自分の場合は注意点は二点あって、一点目は開発期間や費用が下がる一方で、検証の運用コストがあがる所が気になっています。
それから、二点目はやはりセキュリティですね。我々はリーンスタートアップをマーケットのユーザーと大企業の組織内向けにやっています。その中では、セキュリティチェックも同時にしながらNoCodeツールを活用しています。
***
いかがでしたでしょうか?NoCodeツールによって、事業検証のスピードが上がったりしたことのメリットや、スタートアップスタジオでは実際にどのように活用しているのか等、事例を踏まえた興味深いお話がきけたのではないでしょうか。
開発者でなくとも簡単にプロダクト検証ができるようになった反面、後半ではセキュリティ面に関する注意点も指摘されましたね。
これから、日本のスタートアップ業界が盛り上がり、NoCodeツールも益々活用されていく中で、適切な活用方法を起業家自身が模索する必要性があるようです。
トークセッションの最後にはスタートアップスタジオ協会から紹介がありました。
起業に興味がある!自分で事業を創りたい!など、起業家精神のあふれる方、
詳しくは、是非こちらからご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
