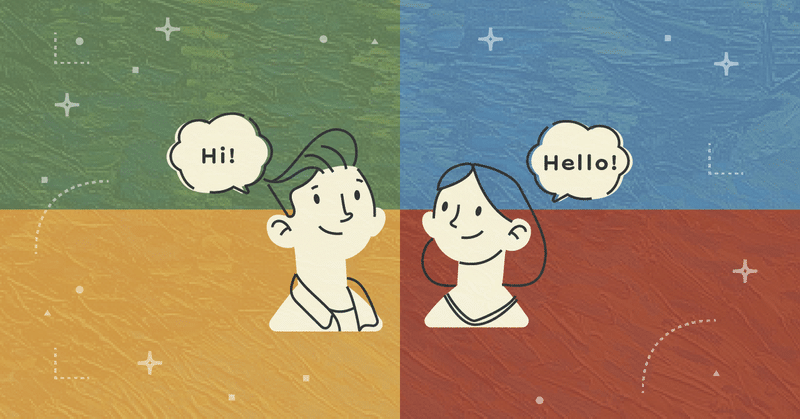
吃音と共に過ごした20年
はじめに
先日、ある動画を見ました。
その動画とは、吃音(きつおん)症の方が、注文に時間のかかるカフェ、というお店で接客をするという内容のものです。
吃音症って、皆さんご存じでしょうか。
ご存じの方は、
「言葉がでにくい人のこと?」
「何を言っているのか聞き取りにくい。」
そんな印象を受ける方が多いと思います。
実は私も、吃音症の1人です。
吃音症では、滑らかに言葉を話せない、言葉につまってしまうような症状がみられます。
完全な治療法は確立されておらず、早くて幼少期や小学生くらいの年齢で発症するタイプと、10代後半、大人になってから発症するタイプがあります。
原因もハッキリとは分かっておらず、症状が出やすい場面として、緊張する場面や、咄嗟の対応の際に言葉が出にくくなる方が多いようです。
この、言葉につまったり、言葉がスラスラ出ないという症状により、私の様に、小さな頃から悩みを抱える方も多いのではないかと思います。
そして、昔に比べ認知度は上がってきたとはいえ、まだまだ吃音症についての理解は十分では無いとも感じます。
多くの方に吃音症について知って欲しいと思い、今回記事にしました。
最後まで読んでいただけると嬉しいです!
言葉が上手く出ない…どうして?
言いたい言葉がタイミングよく出ない、何で、自分だけ…。
想像してみてください。
おはよー!と言いたいのに、お、が言えない。
友達は、何にも言わない私を不思議そうに見ている。
やっと言えたけど、お、お、おおはよー!と綺麗に言えない。
その様子を見ていた人に笑われる。
こんな事が、もしかしたら毎日、しかも、どんな場面で出てくるか、予想がつかない。
恥ずかしくて、悔しくて、顔が真っ赤になる。
これは私が過去に体験した出来事を例えていますが、私1人だけではないはずです。
吃音症は、こんな症状が、早ければ幼少期、小学生から出現し、大人になった今でも、その症状に悩んでいる人が多いです。
周りの同級生との違いに気づいたのは、小学校高学年の時でした。
今から20年も前の事です。国語の授業での音読や、定期的にある音読発表会(田舎だったので全校生徒の前でそういった催しがありました)で、頭では分かっているのに、言いたい言葉が出ないんです。
運よく言葉が出たとしても、例えば、「かかし」と言いたいのに、
「か、か、か、かかかかかかし」
のように、音が連続したり、スピードを調整出来なかったり…。
それで周りから笑われるのが苦痛でしたが、一番苦痛だった事は、教師の理解が無い事でした。
当時、吃音症という言葉も、おそらく知られていなかったのでしょう。
教師が「かかしよ、かかし」と言った直後には「かかし」と言えるのですが、本番になると、また言葉が出ず、沈黙が続き、さらに緊張して言葉が出なくなる…その悪循環でした。
その時の私は、友人から笑われる事より、教師に注意されるのが嫌で、家に帰っても1人で音読の練習をしていました。
でも、本番になるといつもの通り。
今考えると、本当に苦しかったなあと思います。
自分を守ろうと工夫を重ねた
言葉が出ない、出ても上手く話せない自分が嫌で、自分なりに言葉が出しやすくなるように工夫を重ねました。
主にその工夫は2つあり、
(1) えーっと、まあね~と言ってから話す(そうすると言葉が出やすくなりました)
(2) 言葉を言い換える(例えば、面白い!と言いたいけど、お、が言いにくいとします。その場合、同じような意味で、めっちゃうける!と言う。このような方法です)
私の場合は、タ行、ア行、ナ行から始まる言葉が言いづらく、症状がピークだった小学生の頃に比べると次第に落ち着きはしましたが、30歳になった今でも、時々言葉が出づらい場面はあります。
それは、仕事中も、プライベートでも同じです。
吃音症で辛かった事
頭では言いたい事はいっぱいあるのに、タイミングよく言葉に出せない。
私の場合、人から笑われた、という経験は少なく(教師よりも同級生の方が理解があったのかもしれません💦)、そのような症状が最も辛かったのは、友人同士で話す時でした。
数人のグループで話すと、誰かが面白い事を言って、その場がワッと盛り上がることってありますよね。
20代前後だと、特にそうだと思います。
ですが、そんな時、「ああ、これ言ったら面白いだろうに、また言えなかったなあ…。」と感じる事が多くあり、後悔は強くあります。
そして、今でも辛い事が…電話対応です。
電話って、相手の顔が見えないので、表情を読みながら言いたい事を考えられません。
なので、顔を見て話すより、多くの事を考えながら言葉を発しないといけないんです。
それが自分にとっては負担で、時々、
「ああ、また出ない…。」
となる事があります。
ただ、職場では、今まで何回も電話で話した事のある人とは、緊張も少なく、スムースに言葉が出る事が多いです。
無理の無い範囲で、電話の相手とも、普段からコミュニケーションをとっておく事も、良いのかもしれません。
吃音症で良かった事
逆に、吃音症で良かった事って何があるでしょうか?
吃音症の方は、幼少期から症状に悩まされ、コミュニケーションに苦手意識を感じている方も多いと思います。
私の場合は、自分自身が話すのに時間がかかったり工夫する事の大変さを、身をもって知っています。
その分、仕事で対象者(脳卒中の後遺症などで、原因や症状は異なりますが、言葉が上手く出せない方など)と関わる時、相手の話を待つことは苦になりません。
また、友人や、職場の同僚からも、相談を持ち掛けられたり、色々な愚痴を聞かされる事も多い方だと自負しています(笑)
相手の話を待つという姿勢が、自然と相手にも伝わり、話しかけられやすいのかな?とも思います。
気にかけて欲しいこと
吃音症の当事者として、言葉につまっている時や、連続して言葉が出てしまうような場合、周りの方にお願いしたい事があります。
それは、
「焦らないで。」
「もっとゆっくりで良いよ。」
「それはこういう事だよね?」
という声かけは、なるべく控えて欲しい、という事です。
誰も、急いで喋ろうとしたり、ゆっくり話したいわけではありません。
自分の言葉で話したい、けど、言葉が出ない、出てもスピードの調整が出来ないから困っているんです。
どちらかというと、頷いて話を聞いてくれたり、急かさず聞いてもらえると、話しやすくなります。
まとめ
吃音症の治療法は確立されておらず、幼少期だけではなく、学生時代、成人してからも、悩んでいる方が多いのが現状です。
仕事や普段付き合いのある人との関係を通して、今でこそ、吃音症で良かった点を見つけられましたが、一番悩んでいた小学生の時は、とてもじゃないですがそうは思えませんでした。
この記事をきっかけに、吃音症に興味を持つ方が増え、理解が深まると嬉しい限りです。
そして、同じ吃音症の方の苦しみを少しでも減らすことに繋がると良いな、と思います。
今日は吃音症についての記事を書いてみました。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!(^^)!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
