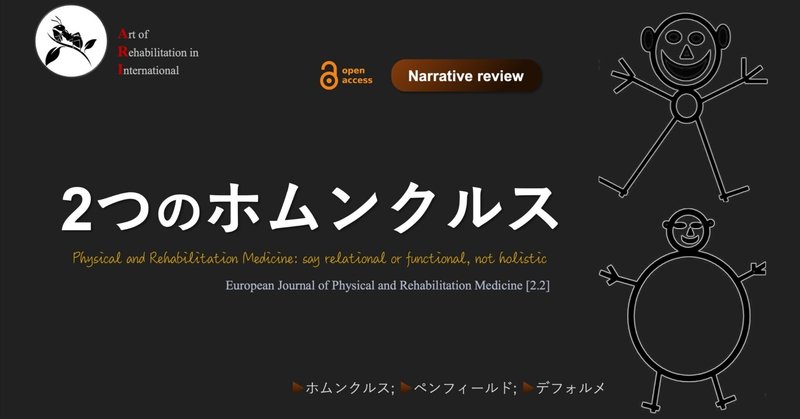
2つのホムンクルス
📖 文献情報 と 抄録和訳
理学・リハビリテーション医学:全人的ではなく、関係的または機能的と言う
📕Tesio, Luigi, Stefano Scarano, and Antonio Caronni. "Physical and Rehabilitation Medicine: say relational or functional, not holistic." European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine (2024). https://doi.org/10.23736/s1973-9087.24.08309-6
🔗 DOI, Google Scholar 🌲MORE⤴ >>> Not applicable
■ 2つのホムンクルス

<身体-外医学のホムンクルス>
・体性筋と皮膚感覚野の皮質表現を反映した形
・人と世界の関係の中核をなすハードウェア
・巨大な手、足、口、舌を持つこのホムンクルスは、リハビリテーション医学の観点と一致している

<内科医学のホムンクルス>
・主に恒常性の役割を果たす器官(例えば、腹部と胸部)で構成され、個々の身体と環境との間の代謝バランスを保証する
・内科医学は, 身体各部位の病気に明確に焦点を当てている
・巨大な体幹、小さな手足、小さな頭部で表現される

[レビュー概要] 現代医学は、身体の一部(分子から臓器まで)を支配する「客観的」法則を約束する学問を優遇する傾向がある。人の病気や障害に関する研究は、(明らかに)"主観 "に限定されている。理学・リハビリテーション医学の専門は、人道的アプローチとみなされることが多く、せいぜい「ソフト」「質的」「準実験的」科学の系列に属する程度である。この専門は、しばしば自らを "機能的 "かつ "全体論的 "と標榜することによって、特異性を主張する。しかしここでは、前者の用語は許容できるが冗長であり、後者の用語は誤解を招くものであることを示す。人間の行動や知覚が問題となる場合、「機能」は人と外界との関係を示す(ギリシャ語の「physis」に由来する「physical」という定義用語ですでに扱われている)。「ホリスティック」という言葉は、心と体の一体性と人と環境の相互依存性を強調するものだが、現在の用法では、あらゆる機能に対する分析的、実験的アプローチの補足的必要性が影を潜めている。医学は、一人の人間の病気や障害と闘うことを目的としている。この努力には、身体の部位とメカニズムを知り、"部分 "への介入が "全体 "にどのような影響を及ぼすかを理解する必要がある。この理解は、実験的手法にかかっている。例えば、与えられた社会的役割(参加)に戻るには、歩行(活動)の回復が必要かもしれないし、弱った筋肉群(障害)の補強が必要かもしれない。全体論的な生物学的・心理学的・社会学的な「全体」にのみ取り組むことは、医学の治療的使命を見失うことになりかねない。
🌱 So What?:何が面白いと感じたか?
子どもが描く地図。
例えば、日本人の子どもなら、その地図は日本が過大に大きく描かれ、その他の国々は小さくなるだろう。
そして、大人はその地図を見て、「まあそうなるよな」と微笑むのだ。
だが、大人だって、大した違いはないのではないか?
例えば、膝関節のスペシャリストは、あらゆる患者さんを膝というレンズを通してみようとしないか?
あるいは、心臓リハビリのスペシャリストは、やはり循環器のレンズから、すべての患者さんを見てしまっていないか?
僕たちの臨床思考過程という地図は、大なり小なり、歪んでいる。
今回の抄読文献における2つのホムンクルスは、それを極端に示してくれた。
もちろん、その歪みが強みとなることもあろうとは思う。
だが、人間には自分の知っている世界が強く存在し、知らない世界は存在しにくいというバイアスがある、ということは理解しておいた方がいい。
そして、自分のレンズを通してみた世界だけが、真の世界ではないかもしれないという謙虚さは、やはり必要だ。
今回のホムンクルスは、それを語りかけてくれたように思う。
⬇︎ 関連 note & 𝕏での投稿✨
📕2つのホムンクルス
— 理学療法士_海津陽一 Ph.D. (@copellist) May 16, 2024
🔹身体-外医学のホムンクルス(従来型)
・体性筋と皮膚感覚野の皮質表現を反映
・人と世界の関係の中核をなす
🔹内科医学のホムンクルス
・恒常性の役割を果たす器官で構成
・内科医学は身体各部位の病気に焦点
各専門(得意)領域ごとにホムンクルスはありそうですね😲 pic.twitter.com/pi7oIv7iB6
○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥
良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』
こちらから♪
↓↓↓

‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●
#️⃣ #理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス #サイエンス #毎日更新 #最近の学び
