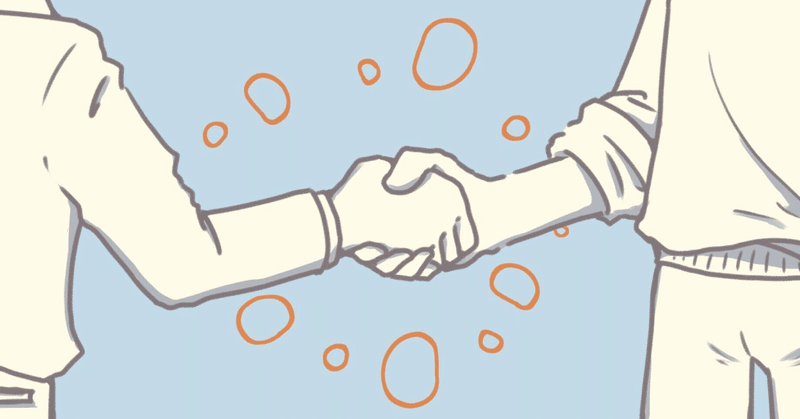
九州の知財判例④ ライセンス契約
特許技術や商標を人に貸すとき、ライセンス契約を結びます。ライセンス契約は知財を活用する上でとても重要な契約で、多くの企業で利用されています。
今回は、ライセンス契約がきっかけで損害賠償の裁判になってしまったケースです。
大阪地裁令和1年7月4日判決(H29(ワ)3973号)
原告X社:蛍光液素の研究開発、製造販売を行う九州の会社
被告Y社:天然樹脂や合成樹脂の製造・販売を行う大手企業
原告X社は自身の特許発明について被告Y社と専用実施権(特許発明を独占的に利用できる権利)の設定契約(ライセンス契約)をしました。
実施料(利用料)は一時金として最初に4500万円、その後は特許発明を使用した製品の売上の5%と決めました。
このライセンス契約には有効になるための条件があり、X社とY社とで共同研究開発契約と製造委託契約を結ぶことが必要でした。
ところが、Y社はいつまでたっても共同研究開発契約を結びませんでした。このままでは、X社は一時金を払ってもらえません。
そこで、X社はY社が研究開発のノウハウだけもらい、お金を払わなくてよいようにわざと共同研究契約を結んでいないとして、Y社に対して一時金の4500万円を求めて損害賠償請求の裁判を起こしました。
裁判所の判断 → 原告敗訴
争点① 専用実施権設定契約(ライセンス契約)が成立したか
少し難しい話になりますが、今回のライセンス契約が成立するには、共同研究契約を締結することが条件だったので、この条件を故意にY社が妨げた場合に、条件が満たされたとみなされて、ライセンス契約も成立する(=一時金を請求することができる)ことになります。
そこで、X社は、Y社が故意に共同研究契約を結ばなかったと主張しました。
裁判所は、「故意に」の判断について、信義則(相手の信頼を裏切らないように誠実に行動すること)に反する行動があったかという観点から検討しました。
事実の概要は以下のとおりです。
もともと、Y社からX社に対して研究を使いたいともちかけており、両者は蛍光色素の製品について共同開発を行っていました。そして、紆余曲折あり、今回のライセンス契約を結ぶこととなりました。
しかし、契約締結後に、X社が他大学との間で同様の発明について共同研究を行っていること、サブマリン特許(権利化していない特許申請)があることがなどが明らかになりました。
そして、Y社は多額の費用をかけてX社の特許を製品化、事業化しようとしていましたが、Y社が重要な研究情報の開示をX社に求めたにもかかわらず、X社は重要な情報を開示しませんでした。
一方、Y社としても、契約の一時金を支払うかのようなメールや契約内容を催促するメールをX社に送っており、X社としても不信感があったようです。
このような事実関係から、Y社が共同研究契約を締結しなかったとしても、締結しないことが信義誠実に反するような事態ではなかったと判断されました。
その結果、今回のライセンス契約は効力をもたず、X社の一時金の請求も認められませんでした。
雑感
本件ではX社とY社は長年共同研究をしてきたにもかかわらず、お互いに不信感がめばえてこのような結果になってしまいました。
もし、Y社が共同開発契約の締結を条件にしていなければ、Y社は一時金を支払わなければいけなかったかもしれません。
今回はY社の戦略が上回っていたようです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
