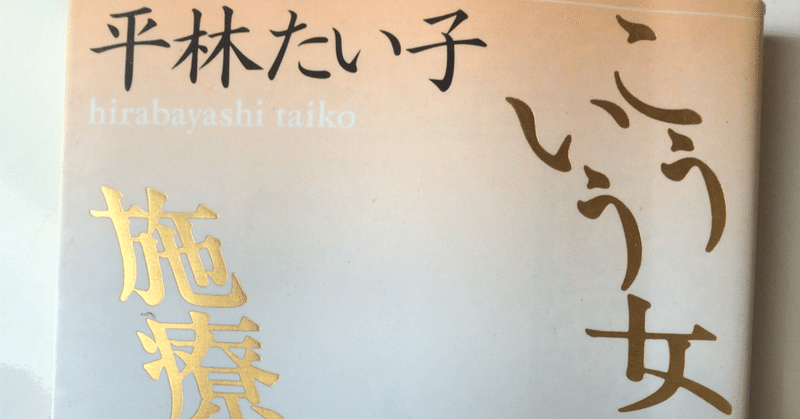
平林たい子「人生実験」
長野県諏訪市というところに4年くらい住んでいたことがある。転勤して、最初に思ったのは、湖がきれいで、温泉がたくさんあるなということだった。田山花袋の『温泉めぐり』というエッセイを読んだときにも、上諏訪温泉のことは記載されていた。
ただ、一人だと暇を持て余した。グルメだカフェだといっても、一人では十分に楽しむことはできない。古書店も少なく、図書館もイマイチだった。建物は文化会館だったのでそれなりの建物で重厚感があったが、選書が微妙で、楽しめたのは郷土資料のコーナーと新田次郎のコーナーだったか。
ただ、諏訪の町をぶらぶらしていると、平林たい子記念館という小さな建物を発見した。主婦の友を祖母が購読しており、そこで連載されている小説などの作者として名を記憶していたが、人生は知らなかった。入ってみると、戦前から戦後にかけて活躍した女性のプロレタリア文学者ということだった。
さほど興味をひかれたわけではなかったのだが、そこで一冊の本を買った。ただ出ていくのも申し訳なく思ったので、平林たい子『こういう女 施療室にて』を入手した。講談社文芸文庫ならば、デザインも好きだし、読まなくてもインテリアとして活躍してくれるだろう。
暇な日が続いた。独身で諏訪に4年間。もちろん、車山の湿原に登ったり、諏訪五蔵の日本酒に舌鼓をうったりと、それなりに楽しい毎日だったが、あまりにも暇な日に、そこにあった平林たい子の『こういう女 施療院にて』を読み始めた。その中から、おおっと思った短編「人生実験」を取り上げたい。
あらすじ
中年になった松子は、情念のうねりのようなものに日々とらえられたりしているが、ある時家の近所に、見知った男の名前と同じ表札が出ていることを発見する。
その男の名は、沢田岩男。松子が上京してきたときにはじめて恋をして、「松子の二十歳だった出発に最初に人生の文字をしるした男性」であった。そして、その男性の名前をみると、男性のことよりも「身も心もゴムまりのように台地に投げつけ踊っている松子自身の姿が現れてくる」のだった。
松子は、幼少期より「容貌」の問題に悩まされていた。実際、大人になり、社会に出るとそのことは経済問題以上に自分の前に立ちふさがってくる。自身でもとても興味がある「性の行動」について、この障壁を超えて、その内奥をもっと知りたいと望んでいた。
そんな折に沢田岩男と出会った。沢田とは社会主義の問題を議論したり、沢田の兄とのエピソードなどを話しながら、仲を深めていった。その結果、とうとう「性の行動」を実践するときが訪れた。さて、いざというときの沢田は滑稽でもあった。その瞬間がおとずれたときに、松子は沢田をはねのけた。いったいあったのかなかったのか。
その後沢田は、繰り返し求めてくる。松子は、終わったと思っていたが、沢田にとっては始まりだった。その後松子は、今までわからなかった男女の様々な振る舞いが意味を持っていたことを知る。それを読むことができるようになった自分にも驚く。「妾の旦那が来て松子の室を階段口へ斜に通り抜けることあそこに強い線をひいて行くような強いはっきりした意味となった。彼がそこをとおり抜けるときよく握らせる一円二円の金の意味も複雑な意味あいの料金のように思われて来た」というように。
沢田はとにかく松子を求めて、手紙を書いたり、めちゃくちゃ謝ってきたり、追ってくる。人からは、あんたが許しちゃうからこうなるんだよといわれたりする。許したのかどうなのか。そして、沢田とは会わないようにして、自然消滅してしまう。
しかし、別れてしばらくすると、情感のようなものが押し寄せ、覚悟ではなく新たな生の出発にわくわくするような気持ちが生まれた。不思議である。そんな折、沢田と再び出会ってしまう。そして、とうとうことを行ってしまい、しばらくはそうした生活に身を委ねることとなる。いつしか、松子は沢田を愛し始めていることに気づく。そして、松子はふたたび沢田から逃げ出してしまう。
そして、終戦。松子は40歳になっていて、すでに作家としての活動もしていた。その作品にネタに沢田との関係を使ったこともあった。それを見てかどうかわからないが、沢田から手紙が来る。すでに、自分も結婚していること。いろいろな苦労があのあとあったこと。そして今はカストリ雑誌「レディ」を創刊していること。そして、そこに原稿を書いてほしいこと。
あるとき、家に沢田の使いが原稿を頼みにやってくる。松子は断る。すると、使いの男は過去を今の夫にばらされたくなかったら書いてくれという趣旨の脅迫をする。そこにふすまの陰で話を聞いていた夫が日本刀を持って登場。使いの男は逃げ去る。そして、松子はその過去について夫に言うが、遺恨を残す。
そして、冒頭に戻る。ある日、家に帰る途中で、沢田とその妻が歩いているのを見かける。少し、あとをつけてみることにした。ただ、声をかけるのはやめ、わざと通り過ぎて会釈するだけにとどめた。すると沢田は声をかけてきた。原稿を断ったことに対する嫌味を述べ、再度依頼してきた。けれども松子は断る。沢田の妻が戻ってくる。
逃げようとすると沢田にステッキで殴られた。しぶしぶ家のそばまでいき、押し問答をするも、帰ろうとすると殴られる。それを周りで観ている人がいる。松子は、観ている人がいるからやめてという。沢田は「皆さん、これが二十年前に私を弄んで捨てた志川松子という女です。どうぞ皆さん顔を見て行って下さい。これが私を捨てた志川松子です」と騒ぎ出す始末。
仕方なく家に上がると、沢田の妻に「あっちに行ってろ!」と高圧的な口調。そして、かつてのように、松子をくみしだこうとする。しかし、松子は抵抗する。そして覚悟を決め、「細い沢田の腕を捻じ上げ」て、「徹底的に話しましょう」と述べる。
感想
何が面白いの、と思われるかもしれないが、平林たい子という人は、確かにプロレタリア文学の形式としてリアリズムと論説調の二つが文体にまじりあって、読みづらいといえば読みづらいのかもしれない。ただ、自分の肉体や精神を含めて客観的に描写しようとしているところが、性的な場面や暴力にさらされる場面にもカメラとして現れるので、極めて冷静な叙述として現れる。
この松子は、平林たい子自身の投影物だと思われるが、それを第三者の目線で動かせており、分析にも自己憐憫ではなく自嘲的なアイロニーが効いていて面白い。要するに、承認をひたすら求めるような書き方ではなく、自分のダメなところも良いところも含めて、素材をゴロっと投げ出すような書き方をする。嫌味がない。自慢がない。
最後の家の前で沢田に殴られているときに、周りで見ている人が、じっと見ていながらも止めに入らないことを理解しつつ、「殴る人には殴るわけがあり殴られる人には殴られるわけがあったのだから松子はとめて貰いたいのではなかった。しかし、見たいのなら何故大っぴらに来て見ないのか、見るのが悪いと思うならなぜかくれてしまわないのかという反感が溢れて日本人一般への憤りに拡がって行くのはどうしようもなかった。しかしそうは思いながらこういうひたむきな打擲の暗示する情事が日常に屈託している小市民にどんなに薄暗い興味であるかを承認しないわけには行かなかった」と書き付けるところなどは、心と目がきちんと分離していて、なんとも痛快だった。
話は、ある意味で松子の恋愛沙汰が、現代にまで影響を及ぼしてトラブルの種になっていくというものだが、こうした俗っぽい話の中から、平林たい子の生の不屈の魂が立ち上がってくるのが痛快だ。沢田の腕を捩じ上げる場面で、
「ね、貴方は大体人間が成長するということがわからない人なのよ。貴方はふしぎな人だということが自分にわからないのよ。私は成長したかったのだわ。人の生肝をたべても成長したいという気持ちわからない?……だけど一生こんな争いをしても仕方ないからきょうは話すわ。徹底的に話しましょう」
と、啖呵を切るところ、やっぱりいいですねえ、と思うのである。死にたいと軽々しくいう人に、ぜひ読んでほしい。まあ、あまりに怖すぎるかもしれないが。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
