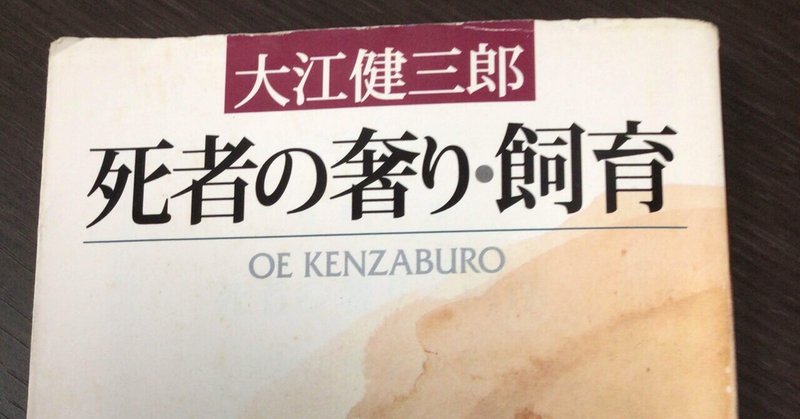
大江健三郎「飼育」
これも随分昔に読んだはずだった。「死者の奢り」と「飼育」は、新潮文庫の表題にもなっていたものなので、絶対にちゃんと読んでいるはずなのだが、「死者の奢り」に比べて、内容をほとんど覚えていなかった。覚えていると思っていたところも「人間の羊」とイメージを混同していて、読んだとはお世辞にも言えないような記憶の有様だった。
今回再読してみて、なるほどこういう話だったのか、と初めて理解できたような気がした。読む人の構えというか意識的な状態が、書籍の理解に及ぼす影響は大きいなと感じた。あの頃は、ただ多くの有名作を読む、ということだけに意識が向けられていて、内容を理解し感じ取ろうという意志に欠けていた。全く恥ずかしいことである。
さて大江健三郎の「飼育」だが、私に言われなくとも超有名作であり、どこかのアイドルグループの人が、「飼育」を肯定的に評価したとかなんとかで、今また注目を集めているようだ。
あらすじ【オチあり】
一応、小説の結末部が示されているので【オチあり】と書いたが、大江作品の多くは結末部に小説の面白みが詰まっているわけではない。したがって、そこまで自分は【オチ】なるものにこだわっているわけではないので、ざわざわ示す必要もないと思いつつも、世間はそうではないので、一応記しておく。
町の人々からは忌み嫌われている谷間の村に住む少年とその弟は、友達と森で遊んでいる時に、アメリカ軍の飛行機が飛来するのを目撃する。その夜、落下音がし、黒人兵が捕虜として谷間の村に連れて来られる。兵は、以後、少年の家に捕虜として軟禁されることになる。
兵に食事を与えたり、時には、ちょっとした関わりを持つようになった少年であり、少年の中では言葉は通じないものの、意志疎通ができたと感じていた。そんなおり、兵の処遇が決まったという雰囲気が少年に伝わり、少年は兵に何かを伝えないといけないという焦燥に駆られる。
少年は兵の軟禁されている部屋に行き、切迫感を伝えようとする。すると兵は少年を人質にとり、部屋の鍵をかけ、閉じこもってしまう。少年は、その立場の逆転を戸惑いながら体験する。結果、押し入ってきた村人たちに、捕虜の兵は殺され、少年は解放される。
その後、少年のもとに町の役人が訪ねてくる。少年はこの役人が、あの兵の処遇を決定したと思い込んでいる。少年は、役人のあるものを取り上げ、捨ててしまう。その結果、役人は死ぬ。
感想【オチあり】
大江健三郎の小説は、しばしばわかりにくいと言われるが、一つにその翻訳のような文体が理由としてあげられるだろう。また、比喩が独特で、日常的に使うものとはかけ離れた連想が提示されていることがあるのも理由の一つだろう。
ただ、それらは、そういうものだと慣れてしまえば、ストーリーの間に挟まる装飾的要素だと思って読んでいけばいいと思う。特に初期短編は。後期になると、語り手が異常なイメージを織り込みながら語る小説が主になるので、そう簡単にはいかないのだが。
冒頭に少年が、乱暴者の友人が捕まえた白い犬を自慢されるシーンがある。そこでは「俺にすっかり慣れたよ」「山犬の仲間の所へ帰って行かない」と誇らしげに語る友人が、白い犬を置いて手を放していたところ、戦闘機の音がして、白い犬が逃げてしまう、というのだが、この関係はのちの黒人兵と少年の関係を暗示しつつ、ちょっとずらして書いているようなお手本的な予告だと思う。
だからこそ「飼育」と名付けられた作品となっている。少年は、捕虜の兵を「飼育」していると考え、そういう意味で心を通わせたと一瞬錯覚する。だから、処遇が決定されようとしたとき、それを伝えに行った。少年のある意味で善意だった。しかし、その善意が兵に伝わると、兵は身を守る為に、最後の挙に出てしまう。白い犬が逃げ出したように、秩序の逆転が、ある一撃で起こってしまう。「飼育」しているはずの側が「飼育」されるという逆転。
これを戦後日本の戯画としてとらえるのも一理ある。また、単純に人間社会の一つの皮肉な寓話としてとらえるもの一つの読みである。私の場合は、他人を遇するときの難しさを読んでみたい。すなわち、善意で発せられたはずの身振りが、逆に、兵の恐怖を引き起こし、それゆえに、逆の結果をもたらしたという逆説。
少年はきっと、ずっと兵との「飼育」関係を続けたかったろうと思う。しかしながら、兵が殺されるかもしれない、と思い、警告を与えに行き、もしかしたら逃亡の手伝いをしようとしたのかもしれないのに、逆にそんな善意の自分が捕らわれの身になってしまう。善意は逆に悪意を引き出すトリガーになってしまうのである。
こういうコミュニケーション上でのトラブルはよくある。そして、『飼育』を読んだからといって、そうしたトラブルが回避されるわけでもない。そもそも、そのように読むことで、書かれている別の事柄に目をふさいでしまっているのかもしれない。ただ、50を手が届きそうな私には、昔であれば戦後の戦争を経験していない世代が書いた小説とだけ評価していただろうこの「飼育」が、ディスコミュニケーションの構造を解き明かしてくれているように感じるのだ。
「飼育」には、令和時代の観点だと差別ととられるような言葉が登場する。ただ、作中人物は作家ではないので、そうした言葉の使用は時代の中に埋め込まれた人間をあますところなく映し出すはずなので、できるならこの言葉のまま保存しておきたいと思わなくもない。まあ、最終的にその辺については私が何を言ったところで影響力はないので、識者にまかせる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
