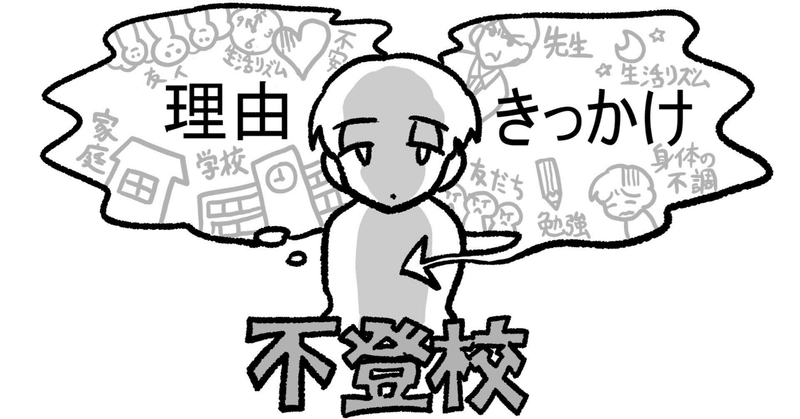
不登校を予防するために特別支援の観点からできること
不登校になる子どもは、
年々増えています。
中には、
不登校を克服し、
登校できる子もいるのですが、
それよりも毎年不登校になる児童の方が多く、
結果として年々不登校が増えているのが、
日本の学校の現状です。
もちろん、
不登校になってから
事後対応をしなければならないのですが、
不登校にならないようにする事前の働きかけ、
つまり「不登校の予防」が現在非常に重要になっています。
では、
不登校を予防するために、
どのような対応を
しなければならないのでしょうか?
実は、
ADHDやASDなどの
軽度発達障害の子供が
適応障害を起こし、
それが身体症状や不安感、
緊張感、抑うつ感、無気力など
精神症状を呈したり、
引きこもり、家庭内暴力など
不適応行動を起こしたりする
児童が増えています。
特に、
不登校の原因として最も多いのが
抑うつや不安感によるものだそうです。
よって、
発達障害のある子供が学校環境に適応し、
安定した学校生活を送ることができるため、
特別支援教育が重要になってきます。
発達障害のある子どもは、
・柔軟に対人関係を形成する能力の弱さ
・場面や状況に応じて行動する能力の弱さ
・衝動的な反応・感情的、情緒的な反応が多い
といった特性を持っていることが多いです。
全ての子供に一律に見られるわけではなく、
その現れ方は1人1人異なります。
さらには、
その違いは個々の特性により生じるだけでなく、
周囲の対応やこれまでの生育歴・教育歴など、
環境要因からも大きな影響を受けます。
つまり、
発達障害のある子供でなくても、
環境要因からそれに似た特性を示すこともあり、
子ども一人ひとり全く同じ特性はいないということです。
オーダーメイドの支援
が叫ばれているのはこのためです。
1人1人違うのだから、
1人1人の実態を把握し、
1人1人の支援計画を
立てなければなりません。
1人1人の支援をふり返り、
成果と課題を抽出して
1人1人のさらなる支援計画を立てていく。
そのサイクルの中で、
子供が環境に適応し、
安定した生活を送ることができるのです。
つまり、不登校を予防する事前の働きかけと言えます。
また、現在通常学級で3人に1人は通級指導が必要な子どもが在籍しているとも言われています。その全てを通級指導教室に入れるわけにはもちろんいきません。パンクしてしまいます。
通常学級の中で、
特別支援の観点から
個に応じた支援を行っていくのです。
全体指導の中で、
個別指導の中で、
グループ学習の中で、
日常生活の中で…
学校生活全体の中で、
特別支援の観点から通常学級で
できることを全部やる。
それでも、不適応を起こしたり、
授業についていけなかったりすれば、
通級指導や特別支援学級などの
学びの場の変更を検討していく。
学校が一丸となって特別支援のサイクルを回していけば、
きっと一人残らず学校に居場所を持てると信じています。
不登校を予防するために特別支援の観点からできること
これは、特別支援教育では当たり前のことを
通常学級でやっていくということです。
これができるのは、特別支援教育に深く携わっているものが
適任でしょう。
つまり、私のような存在です。
まだまだ私は勉強不足で経験不足なので、
これからもっと経験を積み、研鑽を積み、研究し、
学校・地域の特別支援教育の中核となれる人材を
目指して頑張っていきたいと思っています。
(これくらい見栄を切らないと、これから頑張れない(笑))
今日の記事は以上になります。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
参考資料
不登校の予防~発達障害の特性と不登校リスク~https://www.nier.go.jp/shido/leaf/leaf14S.pdf
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
