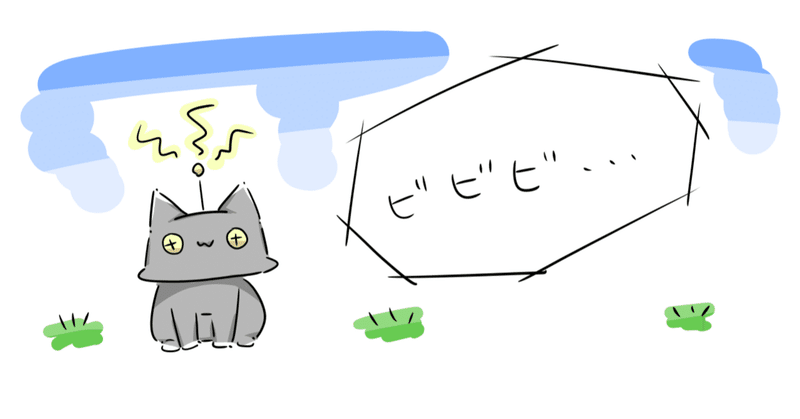
「受信」と「発信」~児童の自立と社会参加のために~
みなさんは
「受信」と「発信」と聞くと、
何を思い浮かべますか?
一番に思い浮かぶのは電話でしょうか。
受信して電話を取る
発信して電話をかける
この原理と同じで
児童への支援の中で、
「受信」と「発信」は
将来の自立と社会参加のために
大切な力となります。
「受信」と「発信」の関係
受信とは、
・事象に自然に伴う状況や、物や事が、子供にとってその事象を予測させる自然の信号になっている状況
・実際の活動が始まる前に、自然に先行する状況によって、次の活動の予測を子供がしていること
になります。もう少し分かりやすくするならば
こちらの「発信」した情報や刺激が確かに伝わっているのか?
子供自身で咀嚼し、理解し、何らかの形で「はい」と返ってきたのか?
ということです。
例えば、教師が
「明日は遠足です!おべんとうや水筒、帽子、タオル、敷物、ハンカチを忘れないように!」
と伝えるとします。
子供は「はい!」と大きな声で返事をして、帰りました。
この時、教師の発信した情報は
きちんと子供へ伝わったのでしょうか?
そもそも、「忘れ物」という言葉を
概念的に理解しているのでしょうか?
具体的に何を忘れてはいけないのか
記憶したのでしょうか?
いつ持ってくるのか
把握できたのでしょうか?
機械的に「はい!」と返事をしただけで
実際に咀嚼し、理解できていなければ
「受信」できたとは言えません。
言葉での「発信」以外にも
遠足とは何か、何をするのか、
何のために持っていくのかを説明する。
黒板に1つずつ書いて伝える。
絵や写真を見せて伝える。
通信等プリントを配っておく。
連絡ノートに書かせる。…
様々な方法で「発信」することで子供は確実に「受信」できます。
「上記の『発信』を全てしなさい」と言っているわけではありません、
目の前の子供の実態に応じて、必要な手立てを取る必要があるのです。
さらには、インクルーシブ教育の考え方を実践するならば、
障害のある子もない子も
全員が理解できる「発信」方法が
望ましいのです。
ならば、
上記の手立ては
必要となってくるでしょう。
「発信」行動の重要性
次に、「発信」について考えてみます。
子供が返事で「はい」と返ってきたときに、
初めてこちらも「受信できたな…!」と知ることができます。
では、話すことが
難しい子はどうするのでしょうか?
話せないと、
「受信」はできないのでしょうか?
そうではありません。
例えば、
①トランポリン ②さんぽ ③体育館
3つの絵カードを提示します。
①から順番に見せ、
自分がやりたいことの時に、
手を動かす、目を動かす、口を動かす…
できる反応を示せば、
その子が「受信」したと
捉えることができます。
さらには
手や目、口を動かす行動は
「発信」行動と言えます。
教師が順番にさせていては
子供は受け身の活動となります。
一方で、自己選択・自己決定のある活動は主体的です。
その子なりの対話ができたことにもつながります。
つまり、「主体的で対話的な深い学び」となるのです。
「受信」・「発信」行動を継続していけば、
おのずと意図的に発信するようになってくるでしょう。
それは、自分の意思を持ち、将来の自立と社会参加のために
大切なスキルです。
自立と社会参加のためのスキル獲得のために
教師はつい、子供の「受信」を考えず、
一方的に活動を仕組み、
できなければ指導、注意、叱責してしまうことがあります。
その結果、子供の自己肯定感の低下や意欲減退を招き、
2次障害を引き起こす危険をはらんでいます。
つまり、「受信」と「送信」は
全ての子供の学校生活全般において
大切にしなければならない行動であり、
自立と社会参加のために必須のスキルです。
ぜひ、皆さんもこのことを意識して
子供と関わってみてはいかがでしょうか。
今日の記事は以上になります。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
