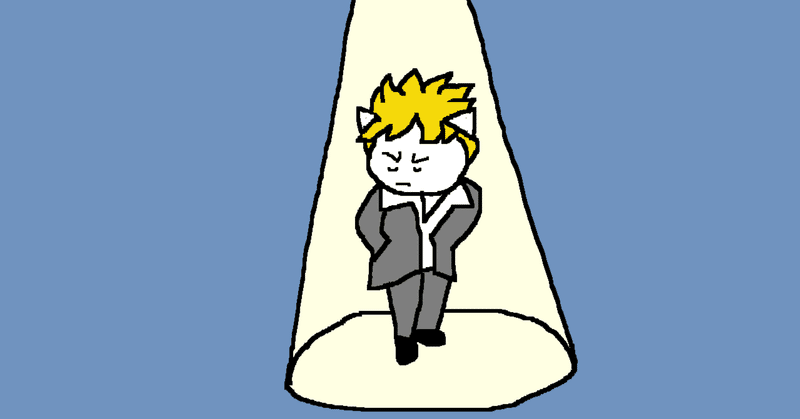
やめる力 〜余白があることで、ゆとりを持って穏やかな生活を過ごすことができる〜
手放すことで、何かを得られる
人生も、モノも、全てを抱えることはできない
キャパシティは決まっている
現在、何かを耐えること、
我慢して最後までやり抜くことが
美徳とされています。
これは、日本ではよくあることです。
「やめる」
仕事、結婚生活、住んでいる場所、友人関係…
様々なことに対して、やめる選択肢が出てくる
はずです。私も、前回の記事で学級担任でいることをやめ
特別支援教育の道で学校のサポートをすることに
全力を注ぐと決め、現在に至っています。
社会に出て仕事を始めた人たちにとっては
とても勇気のあることだと思います。
学級担任は、基本的に1年間担任を
任されることになります。
途中で「ギブアップ!」
と簡単に辞めることはできません。
よって、我慢して教員を続けた結果、
心に傷を負い、休職に追い込まれる人は
後を絶ちません。
私のかつての先輩の先生も、
一度心を病んで休職しました。
一度復帰したそうですが、半年ですぐに求職…
再び復帰できずにいるそうです。
ここで、
やめる力
について考えてみます。
そもそも、
やめる目的
は何なのでしょうか?
それは、
やめるとは、自分にとって
最良の仕事、役割、居場所を
探し求めるためにすることです。
人生が終わる時、
その選択が正しかったかどうかを
考えることです。
続けることが、
自分の人生を振り返ったときに正しければ
もちろんやめる必要はありません。
全うした!やり遂げた!ことが、
その人の人生の生きる証となるのですから。
しかし、
続けることが、
自分の人生を振り返ったときに
後悔の残るものであった場合、
「どうして、我慢して続けたのだろう?」
と思いながら、
人生の幕を閉じることになるのです。
「もっと、やりたいことがあったはずなのに…」
「もっと、周りから感謝されることができたのに…」
「もっと、頼られる役割を果たすことができたはずなのに…」
そう後悔してまで、
今のことをやめずに続けるべきなのでしょうか?
私はそうは思いません。
手放すことで、
得られるものがあるのであれば、
思い切って手放すことは必要です。
なぜなら、
人生も、モノも、全てを抱えることはできないからです。
人間のキャパシティは決まっているのです。
人の脳は大方大きさが決まっています。
ワンピースのベガパンクのように
ミソミソの実を食べていれば別ですが(笑)
スペース、余白があることで、
精神的にも肉体的にもゆとりを持って
穏やかな生活を過ごすことができます。
無理をして、
自分には向かないこと、
苦しいことも我慢してやることが美徳と考えるのは、
恐ろしいことです。
自分自身を見つめ直し、
「自分がやりたいことに没頭できる人生が素晴らしいな」
と最近思うようになりました。
みなさんも、やめるを意識して生活してみませんか?
今回の記事は以上になります。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
