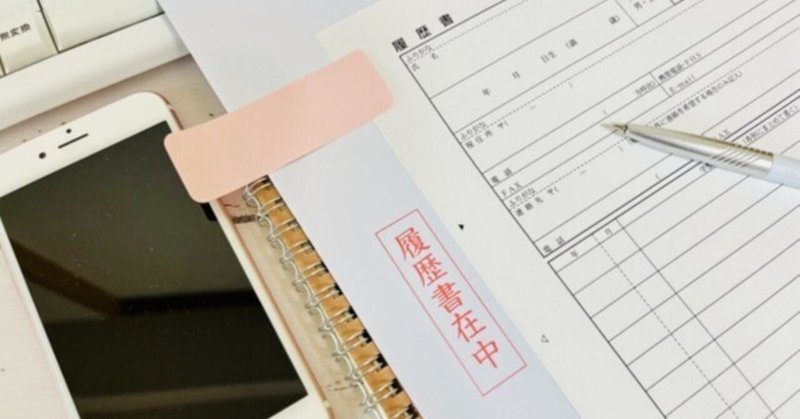
【自己分析ができない】うまくいかない原因と対処法
「自己分析をやってみたが、結局自分についてわからないままに終わった。」
「自己分析が難しくて、行き詰まってしまった。」
就活で自己分析にトライしたものの、こういった理由で心が折れてしまった方も多いのではないでしょうか。
自分自身のことなのに、いざ分析しようとすると、「何がしたいんだっけ?」「何が強み?」
など、何も浮かばないなんてことがよくあります。
スピード感も重視される就活の第一歩で、時間を要してしまうのは、もったいないですよね。
この記事では、自己分析ができずに悩んでいる人に向けて、自己分析がうまくできない原因と、その対処法について紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
自己分析がうまくいかない原因
1.他人と比較している
「強みなんてない」「得意と言えるほどでは…」
など、自分のプラス面が思いつかないようであれば、他人と比較していることが原因かもしれません。
どんなスキル・知識も、周囲を見渡せばいくらでもハイレベルな人たちはいます。クラスで1位になろうが、全国で1位になろうが、もっと優れている人を考え出すとキリがないのです。
将来の目標として他人を参考にするのは構いませんが、自己分析はあくまであなた自身を知ることが目的なので、他人との比較は不要です。
他人の知識や経験と比較して、自分がどうかを判断するのはやめましょう。
2.自分のことを良く言うことに抵抗がある
日本人として生まれ育った以上、どうしても自分を下げて言う「謙遜」の習慣がありますよね?
「私なんて、まだまだです。」
「そんな、大したことありませんよ。」
など。
普段から謙遜するコミュニケーションに慣れているが故に、自己分析で自分のプラス面を書き出そうとする際に、ちゅうちょしてしまうのです。
始めは違和感があるかもしれませんが、自己分析は普段のコミュニケーションとは大きく異なります。選考で自分のことをしっかりアピールするためにも、謙遜する姿勢はいったん忘れましょう。
3.仕事の枠にとらわれすぎている
「何か強みはありますか?」
という問いに対し、
「仕事に活かせる強みか…」
と考えているなら、すでに視野が狭くなっている可能性があります。なぜなら、自己分析の段階でどのような強みが活かせるのかは判断できないから。
自己分析でありのままの自分を理解する。
自分に合う会社や仕事、就活の方向性を考える。
というのが理想の流れです。
会社や仕事を意識した自己分析は、このフローを無視しているので、結果的に本来の自分からかけ離れてしまう可能性があるのです。
「PC得意だから事務職に活かせる強みになるかな…」と、仕事に結びつきそうな強みだけを探すのはやめましょう。
4.客観的に自分を見れていない
友人から、何気ないことで褒められたことはありませんか?自分では当たり前にやっていることでも、他人からすると「すごい!」と思われることは案外あるものです。
自己分析では特に、自分が無意識のうちにやっていることが、見逃されがちです。
自分のことは、自分が一番よくわかっている。それも一理あるかもしれませんが、主観的な分析では気づけないこともあるということも理解しておきましょう。
5.自己分析をする目的を理解していない
そもそも、どうして自己分析は必要なのでしょうか?自己分析がうまくいかない原因として、目的を押さえずにただなんとなくやっている、ということも考えられます。
自己分析の目的は、自身の強み・弱み・価値観などを理解すること。「自分にはどんな会社が合いそうか」といった企業選びの軸が明確になったり、「面接官にはこの強みを伝えよう」など、選考においてのアピールの仕方を知るうえでも重要です。
また、「今は〇〇のスキルが足りないから、これから勉強しよう。」「将来は新規事業に関われるように、既存事業をまずはしっかり理解しよう。」など、自己分析は、未来のキャリア開発に向けた目標設定・方向づけにもなるのです。
ただなんとなくではなく、何のために自己分析をするのか。明確でない方は、もう一度目的からおさらいすると良いでしょう。
6.現在の自分ばかり分析している
自己分析をするにあたって、ここ最近の活動ばかりを振り返っていませんか?
実は、過去を分析することも、自己分析の大きなヒントになります。趣味や部活動、学校の勉強、進学先など、これまでの人生の中に、あなたの価値観が隠されている可能性があるからです。
・小さい頃夢中になっていたもの
・部活動で与えられていた役割
・どんな考えで進路を決めたか
など、過去の経歴を掘り下げてみましょう。1点だけを見つめるとピンとこないかもしれませんが、全体を俯瞰してみると、
「私は自分で決めて行動するのが好きなんだな。」
「常に新しい環境を求めているな。」
など、共通項が見つかるかもしれません。
自分がどんな考えで行動・判断してきたのかを知ることで、そこにある隠れた価値観が見えてくる可能性があるのです。
自己分析ができない人におすすめの方法・やり方
1. 自分の能力の中で相対評価する
例えば学校で得意だった科目を尋ねられたとしましょう。その際に答えるべきなのは、自分の中で一番成績が良かった科目です。「クラスで上位だった」「5段階評価で5」である必要はありません。
例えば、
国語:1、数学:3、英語:1
という成績だったのであれば、数学が一番得意と言えるでしょう。
他人と比較するとキリがありません。世界1位にでもならない限り、自分より上のレベルの人が必ずいますからね。笑
自分が持つスキルや経験どうしを比べ、その中で突出したものをプラス面として選ぶ。
これが自己分析において大切なことです。
2.お金や時間、仕事を忘れて考えてみる
自分のやりたいこと・好きなことが見えない時は
自分にこう尋ねてみましょう。
「生活に困らないお金があったら何をしたい?」
「時間の制約がなければ、何をしたい?」
「誰も反対しないなら、何をしたい?」
自由に発想できない原因としてよくあるのが、無意識の思い込みや制約。「こんな考えは甘いだろう。」「仕事には結びつかないだろう。」といった考えが、あなたの本音を塞いでしまっているのです。
自己分析の内容は、あくまでワーク上でのものであって、本当に目指すのか、面接官に希望を伝えるのかなどは、次のプロセスの話です。
まずは広い発想で自由にやってみたいこと、興味があることなどを考えてみましょう。
3.家族や友人から意見をもらう
前述した通り、主観的な目線だけで自分を評価してしまうと、抜け漏れがある可能性があります。
「私ってどんな性格だと思う?」
「何が強み・弱みだと思う?」
と、家族・友人に尋ね、客観的な意見をもらいましょう。自分では大したことないと思っていることでも、実は他人から見れば、強みである可能性があります。
逆にできていると思っていても、弱みだと思われているならば、強みを見直すきっかけにもなし、努力すべきポイントが見つかって、それはそれでラッキーです。
4.人生曲線を書いて、過去を見える化する
人生曲線とは、あなたのモチベーションの上がり下がりを、時系列にグラフにしたものです。
横軸は時間、縦軸がモチベーションの高さです。

特別なツールを用意する必要はなく、画像の通り、縦と横に線を引いてすぐに作成することができます。
何歳から振り返るかは、やりやすい時期からで構いません。ただ、あまりにも直近すぎると、過去を振り返ってることにはならないので、中学くらいからスタートしてみると良いかもしれません。
グラフを書くことができたら、グラフに変化が起きているところに注目し、どうして高いのか?低いのか?を考え、グラフの横にメモしましょう。
例えば、
「親と喧嘩をした」
「学校の授業がつまらなかった」
「趣味に没頭していた」
「私学にいったのでコミュニティが変わった」
などです。
そして、その理由に対して「なぜ?」「どうして?」「具体的には?」と、問いかけ、深掘りしてみましょう。例えば、
「具体的にどんな理由で授業がつまらなかったのか?」
「没頭していた趣味はどんなもの?
何が継続させるきっかけになったのか?」
などです。
なぜモチベーションが高かったのか?低かったのか?を分析することで、自分がワクワクすることや、逆に避けたいこと・苦手なことが見えてくるようになります。
それらが明確になれば、就活の軸を考える際に、参考になるというわけです。ぜひグラフを作り、客観的に自分自身のこれまでの歴史を振り返ってみてください。
5.「なぜ?」「どうして?」と深掘りする
これは強み・弱み、やりたいこと、全てに共通することですが、自己分析した結果は、深掘りをして再度分析することが必須です。
深掘りをしておかないと、
自分に対する理解が浅いままになってしまい、
面接官にきちんとアピールできなくなるからです。
・なぜそれが強みだと感じたのか?
・なぜそれをやりたいと思うのか?
何においても、具体的な理由やそれを裏付けるエピソード、数字・実績がないと、根拠のないアピールに聞こえてしまう可能性が高いです。
過去の活動と結びつけるであったり、友人や家族からの客観的な意見を参考にするなど、自己分析結果を鵜呑みにせず、深掘りも忘れずにおこないましょう。
6.抽象化して仕事と結びつけてみる
「自己分析したけど、これをどう仕事に結びつけるの?」
「そんな理想的な仕事ないでしょう!」
など、
自己分析結果を具体的な企業・職種と結びつけるのに苦労されている方にオススメなのは、抽象化です。
例えば、
【サッカーが好き】であれば、
球技が好き
スポーツが好き
体を動かすのが好き
室内よりも屋外が好き
チームで戦略を立てて何かをするのが好き
といった具合です。
サッカーというワードに固執してしまうと、サッカー選手やサッカーの解説者などに留まってしまいますが、このように抽象化すると、理想の働き方や環境が見えてきやすくなるのです。
また、
【メイクが好き】であれば、
美容に関わることが好き、
見た目に関わることが好き、
ファッションが好き、
何かをデコレーションするのが好き、
といった抽象化もできますね。
メイクから派生して、美容やファッションという抽象化もできますし、仕事ではなく働く環境という観点では、服装・髪型自由の会社に勤めるといった選択肢も考えられます。
自己分析で出たキーワードをそのまま仕事や企業に結びつけるのは、難易度が高い場合もあります。その際は、言葉を抽象化して方向性を考えてみましょう。
行き詰まった時に大切な考え方
1.自己分析がうまくいかないのは当然!
おそらく大半の方が、自己分析がスムーズにいかないと私は考えています。
なぜなら、人事担当として・キャリアコンサルタントとしてこれまで多くの方の自己分析をお手伝いしてきましたが、ほとんどの方が、すぐに行き詰まっていたからです。
「何をしたいのかわからなくて。」
「強みなんて思い浮かばないですね。」
そんな方を何度もお見かけしてきました。
むしろ、初回でスラスラ自己分析できている方人なんて、一人もいないくらい。
ですので、自己分析ができない自分はダメだ、と考える必要は全くありません。むしろ自然なことだといえるでしょう。
どうか焦らずに取り組んでください。
2.書いたことは後で変えても良い
「弱みって書いたけど違うかも…」
「やっぱりこれもやってみたいかも…」
自己分析は1回きりのワークではありません。
時間を置いてよくよく考えると、違った考えが浮かんだ、なんてことも。
決めたからには責任を持って…!
とご自分の意見を縛ってしまう方もいらっしゃいますが、安心してください。自己分析は、何度でも変更・修正可能です。
初めのうちは、とにかく自己分析を前に進めること、アイデアをたくさん出してみることが大事です。
質は後から高められますので、何度でも修正するくらいの気持ちで、まずは気軽に取り組んでみてください。
3.しょうもなくても、大したことなくてもOK
【やりたいこと】を考える際によくありがちなのですが、遠慮や恥ずかしさで自分の意見を取り下げてしまうことです。
自分には知識がないから…
高望みしすぎかも…
そんなことを考える必要はありません。できるかどうか、該当する企業や職種があるかどうかは別として、まずは思ったことをアイデアとして加えてみましょう。
最後に
自己分析ができるオススメサイト3選
自己分析を始めたいけど、どうすればいいかわからない方は、まずはWEBサイトで簡単にできる自己分析から始めましょう。
今回は、就活活動でも利用することを考え、就活でメジャーなサイト、なおかつ無料でできる自己分析ツールをピックアップしました。
余力があれば、いくつか試してみて、使いやすいものを選んでみると良いでしょう。
・リクナビ自己分析ツール
・オファーボックス「AnalyzeU+」
・DODAキャンパス適性検査GPS
以上、
オンラインで出来る自己分析ツール
を紹介しましたが、他にも
・大学のキャリアセンター
・ハローワーク
・就活エージェント
など、対面でアドバイスをもらうという方法もあります。
要は、ご自身の価値観や強み・弱みが分かれば、どんな方法でもかまわないのです。
まずは、ご自分ができそうな方法で、自己分析を始めてみましょう。
まとめ
というわけで今回は、
自己分析がうまくいかない原因と、
その対処法・大切な考え方
についてご紹介しました。
「自己分析してみたけどなんかしっくりこない…」
という方は、何かしらの思い込みや、手順が間違っている等で、きちんと自分の中にあるものと向き合えていない可能性があります。
ぜひ、ご紹介したような視点でもう一度自己分析というものにトライしてみてください。きっと就職活動において大いに役立つと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
