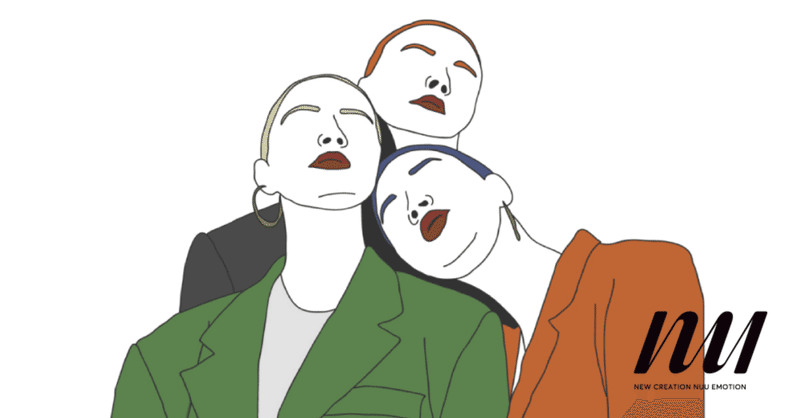
シェアサロン経営のはじめかた 【その4.】 短期間で売上を5倍にする。
勢いよく2店舗目を出店したものの、出だしから焦燥感が漂う。
私は緻密な計画を立てられない人間で、始めてみた後に後悔する事が今までもたくさんあった。
なのになぜ学ぼうとしないのか。それは何かを経験してきたつもりで何も理解していなかったからかもしれない。
逆に、後悔から学ばないからこそ無邪気に新しいことを始められる勢いとアホさがあるとも言える。
新しい事業をスタートすると強い負荷がかかることはわかりきっているのだから適切に学べる人間であれば何度もやろうなんて思わない。
学んできたことがあるとすれば、追い込まれるほどに何かを閃くということ。
自らを崖の端に立たせることで光明を見出す。
悲観的な考えを寄せ付けず、楽観的な未来を信じる。
それが起業、それが経営。
都合のいい解釈で自分を奮い立たせるが、つまるところこれではただのギャンブルである。
それでも私の記憶には1つの真実として刻まれている。
さて、目の前に横たわるのは現実問題。
たくさんの方に利用いただけなければシェアサロン事業は赤字を垂れ流し続ける。
しっかりとした利益を生み出すために初月の売上(137万)の5倍を短期目標としたい。
「売上は全てを癒す」とは故ダイエー創始者の中内功の言葉だが、今やるべきことはビジネスを成立させるための売上の確保。
ここにきて私は、ようやく利用者獲得のためにマーケティングやブランドポジショニングと正面から向き合うようになる。
利用者集客に向けて最初にやったことは、広告配信のためのリサーチ。
見学者の住居地、年代、要望、希望、お悩みごとをデータ化しエクセルに蓄積。
見学者の基礎情報を元に配信すべきエリア、年代、訴求内容を選定し「こういう人に情報を届けたい」という人物像を設定した。いわゆるペルソナ設定というやつだ。
設定した人物像を元に、どのような広告を配信すれば「nuuを利用してみたい」と思ってもらえるのかを考え、広告用のビジュアルを作成。
広告配信→google・フェイスブックの分析ツールで解析→より訴求効果の高そうなクリエイティブとコピーライティングの可能性を探る→また作成。
そういった地道なPDCAを繰り返すことを続けた。
広告作成と同時に、予約アプリと連携して見学の問い合わせから、見学日程の管理まで滞りなく進められるよう導線を整備。
問い合わせも徐々に増えだし手応えを感じはじめる。
見学者に対する上原の対応も素晴らしかった。
彼女が心掛けたのは一人一人親身になって対応すること。
なぜシェアサロンで働きたいのか?プライベートでどんな悩みを抱えていて、どう改善したいのか?
女性同士だからこそ共感・共有できることがあるものだ。
このフェーズでは質より量を重視した。
オシャレ感強めな広告も作ってみたし、「80%バック!」「稼げる!」「自由に楽しく!」などのうるさめな広告も作った。
実績がないうちは弾数と実戦。
カッコつけずに手当たり次第発砲して飛距離を確かめてみる。
そこで気づいたのが、「女性専用だからこそ訴えることのできる価値がもっと別にあるのではないか?」という可能性。
男女兼用サロンの場合、訴求する対象が両性になるので
「高還元」
「立地が良い」
「自由で制約のない」
「オシャレで綺麗なサロン」
など、広い対象に向けた普遍的なものになってしまいがちである。
その結果、訴えたい軸が「稼げる」などの機能的なものか、「自由」のような抽象的なもののどちらかになりやすい。
女性美容師さんがシェアサロンを選ぶ条件とはなんだろうか。
歩合還元率はどこも同じくらいで、システムも似ている。それ以外の差別化要素は立地や内装のオシャレさくらい。
そこで我々は別の切り口で価値提案すべきだと考えた。
「わたしたちは何を訴求し、何を提供したいのか?」
伝えるべき本質と向き合い検討を続ける。
見学対応している上原からのフィードバックと接するうちに、私の中でぼんやりと方向性が見えてきた。
それはnuuが訴求すべき価値は「場所」や「機能」ではないのではないか?という仮説。
シェアサロンのビジネスモデルは不動産賃貸業やスポーツジム経営と似ている。
場所を提供し、対価として家賃や利用料をいただく。
通常の発想として機能的価値にフォーカスを当てがちだが、我々が提案すべき内容はもっと別の領域にあるのかもしれない。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
