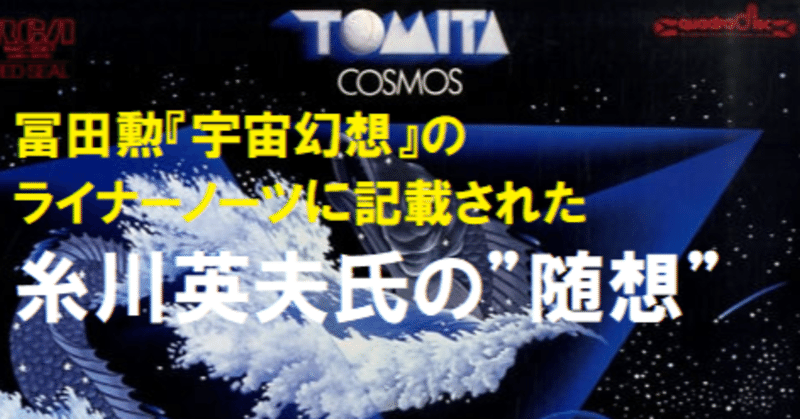
冨田勲『宇宙幻想』のライナーノーツに記載された糸川英夫氏の”随想”
1978年に発売された冨田勲氏の『宇宙幻想』というLPレコードのライナーノーツに記載された糸川英夫氏の解説(随想となっている)をテキスト化してみた。今、断捨離の最中で手持ちのLPをMP3化してから処分する予定だが、LPにはライナーノーツが同封されており、たまに興味深い文章が見つかる。その中の1つを電子的に保存したいと考えた。
一部、通常の文字では表現できない専門的な表現があったりルビが振られていたりして完全再現となっていない点は致し方ない。(例によってOCR利用のため誤字脱字ご容赦←今流行りのAIである「ChatGPT」に校正させたら勝手に文章を変えられてしまったので使えなかった)
随想ー糸川英夫
リチャード・バックの小説「かもめのジョナサン」は私の最も愛する小説の一つである。この小説を羽田から福岡へ飛ぶ機上で読んでいるうちに何度も目が涙で曇ったものである「群」をはなれる「孤独」を恐れる心よりも、もっと強い創造への執念にもえている人を私はいつも尊敬する。
「かもめのジョナサン」にとって、アメリカ大陸は生まれやすく、住みやすい筈である、日本に比べれば。
冨田勲は、かもめのジョナサンである。リチャード・バックはパイロットで、飛行機というメカの中に生涯の情熱をかけている人である。彼にとって、flying は「ことば」なのだ、と彼自身が語っているように。
冨田勲のシンセサイザーとそれをとりまくもろもろのエレクトロニックスのメカは、リチャード・バックの飛行機である。
バックが飛行機というメカをこよなく愛し、その操縦に、芸術的、哲学的法悦感をもちつづけているように、トミタ・イサオは彼の仕事場に充満しているエレクトローアクースチックのメカ群の操縦をこよなく愛し、その操縦に芸術的、哲学的法悦境を創造しつづける。
バックにとって「かもめ」は彼のパイロットとしての現実を芸術の世界に昇華抽象したもので、文学作品「かもめのジョナサン」へ結晶したように、トミタ・イサオは作曲家としての彼の情熱を「音の創作」を通じて、音楽という作品に結晶させる。
彼の作品が、第1作のドビュッシー「月の光」から、アメリカのレコード会社によって採り上げられ、世界的に知られるようになったのも、リチャード・バックの「ジョナサン」が、アメリカで出版され、そして、世界中に翻訳されたのと軌を一にしているのは、現代の日本に生きる人間の一人として、まことに印象的である。
私が、彼の音楽について、格別の共感と関心をもっている理由は、しか
し、この他にある。
処女作品の「月の光」以来、「火の鳥」「展覧会の絵」そして「惑星」に
ついで、これは作品番号"5"である。
多くの音楽愛好者、レコード・ファンにとって、トミタ・シンセサイザー・ミュージックとは、どういう地位を与えられているのであろうか。
新しい「音」への追究は、多くの作曲家達によって、それぞれの独創力と個性で絶えず試みられている。モーツァルトや、ベートーヴェンかバッハになかった「音」を求めたのと今も変わりがない。
通常楽器、例えば弦楽器を、弦のところで弾かないで、木の骨材部で弾くように指示したり、ヴァイオリンやチェロの背中を手で叩かせたり、演奏家泣かせの奇手から始まって、ミュージック・コンクレートという、自然音をそのまゝ使う手法、それから電子楽器による作品、それらの組み合わせから「今までになかった音の芸術」を創作する、という試みは絶えずつづけられている。
しかし、こういう、いささか「前衛」がかった音楽は、風変わりな作品として、コンサートで演奏されても、レコードになっても、一部の特殊な「愛好家」やもの好き的少数派によって支持されるのがせいぜいである。
コンサートで演奏されれば、せいぜい「物珍しさ」と、こういう作品をとり上げた演奏家や、オーケストラや、指揮者の勇気に対して一応の拍手を送りはするけれども、コンサートの帰路の途上、いつまでも「感動」をもちつづける、といったようなことは「滅多」におきない。
一言でいえば、アーチストのひとりよがりであって、入場料を払った聴衆の存在を無視した、聴衆不在、少なくとも「大衆不在」の音楽である。
トミタ・シンセサイザー・ミュージックもこれらの「ニュー・ミュージック」の一つだ、と誰かが考えたとしても、その人を責めるわけにはいかないかも知れぬ。少なくとも知れなかった。
そうでないことを私が身をもって体験し、発見したのは1977年10月28日、29日にわたって、東京、帝国劇場で行なわれた貝谷八百子バレエ団の秋季公演によってである。
貝谷八百子は、トミタ「惑星」のバレエ化に挑戦した。
これは一つの冒険といってよい。何故ならば、すべてのバレエ(クラシック・バレエ)は必ず、オーケストラと指揮者を必要とし、それに、「白鳥の湖」にしても「ジゼル」にしても、「ストーリー」つまり「物語り」から成り立っているのに、この「惑星」バレエは、テープと、アンプと、スピーカーという電子音響装置だけで、ナマオケも指揮者も存在せず、それに、ストーリーなし、筋なし、物語りでないそれこそ「純粋芸術」であったから。
当然予想されたことは、「一部の極めて、水準の高い観客」によってのみ理解され、その他の「大衆」はチンプンカンプンのうちに幕がおりるのではあるまいか、という危惧であった。少なくとも出演者の一人として、私にはプランの段階で、そういう結末に対して覚悟をきめておくことが必要であった。
結果は予想をくつがえした。
3回の公演を通じて、あの広大な帝劇の観客席を満席にした、のべ5000人の聴衆は、一人のこらず、といってよい程の、深い感動につつまれて帰路についたのである。
それは前半の演し物「オーロラの結婚」(眠れる森の美女)、で若手が華麓なバレエを美事に演出した感動を数段上まわる迫力で「惑星」が圧倒した。
この観客の中には、平常、音楽や、バレエとは殆んど無縁で生活しておられる、それこそ「普通の人」達が多かったが、これらの人が受けた感動は、近来にないものであった。
公演の直後から、直接に、電話で、手紙で、私一人だけがうけた反響も妻凄まじい、といってよかった。「大感動」「忘れられない感銘」「もう一度見たい」。それは貝谷バレエ・ファミリーの一員になってからの過去6年に経験した、どのイペントも桁違いに凌駕した。
その方々が何といったか。
「惑星、ホントに素晴らしかった。"音楽"がよかった。そしてあの照明のすばらしさ。そして、息つくひまもないようなバレエの流れの美しさ、力強さ」。
こういう表現をされたのは、平生コンサートには無縁な中小企業の社長さんであり、毎日の生活に追われている主婦の方々であり、そして中学1年の女子達であった。
全く同じ表現を観客の一人であった竹村健一氏も吐露された。
その感動は、「惑星」の作曲者のホルストか何年に生まれて、何年に、何を作曲したか、など知らない人、原曲の「惑星」が「女性合唱を必要とするため」、ナマオケの演奏回数が少ないのだ。などということを全く知らない人から生まれた。
つまり「音学」でなく「音楽」であった。
プログラムをよまなくても、解説の必要もない、万人のハートにストレートに響くものであった。
トミタ・シンセサイザー・ミュージックが、ロックよりも演歌よりも現代日本の大衆の心をとらえるものであった。というのは私にとって嬉しい発見であったのである。
トミタ・シンセサイザー・ミュージックに私がひかれる理由はもう一つある。
冨田勲氏は少年時代、私の設計した「隼」「鍾釚」などの戦斗機に、今の子供達にとってのスーパー・カーみたいにあこがれたそうである。その設計者は昭和20年、ポツダム条約によって、日本に於ける一切の航空宇宙に関する研究の禁止の宣言をうけて以来、東京大学で音響工学の講座を担当することになった。
それからの10年間の私の研究テーマは「名器、ストラデバリウスの秘密」を解き明かすことであった。
ストラデバリウスのヴァイオリンと、近代の工場でつくられる楽器のどこがちがうのか。
この秘密を解きあかす数学物理的道具は一つしかない。

フーリエの級数理論といわれているこの式である。(数学アレルギーのある方は、詩の一節だと思って眺めていて下さい。)
f(x) =・・・でなく、f(x) ⇆・・・とかいてあるところが、ミソである。f(x)→ の方はf(x) が、ストラデバリウスならば、その音の秘密を「分析、解析」した結果が、右辺の各項である。
この仕事を10年つづけている間に、私の頭を去来したのは、f(x)← の略称、つまり、多数のオシレーターで、多数の余弦波、正弦波をつくり、その長さ、周波数、振巾、位相を調節することによって、ストラデバリウスの音を「全く物理的に合成(シンセサイズ)」出来るのではないか。
という発想である。
当時の私の研究室は、発振器、フィルター、位相調整器、プラウン管でゴッタ返していた。ただトランジスターは、まだ生まれていなくて、サブ・ミニアチュア・チューブ(超小型真空管)しか手に入らなかった。
合成(シンセサイズ)された音は、およそストラデバリウスとは程遠いもであった。
昭和30年に私はこの研究を打ち切った。宇宙ロケットの研究ヘスタートするために、手づくりの一本のヴァイオリンと「輪型細隙の音響イムピーダンス」という学位論文が残っただけである。
それから20年たって、トランジスターの進歩による驚異的な電子音響技術をフルに駆使して、私の夢を実現した人がいる。
冨田勲氏である。
冨田氏が少年時代に「隼戦斗機」にあこがれたように、私は終生トミタ・ミュージックにあこがれつづけるであろう。
トミタ・シンセサイザー・ミュージックの、数学的、技術的根拠をつくったフーリエという数学者は1768年、フランスで生まれ1830年に死亡し、一生の間ナポレオンと運命を共にした。ナポレオンがエジプト遠征した動機は、フーリエの数学理論を"無知蒙昧"なるエジプトの民に施すためであった。
フーリエが級数理論をかき上げたのは1807年グルノープルに於いてである。
このトミタ・シリーズ5番に当たるアルバムに収められた曲のうち、バッハは1685-1750年、「ペール・ギュント」のグリークが1843-1907年、ワーグナー1813-1883年、ディニーク1889-1939年、アイヴズ1874-1954年で、フーリエは、バッハの死の直後に生まれ、ワーグナーの生まれる頃死亡した。
人類の文化の歴史の興味深い綾の一つのように思えるのではないだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
