
最近読んだ本(4月編)
気づけば4月ももう終わり。日本ではGWらしいですね。
僕の旅も、タイのバンコクから、ウズベキスタンのタシュケントへと場所を移しました。
というわけで、備忘録も兼ねて、4月に読んだ本の紹介です。
合計:16冊(2024年累計:39冊)
ソニー再生 変革を成し遂げた「異端のリーダーシップ」

私はよく「肩書で仕事をするな」と言う。部長になった途端に、あるいは役員になった途端に部下への接し方が変わってしまう人は、読者の皆さんの周りにもいると思う。そんな人が「票」を勝ち取れるか。答えは述べるまでもない。 これは決して精神論ではない。リーダーがどう振る舞うかで、成果がまったく違うものになってしまうのだから、結果を出すために必要なことなのだ。
新・ラグジュアリー 文化が生み出す経済 10の講義

ひとつ具体的な方向例を挙げれば、「新しい価値やビジネスモデルへの受容の高まり」があり、キーワードは「オープン」です。これまで排他的に「クローズド」を好むと思われてきたラグジュアリーの消費者が、「オープン」になってきています。そのために企業側が「ラグジュアリーとは何であるか」を決めるのではなく、消費者が自分の価値で「ラグジュアリー」を判断し、自己表現に用いる方向に動いていくというのです。企業と消費者の両方向からラグジュアリーの新しい意味がつくられていくのです。これはラグジュアリー企業が直面する現実をよく示しています。
だからタイはおもしろい~暮らしてわかったタイ人の「素の顔」~

低所得者層のリアルな生活を舞台にしたら夢なんか見られない。現実世界でも、富裕層にしか夢を追いかける余裕がない。たとえば、タイではスポーツをしたり芸術を 嗜んだり、芸能人になるのはほとんどが富裕層の子どもたちだ。監督や脚本家も同じ。一切交流のない下層の生活を彼らは知らないのだから、それを描くことができないともいえる。通う飲食店やライフスタイル、受けてきた教育水準も違うので、富裕層と貧困層が交流することはおろか、会話すら噛みあわない。だから、タイでは富裕層と低所得者層がくっつく玉の輿、逆玉といったシンデレラストーリーは存在しない。
マッキンゼー ホッケースティック戦略―成長戦略の策定と実行

差別化には長期的な視点が必要ですが、四半期ごとの収益に追われていると困難です。今年度の予算を達成しないとならないときに、研究開発の予算をカットしたことはありませんでしたか? 非上場企業に関する極めて興味深い分析によると、非上場企業は類似の上場企業に比べて、およそ2倍の投資を行っていることが示されています。四半期ベースの収益を出すことに専念している企業では、短絡的な考えが横行しがちです。市場に対して前向きなメッセージを発したいがために、新製品を中途半端な状態で、利益率を少々犠牲にしつつも発売したことはありませんか? 戦略的な大胆施策の中で、この差別化の大胆施策ほど、短期的な利益のために犠牲になりやすいものはありません。
普通をずらして生きる――ニューロダイバーシティ入門

ニューロダイバーシティは社会に、テイストを作るレッスンと、テイストメーカーを理解するレッスンの両方をもたらしうる思考のあり方です。分離から混淆へ、人々はもっと積極的に混ざり合ったほうがいい、というのがこの本の最大のメッセージといえるのかもしれません。
人間主義的経営

また若い世代には、自分だけでできることよりもずっと美しく、楽しく、実り多く、それゆえもっと上手に遺産を築く方法をアドバイスしたいと思います。それは、美しいもの、気高いものを敏感に感じ取ること、自然や、風や、小川や、海や、空の奏でる音や人々の声に耳を傾け、宇宙の調和を維持することの重要さを知ることです。老人の話にじっと耳を傾ければ、顔の皺の間に老人が子どもだった頃の記憶を発見して感動することでしょう。両親と対話し、友人の話に耳を傾ければ、互いに共通する喜びや苦しみを理解することができるでしょう。そうして来るべき未来の黄金の果実を手にする準備ができるのです。
The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness

A human child doesn’t morph into a culturally functional adult solely through biological maturation. Children benefit from role models (for cultural learning), challenges (to stimulate antifragility), public recognition of each new status (to change their social identity), and mentors who are not their parents as they mature into competent, flourishing adults. Evidence for the idea that children need rites of passage comes from the many cases where adolescents spontaneously construct initiation rites that are not supported by adults in the broader culture. In fact, anthropologists say that such rites come about precisely because of a society’s “failure to provide meaningful adolescent rites of passage ceremonies.”
Unreasonable Hospitality: The Remarkable Power of Giving People More Than They Expect

I often describe “being present” as caring so much about what you’re doing that you stop caring about everything you need to do next. That second group of servers embodied that beautifully. When they were talking to guests, they were fully present with them. They were being rewarded for their hospitality, not their excellence.
いつも旅のなか

この、勘、というやつを私はかなり信用している。何気なく通りをぶらついていて、食べもの屋の前を通った瞬間、勘が体内でわめきたてることが、旅をしていると多々ある。混んでいるとかいないとか、安そうだとか高そうだとか、いっさい関係ない。実際、勘がどんなにわめき立てようと、入りにくい店というのは歴然としてある。自分は薄汚れた短パン姿なのに、真っ白いクロスがまぶしい高級店には入りづらいし、地元の酔っぱらいでぎゅうぎゅうに混んでいる店も、入るにはかなり勇気が要る。勘なんてあてにならないや、と言い訳するように、勘のいっさい働かない別の店で食事をすると、やっぱりあまりおいしくない。「ほーらごらん」と勘があざ笑う。勘に従って勇気を奮い起こし「えいやっ」と店に入る。不思議なことに、こういう店で供される料理はじつにうまい。はずれたことがない。
会社は頭から腐る

理論武装した若いコンサルタントが、時々陥る罠がある。会社を偽物的に見てしまうことだ。あるいは、あたかも機械のように見てしまう。組織論や人事管理論の教科書を一生懸命に勉強し、まるで組織を機械のように規則正しく動くものと見立てて、歯車の噛み合い方から資源の配分まで完璧に構築する。そうすれば、効率的に機能するはずだと考えてしまう。 ところが、現実に企業を動かすのは、人間である。機械のように人間は動いてくれない。歯車をやりたい人が、クラッチをやってくれといわれても、簡単にはやってくれない。これでは車は動かない。そこで若いコンサルタントは悩み、思考が停止してしまう。あるいは「これは相手がわかっておらず、自分の素晴らしい経営アドバイスを理解できないからだ」と決めつけてしまう。つまり、学問としての経営を学んでも、実際の経験を積んでいないコンサルタントは、本当の意味での組織や、人間の現実をまだ見ていないのである。
エコシステム・ディスラプション―業界なき時代の競争戦略
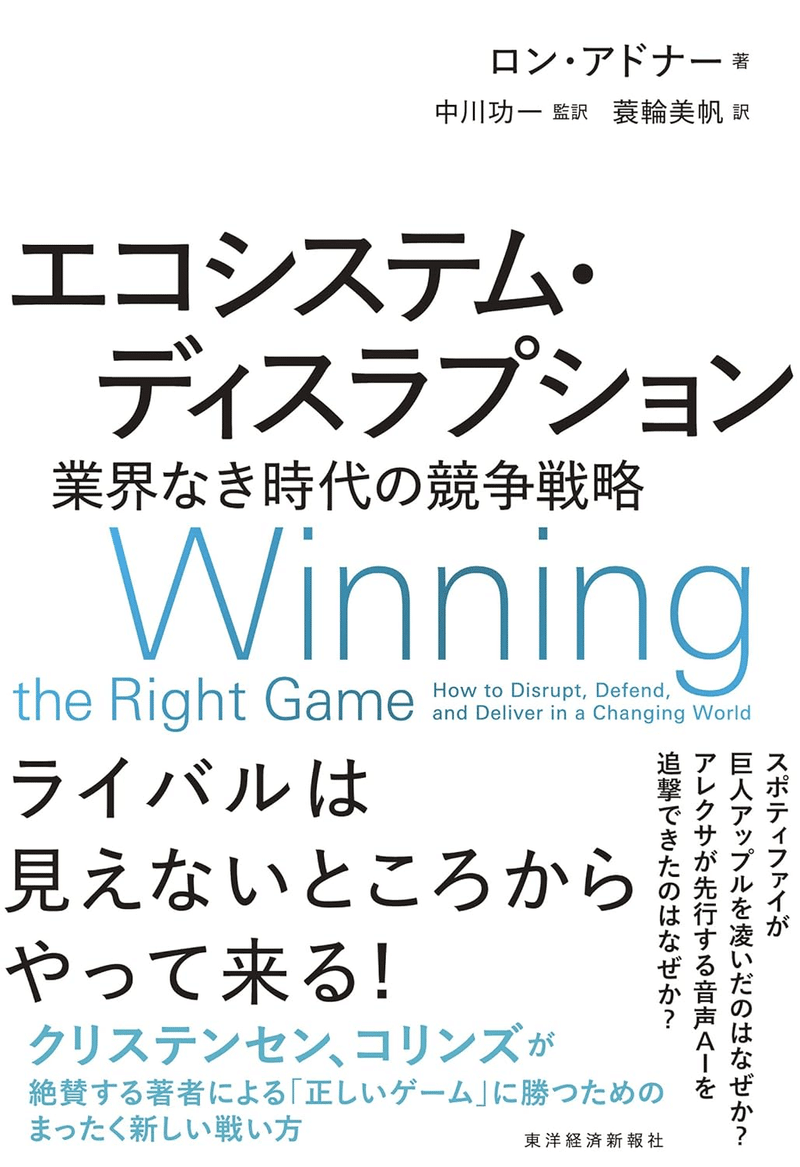
自社の価値構造を修正すれば、必然的に価値提案を構成する具体的な価値要素が変化することになる。変化する競合の状況を踏まえて価値創造の理論を更新するのである。価値要素は他社との協働で生み出されるため、価値要素の修正をじっくり検討することは、パートナーの戦略を調整することにもつながる。 防御をする際には、一般的には自社に有利で攻撃者に不利になるように価値構造を修正する機会を探る必要がある。自社の狭い注力分野を活かして、より高度な活動に集中し、専門性を強みにするのだ。
人生の短さについて

あなたの精神は、これほど強い活力に満ち、最も偉大な事柄に向き合うことができる。あなたの仕事は、たしかに尊敬に値するものではあるが、幸福な人生をもたらしてはくれない。だから、あなたの精神の力を、そんなところにつぎ込むのはやめなさい。よく考えてほしい。あなたは若いころから、教養を身につけるために、あらゆる教育を受けてきた。だがそれは、大量の穀物を上手に管理するためではなかったはずだ。あなたが大志を抱いていたのは、もっと偉大で崇高な仕事だったではないか。 几帳面で仕事熱心な人間なら、ほかにいくらでもいる。荷物を運ぶには、歩みのおそい家畜のほうが、血統のよい馬よりも、はるかに適している。わざわざ重い荷物を載せて、生まれながらの俊足をだいなしにしてしまうような者が、どこにいるというのか。
Technofeudalism: What Killed Capitalism

Every time we go online to enjoy the services of these algorithms, we have no option but to cut a Faustian deal with their owners. To use the personalised services their algorithms provide, we must submit to a business model based on the harvesting of our data, the tracking of our activity, the invisible curating of our content. Once we have submitted to this, the algorithm goes into the business of selling things to us while selling our attention to others. At that point something more profound kicks in which gives the algorithm’s owners immense power – to predict our behaviours, to guide our preferences, to influence our decisions, to change our minds, to thereby reduce us to their unpaid servants, whose job is to provide our information, our attention, our identity and above all the patterns of behaviour that train their algorithms.
ユニクロ

この講演で柳井はそれを、こんな風に表現していた。 「こいつアホじゃないかと思われるような非常識な目標。これがイノベーションのもとになると思います」 それこそが宇部の紳士服店で暗黒の 10 年間を過ごした末に柳井が見つけたユニクロという「解」で実現しようとし続けてきたことだ。居並ぶパナソニックの社員たちに、柳井はこう続けた。 「世の中には待っている人がほとんどなんですよ。世界は変わるだろうと。でもその時にはもう手遅れです。(問われるのは)自らが変われるか。よく経営者とか中堅幹部にいるんですよね、人に変わるよう命令する。でも、自分が変わらなければ、人が変わらない原因を作ります」 時代の変化を傍観するのではなく、今手の中にあるもののはるか先にあるもの、周囲からは「アホじゃないか」と思われるくらいのことを考え、行動に移せ──。
センスは知識からはじまる

よきセンスをもつには、知識を蓄え、過去に学ぶことが大切です。同時にセンスとは、時代の一歩先を読む能力も指します。はるか遠い未来に飛んでしまっては、消費者は未知のものへの恐怖や違和感を覚え、ついてきてくれないと述べました。アウトプットそのものは時代の半歩先であるべきです。しかし、半歩先のアウトプットをつくり出すためには、一歩先、二歩先を読むセンスがなければならないのです。過去を知って知識を蓄えることと、未来を読んで予測することは、一見すると矛盾しているように感じます。しかし、僕の中でこの二つは明確につながっています。 知識にもとづいて予測することが、センスだと考えているのです。
The Pathless Path: Imagining a New Story For Work and Life

Eleanor Roosevelt once argued that “when you adopt the standards and the values of someone else or a community… you surrender your own integrity. You become, to the extent of your surrender, less of a human being.” I learned this slowly, jumping from job to job doing the same thing that Durant was doing, trying to achieve someone else’s goals. For years I believed that once I had achieved an imaginary future leadership position, I would then finally be able to be myself. This is an obvious delusion, but one many people tell themselves.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
