
最近読んだ本(1・2・3月編)
早いもので、今年もすでに3ヶ月が過ぎてしまいました。高城氏のメルマガでの回答を受け、本を読みながら放浪しているわけですが、備忘録も兼ねて、(おそらく)Q1で読んだ(であろう)本とハイライトの一部を紹介したいと思います。
いいじゃないですか、「しばらく海外放浪」。
思う時に思うままに旅しながら、いままでの人生なんか振り返らずに、日々を楽しんで、気がつくと未来に没頭する。
そんな日々を送ってみましょうよ。
このような時期は、一生通じて何度も訪れるものではありません。
つまり、いま人生を変える大チャンスがやってきました!
そこで、僕からアドバイスをひとつだけ。
持てるだけの書籍を持って(KIndleと自炊)、いまこそ年間1000冊読破しましょう!
この旅の際、「収入源」なんて考えてはいけません。
それは、いまから過去に培われてきた知識の還金に過ぎず、そんな時間あるなら、未来のために一冊でも多くの本を読みましょう。
時間は、誰もが持つ平等かつ最大の財産です。
どうか未来につながる素晴らしい時を!
合計:23冊
Ejaculate Responsibly: A Whole New Way to Think About Abortion

We’ve put the burden of pregnancy prevention on the person who is fertile for 24 hours a month, instead of the person who is fertile 24 hours a day, every day of their life.
脳と森から学ぶ日本の未来
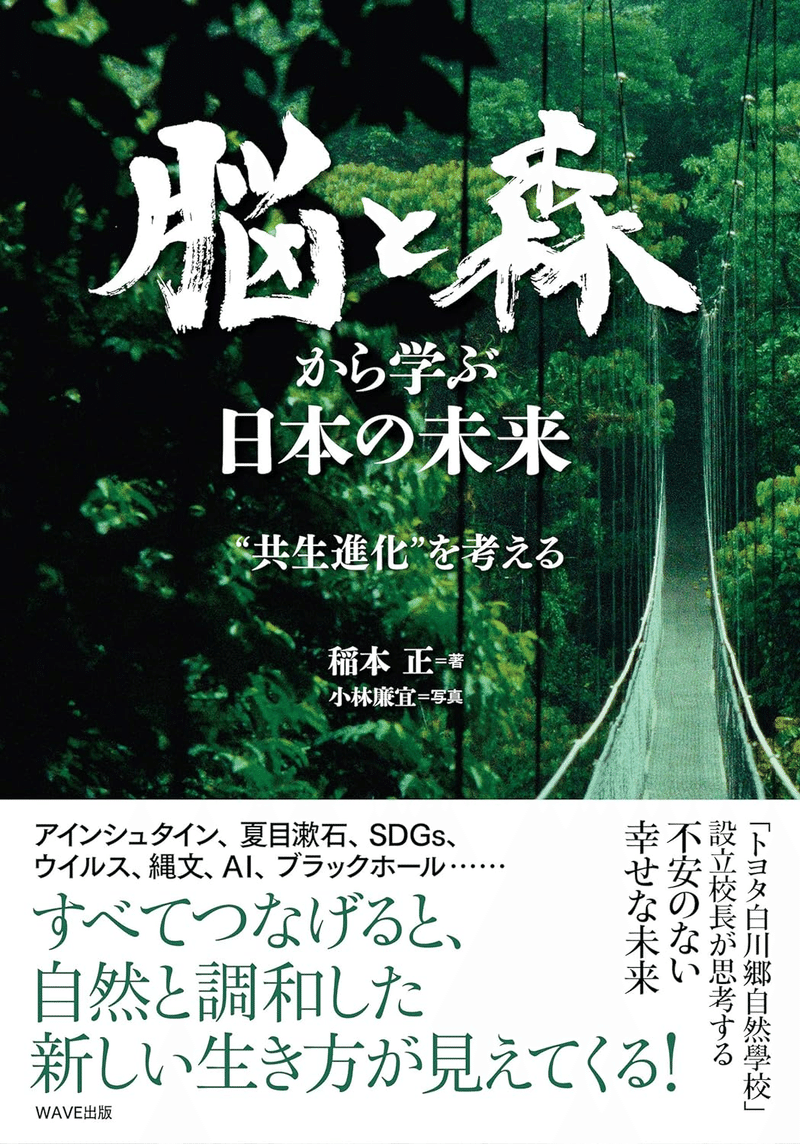
そもそも日本は、縄文時代の「狩猟採集+菜園式農林社会」が1万年も続いたため、それが日本人の身体と精神の底の底まで染み込んでいる。ひょっとしたら遺伝子的にも少しは変化を及ぼしたかもしれない。その後の「農耕社会」も3000年近く続いた。二つの時代を合わせて1万3000年以上は、四季折々の自然に左右される社会構造で、それは日本人の精神構造までをも形づくった。だから、未だに「今日はいい天気ですね」とか「何か肌寒いですね」などと、自然の変化を挨拶がわりに口にする事が多い。
Read Write Own: Building the Next Era of the Internet

So yes, blockchains create networks, but unlike other network architectures—and here’s the key point—they have more desirable outcomes. They can incentivize innovation, reduce taxes on creators, and let the people who contribute to the networks share in decision making and upside.
共感革命 社交する人類の進化と未来

資産とは不動産でも動産でもなく、未来の可能性だと考える人が増え始めてきた。今、資産とは何かといえば、信頼し合える人的資産かもしれない。世界中に信頼する友だちを持てれば、子どもたちはその人たちを頼りにして、自らの未来を切り拓くことができる。これはお金で買えるものではない。そういうものを残していくのが、最も子どもたちのためになると考える大人も増えるだろう。人びとの意識は、ドラスティックに変化していくのではないか。
表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬

ぼくは革命博物館で涙を流さなかったし、今の生き方も考え方も変えるつもりはなかった。だけど、ぼくはきっと命を「延ばしている」人間の目をしていて、彼らは命を「使っている」目をしていた。 ゲバラやカストロの「命の使い方」を想像した。 日本で生きるぼくの命のイメージは「平均寿命まで、平均よりなるべく楽しく生きる」ことなのではないかと、そんなことを初めて考えた。いや、そうやって生きられるのは成熟した社会ならではのことで、そういった国を作ってくれた先輩たちには感謝してもしきれない。 ゲリラ戦で命を懸けて戦って、革命を成し遂げた男たちに引け目を感じる必要はない。だけど、ぼくは革命博物館で「命を使いたい」と思った。それぐらい、彼らの生には私欲を超えている者特有の輝きがあった。
採用基準

リーダーがなすべきことは 目標を掲げる、 先頭を走る、 決める、 伝える、の四つに収束します。シンプルに見えて、とても重要なことばかりです。 逆に言えば、決断をしない人はリーダーではありません。伝える努力をしない人も、先頭を走る覚悟のない人も、成果目標を掲げて見せてくれない人もリーダーとは言えないということです。調査する、勉強する、考えるなどの行為は、どれほどの時間と熱意をかけてそれらに取り組んでも、それでリーダーの役割を果たしているとは言えません。「後ろから部下を見守っている」のもリーダーではありません。 目標を掲げ、先頭に立って進み、行く道の要所要所で決断を下し、常にメンバーに語り続ける、これがリーダーに求められている四つのタスクなのです。
Million Dollar Weekend: The Surprisingly Simple Way to Launch a 7-Figure Business in 48 Hours

A good wave isn’t about being cool; it’s about having customers. What I’m saying here is that your job is not to create demand for something that seems exciting, it’s to find existing demand and satisfy it.
コンテンツ・ボーダーレス

このような現象についてアメリカなど海外の社会学者たちは、コンテンツを消費するという概念はもう古い、つまり 消費者にとってコンテンツはライフスタイルの中の同伴者(companion) である と強調しています。それもそのはず。朝起きて出勤時間はもちろん、家に帰ってきてからも、私たちはコンテンツと共に過ごしています。
世界の賢人と語る「資本主義の先」

─新自由主義への巻き返しが世界で起きている。新自由主義は終わったのか。 「いや、これからの変化はもっと激しいものになるだろう。金融の完全な自由化に必要だったイデオロギーが新自由主義であり、これが二〇〇八年の金融危機を招いたわけだが、私の見方では、資本主義はこの危機から完全には回復していない。今世界で起きているインフレも、日本が苦しんだデフレも、すべては二〇〇八年の危機の異なる断面に過ぎない。社会主義が一九九一年に死んだように、資本主義の死も二〇〇八年に始まっている。世界は私がデジタル封建主義と呼ぶ、さらに極端な富の集中や、少数企業が持つ技術への隷属に取って代わられつつある。 私や(米経済学者の)スティグリッツのような人たちへの注目が増しているとしたら、人々はいま、一つの時代が終わろうとしていることを深層意識で理解しているからだろう。私が考えるには、これは新自由主義の終わりではなく、資本主義そのものの終わりだ。共産主義者の友人たちの中には『資本主義が死につつあるなら、社会主義の勝利だ』と言う人もいるが、それは間違っている。より恐ろしいものが勝ちつつある。技術的にとても進んだディストピア・バージョンの封建主義だ。 これは特に日本のような国にとっては激しい不安定をもたらすだろう。日本は工業国であり、ものづくりが中心で、物理的な基盤に依存しているからだ。残念ながら、製造業における資本家すら、アマゾンのような企業には従属していくことになるだろう。一握りの多国籍企業に富が集中し、経済全体としての需要は減っていく。日本のような工業国にとっては、マクロ経済の不安定さはさらに高まるだろう」
ロングゲーム 今、自分にとっていちばん意味のあることをするために

ロングゲームの大前提は、「現状の犠牲者にならない」ということだ。今の時点での現実が、この先も永遠に続くわけではない。
ヒューマノクラシー――「人」が中心の組織をつくる

よりイノベーティブになり、また適応力や発想力を高めるためには、組織に新しいDNAを注入し、ヒューマノクラシーの原則の上に組織を築き直す必要がある。既存の仕組みや工程の微調整だけでは、つまり短時間のマインドフルネスのトレーニングや、アジャイルチーム、DX(デジタル・トランスフォーメーション) の試行、表面的なアナリティクスなどだけでは、組織の力を急上昇させることはできない。私たちは、原則に立ち戻る必要があるのだ。
The Molecule of More: How a Single Chemical in Your Brain Drives Love, Sex, and Creativity--and Will Determine the Fate of the Human Race

By spending time in the present, we take in sensory information about the reality we live in, allowing the dopamine system to use that information to develop reward-maximizing plans. The impressions that we absorb have the potential to inspire a flurry of new ideas, enhancing our ability to find new solutions to the problems we face. And that’s a wonderful thing. Creating something new, something that has never been conceived of before is, by definition, surprising. Because it is always new, creation is the most durable of the dopaminergic pleasures.
Hidden Potential: The Science of Achieving Greater Things

Backing up puts us on new terrain—we’re in uncharted territory. We’re taking an unfamiliar path to a destination we’ve never visited, and the summit might not even be visible at the start. To find our way, we need scaffolding in the form of some basic navigational tools. The bad news is that a perfect map won’t exist. The exact route hasn’t been plotted for us—there may not even be a road. We might have to pave our own way, figuring out the route as we go, one turn at a time. The good news is that to start moving, we don’t actually need a map. All we need is a compass to gauge whether we’re heading in the right direction.
マルクス・アウレーリウス 自省録

この私という存在はそれが何であろうと結局ただ肉体と少しばかりの息と内なる 指導理性より成るにすぎない。書物はあきらめよ。これにふけるな。君にはゆるされないことなのだ。そしてすでに死につつある人間として肉をさげすめ。それは凝血と、小さな骨と、神経や静脈や動脈を織りなしたものにすぎないのだ。また息というものもどんなものであるか見るがよい。それは風だ。しかもつねに同じものではなく、時々刻々吐き出され、また吞み下される。第三に指導理性だが、つぎのように考えるがよい。お前は老人だ。これ以上理性を奴隷の状態におくな。利己的な衝動にあやつられるがままにしておくな。また現在与えられているものにたいして不満を持ち、未来に来るべきものにたいして不安をいだくことを許すな。
知的複眼思考法 誰でも持っている創造力のスイッチ

「常識」にどっぷり浸かったものの見かた・考えかたは、「単眼思考」と呼ぶことができます。世間で何度も使い回され、通用しているものの見かたは、まさに、ものごとの一面だけに目を向ける単眼思考です。その時点で自分なりの考えを放棄してしまうと、そこで見落とされたことがらには目が届かないままに終わります。
Elon Musk

All technical managers must have hands-on experience. For example, managers of software teams must spend at least 20% of their time coding. Solar roof managers must spend time on the roofs doing installations. Otherwise, they are like a cavalry leader who can’t ride a horse or a general who can’t use a sword. Comradery is dangerous. It makes it hard for people to challenge each other’s work. There is a tendency to not want to throw a colleague under the bus. That needs to be avoided. It’s OK to be wrong. Just don’t be confident and wrong. Never ask your troops to do something you’re not willing to do. Whenever there are problems to solve, don’t just meet with your managers. Do a skip level, where you meet with the level right below your managers.
厨房の哲学者

何にでもなれる未来なんて、ほんとうはどこにも存在しない。 何にでもなれるのは、何も選んでいないからだ。 どこかに辿り着くためには、道を選ばなきゃいけない。ひとつの道を選んで、その道を歩き続けなければいけない。 僕が恐れていたのは選ぶことだった。 何かを選ぶことは、それ以外のすべてを捨てることだから。選んでしまったら、そこで自分の未来の可能性は閉ざされてしまうと思い込んでいた。 それが間違いだった。 選ばなければ、人生は始まらない。 何ヶ月も中華鍋を洗い続けて、ようやくそのことに気がついた。 そして、僕は中国料理の道を選んだ。
新版 南洲翁遺訓 ビギナーズ 日本の思想

忠孝仁愛教化の道は政事の大本也
The Millionaire Fastlane: Crack the Code to Wealth and Live Rich for a Lifetime

Money isn't attracted to selfish people. It is attracted to businesses that solve problems. It's attracted to people who fill needs and add value. Solve needs massively, and money massively attracts. The amount of money in your life is merely a reflection of the amount of value you have given to others.
約束の日 安倍晋三試論

このような状況にあって、今後のあるべき日本の方向を、勇気をもって、国民に指し示すことこそ、一国のトップリーダーの果たすべき使命であると考えます。私が目指すこの国のかたちは、活力とチャンスと優しさに満ちあふれ、自律の精神を大事にする、世界に開かれた、「美しい国、日本」であります。この「美しい国」の姿を、私は次のように考えます。 一つ目は、文化、伝統、自然、歴史を大切にする国であります。 二つ目は、自由な社会を基本とし、規律を知る、凛とした国であります。 三つ目は、未来へ向かって成長するエネルギーを持ち続ける国であります。 四つ目は、世界に信頼され、尊敬され、愛される、リーダーシップのある国であります。
回避性愛着障害~絆が稀薄な人たち~
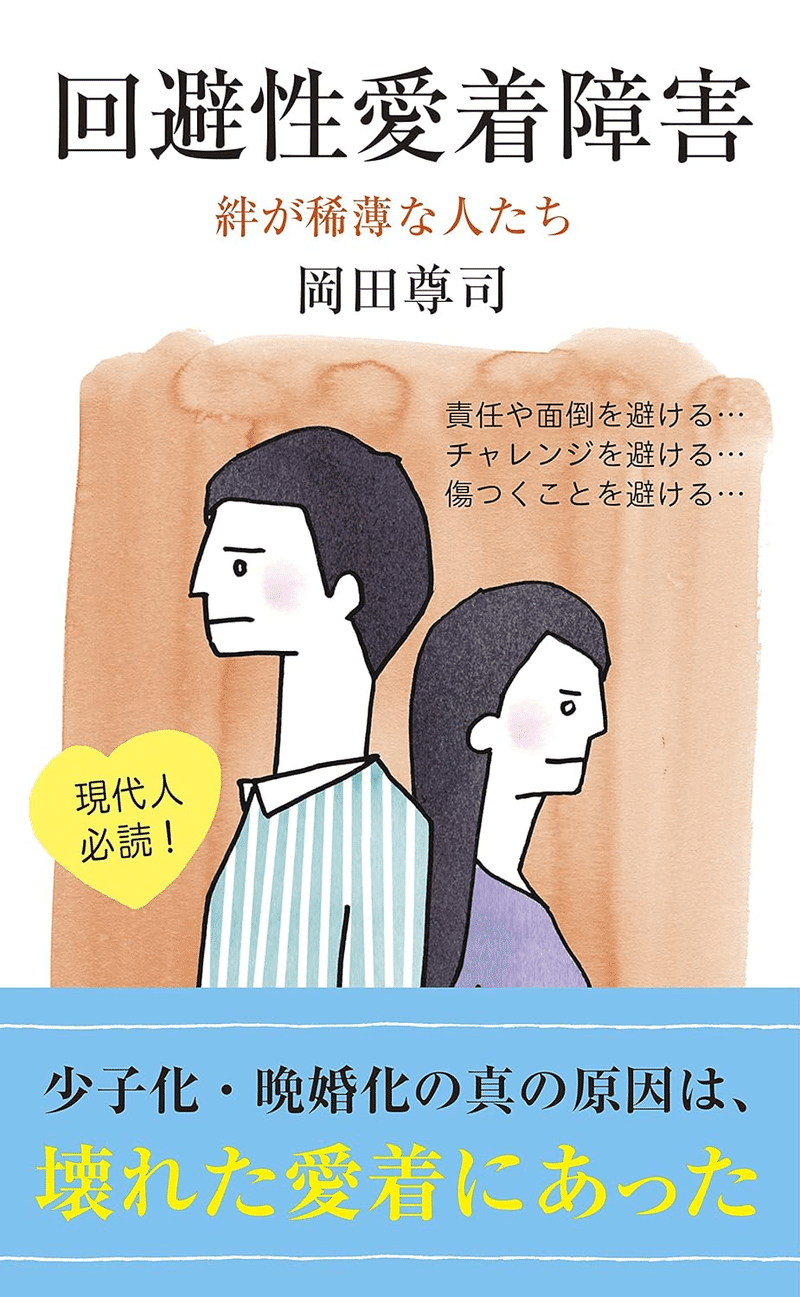
安全基地とは、安心感を回復させてくれる存在である。ひと言で言えば、どんなときであれ、「大丈夫だよ」と言ってくれる存在である。 その基本的なスタンスは、共感的な応答である。相手が求めたときに、相手の気持ちに立って応えるということである。求めているのに無視したり拒否したりすれば、それは安心感を傷つける。また、求めてもいないのに一方的に押しつけたり、お節介な口出しをすれば、安全感や主体性を損なってしまう。本人のペースと意思を尊重することが重要になるのである。 親子やパートナーの間で、安全基地が安全基地でなくなってしまう場合に起きやすいのは、相手を自分の思い通りにしようとすることである。たとえわが子や配偶者であっても、独立した人格をもつ存在として尊重し、主体性を侵害しないように細心の注意を払う必要がある。遠慮のない関係イコール、安全基地というわけではない。相手が、仕方なく合わせているだけで、本音では嫌がったり、迷惑しているという場合もある。「 腫れ物に触るように」という言葉はネガティブな意味で使うことが多いが、むしろそれくらいの慎重さが必要である。実際、愛着に傷を抱える人は、その傷が 化膿 して腫れているようなものであるから、手加減もなく触ったりして、いいわけがない。
Troubled: A Memoir of Foster Care, Family, and Social Class

The chief purpose of luxury beliefs is to indicate the believer’s social class and education. When an affluent person expresses support for defunding the police, drug legalization, open borders, looting, or permissive sexual norms, or uses terms like white privilege, they are engaging in a status display. They are trying to tell you, “I am a member of the upper class.”
散歩哲学 よく歩き、よく考える

今日の日本では「無臭化」が進んでいる。パリやニューヨークに漂う世界標準の悪臭からは程遠く、トイレは消臭機能付きで、ホームレスも排除され、ドブのニオイもせず、乗客も会社員も学生も脱臭に努めている。社会の無臭化には何か不吉な気配が漂う。ニオイは自己主張であり、存在証明であり、抵抗であると捉えれば、無臭は沈黙、服従、管理のメタファーになる。生きているものも死んだものも、この地上にあるものは全て多かれ少なかれ、臭いのだ。臭いものにはむやみに蓋をしてはいけないのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
