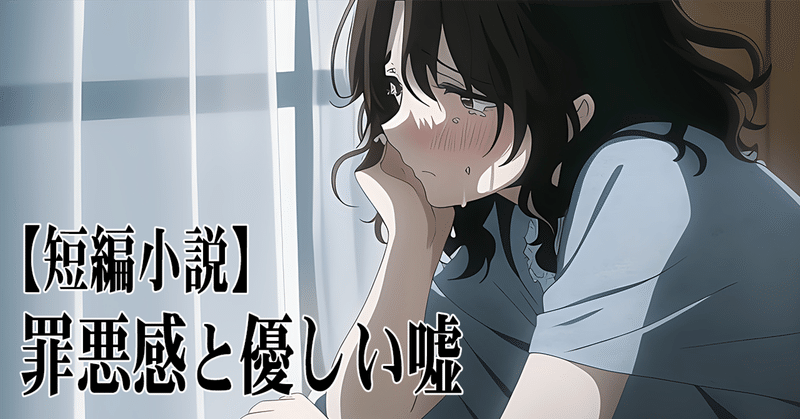
【短編小説】罪悪感と優しい嘘
「人の罪悪感と優しい嘘に、疲れてしまったよ。」
彼が自死を遂げる1ヶ月前、彼の口から聞いた、初めての弱音だった。その言葉とは裏腹に、表情は苦笑を浮かべていた。
社会人になってからは猛烈な忙しさの波に攫われ、気づけば30歳になっていた。私生活で会っていたのは、昨年に結婚した妻がほとんどだった。亡くなった彼とは、学生のときは週1回くらい会っていたが、今では年1回会うくらいのペースになっていた。
1ヶ月前、彼と会ったのは、年末に向けて仕事で佳境を迎えており、久々に休みが取れた日だった。12月にしては、寒すぎる日だった。彼の口から出た弱音は、そこまで重いものではなく、お酒で語り合えば治るものだと思っていた。
どうやら、彼は失恋をしたようだった。だから自分も、仕事でのツラい話や妻に関する悩み事で応戦した。彼が弱音とともに浮かべていた苦笑は嘘のように、微笑みに変わっていた。
散々飲んだあと、すっかり外は漆黒の空に覆われていた。夜の寒さは、酔いで熱くなった体でさえ、凍てつかせた。彼との会話の内容は、途中からちゃんと覚えていないが、他愛のない話に終始したんだと思う。
彼は酔いに身を委ね、恍惚とした表情を浮かべ、「じゃあ、またな」と言っていた。その声色は黄色いものであった。彼から初めて聞いた弱音すら、もうその時は、忘れていた。
その1ヶ月後、彼は自死した。警察から急に電話があり、私は知ることとなった。特に遺書がなかったため、彼の関連する人に事情聴取が行われたようだが、事故状況から、最終的に自死と判断された。
葬式は、彼の親族だけで執り行われた。
胸にぽっかりと穴が空いた虚無感とともに、そのあとは、強い罪悪感に襲われた。自分は、1ヶ月前、彼に追い詰めることを言ってしまったのではないか。
「人の罪悪感と優しい嘘に、疲れてしまったよ。」
急に思い出すあの言葉。一体、意味はなんだったのか。でも、考えても考えても答えは思いつかず、遺書なき彼の骸からは答えを聞くこともできなかった。
大学のときに聞いた彼の話によると、彼の父親は早くに病気で亡くしていた。その分、母親から強い愛を受けて育ち、彼は日々感謝をしていた。
そうしたこともあってか、彼の母親は、彼の自死で心に深い傷を負い、塞ぎこんでしまったようであった。
きっと自分とは比べ物にならない、罪悪感と虚無感に襲われたのだろう。
でも、彼の死によって日常は止まらず、無情にも明日は今日になっていた。日に日に、自分の頭から記憶は薄れていき、心からも罪悪感が消えていった。
そして気づけば、季節は8月のお盆になっていた。
燦々とした日射を浴びながら、自分は彼の墓に向かっていた。
なぜなら、彼から、昨日メールを受け取ったからだ。決して、天国から届いてきたメールではない。彼は自分と飲んだあの日、このお盆の日に合わせてメールの送信予約していたのだった。
◇
そろそろ、君の罪悪感が消えてきた頃だと思う。だから、君に感謝のメールを送ることにする。
一緒に飲んだあの日、俺は、付き合ってた彼女との失恋の話をしたよね。
「ごめんね。君が悪いわけじゃなくて罪悪感が大きいんだけど、別れたいんだ。」
俺は彼女から聞いた言葉を聞いたとき、自分の心に痛みを感じなかったんだ。だって、罪悪感と優しい嘘は、何十回も聞いたから。
俺は人生で、真面目に生きすぎたんだと思う。だから、周りから気を遣われて、本音を言ってもらえなかった。俺が傷つかないように、みんなから優しい嘘が重ねられてきたんだと思う。
あと、罪悪感という言葉を何回も聞いたけど、あれは相手に申し訳ないと思って浮かべる感情じゃないんだ。自分は加害者ではないと思い込もうとするための、自分を守るための言葉なんだ。
そんな中、君だけが、ずっと俺に本音を言ってくれた。言い続けてくれた。
でも、君にも君の人生がある。俺は、もう君に頼り続けられない。だから、一緒に飲む日はこれで最後だと決めた。
君は、あの日、奥さんの不倫で悩んでいた話をしてたよね。君も、優しい嘘と罪悪感を重ねられているんだと思う。
ただ、君は俺と違って、心の痛みを強く感じていた。
きっと、心の痛みを感じることは、生きている証なんだと思う。だから、心が痛むうちに、君だけには我慢せずに、君の人生を取り戻してほしい。
あと、最後にこれだけは言っておかないと。君がいなかったら、俺はここまで生きることができなかった。
本当にありがとう。君は俺にとって、最高の友人だったよ。
◇
お盆であるその日も仕事に追われていたけど、自分の足は、おもむろに彼の墓に向かっていた。汗まみれで彼の墓に到着したとき、自分より先に墓の前で座り込み、泣いている人がいた。彼の母親だった。
「息子のこと、本当にありがとうございました。」
彼の母親からの第一声だった。決して、待ち合わせをしていたわけじゃない。でも、その瞬間わかった。彼の母親もまた、彼のメールでここに導かれてきたんだと。
その日、彼の母親と喫茶店で長話をした。最初は、無言が続いたけど、時間が経ってからは、彼の母親は涙とともに、言葉が止まらなかった。何か堰き止められていたものが、決壊したのだろう。
彼は、自死の半年前から心身が不安定になり、仕事ができない状況になって、実家で過ごしていたそうだ。無表情で家から出ない日が多かったようだが、自分と会ったその日だけは、生気が戻っていたのだと。
彼が死んだのも、優しい嘘だったら、どれだけ良かったことか。でも、生から死は一方通行で非可逆的だ。
きっと、今までの自分だったら、罪悪感という自分を守るための感情を浮かべていたことだろう。でも、彼の言葉を借りれば、罪悪感を馳せても彼のためにはならない。
そして、1ヶ月後。
自分は、妻と不倫に関する話し合いをした後、離婚することにした。最後まで妻の口から出る優しい嘘と罪悪感に心が痛んだけど、もう無理に我慢するのはやめようと心に決めていた。
季節はまた巡り、12月になっていた。今日もまた、あの日のように寒かった。
川のほとりを歩きながら、彼のことや妻のことを思い出していた。やっぱり思い出すだけで、まだ心が痛い。これまでは、この痛みが自分の首を絞めるものだと思い込み、生きることが嫌になることもあった。でも今は、その痛みを感じることで、自分が生きている感覚を噛み締めていた。
急に川から、ぴちゃっと音が鳴った。何かと思い、そちらを向いた。1羽の白鳥が、華麗に羽を広げ、飛び立って行った。
(あとがき)
はじめて、小説を執筆しました。拙い内容ですが、ご覧いただき、ありがとうございました。
本作品は、私自身の実体験とフィクションを合わせたものとなっています。テーマは重めですが、前向きなメッセージを込めました。
本作品は、京都の鴨川沿いの喫茶店で執筆しており、ラストシーンは鴨川をイメージして書いていました。
いつもはエッセイの投稿をしていますが、マイペースに、短編小説も投稿したいと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
