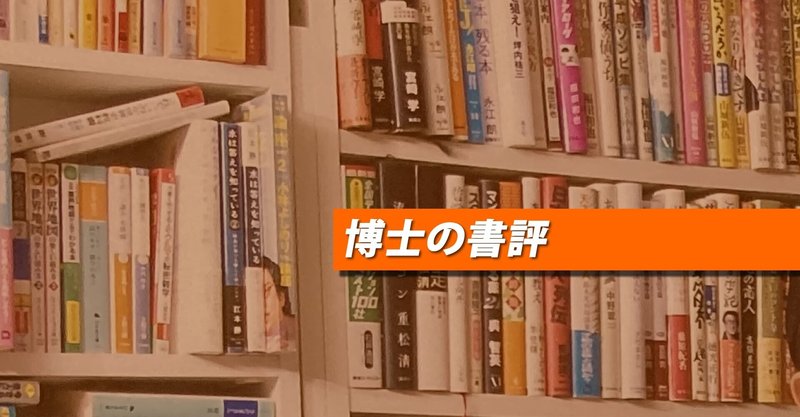
「2012年の町山智浩」〜『アメリカは今日もステロイドを打つ』文庫解説より
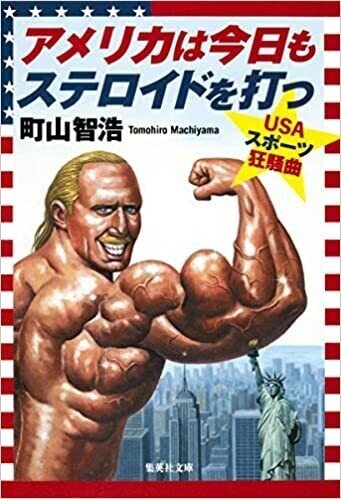
(集英社 2012/7/20刊)の文庫解説より抜粋。
ご承知の通り、この本の著者、町山智浩さんはスポーツライターではない。
在米の映画評論家である。
毎年、年末に町山さんの選ぶ年間ベスト10は日本のボンクラ映画ファンに注目されている。
さて、その町山さんの選ぶ2011年ベスト1の映画は『宇宙人ポール』であった。
この映画を日本で最初に上映したのは、2011年9月に開催された『浅草下町コメディ映画祭』だ。
このイベントで町山さんは我々、浅草キッドを従え舞台で映画解説トークショーを開催した。
物語はイギリス人おたく二人がアメリカでエイリアンと遭遇する筋だが、SF映画へのオマージュが散りばめられたコメディでもある。
「スピルバーグ映画に憧れ、オジさんになってアメリカに渡ってハリウッドが描いた映画の世界とは全く違う本当のアメリカを見てびっくりする、という主人公は実はアメリカ人にとってエイリアンであるオイラ自身なんだよ……」

と町山さんは真面目に語っていくのだが、しかし、壇上では漫才師のボクたちがサングラス、黒スーツのMIBスタイル。
そして、その間に挟まれた町山さんは下半身のポールもっこりの全身タイツ姿、つまり〝捕まった宇宙人〟のイデタチなのだ。
かように〝おふざけ〟がないと〝ごもっとも〟なことを人前で語れない、常にポールに〝バカ〟の筋が通っている人なのだ。
それは、僕が町山さんと三年間共演した昼間のTBSの『キラ☆キラ』のラジオコラムでも同じく生放送だと言うのに、毎週、国際電話越しに直球のエロワードをボンボン投げ込んでくるのを常とした。
よって、この名物コラムの町山さんの呼び込みのキャッチフレーズは「映画とエロの伝道師」であったが、途中から「年頃の娘が聴いているのから変えて…」と町山さんから泣きが入り「映画とエロスの伝道師」と一文字加え、エロス=性愛を語る神、つまり”神様”に昇格させる折衷案で決着した。
今やサブカル・ネット界でも「最新型の権威」(@樋口毅宏)と認識されるほどに「神」格化した町山さんだが、もともと僕がその存在を知ったのは80年代の通称『バカ町山』時代であった。
早大卒業後入社した宝島社の新米社員時代、担当だったみうらじゅんさんから「バカの町山」と命名され名物編集者として、裏方ながら、よく誌面に登場していた。
そんな元「バカの町山」さんが、ある事件をきっかけに宝島からアメリカ大陸に渡ったのは1997年のことだ。
渡米後も自身が立ち上げた『映画秘宝』への寄稿を続け「映画ライター」を名乗っていたが、その後、2002年に『映画の見方がわかる本』(洋泉社)を上梓。
その後は「映画解説者」の肩書を名乗るようになる。
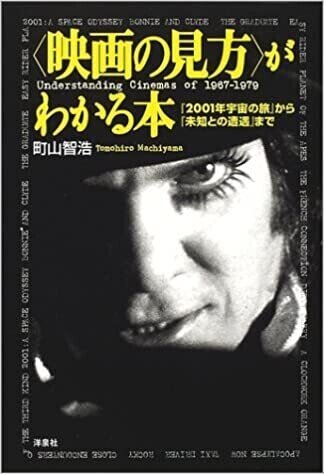
(この当たりの肩書き、プロ意識への矜持は町山さんの強いこだわりがあると思う)
その後、在米10年を超えて、アメリカンサブカルチャーの紹介、観察、分析のエッセーを各紙で量産、このジャンルは、もはや町山智浩の独壇場となっている。
アメリカの政治システムや産業構造や社会の歪みを小難しく語る人は今まで多々いただろうが、我々が日常に接する映画やテレビ、ゴシップ、文化の裏側、所謂、サブカルチャーの視点で、ここまで軽やかに、そして下世話に紹介する書き手は今までいなかった。
特に2008年後半から2009年にかけて「バカのアメリカ」を抉り出す、単行本は共著一冊を含め5ヶ月で5冊!の固め打ちで上梓した。
まるでソーサとマグワイアーか、バリー・ボンズか、彼らの疑惑のホームランのようなハイペースだった。
『アメリカ人の半分はニューヨークの場所を知らない 』(文藝春秋)
『キャプテン・アメリカはなぜ死んだか 超大国の悪夢と夢』(太田出版)
『新版 底抜け合衆国 アメリカが最もバカだった4年間』(洋泉社)
『アメリカは今日もステロイドを打つ USAスポーツ狂騒曲』(集英社)
本書は、この町山版〝アホでマヌケなアメリカ白人〟4部作とでもいうべきシリーズのスポーツ編と言えばいいだろう。
その文庫版である。
あの矢継ぎ早の量産時期は、ようやく2期満了を迎えつつあったジョージ・W・ブッシュ政権末期に重なり、日本にも遅まきながらに芽生えたブッシュ政権への厭戦感と猜疑心に、町山さんの多産の供給がその鬱憤を晴らしとして応えていった。
僕は、この頃のコラムの熱烈な読者であり、当時、出版界だけでなく、もっとテレビ界にも町山さんを世に知らしめたいと画策した。
それは『町山智浩サブカル版・池上彰化計画』と題して実行された。
まず、僕が司会するネット番組『博士も知らないニッポンのウラ』で、町山さんにゲスト出演して頂いた。
その際、この本のなかでも紹介されている「日本で公開されていないドキュメンタリー映画が見たい!」と嘆願し、この企画が東京MXテレビで『松嶋×町山 未公開映画を観るTV』と題して開始した。
そして、この本の「まえがき」で語られる『もっとデカく!強く!速く!』や『サーフワイズ』がTVで本邦初公開され、上記4冊のなかで紹介されている未公開映画の数々も放送された。
そして、2011年1月18日に渋谷で開催された『未公開映画祭』では、番組のファンを自称する長州力さんを、ブッキングして急遽参戦したのは、まさに掟破りの異種格闘技戦であった。
あの長州力がプロレス界から映画界の38度線を「またぐ」とは、誰が想像出来るだろう?
そう言えば、異ジャンル交流と言えば、文春の『アメリカ人の半分は…』の単行本の帯文を僕が書かせてもらった。
「殿に今、一番面白い評論家は誰だ?」と聞かれた。
「俺は自信たっぷりに『町山智浩です!』と答えた。
もし疑うなら、この本を読んで欲しい!!」
と帯分を書いたのだが、その直後に殿に「この町山さんに会おう!」と言われ銀座の高級フランス料理店をセッティング一緒にお食事した。
「流石にTシャツじゃ、まずいでしょ」と、町山さんが、わざわざ直前にYシャツと背広を買いに行ったことや、殿が「町山さんってなんでアメリカに行ったの?」と尋ねると「あの…ボク、たけしさんを真似て出版社を襲撃したんです!」と答えたのも大笑いだった。
そして「町山さんの淀川長治スタイルの映画解説が聞きたい!」という、更なる僕の願望も今やWOWOWで実現、その解説が恒久的にネットでも見ることが出来るのだ。
『もっとデカく!強く!速く!』ではないが「もっと!もっと!町山解説を!」と僕が描いた計画は、日本で次々に実現していった。
本の解説に戻ろう。
本書は、どの一篇も4ページと短いが、どれも映画一本分のドラマ性を持ちながらも「おバカなアメリカ」をスポーツの側面から捉えた実例集、ガイドブックに「過ぎない」のが特徴だ。
だから、小難しい論評も分析もない。淡々と掌編が続く。
人生の悲惨な話、全米に根深く残る差別、間抜けすぎる現実、が次から次へと。決して陰惨にもならない。倒置法の多い翻訳調、読点の多い短文調を駆使して町山さんは調べ上げた事実を紡いでいく。
必要以上に「だからアメリカは!」なんて講釈を付加しない。
常に冷笑的であり微温的だ。
それが逆に読者は自分の力でアメリカの病巣を抉った気分になり、悪悟りを産む。
白黒の抽象にとどまっていた批判がカラー映画になった気がするほどだ。
それは皮相なアメリカ批判も、大きく、強く、早合点に増長する。
すぐにでも受け売りしたくなる。
明日にでも飲み屋でどれか一編でも講釈して、どうだ知らなかっただろうと、アメリカ批判を気取りたくなる。
この本を読んだ副作用は読者の受け売り症候群だろうとさえ思えるほどに。
世界中が注視する巨大な産業でもあるアメリカのスポーツを描いたエッセィとしても、のっけから視点が異色でありアイロリーに満ちている。
なにしろ、第1章から、初めの3話でアメリカンスポーツに夢見る読者を谷底へ突き落とす。
大学生、高校生、小学生のアマチュアアスリートの夢と希望を木っ端微塵に粉砕する。
ステロイドの副作用による自殺未遂。プロになることの狭き門。そして全米のプロスポーツ人口は、たったの2400人という事実!!
翻ってマイクロソフトは一社で一万人の雇用があると諭す。
そして、アマチュア選手の70%は高校卒業までに辞めてしまう現実。
スポーツ選手への過度な期待は親の夢を背負わせられてるだけだと。
スタローンがシュワちゃんがホーガンがボンズが免罪符となり、ステロイドの使用率の85%は実はアマチュアだという現実。
誰もが憧れるアメリカン・ドリームそのものである、スポーツの光と闇、いや、むしろ暗闇、陥穽そのものを淡々と教えてくれる。
町山さんは、彼らが栄光と共に手に入れてしまう常人離れした怪奇な生き方にスポットを当てる。
本書ではガチンコスポーツであるはずの、MLBやアメフトにステロイド八百長が蔓延したり、元々ソープオペラに過ぎないはずのプロレスが、その人間模様、筋書きを越えたガチンコの破滅的人生に辿り着く宿命を暴く。
新日常連外人であったクリス・ベノワは何故、非業の死を遂げたのか?
僕も日本のマットで、その活躍した勇姿を知るだけに読み進めるうちに、しばし、ため息と共に本を閉じ想いを馳せた。(また一方で、あのテッド・デビアスがミリオンダラーマンの後に牧師に転じているとは…)
元・大リーガーのホセ・カンセコも、その後、格闘家に転身しK-1に出場したが、この本の挿話を思い出し、僕は彼の股間のバットの大きさ、規格外の勃起角を凝視し、そこから別れた妻や彼女の父親のエピソードまで妄想が隆起した。
そして、日本でも〝一番〟おなじみのプロレスラー、ハルク・ホーガンのその後は興味深い。
リングを降りてもリアリティショーの中で、ハルク・ホーガン一家が常に脚本に動かされていたマット界でも演じて来なかったような想像を絶するリアル家庭崩壊へとダッチロールに突き進んでいく。
ガチとドラマが倒錯をきたし、今、なお終わらないドラマとして現在進行形で継続している。(興味のある方は是非、検索して欲しい、この本で語られるホーガン一家のドラマは、まだ序章に過ぎないだから…)
しかし、そのアメリカの象徴たる一家の倒錯が世界の警察を名乗りながら、言い掛かりの戦争をし、世界一の繁栄をしながらサブプライム住宅ローンで偽りの繁栄を謳歌していたアメリカそのものと同じようなものだと、文章から国家が浮かび上がる。
町山さんの皮相的にならない切り刻み式の映画解体評論で鍛えてきた観察眼が、社会自体が劇場化したアメリカの現実社会を映画評論してくれる。 「アメリカについてしか知らない人はアメリカについて何も知らない」
という格言があるように比較文化論の要諦は互いの文化圏で、実際に生活することだろう。
本書の連載が開始された2005年頃は、町山さんはカリフォルニア州のベイサイドに住んでいたが、そこはオークランド、全米屈指の治安の悪い地域だった。
その後、町山夫人が強盗に襲われるなどして2007年からは現在まで在住している隣町のバークレイに移っている。
しかし、そこでも地元紙のスポーツ面で集団自殺事件を起こしたカルト教団、人民寺院の教組の息子が今は高校でバスケをし地区優勝に導く活躍してる記事を目にする話は、本書でも語られた通りだ。
アメリカの隅々にホームラン級のネタが転がっている。
それは、まるでアメリカという巨大な球場を渡り歩きながら、コラムというボールを集めるマニアックな「スナッグ」を彷彿させる。
アメリカに住んでるだけでネタに困らない。
しかも、引きこもり取材で記事を済まそうとする日本の評論家は、いつでも一蹴できる。
「アメリカでは…」と語りだす自称・事情通も多いが大衆が知らないことをいいことに、相互監視が機能しないところに嘘やデタラメがはびこることを知っている。
町山さんの場合、とにかくラジオコラムでも「僕、実際この人に会ったんですが…」と前置きして話をすすめることが多い。
本書では、カナダの英雄、NHL伝説の男、ウェイン・グレツキーに通訳として会った時の挿話などが明かされ、しかも「イチローに会わせてくれよ」なんて言葉をグレツキーから引き出すところも肝だ。
かように町山さんは現場主義を貫く。
そしてスポーツを題材にしながらも常に軽蔑するものは決まっている。
戦争であり、民族主義であり、大衆を見下す権威であり、政治とメディアが結託した嘘っぱちである。
そういうものと結託する輩を決して許さない。
手品師がミスディレクションするように人々が一つのものの見方に目を奪われてる時こそ裏の見方、別の視点を探る。
それが町山さんの真骨頂なのだ。
第6章の「多民族国家のバトルロイヤル」での、スコット・フジタや、ハインズ・ウォードの苦難の人生、知的障害者のスペシャルオリンピックスに潜入する映画『ザ・リンガー』へ町山さんが注ぐ眼差しは暖かい。
続く第7章は、この本の白眉、町山版「敗れざるものたち」だ。
僕にとっては、この章に書かれた話を初出誌を切り抜いて保存していたほど印象深い。
「『ミリオンダラー・ベービィ』を書いたカットマン」の話は、このままイーストウッドが再び映画化しても良いと思えるほどに琴線に触れる。
そして、パラリンピック女子スキー殿堂入りのダイアナ・ゴールデン!
半身不随、四股欠損のアスリートの偉大な生涯が描かれる。
実際、お笑い芸人として、この章は示唆に富む。
人種問題、障害者問題。タブーのオンパレードであるが、ただのお涙頂戴の感動物語にすることはない。見事に両義的、健常者と障害者のアンビバレントな感情を揺り動かす「ネタ」になっている。
そして、最後に語られるのはスターレスラーになりながらも、耳から膝から心臓まで満身創痍のまま血だるまでギャラ2万円で戦い続ける50過ぎのレスラーを描いた映画『レスラー』の話。
この映画を演じるのは、実際に破産し、妻を殴り逮捕、家賃五万円のアパートに住む、かつてのハリウッドスターのミッキーローク。

この本は夢の国アメリカの挑戦権が等しく与えられる「栄光前からの挫折」で始まり、「栄光後の挫折」をラストに置く、対構成にして終わる。
実は、この映画は同年のベネチア映画祭の金獅子賞作品でもあり2008年の町山智浩のベスト1である。
そう言えば、この映画を語る時も町山さんは主役のミッキー・ロークに自分に重ねあわせていた。
セックスシンボルとまで称されたミッキー・ロークがボクサーに突如転向、映画界に戻る場所もなく家も、財産も、奥さんもすべてを失ったかのような、丁度、その頃。1996年、町山さんも宝島社からの左遷先、洋泉社で立ち上げた映画雑誌『映画秘宝』の編集長時代、業界の老舗『キネマ旬報』の挑発に乗り事件を起こし映画界を去った。
文字通り”バカ”なことをしたのだ。
これこそが、前述の「たけしさんを真似て出版社を攻撃」した伝説の「ビートたけしフライデー編集部襲撃事件」のパロディ事件だ。
ただし、ビートたけし一行はフライデー事件で消化器を用いたが、泡違い、町山さんはシェービングクリームテンコ盛りパイで相手編集長に顔射の奇襲攻撃をやってのけたのだ。
町山さんは洒落っ気たっぷり、プロレスをしたつもりだったが、相手や会社はシュートと受け取った。言論ではなく武力行使で仕返してしまった。
この専守防衛の掟を破った責任を取り退社し、そして35歳の時、アメリカの大学院に留学する妻に付き添い渡米するも本人は、無職のまま。
その後、IT企業の再就職を果たした妻の稼ぎに生活費は頼り、幼い一人娘の育児を任され主夫生活も体験する。
つまり不逞無頼の日々を送った……。
その雌伏の時間を経て、町山智浩はリターンした。
この時間が今の町山さんの文章の肝とも思える、強さとやさしさ、さらに言えば、論的の技を受けきるファイトスタイルを作ったのであろう。
町山さんに筋肉増強剤はいらない。
ナチュラルの知の強さがある。
あまりにも頭の良すぎる文化系不良であり、見せる筋肉に価値を置かない。(ムキムキになることはなくてもムキにはなるが……。)
あの時のことに触れ、町山さんは語っていた、
「ミッキーロークはオイラ自身なんですよ!」
そう、あの編集部でパイを投げた瞬間は無謀にもトップロープからダイブするランディそのものだ。
でもロークと違ったのは奥さんは逃げなかったこと。
そして娘も共にいた。
映画とエロの伝道師は、映画とロークの体現者となったのだ。
今年、ゴールデングローブ賞では紋付袴姿の町山さんがレポーターとしてレッドカーペットを歩いていた。
WOWOWのアカデミー賞の生中継では裏方として、俳優、監督、ハリウッド関係者の顔を瞬時に見分ける芸当で中継の司令塔役も務め上げた。
しかし、何時か我らが町山さん自身にピンスポットが当たるであろう。
評論か、文芸か、あるいは映画か、大いなる晴れ舞台に立つ日も近いだろうと夢想する。
それは『宇宙人ポール』でコミコン(アメリカのコミケ)のボンクラ同人作家レベルだったオタクの主人公たちが、2年後、宇宙人小説で成功し大出世を遂げ、今度はメインゲストとしてトークショーに登壇する大団円のラストのように。
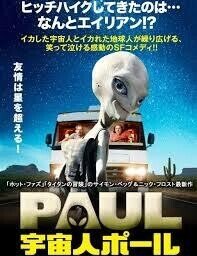
そして町山さん!
その時は壇上で思いっきり、しょうもないシモネタをかましてくれ!!
サポートありがとうございます。 執筆活動の糧にして頑張ります!
