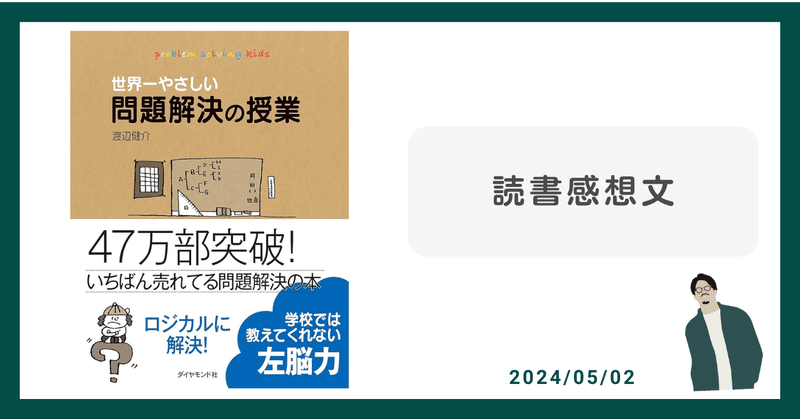
読書感想文「世界一やさしい問題解決の授業」
こんにちは!
じっくり読み込む事もあれば、ググるように要所要所でスピーディーに読む事も…
いろいろな読書スタイルはあれど、inputをしたら何かしらoutputを、という事で読書感想文シリーズです。
本のサマリではなく、あくまで「今の自分が読んで感じた事や、重要だと思った事」に絞ってメモメモしていきます。
読んだ本
それでは、レッツ読書 & メモ!
どんな本?
今回読んだのは、渡辺健介さんの「世界一やさしい問題解決の授業」です。
平易な言葉と子供でも分かる具体例で、「問題解決とはどういう事か?」「どのように問題解決を行えば良いか?」を解説してくれる本です。
ロジックツリーの作り方や、4象限でのプロット、具体的なアクションへの落とし方など。オーソドックスなフレームワークもあえて小難しい言葉を使わず、子供が理解できるよう表現を工夫されている印象です。
子供向けに易しく基本のキだけ抽出した内容だからこそ、「最低限ここを意識すべし」という超基本が凝縮された本。と個人的には捉えています。
何か壁にぶち当たっていたり、物事が上手くいかない時って…基本を忘れていたり、本質から外れていたりする事が多いです。そんな時に、基本に立ち返るためにサク読みすると良い本です。
なんで読んだ?
以前、けんすうさんがnoteで紹介していて購入し、そのまま放置になっていました。(自分が見たのはXの投稿だったかも)
過去購入本や最近買った本を整理する中で、まずは一番サクっと読めそうな本書から始めた感じです。
この本をあえて買った/読んだ理由としては、いわゆるロジカルシンキングとか、課題解決的な思考を、超簡単にすると何を抽出してどう表現するんだろう?にすごく興味があったからです。
部下や子供に教える人にとって、こういう平易な表現の本があると、すごく役立つと思います。
感想メモ
ここから、本の要約ではなく、自分が気になった部分や感想など、超偏ってピックアップしていきます。
問題解決思考は進化スピードを早める
意外と抜けていて「たしかに」と思った話。そもそも問題解決的な思考ってなんで必要なんだっけ?
仕事でより高い価値を発揮するため、部活の練習効率を上げるため、いろいろ理由はあると思いますが、本書では問題解決キッズと「否定型」「評論家型」「気合と根性型」を比較し、進化度合いとスピードが大きく違うよ!という話を、冒頭にしています。
これ結構本質だなと思いました。やりたい事の実現や、超えたい壁を超えていく方法って、自分が必要な度合い・スピードまで自律的に進化し、それを継続する以外、ほぼないと思います。「自分は成長せず誰かに頼り続ける」も限界ありますしね。
というわけで、「なんで問題解決思考が必要か?」「そもそもなんで読書やinputするのか?」という大元を考えると、自律的に速く進化するためだよなぁ。という事を気付かされました。
検証とは、仮説が正しいか確かめること
これも基本のキですが、超重要な考え方です。
なんでも調べられる時代、片っ端からググったりGPTさんに聞こうとしてしまったり。(そういう調べ方が必要な時も、もちろんあります)
小澤さんもPodcastで言ってましたが↓
まずは仮説を立てて、それがどれ位正しいか?を確認するのが理想の調査です。本書ではそれが「検証」だと説きます。
そして、本に出てくる中学生の、仮説の一部は大きく外れます。個人的にはこれがめっちゃ重要だと思っていまして。
「検証」や「仮説立て」ってのは、正解するためにやるわけではないんですね。無意識にそういうバイアスになってしまうのは、正解探し色の強い日本の義務教育の弊害かなぁと思ったり。。。
個人的には「仮説が違った」という発見とそのプロセスが超重要だと思います。なぜなら、自社や自チームの認識と事実のGAPが可視化されたという事で、この発見からの軌道修正→アクションへの落とし込みが、強力な一手になる可能性が高いです。
本書でも「仮説と違った事実」から中学生質が対策を立て、見事に問題解決を成しています。
まずは仮説を立てて確かめるというスタンスが調査には大切で、ただし正解する事が大事ではなく、確かめる行為そのものと事実と仮説のGAPを可視化する事こそ、検証の最重要ポイント!(とは本書では言ってないですが、個人的な解釈)
量を出してから絞っていく
ロジックツリーやフレームワークの使い方に頭がいきがちな人が意外といますが
アイデアや選択肢の、量をそもそも出しまくってるか?というのは落とし穴です。
本書でも、まずは量を出して、そこから評価するための軸の整え方だったり、打ち手の選択をするための思考法を解説しています。
まずは幅広く洗い出すというのは、日常・仕事、いろいろなシーンで忘れずにいたい事です。
4象限プロット後に移動させる
個人的に本書で一番の学びはこれ。
例えば、効果×実行のしやすさでプロットした場合、結構やってしまいがちなのは「まずは効果が高く実行しやすい所からやるぞー!」と、プロットした結果を前提とし、そこからすぐに整理に入ってしまうパターン。
私もこういう思考してるなーと思いました。こういう思考の型やフレームって、無意識に使うようになるほど慣れきて、疑わなくなったりします。
本書で出てきた具体例は、プロット時点で「実行しづらい」項目を、得意な人をプロジェクトに巻き込む事でプロット位置を能動的に変えるという流れ。
このように、視点を変えたり前提条件を変える事で、プロットの結果そのものを変化させる事ができます。
このプロット結果への干渉や疑問の提示なんて、まさにリーダーやプロマネが持っていると強い能力なのでは!?と思いました。
しれっと本書で中学生がやってのけていますが、仕事現場では非常に重要かつ難易度高めな視点だと思います。
プロットし、優先順位を付ける前にプロット結果自体を変えられないか?考えてみる癖を付けたいです。
以上、読書感想文でした!
ではまた🔥
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
