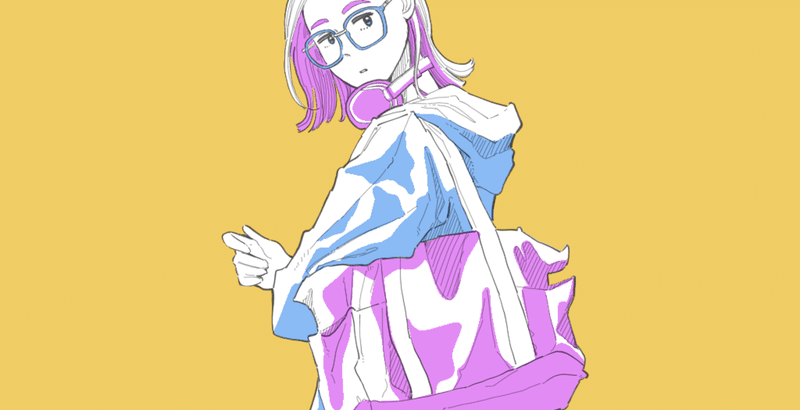
Good-by|ショートストーリー
彼女は"少し"変わった女の子だった。
話したことはなかったけれど、いつも大きな眼鏡とヘッドフォンをして気だるげに窓の外を見ていた。私と彼女"メアリ"はなぜだかいつも同じクラスになる。だけれど、一度も話したことはなかった。きっと彼女は私のことを、同じクラスのやつと思っていたに違いない。
彼女はいつもひとりだった、けれどそれが彼女にとって息をするくらい普通で、日常なことのようで、まったく気にしたそぶりはない。
彼女の書く文字はいつも右上がりになる。
ノート、黒板の文字、なんでもそうだ。
彼女は声が低い。その声はどこかラジオの向こう側の音声のようで、私は好きだった。彼女は気に入っていないみたいだ。
+
普通の子だと思っていた。けれど、その日は突然やってきた。
ある夏の夜、うちのアパートメントの下を彼女がスケートボードで通り過ぎた。それは遅い時間で、こんな時間に外に出るような子はとんだ不良か、家出か…ともかく私はいい子ではなかったし、気になったので彼女の後をスクーターで追いかけた。
オレゴン州の片田舎のこの街は、古びていて、夜もとても静かな場所だ。
私は素知らぬ顔をして彼女の後を追いかけた。
メアリも素知らぬ顔をしていた。
彼女は近所の大型スーパーの前までくると、スケボーから降りて、閉まっているはずのスーパーの裏口に鍵を差し込み入っていった。
彼女はその鍵をどこで手に入れたのか?
なぜこんな夜中に?
そんな疑問よりも驚くべきことがあった。時間が止まっているのだ。
小雨は空中で止まり、車や歩行者、信号、テレビ。
私と彼女以外、全部が止まっていた。
わたしはぐわんぐわんとする頭を押さえて、彼女の通った扉を開けた。
何か知っているなら、彼女しかいないはずだ。
「ねぇ、アンタ」
はっとなって顔をあげると彼女がこちらをにらんでいた。
「なんでここにいるのよ」
こっちが聞きたい。
+
彼女はスーパーの明かりをつけて、レジで家から持ってきたキャンディを食べている。もしわたしにこんな能力があるのなら店のものを食べちゃうというと彼女が「それだと完全犯罪にはならないじゃないの」と呆れたように言った。
この世界に誰かが入ってきたのは、これで二度目だという。
一度目はメアリのお姉さん。彼女とは正反対の性格で、友達が多く、明るい人らしい。
「なんで二度目があんたなのかな」
「知らない、これってずっとこうなの?」
「ずっとって?」
「毎晩?ってこと」
「そうだよ。けど、昔からこうだった。私にとってはこれが普通。だからあんたがここにいるのが一番今、変な事なの」
わかる?と彼女は機嫌悪そうに言った。
彼女はキャンディの包み紙をくしゃりと丸めて、スーパーのごみ箱に慣れたように投げ入れた。何味だったんだろう。
「あたしのお姉ちゃん、このスーパーで昔働いてたのよ」
「へぇそうなんだ」
「そう、だけど死んじゃった、そこの交差点で事故にあって」
私はどうこたえようか言葉に詰まってしまった。
「でもこうやってふつうにみんな生きていくって気が付いたら、なんだか反抗したくなって」
「反抗」
「そう、で、それからこうやってスーパーに忍び込んで飴を食べてごみを捨ててる」
馬鹿みたいでしょと彼女は不機嫌そうに笑った。
「あんたも食う?」
彼女はポケットから飴を2つ取り出していった。
+
口に広がるのはアップルミントキャンディー。
静かな空間に飴を口の中で転がすカランという音だけが鳴っていた。
「私あんたのお姉ちゃん知ってるよ」
「そう」
「声が好きだったのよ」
「へぇ」
「いや、彼女が好きだったのかも」
彼女は不意を突かれた顔をした。
「妹にそれ言う?」
「ごめん、でもきっと振られてたね、だってお姉さん」
「婚約者がいたもんね」
キャンディーを食べ終わって、私は包み紙をくしゃりとつぶしごみ箱に投げ捨てた。ごみは途中で落ちて、時間は止まっているのに重力はあることを不思議に思い顔をしかめた。
「下手くそ」
そういって笑った彼女の笑顔はお姉さんそっくりだった。
彼女はスーパーの合鍵をレジに置いてそのまま扉から出ていった。
誰もいない深夜の時間が止まったスーパー。
私はメアリとお姉さんに向かって言った。
「Good-by」
読んでくれて、嬉しいです。 ありがとうございます。サポートは日々の執筆に使わせていただきます。
