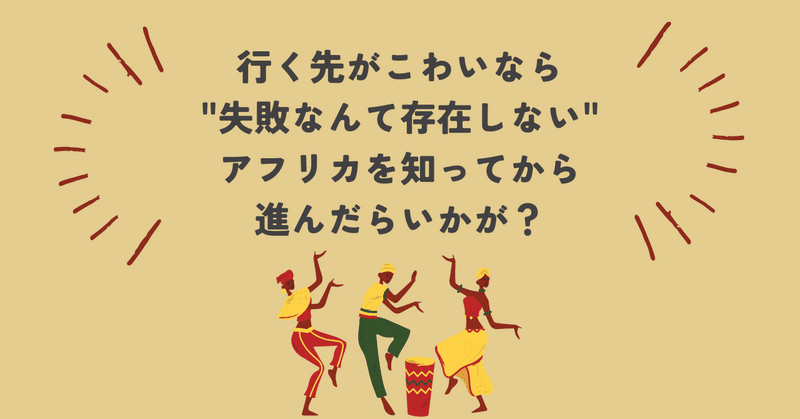
行く先がこわいなら"失敗なんて存在しない"アフリカを知ってから進んだらいかが?
明日、友人がニュージーランドに旅立つらしい。出発直前、彼はこんなnoteを書いている。
たくさん失敗したら良いよっていうけど、でも失敗は怖い。し、しんどい。
宿だって別に現地に行ってから見つけたら良いっちゃ良い。けど、現地でバタバタと探すのって大変そうだし、不安だ。
そもそも失敗ってないのかもしれないけど、そんなことは失敗を受け入れられた時に言える。やる前は怖い。
実際、ニュージーランドにワーホリに行くということは正しい選択なのだろうか、と何度か頭をよぎった。
特に宿が見つからなかった時、不安や心配に苛まれて過ごしていた。
めちゃくちゃわかる。わたしも協力隊という挑戦を選び、日本で積めたキャリア、出会い、その他いろんなものを手放してここジンバブエにきた。日本を出る直前はさすがに少し不安にもなった。
けれど不安だったのは過去のわたし。
今、このnoteを読んで思うのは、のすけのニュージーランドに行くという行為も、わたしの協力隊という選択についても、失敗なんてないし、なんなら正解もないんだろう、ということ。
先日29歳になり、20代の終焉を迎えつつある今日この頃。自分の20代を振り返って思う。特に20代、経験を積むための行動に失敗なんて存在しない。
20代の経験に失敗なんてない
日本人はときに、失敗を恐れすぎ、同時に成功を求めすぎるような気がする。わたしも以前はそうだった。けれど、アフリカに住むようになってまた特に、失敗を恐れない自分に変わってきたなあと感じている。
というのも、アフリカ人、失敗という概念がほぼない。ということは、"失敗しない"のだ。とはいってもドクターXの大門未知子のように完璧というのではもちろんなくて、失敗という概念のハードルが限りなく高いというべきか。成功のハードルが限りなく低いというか。
アフリカ人には失敗という概念が日本と比べて非常に薄い。楽観的すぎてイライラすることも多いけれど、アフリカにいると、この成功/失敗のハードルの高さは、人に決められるものではなくて、自分で決めていいものなんだ、ということは感じさせられる。
そんなアフリカ人たちに多少なりとも影響され、え?失敗ってなんだっけ?という考えを一旦挟めるマインドを多少なりとも自分にインストールできたのはこの半年の良い影響だと感じている。
そもそも失敗ってなんだっけ
辞書で「失敗」と引くと、こう出てくる。
しっぱい
【失敗】
《名・ス自》
方法がまずかったり情勢が悪かったりで、目的が達せられないこと。
協力隊で活動がうまくいかなかったら、生活が楽しくなかったら失敗?
留学やワーホリで、ぜんぜん英語が話せるようにならなかったら失敗?
そうじゃあないだろう。失敗を「目的が達せられないこと」と定義するのならば、ひとつの経験の目的の置き方は一つだけではなくて、さまざまにできるはずだ。
特に20代に海外に出る、という行為の目的は、言語習得だけでも、仕事を達成することだけでもない。まだ新しいものに感動できる感性が残っている20代のうちに、異文化のなかで苦しみ/楽しみながら生活するというこの経験は、今後の人生に大きく影響するだろう。他者への想像力を育み、優しい人になれるかもしれない。世界中に友人ができて、自分ごとにできる範囲が増えもするかもしれない。
わたしはまだギリギリ20代で、30代、40代以降のことは想像するしかないけれど、数多くの尊敬する人生の先輩たちが「若いうちに外に出ておけ」と言うのだからさすがにそうなんだろうと信じている。
海外に住むなどという大きなことでなくても、20代における人生の選択が失敗と断ずることは誰にもできない、という話はどこの誰にでも通用することなんじゃないだろうか。
数年前、わたしは新卒の就活を失敗したと感じていた。細かい話は省くけれど、焦って会社を選んだ結果、いろいろなことが合わなくてすぐにやめてしまったのだ。
今でも正直、あの会社を選んだという選択はあのときの最善ではなかったかもしれない、とは思う。けれど、29になった今、自信を持って言える。決して、失敗などではなかった。あの会社で学べたことはいろいろな面で今の選択に生きていて、ありがたいことに人間関係も残っている。どんなに当時しんどかったとしても、悪い影響を残したとしても、24.5歳はまだ若い。それはその後の人生の行き方次第でいくらでも「良い経験だった」と言えるはずなのだ。
クォーターライフクライシス
今までの話は、「クォーターライフクライシス」という現象にも通じる。
クオーターライフ・クライシス(Quarter Life Crisis、QLC)とは「20代後半から30代半ば頃の年齢に陥りがちな人生の危機」のことです。 社会に出てから数年が経って現実が見えはじめ、自分の人生や今後の生き方に悩んだり、他人の人生の方が良く見えてしまい落ち込んだりする状態に陥ることをいいます。
わたしはクォーターライフクライシスを25歳くらいの時からずっと、うっすら感じながら生きているような気がする。初めてこの言葉をみたのはTwitterだった気がするけれど、「まさにこれじゃん、、」と驚いたものだ。
悩むのは当たり前。日本には仕事も恋愛の選択肢も(アフリカと比べて笑)山ほどあり、他の人の様子もSNS等で簡単に見えてしまう。そのなかでもがきながら行動していくことが、人生を前に転がしていくんだろうと思っている。
思うに、20代の経験なんて、30代以降でいくらでも帳消しにもできるんじゃないだろうか。20代の悪い経験なんて、すぐに取り返しがつきそうだ。それくらい、20代は何をやっても良いはずだし、逆に何をやっても30代以降の失敗一つで人生転がり落ちれそうだなあとも感じている。
そんなにパキっと30歳でなにかが変わるということもないんだろうけれど、これからは少しずつ人生の選択に慎重になっていくんだろう、と予感はしている。主に仕事の選択、恋愛や結婚の選択。ちょっとずつ、動かせない柱、みたいなものが自分も周りも増えていきそう。これは悪いことではなくて、大事にしたいものが時間と共に増えていくだけ、だと思っているけれど。
私自身としても、29にして自分というものがやっと定まってきた感覚がある。ここまで長かったけれど、全てが今の自分を構成するプロセスだったなあと自信を持って言える。これからは悩みのレイヤーが変わっていくだろう。ベースで悩んでいたのが、ベースは定まって、その上の層で悩んでいくんだろうというような感じ。
アフリカにおける成功・失敗の概念
せっかくなので、アフリカで感じる成功/失敗という概念の日本との違いについてもう少し考えてみよう。
アフリカで隊員という現地人に指導するような立場をやっていると、隊員同士でアフリカ人に「失敗」の概念がないよね、という話で盛り上がる。
ちょっと意味がわからないかもしれないけれど、アフリカ人って「失敗した」とか、「未来が不安」だとか、そういうことを全然考えないのである。
物事はうまく行ったか、めちゃくちゃうまく行ったかの2択。日本人からして「そりゃ明らかに失敗だろ!」と思っても、どこかに意義を見出すか、達成すべきゴールを簡単な方にずらして、成功した風にしてしまう。もはやあっぱれ!である。
例えば、野球の大会が予定通り全部の試合をできなくても、それは彼らにとって失敗ではない。たとえ準備不足が原因であってもだ。なぜなら、どうにかこうにか開催はすることができたから。予定通り全部の試合を終えることまでが目的に入っていない、とも言う。「俺たちは全力で準備して、ここまでできたのだ」と考える。
日本人からしたら、せっかくタイムスケジュールを切ってこれだけの参加者に集まってもらったのだから、予定通り最後まで試合が遂行されることが成功であり、そうならなければ失敗で、反省すべきことになる。
ジンバブエ人は、多少のゴールを自分側にずらすことをいとわない感じがする。それは成長もしなさそう(もしくは、成長が遅そう)だが、楽で常に楽しい世界である。
我々日本人は、全員とは言わないが、一部、スポ根のような世界を信じているところがある。努力してできるだけはやくゴールを超えていくことを成長と呼ぶ美学みたいなもの。アフリカ人にはこの感覚が見事にない。多少あるのかもしれないけれど、全然見えてはこない。
他にも、例えば、わたしは学校に勤めているけれど、学生が勉強や課題が何らかの理由でできずに学校を卒業できなくても、彼らの感覚として「失敗」とはとらえない気がする。頑張ったけどいろんな要因があってできなかったから仕方ない。またチャレンジできるときにすればいい。
日本だと失敗のレッテルを貼られることが、ここだと失敗にならない。つまり、アフリカ人、自己肯定感はめちゃくちゃ高い。
日本人からするとイライラするポイントでもある。「失敗を反省して、次に活かす」ということが染み付いていて、成長意欲が高い日本人は、(そもそも失敗と思わないために)いつまで経っても成長しないアフリカ人にめちゃくちゃイライラするのである。
数年後の漠然とした不安、なども、日本と比べて圧倒的に感じない。ジンバブエの経済状況ですら、みんな「全くもう〜」と多少困りつつもけらけら笑って過ごしている。それはもう、とんでもなく楽観的に見える。
不安遺伝子の違い
この楽観性の違いは、生物学的に証明もされているらしい。
下の記事によると、人間には「不安遺伝子」なる不安の感じやすさを決める遺伝子があるらしく、日本人の8割が不安遺伝子を保有するのに対して、アフリカ人は3割しか不安遺伝子を保有しないという。
不安遺伝子ってなに?ということだけれど、例えば、コップに水が半分入っているとき、「半分しかない」と思う人は不安遺伝子が強く、「まだ半分ある」と思う人は弱い。日本人は他の民族と比べて不安を感じやすいらしい。
日本の災害の多さとか、いろんなことが原因としては示唆されているけれど、もう遺伝子レベルならば仕方ない。 それは違う人間のように感じるはずである。彼らは同じ出来事を聞いても、私たちより不安に思わないのだから!
おわりに:異文化を知り、想像すること
アフリカと日本を比べて、どちらが良いという話ではない。日本はその不安遺伝子を駆使して戦後の経済発展を成し遂げて、今も世界的にみて秩序性の非常に高い世の中を作り出している。アフリカは経済こそまだまだだけれど、ものがなくても金がなくても人々はどことなく幸せそうだし、失敗なんてない世界で純粋にゆったりした時間を家族と楽しんでいる。
大事なのは、地球の裏側にこんな人たちがいるんだよ、ということを、できるだけ多くの人が、できるだけ実感を持って知ることだと思う。それは教養レベルを上げることとも言えるかもしれないし、異文化理解を促進することと定義できるかもしれない。
そして、想像力を持って生活すること。異文化があるということを想像すれば、行動が変わる場面はいくらでもある。失敗が存在しない文化を知っていれば、失敗したからといって絶望することが減るかもしれない。不安を感じやすいことが遺伝子で決まっているとわかっていたら、その不安に対して適切な対処ができるかもしれない。もう少し大きな目線で見るならば、差別的な行動も減っていくだろう。
わたしたちは、多様な世界に生きている。世界は広くて、醜くて、美しい。失敗なんて恐れずに、30代に入ろうがなんだろうが、広い世界を見て心を動かしていきたい。そうやって進むことができる限り、わたしたちは、大丈夫なのだ。
もしよろしければサポートお願いいたします。 いただいたサポートは新たな旅の資金とさせていただき、新しいnote記事のための経費とさせていただきます。
