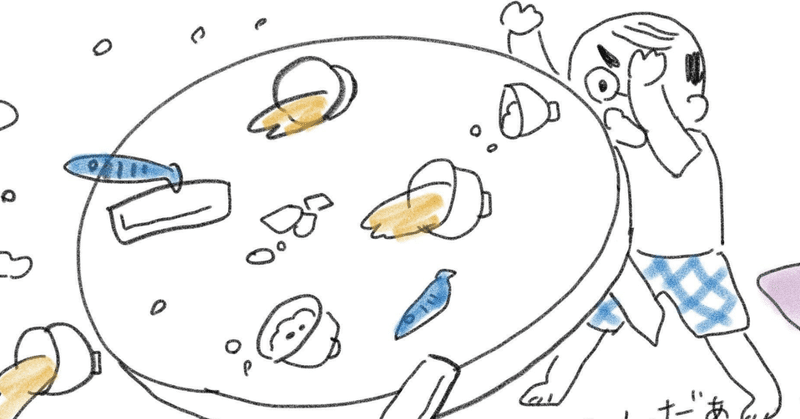
調査企画~成功する調査ではクライアントへの「ちゃぶ台返し」は日常茶飯
前回は、「それではうまく行くはずないよ」という業界の内幕でしたが、では、具体的にはどのようなことがあるのか、するべきなのか、という観点での事例も必要だと思い、さらにこのシリーズを続けます。
そもそも「インタビュー調査」の話なのですが、前回ご紹介したように「満足度3.8%」という悲惨な実態がなぜ起きるのかということを認識しておかないと、いくら「聞き出す力」とやらだけを身に着けても全く無意味であるということをご理解いただきたいわけです。
あるカルチャー教室の運営会社からの依頼を受けたことがありました。
依頼の内容は「学習意向はあるのだけれども、実利用に至らない層を獲得したい」為の調査だということでした。その為に、その層を対象に「なぜ利用しないのか、どうしたら来てくれるのか」を探る調査をしてほしいということだったのです。その層をこの会社では「ウダウダ層」と呼んでいました。ウダウダと実行できないでいる人たちです。
「なぜ利用しないのかを探りたい」という調査要望はクライアントとリサーチャー間のC/C領域の話です。「実利用に至らない層がいる」というのは当然の常識でもあるのでやはりC/C領域です。ところがこの会社がそれに悩んでいて、獲得に乗り出そうとしているというのはC/S領域の話であり、それについては今までも、高額なギャラのタレントを使ったCMだとか、販促だとかの努力を行ってきているが思わしい成果がでていないというのもC/S領域です。
要はオリエンテーションで、当方が先方から得たのはそういった情報であったわけです。
一方、下記は私がクライアントに説明したS/C領域の情報です。
自己啓発や職業スキルの獲得から、趣味をより楽しみたいということまで、幅広い動機でこの教室は利用されていますが、身に着けることがある意味「勉強する”べき”」ことであるので、アンケートなどのアスキングで「やりたいか?」と問われると「できればやりたい」という反応が得られるわけです。
ところがそれを本当に実行するかというと、「時間がない」とか「お金がない」というような理由で利用に至らないわけです。
身に着ける”べき”「勉強」なのですから、「やりたい」と答えるのはタテマエ上当然のことです。タテマエというのは、子供のころから刷り込まれた「社会規範」や「常識」、「通念」ですから、本当にそう思っています。一方その人たちが利用に至らないという方はホンネです。以前にも述べたと思いますが、人のホンネは言葉ではなく行動に表れます。本人すらそう思っていなくても、行動を見ればホンネはわかるのです。
ですので、この課題の場合、その「ウダウダ層」を対象に「なぜ利用しないのか」を探ってみても、そのタテマエとホンネのはざまの中で、「高いから」、「時間が無いから」、ちょっとひねったものは「通勤途上に教室がないから」などという「言い訳」を聞かされるのみになることが予想されるわけです。その人たちのホンネは「勉強する”べき”だとは思っているが、今すぐは必要ない=勉強するニーズは強くない」ということなのです。通勤途上になくてもニーズが強ければ多少回り道しても学ぼうとするわけです。高くても、時間がかかってもそのトレードオフを払おうとするわけです。つまりホンネではこの人たちはニーズの無い人たち、弱い人たちなのです。これは梅澤ニーズ理論からの演繹です。
では観点を変えてみて、この人たちに「どうすれば教室へ行くようになるのか?」と聞いたとします。この人たちにとってこの質問は正に対象者と調査主体間の「S/C領域へのアスキング」となります。この人たちには「教室へ行くようになった」という「生活体験」がないわけですから、その質問には本来答えられないわけです。従って「値段が安くてサービスが良ければ良い」とか「教えるレベルが高ければよい」とか「教室が近くにあれば良い」とか、挙句の果てには「一回で話せるようになれば良い」といった「べき論」や「理想論」で「意見」を答えるわけです。ウダウダ層にはいわゆる「真実の瞬間」(Moment Of Truth=MOT)がなく、空疎な意見を述べるに過ぎないのです。これは意識マトリクス理論からの演繹です。
これでは正に「O家具理論」のストライクど真ん中の調査です。それを真に受けてマーケティング投資をしたら良くて収益低下、悪ければ、赤字、倒産すらあり得るわけです。
ここまでがS/C領域です。ニーズ理論や意識マトリクス理論に基づいたマーケティングリサーチのプロとしての知見の開示です。
ではどうすれば良いのか?
ここから先がS/S領域の話となります。私の提案は以下の通りでした。
同じ人でもそのニーズは状況に応じて強弱が変化します。つまりニーズの弱いウダウダ層でも、そのニーズが強まる状況があるわけです。従って、「ウダウダ層の教室利用への態度・行動の変容」こそがこのマーケティング目的・課題の核心にあります。つまり、調査目的はその変容/非変容の要因を探り出せばよいということになります。その要因を知れば、ウダウダ層の取り込み施策を立案することができるでしょう。それが調査結果の利用法となります。その施策によって、「ウダウダ層の取り込み」というマーケティング課題を解決することができるわけです。
従って、この調査は「ウダウダから教室利用へ態度・行動変容した生活体験」を対象者と調査主体間のC/S領域として設定するべきであるということになります。それが、このマーケティング課題解決に対して潜在していたまさに「わかっていない」ことであるわけです。すると調査対象者はクライアントの要望にあった「ウダウダ層」ではなく、「元ウダウダ層の教室利用者(態度変容層)~できれば長い期間ウダウダしていながら、最近に態度変容した人で、複数の選択肢からこの教室を選択した経験がある人」が望ましいということになり、調査課題は、「ウダウダ層のウダウダの理由と、どうしたら利用するようになるのかの意見聴取」ではなく「元ウダウダ層の態度・行動変容の実態」であるべきだということになります。この調査では「態度・行動変容」=「言葉ではなく行動」ですから、ホンネがわかるわけです。このイメージが下図です。

つまり、調査目的、調査課題、調査対象者が当初のクライアントの要望から全て「ちゃぶ台返し」されているわけです。これは元々クライアントが思い付きもしなかったことですし、当方も、クライアントの状況を知らなければ思いつきもできないS/S領域の調査構造です。特にこの調査は、「マーケティングターゲット」と「調査対象者」が異なるという特異な特徴を持ったものですから、通常は発想され得ないものであるわけです。
しかし、どちらがよりクライアントのマーケティング課題をリアルに解決することができるかというと、それは言うまでもないでしょう。
私の場合、こういう「ちゃぶ台返し」は普通にあることです。かたや失礼ですがアマチュアの思い付き、かたや、知識も経験もあるプロフェッショナルなのですから当然です。一方それで受注率も高いのですが、なぜならばクライアントは、リサーチの結果をマーケティング課題を解決できるような満足できるものにするために、プロとしてのリサーチャーにそれを期待しているということだからです。調査会社が「クライアントの指示通り」という態度であった前回の事例とは真逆だとお気づきください。そもそも、マーケティングにおいては、コストを使いたいのは開発費用や広告費用、営業費用なのであって調査費用などかけたくはないわけですが、それを使おうかというところに、クライアントの期待感、渇望感、不安感が凝縮しているわけです。プロはそれに応えなけらばなりません。
以上が、クライアントとリサーチャー間の意識マトリクスによる調査企画のリアルな運用実例です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
