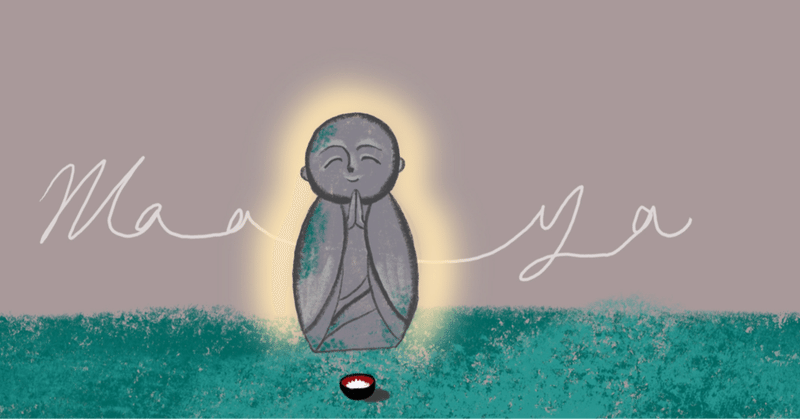
食べることの大切さ〜五観の偈(ごかんのげ)
私たち日本人には、食べる前の「いただきます」、食べ終わった後の「ごちそうさまでした」を言う習慣がありますね。特に「いただきます」は、私たちが食べる全ての命に、また、食事を用意する人や食材を提供する人たち全てに感謝する、日本特有の素晴らしい言葉です。
仏教の教えにも、「五観の偈」と言う、僧たちが食事の前に唱える言葉があります。食に対する姿勢が示されていますので、ご紹介します。
五観の偈
一つには功(こう)の多少を計り 彼の来処(かのらいしょ)を量る
二つには己が徳行(とくぎょう)の全欠(ぜんけつ)と忖(はか)って供に応ず
三には心を防ぎ過(とが)を離るることは 貪等(とんとう)を宗とす
四には正に良薬を事とするは形枯(ぎょうこ)を療ぜんが為なり
五には成道(じょうどう)の為の故に今この食(じき)を受(う)く
一つずつ解説します。
一つ、このご飯はどこからきたのか考えます。食材の命の尊さと、かけられた多くの手間と苦労に思いをめぐらしましょう。
二つ、今日の自分の行いを振り返ろう。この食事をいただくに値する正しき行いをなそうと努めているか反省しましょう。
三つ、欲張らず、心静かにいただきます。むさぼり、怒り、愚かさなど過ちにつながる迷いの心をいましめていただきましょう。
四つ、よく噛んで、丈夫な体を作ります。欲望を満たすためではなく、健康を保つための良き薬として受け止めましょう。
五つ、このご飯、今を大事にいただきます。皆で仏道を成すことを願い、ありがたくこの食事をいただきましょう。
「いただきます」の具体的な内容です。幼い頃、父(曹洞宗の住職)と一緒に食卓に着いた時にはこの五観の偈を唱えてから食事をしていました(父がいない時にはサボっていましたが)。
小さい子供にはなんともいえない緊張感があり、味もわからなくなりそうな妙な感覚でした。言葉の意味も教えられてはおらず、ただ暗唱していたのですが、大人になって実感として食の大切さに感謝するようになり、まさかこの言葉を思い出すとは、思いもよらない事でした。
最後に、「ごちそうさまでした」の時に唱えた次の言葉をご紹介して終わります。
願わくは此の(この)功徳(くどく)を以て(もって)
普く(あまねく)一切に及ぼし
我等と衆生(しゅじょう)と皆共に
仏道を成(じょう)ぜんことを
この食事のおかげで、全ての人が健康を保ち、仏様の教えを守って生きられますように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
