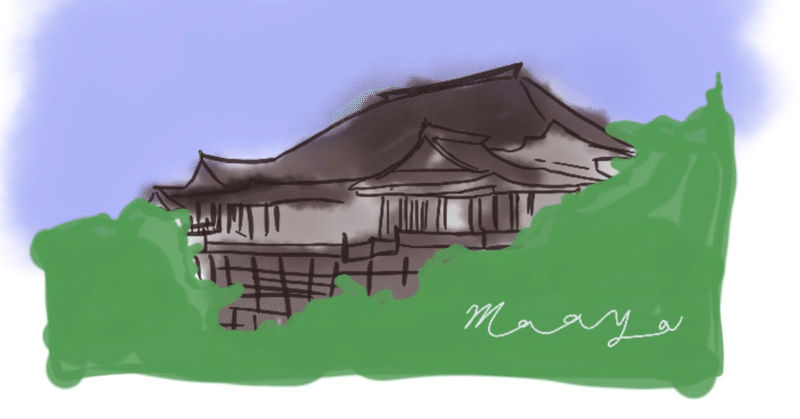
仏教⑦日本人と仏教
「たとえためになることを数多く語るにしても、それを実行しないならばその人は怠っているのである。」 byブッダ
インド、ネパールで生まれた仏教は、中国、朝鮮半島と大陸の北ルートを経て日本へ伝わります。南ルートもあるのですが、日本に伝わったものとは少し違います。6世紀半ば、飛鳥時代の欽明天皇(きんめいてんのう)の時に百済(くだら)の王様から、仏像や経典がもたらされました。
それまでの日本人の信仰は山や太陽などの自然であったところに、キラキラの仏像などの登場はセンセーショナルだったことでしょう。政治的に反発もありながらも、元々多神教だったこともあり、日本に仏教が定着していきました。
以前の回で、お釈迦さまの説いた教えをのちの弟子たちが文字に起こしたというお話をしましたが、他の誰かの解釈を加えながら場所も移動するのですから、”お釈迦さまの教え伝言ゲーム”も、少しずつ形が変わっていきます。
仏像だって、元々は特定の人の形を作らない偶像否定の概念が主流で、仏塔(ストゥーパ)を各地に建てたりしていたのにも関わらず、結局様々な仏像が作られることになりました。人はあやかる対象を人間の姿に求めるのでしょうか。
僧など教えを守る人に対して、インド周辺では厳しい戒律が今でもあります。でも、広まるにつれて自分たちに都合のいいようにだんだんとゆるくなりました。それが良い悪いではありませんが、日本ではさらにゆるくなりすぎて原型はとどめていません。戦国時代には、寺院が兵力まで携える始末です。
ところで、あなたは「仏教徒」ですか?以前、私たちの生活に仏教の考え方が定着しているということを書きましたが、自分が仏教徒だと思っている方は少ないかもしれませんね。では、「檀家」(だんか)という言葉は聞いたことがありますか?
江戸時代、幕府は全ての人がいずれかのお寺の檀家になることを強制し、身分証明書を発行しました。それを「寺請制度」(てらうけせいど)といいます。キリスト教をはじめとした禁止宗教を除外するためと、戸籍を管理する役所の仕事を寺にさせるためです。檀家に対して寺のことを「菩提寺」(ぼだいじ)といいます。
寺請制度は明治時代に入り廃止されましたが、「檀家」と「菩提寺」の関係はそのまま残りました。お寺や各家にとって、良いことももちろんあったとは思いますが、これが日本流にアレンジされた仏教です。
かと思えば!仏教伝来から1400年近く経って、明治維新の動乱の中、何を血迷ったか薩長新政権は「廃仏毀釈」(はいぶつきしゃく)というとんでもないムーブメントを巻き起こしました。
これによって、日本全国の仏像、寺院が破壊され、僧侶は激しい弾圧を受けました。仏像の破壊といえば、最近のイスラム原理主義のタリバンの破壊行動が記憶に新しいですが、日本の廃仏毀釈の方がはるかに規模は大きい破壊だったようです。
戦時中もお寺の鐘や仏像などの金属という金属が武器になるために回収されました。鐘や仏像を取られたからどうということではありませんが、日本人にとって仏教とはなんなのか、仏教は何ができるのか考えさせられます。
今、見直されるべき仏教と岐路に立つお寺の存在の問題が”ひっそりと”あります。みんなの幸せのために力になれる存在として続いてほしいと願っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
