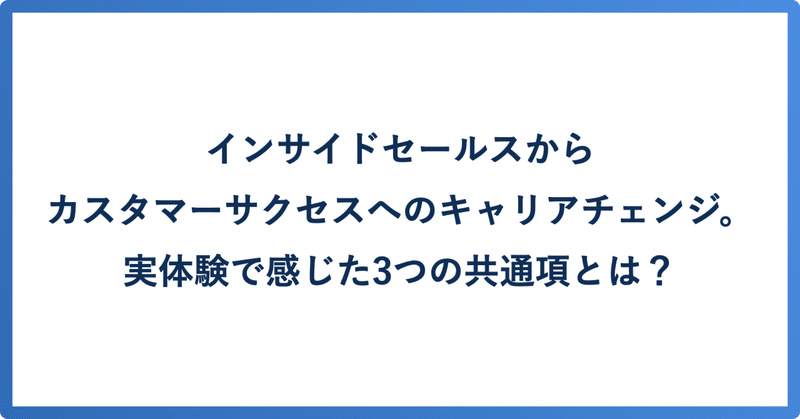
インサイドセールスからカスタマーサクセスへのキャリアチェンジ。実体験で感じた3つの共通項とは?
このnote記事は、スタメンnoteリレーの5日目です!
スタメンのnoteリレーにはついてはこちら👇
これまでnoteリレーは3回開催しており、皆勤賞で参加をしています!
自己紹介やこれまでのnoteは、下記にあるのでよければご覧ください。
このnoteはこんな方におすすめです!
インサイドセールスから次のキャリアをどうしていくか迷っている
インサイドセールス→カスタマーサクセスのキャリアのイメージが湧きにくい方
カスタマーサクセスって実際どんなことを考えているんだろう
などをこれまでの経験から類似する部分や、活かされていることについて書いていきたいと思います!
私のキャリアについて
簡単に私の経歴についてご紹介をしたいと思います。
2016年4月:新卒で不動産会社の営業として入社、新規開拓営業やマネジメントに従事。
2019年10月:ご縁があり株式会社スタメンにフィールドセールスとして入社。
2021年1月:インサイドセールスに異動。BDR、SDR、ウェビナー等幅広く担当。
2022年1月~現在:カスタマーサクセスとして、エンプラを中心に担当。
上記のように、スタメンの中でもすでに3回異動をしておりますが、
それぞれの部署でこれまでの経験を活かすことができ、非常にいい経験を積ませてもらっています。
ISとCS、3つの共通項
これまでの経験を通じて、意外に共通項が多いなと感じたのがISとCSでした。
CS配属になる前は、「未経験領域だからめちゃくちゃ不安だな…」と思っていたのですが、
いざ業務に入ってみると
IS時代のこの知見は活かせそう
ISの時の思考回路と似ているな
などISでの経験が活かされるシーンが多いです。
その中で、特にここが似ている!
という3つを紹介していきます。
1.【IS】SFAによる受注分析≒【CS】顧客の利用状況分析
まず最初に着目をしたのは分析力です。
IS時にはとにかく数字を絶対として、
広告別からの商談獲得率や受注率
広告別や業種別での受注傾向分析
営業毎の受注傾向から逆算をしたアサイン決定
商談獲得率やMQLを分析しながらマーケにフィードバック
など、SFAを用いて様々な角度から色々な数字の分析と改善を繰り返していました。
上記は顧客の利用状況を分析しながら客観的に課題特定をしていくことにもつながっており、
顧客の利用状況をダッシュボードで分析をしながらアプローチのをすり合わせ
データを基にした課題特定と次アクションの提案
などに役立てることができています。
ただし、利用状況からの課題特定はあくまで
「プロダクト自体が利用できているか、浸透しているか」の数字になるため、部門毎の数字や差分をみながら「組織状態や売上、離職率と相関性があるのか」などを顧客とすり合わせをしています。
このように、利用状況から組織状態の紐付けをカスタマーサクセスが実践をすることで、
顧客の気が付かない視点からアプローチをすることができた実体験もあり、
ISでの分析癖や能力がCSでも活かされているなと感じた項目でした。
2.【IS】ナーチャリング≒【CS】エクスパンション
2つ目は、ナーチャリング施策とCSのエクスパンションの動きが類似しているなという話です。
※エクスパンションとは:顧客の利用拡大(ここではアップセルやクロスセルを指します。)
IS時代にナーチャリング施策の一環で、ウェビナー企画の立ち上げやメルマガによる意向上げなどを行なっておりました。
ナーチャリング施策を行う中で、
数多くのハウスリードの中からどのような内容が興味を持っていただけるのか
意向が上がってきているリードに対して、商談獲得はどのタイミングが適切なのか
など、それぞれどのタイミングでどのように提案をして商談獲得をするのかを考えながら、
ナーチャリング施策を行なっておりました。
これはCSにおけるエクスパンションの動きにも近いものがあります。
オプション機能の追加は
「お客様の最適なタイミングかつ効果が最大化するもの」を提案していく必要がある一方で、
「機能を知らない」状態だとそもそも検討の土台に上がらないことも多いです。
そこで登場するのが「ナーチャリング」という考え方です。
将来顧客にとっては必要になる機能だな
そのために事前に紹介はしておきたい
そしてタイミングや時期をすり合わせしながら、既存機能で運用改善を行なっていく
このように顧客毎かつ機能毎にナーチャリングをしていくことで、
顧客の適切なタイミングでのご導入も実現ができますし、押し売りの営業ではなくなります。
ISを経験していなければもしかしたら、ゴリゴリと押し売りをしてしまっていたと考えると、
ナーチャリングの考え方は、私のビジネス経験においても非常に大きいものとなっています。
3.【IS】電話アプローチ≒【CS】顧客への情報提供
3つ目は、IS時代の電話アプローチがCSにおける情報提供に活かされているという点です。
IS時代は、
業界に合わせた導入事例のピックアップ
課題に合わせた事例のピックアップやSEO記事の送付
営業が商談を前に進めやすくするための事前情報提供
などを徹底して行なっておりました。
これらを行なっていくと、マーケで作成いただいている事例やSEO記事などは当然すべて目を通しているため、自ずとサービス理解が深まりましたし、チョイスする力も身につきました。
これは意外と今のCS組織においても自分の強みになっており、
打ち合わせをしている中で「他社さんだとどんな事例があるの?」と質問をいただいたり、
サンクスカードをやる目的とかを書いている記事とかあるの?と言われた際に、即座に事例などを送ることができています。
また、TUNAGはカスタマイズ性が高いサービスなので「顧客毎に合わせた機能をチョイスしていく」ことも重要なスキルになります。
このチョイス力も、ISで培ってきた力を活かすことができているなと実感しています。
最後に
ここまでISとCSの共通項について記載をさせていただきましたが、
それぞれのスキルの抽象度を上げていくと「共通項は多いな」と感じることがあったのと、
IS→CSのキャリアは想像できないなという方もいるのかなと思い、今回記事にしてみました!
現在、東京拠点のカスタマーサクセスを絶賛募集中になりますので、
ご興味のある方はぜひカジュアル面談からでもお話ができればと思います!
最後まで記事をご覧いただき、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

