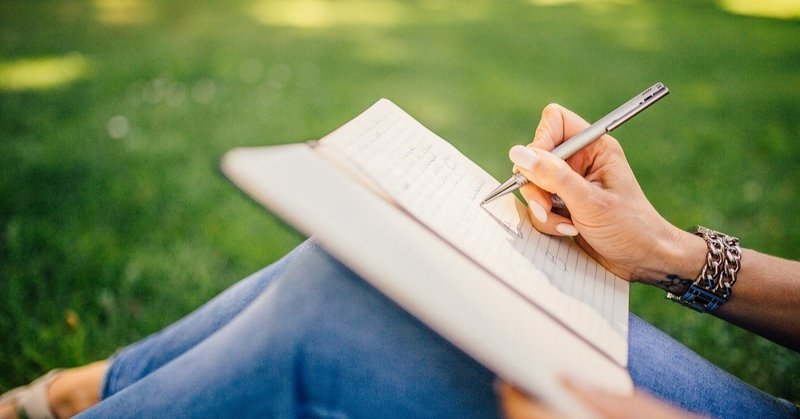
【大人】植物学③ 植物理解から人間理解へ
森の中で3つのワーク(具体的なワークや、その時の参加者の様子などは植物学① 植物学②参照)をした翌月、教室に戻ってシュタイナーやその周辺の人たちが植物に関して残した言葉を一緒に味わってみました。以下に、私たちが読んだ言葉の抜粋を挙げておきますので、関心のある方は、ぜひ直接本を読んでみてください。
『人間理解からの教育』(P69〜77からの抜粋)
広い大地がその植物に属している。髪の毛が人間に属しているのと同じように。植物は大地とともに生きている。地球自体が生き物で、地球の髪が植物だ。草を(髪を)地球から(人間から)離して観察しても、生きた姿は理解できない。
植物を理解しようとする時、細かく分けて動かないものとして追求していく事と、地球全体の中での役割をイキイキと理解しようとする事は、まったく異なる。地球と植物を一緒に観察することによって、子どもが知識だけでなく正しい感受性を獲得することができる。
『オックスフォード教育講座』(P166~172からの抜粋)
植物は、その生えている土地とともにあり、大地からそれを生じさせたいろんな力や太陽の力とともにある時のみ、完全な存在である。植物を扱う時には地質学的なものから出発すべき。有機体としての地球(最初は自分の身の回りの環境)を生命あるものとして捉え、その上で植物が繁茂している様子を取り上げる。
他に、『一般人間学』12講などからも。
▼切り離して見えるもの、つながりで見えるもの
「植物について知る」という時、植物を他から切り離して単独で見るのか、大地や環境とのつながりの中で生きている姿を見るのか。この2つの姿勢は決定的な違いになりそうです。
大地から切り離した植物を、さらに切り取って部分ごとに特徴を理解すること。「これは、被子植物だ、裸子植物だ」と、形状の違いを整理するには便利です。自然科学的な、おなじみの方法です。が、その植物はもはや生きているとは言えません。
もうひとつの方法。
それは、大地に生きている植物を、切り取られた瞬間だけでなく、生きた状態で、その変化も含めて観察、理解することです。その植物の周りには、大地、太陽の光、風や水、鳥や虫、ミミズなんかも一緒にいて、互いに密接に関連しながら、全体としての命を育んでいます。そのどれにも大切な役割があること。全体のためには、何ひとつ欠かせないこと。自分も同じ世界に生きていること…。
植物について学ぶことで、自分がそれら奇跡のような世界の中に、同じ生き物として、共に存在すること。そんな、大いなる安心感を静かに噛みしめながら、そして、人間は無自覚に、それらを好き放題搾取しているという苦い気づきもありつつ、テキストを味わいました。
▼つながっている時が生きている時
植物なら、一部を切り取られても文句は言いませんが、大切な子どもたち、そして私たち自身だって、前者のようにほんの一部分の特徴で分類されがちです。成績とか、仕事とか、年収とか、趣味とか…きりがありません。
植物を大地と切り離して観察しても、その植物のことが一部しかわからないのと同じように、私たち人間も、独房に入れたり、殺して解剖しても、その人間の一部しかわかりません。わかるのは、せいぜい、身体の物理的な特徴。身長や体重、視力や血糖値…、頑張って観察して性格の傾向くらいでしょうか。
その人が、社会の中で何とつながり、どんな風に生きてきたのか。何を求めて何をしてきたのか。それは、一人を切り離して分析しても調べられません。植物も同じように、根っこから抜いて観察しても、わかるのはそのうちの一部です。人も植物も、その本質は、つながりの中で見てはじめてわかることであり、時間の変化の中でゆっくり表れてくるものでもあります。それこそ、その人の大切な要素なのだと思います。
そんな大きな話ではなくても、現れた現象と、全体のつながりの中で理解することとが、まったく別ものになることって、日常的にありますよね。ケンカで殴った方を咎めたら、実は殴られた方が先にひどい暴言を吐いていた、なんてことが。
▼植物へのまなざしから人間理解へ
子どもも、自分も、植物も、全体の中で生きています。ならば、切り離して死んだ状態ではなく、生きている状態で、成長してゆく命の一過程として、理解したいと願います。
面倒な反抗期だって、時間軸を伸ばして、成長していく過程だととらえると「今は自分を立てようと苦しんでいる時期だから、身近な親にぶつかって確かめているのかな?」「親に反抗する力がそのうち社会を変える力に育っていけばいいな」というふうに、違った見え方になってきます。
地球の環境と一緒に生きている植物を理解する視点で、人間を理解するとは、どういう風に理解することでしょうか。植物が大地に属しているのなら、人間は何に属しているのでしょう。
社会? 学校? 家庭? サークル? 人が属する場所はひとつではありませんし、植物と違って、人はどこに属していても、独立して自由に行動できる存在でもあります。…今はとてもそうは行動できなくとも、少しずつ自由になっていくことが課題なんだと思います。
植物と同じように、人は全体と調和した自然の一部であること。植物と大きく違うのは、人が場所や環境から独立して自由に行動できること。
植物へのまなざしが深くなったことで、人間へのまなざしも、少しずつ、深くなっていけばいいなと思います。これからも、森や公園、庭先や道端で、植物にいろいろ教えてもらえますように。
私たちも、何かの集まりや観察会に参加する特別に切り離された時間の中での学びを楽しんだ後は、日常の時間の中でその学びを生かすことを意識してみましょう。何気ない普段の時間を学びの時間に変えて行くことで、死んだ学びを少しずつ生きた学びに変えて行けるのではないでしょうか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▼オキツ 神戸シュタイナーハウス代表 大人クラス担当
小さな勉強会や書くことに関する仕事、普段の暮らしなどを通して自分の考えを深め、表現する。その結果、自由で愛のある社会に近づけるといいな。
ブログ毎日更新中。https://blog.goo.ne.jp/oneby1
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
お読みくださりありがとうございました! スキやコメントをいただけると励みになります。 サポートは子どもたちの活動費用に使わせていただきます。
