
なぜ『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』は傑作なのか?
HiAika
https://twitter.com/HiAika666
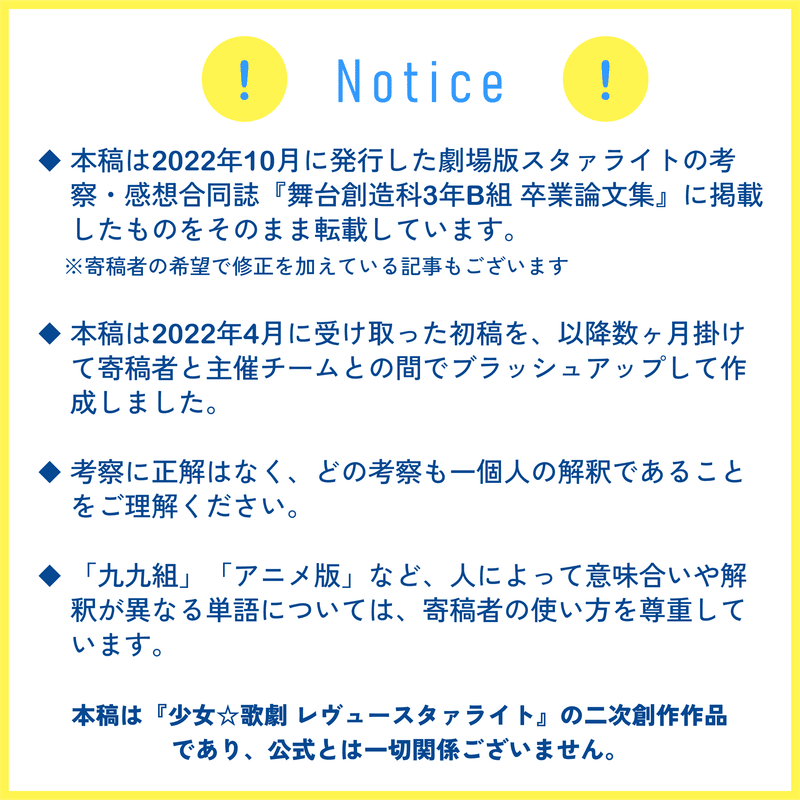
1.はじめに
演劇、ミュージカル等、舞台芸術にとってもはや定番とも言える演出方法に「客弄り(または客席降りとも)」というものがある。もっともオーソドックスな例は、演者が客席側のドアから入場し、台詞を紡ぎながらステージへと入場していくというものであろう。しばしば、客席に演者が潜り込み、観客に干渉を行う例もある。それらは「第四の壁」を超えて、演じる側と鑑賞する側を越境するという目論みであり、また外的な視点から眺めれば極めて芸能的な意味でのサービスの一環であるとも受け取れるかもしれない。
個人的な意見を述べさせてもらえば、筆者はこの演出が苦手である。もちろん、劇という構築物に自ら(もしくは他の観客)が介入することでシミをつけてしまうのではないかという動揺もあるが、それより他に何か漠然とした不安のようなものを感じていたからだ。それはもしかしたら、ステージに張り巡らされたフィクションの壁が瓦解して、我々の現実が舞台上のフィクショナルな現実に呑み込まれてしまう錯覚。自らの立つ安定した地平が、自分たちよりも下位にあったはずの物語|ナラティブに揺るがされるという不安だったのかもしれない。
『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』——塔の上で神楽ひかりと再会した愛城華恋は、「それはあなたの思い出? それともこの舞台の台詞?」と指摘されたことで、自らが劇を演じていることに気づき、そしてそのひりつくような恐怖を初めて肌で感じる。客席を見つめながら、「私、見られている?」と問いかける彼女を前にして、この映画の観客もまた戦慄する。それは単なるフィクションとして了解していた作品が、我々の現実へ侵攻することの不安、言い換えれば圧倒的な優位と信じていたこちらの現実が、作品という下位の現実に揺るがされることの恐怖であるのかもしれない。サルトルを引用するまでもなく、誰かの眼差しに晒されるのは震えるほど怖い。彼女たちに見つめられることで、我々もまた観客としての役割を強制的に負うことになるのだ。
さて、閑話休題。上記の議論は、(さも「チェーホフの銃」のごとく)後々の議論に生きてくるので覚えていて欲しい。本稿のテーマは「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト(以下、劇スと表記)の傑作(masterpiece)性」についての考察である。傑作性という言葉によって筆者が提示したい劇スという作品の批評的価値(*1)の定義は、専門的な美学研究の意味合いではなく、その作品がどれだけ観客の感動を誘うか、また作中の革新的な表現がどれだけ業界に認められているかという意味である。
劇スが上映されて早半年以上が経過し、「名作」「怪作」「アニメ界の歴史を画する作品」などという評価が散見される。だが、本稿で行いたいのはその評価が妥当でありえるかを論証することではない。ここで語るのは、他作品と比べた上で見出される相対的な作品価値ではなく、あくまで純粋に作品内部で果たされた表現による突出した価値を考察することであり、それによって裏づけられた個人的な価値評価である。
本稿の論旨は、劇スという作品の傑作性が「レヴュー」という表現の発明に負っており、さらに劇中におけるメタ表現とレヴューという表現枠組みによって規定された作品全体の構造が既存のアニメーション作品を超えた演出に寄与しているというものである。続いてさらに議論を深化させ、最終的には劇スが果たした『レヴュースタァライト』というコンテンツそのものにとっての意義について論を進めたい。そのために幾つかの観点から、考察を展開していきたいと思う。
*1 批評的価値という言葉の使用で筆者が念頭に置いているのは、ノエル・キャロルが『批評について』で展開した「批評行為とは、理由にもとづいた価値づけである」「優れた作品の価値とは、制作者が何を意図しその作品の中で何を達成したのかで決まる」という議論である。
2.レヴューの「魂」
『レヴュースタァライト』という作品群において印象的な要素である「レヴュー」は作中においてある種の用語として機能している。必ずレヴューの前にはエピソードの展開に即した熟語が銘打たれ、「歌って、踊って、奪い合いましょう」というキリンの台詞通り、舞台少女たちはままならない想いと覚悟を胸にして与えられた武器を振るい火花を散らす。
元々、「レヴュー(revue)」という用語はフランス語が由来であり、「物語ではなく断片的な場面を寄せ集めた舞台ジャンル(宮本 2014 p.61)」であり、「スペクタクル性、豪華な舞台とコスチューム、最新の舞台テクノロジーなどが主眼(p.61)」となっていた演劇ジャンルである。
日本においては一にも二にも宝塚歌劇団が有名であり、同劇団では「レヴュー」は「ショー(show)」と対置される。本質的な違いはないものの、前者が時代劇、後者が現代劇の相を帯びた作品であると説明されている。劇団独自の「オーディション」システムが開発された経緯と合わせて、宝塚歌劇団が『レヴュースタァライト』に与えた設定の素地。その重要性は捨て置けない。
しかし、『レヴュースタァライト』において「レヴュー」が、果たしてどのような枠組みにおいて設計されたシーンであるかを言い当てるのは難しい。別の言い方をするなら、他作品における「戦闘シーン」と何が違うのかを説明することが難しい。確かに『レヴュースタァライト』の「レヴュー」は舞台風の演出が特徴的な戦闘シーンと言えるが、果たしてそれだけで演出のニュアンスの違いを説明しきれているのか。
もっともキリンは「レヴュー」について例えば、「歌とダンスが織りなす魅惑の舞台」「舞台少女のキラめきを感じれば感じるほど、照明機材が、音響装置が、舞台機構が勝手に動き出す」と言い添えているが、TVシリーズにおいてオーディションの一幕として行われた(あくまで客観的な視点に立った場合)その決定的な違いとは何なのだろうか?
例えば史実において「1575年6月28日に行われた武田軍と織田軍の戦闘」を「長篠の戦い」と呼称するように、「『レヴュースタァライト』TVシリーズ第2話・愛城華恋と星見純那のレヴュー」は「渇望のレヴュー」と名づけられている。
しかし『レヴュースタァライト』において「レヴュー」に見られるこの単純な文以上の付加価値はどのようなものであるかについての説明が、少なくともTVシリーズにおいては(個人的には)不足していると感じていた。
劇スに視点を移そう。TVシリーズ(及び舞台版の諸作品)と劇スの「レヴュー」概念には決定的な差異が見られる。それは劇スの「レヴュー」とは明確に、視聴者である我々に直接的な志向性をもって与えられたシーンであるということである。つまり、資本として確立された演劇の本質である「観客を愉しませる」という精神性(例えば序文で触れた「客席降り」のように)が、劇スでの一連のレヴューには宿っているのである。
本編冒頭で大場ななは、6人に圧倒的な力の差を見せつけて鏖殺せしめる。その圧倒的な力の差を誇示しながら舞うように刀を振るう彼女を観て、映画館へと足を運んだ観客はふと思う。ああ、これがずっと観たかった『レヴュースタァライト』だ、と。もっとも、「皆殺しのレヴュー」(と「狩りのレヴュー」)においては事情はもっと特殊で、大場ななはおそらくこのレヴューで「処刑」というスペクタクルを視聴者たちに供するべく、意識的に刀を振るっていたのだろう(*2)。「これはオーディションにあらず」という台詞によってTVシリーズと劇スの「レヴュー」概念が全く別の相を示していると判明する。
ワイルドスクリーンバロックは、誰かに主催されたオーディションという体のレヴューではなく、彼女たち自身が創り上げた舞台として我々に供される。TVシリーズでは競演することのなかった(ふたかお、かれひかを除く)因縁の相手同士が、互いに譲れない想いをぶつけながら、多彩な衣装に身を包んだ劇スのレヴュー群。自分本位の欲望を原動力として、オーディションを勝ち抜こうとするTVシリーズとは対照的に、劇スには、視聴者たちを心から愉しませようという本物の舞台女優に欠かすことのできないプロ精神と願いが溢れている。
この地点において、監督、脚本家、キャスト、諸々の『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』を創造した人々の想いと、作品内部のキャラクターである彼女たちの良い舞台を創りたいという想いが完璧にパラレルなレベルで釣り合っていることに驚嘆してしまう。それはまた、彼女たちが舞台少女という殻を脱皮して、女優として羽化したことを意味している。
「舞台は私たちの心臓。歌は鼓動。情熱は血」、そして「私たちは舞台に生かされている」というTVシリーズ11 話の台詞があるが、劇スで起きたことはまさにその通りと言える。彼女たちはなりたい自分を目指すべくレヴューを通して過去と決別していくことで、自らを舞台女優へと再生産していくのである。
以上、説明したように「レヴュー」という『スタァライト』の表現手法は、劇スにおいて完全な形で完成したと筆者は考えている。もちろん各レヴューの絵作り、演出が舞台演劇をテーマにした作品のシーンとして純粋に素晴らしいスペクタクルであることは間違いない。しかし、それ以上にその情景が登場人物たちの成長や想いとオーバーラップし、現実を侵食する(そんな錯覚さえ覚える)——まるで冒頭に記した『レヴュースタァライト』と実際の演劇との相似点のように——描写の数々を計算的に生み出した演劇アニメとしての卓越性には目を見張るものがある。認めよう。劇スのレヴューは、単なる戦闘シーン以上の価値がある。
そういえば、『レヴュースタァライト』には「二層展開式少女歌劇」という肩書きがあった。現実の舞台とアニメがシンクロしていくコンテンツという意味だったのが、今やその肩書きは本来の意味合い以上の価値を持っているということができるだろう。「レヴュー」の真の完成。それが私が見出した、劇スが傑作である理由の一端である。
*2 中世において公開処刑は、大衆にとって演劇に比しうる娯楽であった。
3.再生産される、レヴュー『スタァライト』
……演劇が暗々裡に含んでいる形而上学は、常識と同様に実在論的である。それは思惟に還元できない宇宙を前提とし、色彩、音、さらに形のなかにさえも、いかなる化学もその代わりとなりえない一つの実験に現前を結合する。
演劇はその宗教的な本性を一つの類似(similitude)より得ている。この上なく卑猥なノードヴィルさえ神の所業の模倣である。己が夢を外化しようとの意思より生まれて、劇はその意志を全能の想像力という完全性に到達させんとする欲望を表している。劇は神の似姿たらんとする人間の、最高の世俗的努力を表している。(佐々木健一訳)
以上は、フランスの哲学者、アンリ・グイエの著書からの引用であるが、彼はここで「劇とはひとつの宇宙であり、劇作とはもうひとつの現実性(*3)を創造する形而上学たりうる」と述べている。
幼いひかりが発した「舞台の上ではどんな奇跡だって起こる」という台詞はその本質を端的に表している。『レヴュースタァライト』のメタフィクション性は演劇の形而上学と噛み合っていると言える。なぜなら、劇中のレヴューで描写されるどんな不可思議な現象、演出、ツダケン声で喋るキリン——たとえそれが死であってさえ——も、それは現実の舞台で起こる出来事と同じように、物語の中で実際に起きた端的な現実として回収されてしまうのだから。
しかし劇スにおいて、その作中の現実性もまた、より上位の現実性に回収されるという事態が起きてしまう。愛城華恋は舞台に立つ恐怖に慄き、『レヴュースタァライト』を演じ終える恐れから心臓を止める。そのシーンで突如として隠されていた真実が告発される。我々が『レヴュースタァライト』として認識していた作品さえも、レヴューのひとつであるレヴュー『スタァライト』であったのだ(*4)。その事実は否応なく我々に動揺をもたらす。物語の中で彼女が愛城華恋役の愛城華恋として、その一挙手一投足に演技が伴っていたこと。物語内部において平坦だと思われた物語と登場人物たちの身分が、そもそも現実の役者–役柄という関係と同じように、レイヤー的に分化していたという複雑な入れ子構造を成していたこと。まさに、今までの『レヴュースタァライト』観が根底からひっくり返るような告発ではないか。
『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』というひとつのレヴュー。その枠組みが導入されたことによる作品内への寄与は、もちろん観客の意表を突くという一点に留まらない。
考えてみれば『レヴュースタァライト』とは、実際の舞台とアニメーションが双方向に影響を与えながら展開していく稀有なコンテンツだった。神楽ひかりとの約束のためではなく、舞台と観客のために演じる役者として再生産を果たした愛城華恋。「愛城華恋は舞台に一人」という高らかな口上は、愛城華恋が愛城華恋役としての『スタァライト』という戯曲の呪縛から解放されたことを指している。舞台版『レヴュースタァライト』では演者:小山百代−役:愛城華恋という絆が結びついていたように、アニメ『レヴュースタァライト』では媒体の違いによる差異こそあれ、演者:愛城華恋−役:愛城華恋として結びついていると考えられる。しかし再生産を果たした愛城華恋はもはや「愛城華恋という役」から脱し、端的な実在として浮遊する役者–愛城華恋へと自己を再定義したのだ。アニメという媒体でありながら、劇スは物語に登場するキャラクターを、他ならぬそのキャラクター自身が超越的に演じ、しかも自身が自身を役として演じていることに自分で気づくという——演劇の本質に即した構造に則って——稀有な演出を取り入れている。このシーンの存在によってこの作品はフィクショナルな存在であるキャラクターたちを、極めて高い水準で実存(現実としての存在)へと昇華させていると言っていい(*5)。さらに舞台として生身の人物が演じる舞台少女たち(キャラクター)が、相補的に役としての舞台少女たちを補完していく。そこに『レヴュースタァライト』という作品群の真髄があると言えるだろう。
加えて、劇スによって再生産を果たしたのは、なにも登場人物たちだけではない。『レヴュースタァライト』もまた、物語の主人公である役者−愛城華恋と共に再生産を果たした。そう私は解釈している。愛城華恋が神楽ひかりと幼い頃約束したあの「スタァライト」を演じるために奮闘し、紆余曲折の末に2人で共に舞台に立つ。それがTVシリーズにおける『レヴュースタァライト』の概略であった。だが劇スの結末において2人はもはや決別し、役者−愛城華恋は再び生まれ変わって『レヴュースタァライト』を演じ終える。再び生を受けた愛城華恋と神楽ひかりの間に、「レヴュースタァライト」の電光が橋のように掲げられているのは印象的だ。彼女たちは、まだ見ぬ自分だけの舞台へと歩を進めていく。ならばきっとこれから先、我々の前に展開されていく『レヴュースタァライト』もまた、あの時死んだ役−愛城華恋とともに列車に乗って再び生まれ変わるのかもしれない。『レヴュースタァライト』はもはや、愛城華恋が神楽ひかりとともに「スタァライト」を目指す物語ではない。新たな彼女と同じようにそれは今までと同じような相貌ではなく、かつての『レヴュースタァライト』とは全く違った新しい舞台となるだろう。
——列車は必ず次の駅へ。破断と再生という革新を行いながらも、傑作であった劇ス“後”のこれからの『レヴュースタァライト』が栄えのあるものになるように。筆者にはそんな、『スタァライト』製作陣の気概と祈りを感じざるをえないのである。
*3 哲学に明るくない方に向けて軽く説明させていただきたい。形而上(けいじじょう)学(metaphisics)とは経験的に実証することのできない事象を探究する学問、つまるところ答えのない議論を延々としている、世間がイメージするだるい哲学像のことである。さらに「現実性」という言葉で筆者は永井均、入不二基義(いりふじもとよし)らが牽引しているいわゆる「現実の哲学」を念頭にしていることを一応書いておきたい。これは専門用語で「ナマの事実(Brute fact)」と呼ばれる概念に連なる議論である。めちゃくちゃ簡単に(多分間違っている)説明すると「それ以上でもそれ以下でもなく、ただ事実として受け入れることしかできない類の事実」である。「現実の哲学」は、今ここに生起して、それを端的な事実として受け入れることしかできないこの現実(あなたが今まさにこの文章に目を通している(た)という事実が、まさにそれなのである)についての議論である。
*4 議論の補足のために、『スタァライト』という作品において「(レヴュー)スタァライト」という言葉が持つ意味合いを列挙してみよう。
我々がブシロード発のコンテンツとして享受する「スタァライト」。
作品の登場人物が演じ、愛城華恋が作中で その存在を仄めかした「スタァライト」。
幼い頃、愛城華恋と神楽ひかりが鑑賞した、作中の演劇作品として登場する「スタァライト」。
愛城華恋の口癖であり、おそらく舞台に立つ役者として観客を魅了する様を意味すると解釈できる「スタァライト(しちゃいます!)」。
*5 ここで少し補足で、キャラクターの実在性について議論を加えてみたい。マンガやアニメの登場人物はあくまで架空の存在であるというのが、世間の一般認識である。が、一歩引いた視点から見てみると、我々と同じ有機的なあり方をしていないだけで、そもそも紙面やスクリーン上には確かに現実の対象として存在しているのである。その意味では、確かにキャラクターもまた実在していると言えるだろう。我々はキャラクターの非在性に依拠し、依存しながら、その実在を探し求める矛盾した存在なのである。
4.さいごに
筆者と『レヴュースタァライト』の出会いは、note(*6)にもすこし書いた通り本当に偶然だった。
作品の存在そのものは昔から知っていたが、視聴する機会はなかった。劇スの評判を知り、当時演劇をモチーフとした小説を書いていたので興味を持った。1週間でTVシリーズを観終えて、何の気なしに映画の予約をした。その結果、頭は爆ぜ、人生で2番目に衝撃を受けたアニメ作品になってしまった。今までどんな映画も1度観れば満足していた自分が10回を超えるほど映画館に通い詰め、例外なく嗚咽を溢し、その回数は現在でも進行的に数を増やしている。
今回、劇スについての考察を卒業文集という体で合同誌にまとめると聞いて、及び腰ながらも参加させて頂いた。結果的にまとまりなく、癖を全開に出した小難しいだけの文章になってしまったかもしれない。あくまで『スタァライト』という作品についての考察記事なので突っ込んだ理論研究の説明ができず、色々な意味で中途半端な文章になってしまったという自覚もある。しかしこれで、『レヴュースタァライト』について私が書きたかったものは全部吐き出したつもりである。
——列車は必ず次の駅へ。
ここまで不出来な文章をお読みいただき、感謝に堪えない。すこしでも何かを感じていただいたのなら、これ以上嬉しいことはない。本当に、ありがとうございました。
*6 https://note.com/preview/nd3859b91b11d?prev_access_key=8c17220f75c468513b07ac691bd7ff16
参考文献
宮本直美(2014) 『レビューのmortality とimmortality ——ジャンルとしてのレヴューと宝塚歌劇団』立命館文学(635),60-75.
Noel Carroll(2008). On Criticism(Thinking in Action).Routledge. (ノエル・キャロル 森功次(訳)(2017). 批評について 勁草書房)
Henri Gouhier (2001). L'essence du théâtre (二版). Librairie Philosophique Vrin.(佐々木健一(監訳) (1976). 演劇の本質 阪急コミュニケーションズ)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
