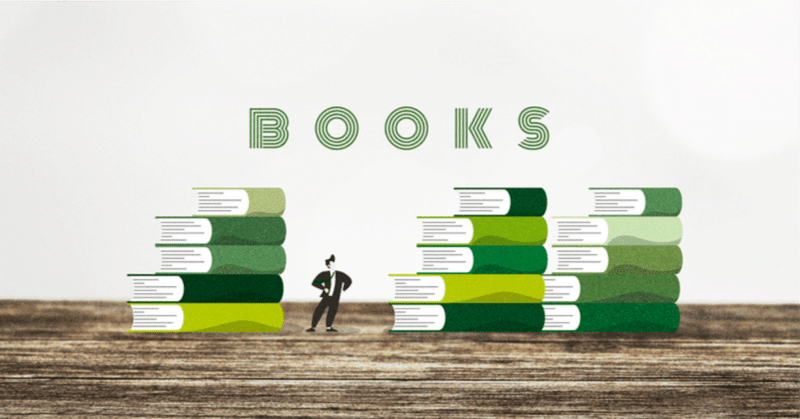
《コラム》なぜ私は「書評」を書くのか?│(「僕が批評家になったわけ」)
※この記事は、書評記事として執筆を始めたものの、冒頭だけであまりに長くなったので、単独コラムとしたものです。書評記事は近日中に投稿予定です。
────────────────────
私は、現在、noteに「書評」と題した記事を5本投稿していて、今後もしていくつもりである。しかし、なぜ「読書感想文」ではいけないのか、という疑問がある。というのも実際、noteでは、「#書評」の着いた記事より、「#読書感想文」の着いた記事の方が多い。人によっては、書評など「何様だよ」と思うかもしれない。
では、なぜ私は書評という形式を取るのか。正直な事を言うと、あくまで私個人の感想なのだけど、「書評というのは何か大人っぽい気がするから」というのが第一である。もう少し補足すれば、評論の方が、個人の感想より社会的意義を持つのではないかといった具合だ。実際、新聞にも書評欄はあれど読書感想欄はない。レビューにはある一定の社会的意義があるのだろう。「読書感想をネットに上げてます」より「書評をネットに上げてます」と言った方がちょっと素敵な気が、私はする。
しかし、では何故、評論というのにはある種の意義があり、個人の感想と一線を画すのかという理由については、これがサッパリ分からない。私も、人並みに、「書評を書く理由」といった記事を書いて、なるほどこの人はだから感想ではなく書評を書くのかと納得されたい。しかし、前段落で書いた通り、私が書評の形式を選んだのは単なるファッションである。そこで、この本を見つけたのである。
「僕が批評家になったわけ」、ならば批評というものの性質を恐らく論じている事だろう。そして、単なる感想には留まらない評論の価値というのにも言及があるかもしれない。それを知った上で今後書評を書くのと、知らないで書くのとでは、雲泥の差である。つまり私は、本書からその論理を有難く拝借させて頂こうと、盗人根性で読み始めたのだ。
それが間違い
さて、この私の姿勢は、素晴らしい噛み合いで即刻著者に指摘される事になる。
もっとも、この本のそもそもの趣旨が批評とことばの本だ。批評とは何か、ということで専門家(?)がふだんはどういっているのかを知りたいという人も、いるだろう。実は筆者も、そのことを少し知りたくなった。(中略)
いまはむしろ、違うことをいいたい。こちらのほうが大事かもしれない。
それは、もしあなたが、そういう読者なら、というのでいうと、批評とは、そういう知り方のレールから、脱線することだ、ということだ。
つまり、批評の核心とは、「自分の頭で考える事」だという。本を一読して、「ああ、著者の言う通り!」というのでは批評ではないのだ。さて、私は弁明しなくてはならない。このままだと「批評家」(名乗ったつもりはないが)「失格」だとこの記事の読者に看做されてしまう。実際、書評を書く意味を自分で考えなかった事は致命的な気がしてきた。
改めて、本書はまだ読み途中なので、重大な記述が出てくる前に、書評の意味を考え直そう。私が考えたのは以下の通り。
書評とは、作者の思考の表現媒体としての作品に対し、こちら側の思考で応答する試みである。つまり、二次的な創作行為である。感想というのはあくまで個人の側、作品を読んだ私の側を論ずる行為である。これに対して、評論の場合、作品の側と私の側を交互に論じる。つまりは、私が受けた感想をベースに、この作品とはこういった性質を持つと論じ、それに対して応答する。ここでは、作品の構造の読解が求められるだけでなく、ある種の論証的な主張を提起する必要がある。
さて、評論における社会的意義だが、むしろ意義がないというのが考えられない。日常生活は往々にして、「評価」によって成り立っている。例えば、今、noteという媒体を使うか、個人ブログを立ち上げるかを決める場合、これは2つの媒体の評価が必要である。作品に至っても、善し悪しだけでなく、前衛的なのか伝統的なのかを推し量り、作品を「位置付ける」には、評論が必要である。もう少し言えば、作品が売れるか売れないかは読者の評価によって決まるが、その評価を提示するにあたって、ある種の理屈を付けるなら、評論という形式を取る。
多くの人は、評論を必要ないと思うかもしれない。自らの個人的な感想だけで十分ではないか、と。しかし、ある種の客観性を主張する事は、バラバラであるが故に見えなかった作品の本質を、定めようとする試みである。客観性の意義は、誰の間にもその論理が共有される事、ではないか。無論、それを一人の人で完全にやってしまおうというのは、確実に傲慢さが出る。しかし、多数の評論という形で集合知が発揮される時、その作品は位置付けを正式に完了される。
と、いった所で勝負したい。本書はそれ以上の回答を見せてくれるのだろうか。
※今までに書いた書評記事の例
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
