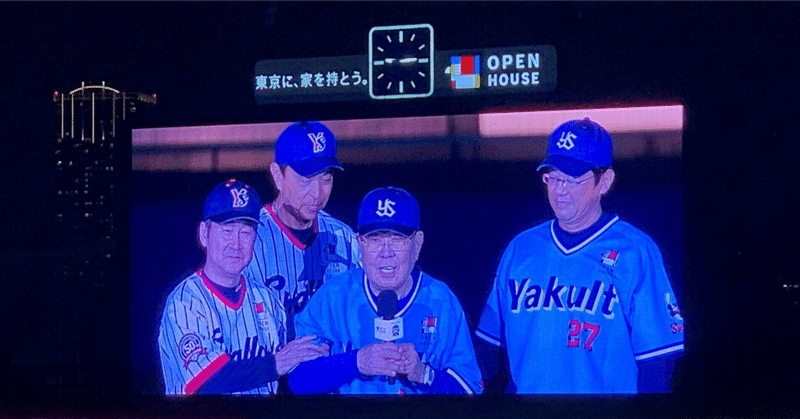
#110 野村哲学の深層〜言葉のチカラと人材の成長〜
はじめに:コミュニケーションの中核に立つ言葉の意義
言葉の選び方一つで、組織の雰囲気や文化が大きく変わることがあります。特に、新しいメンバーのオンボーディングや経験者のさらなるスキルアップの場において、正確かつ感動を呼ぶ言葉を用いることは欠かせない要素となります。この記事では、野村克也氏の言葉を元に、効果的なコミュニケーションの方法を探る旅をしてみましょう。
1. 言葉を使い分ける力
(1)相手の立場と感情のキャッチ
新入社員やチームメンバーの背景、知識レベル、現在の感情や状態を理解することで、その人に合わせた最も効果的な言葉を選ぶことができます。例えば、チームプロジェクトの進行中、メンバーが迷っている時に「大丈夫、一緒に考えよう」と声をかけることが、信頼関係の構築に繋がります。
(2)フィードバックの技法
ミスや問題がある場合、どのようにそれを伝えるかは非常に重要です。直接的すぎると反発を招く可能性がある一方で、曖昧すぎると伝わらない。例として、プロジェクトの遅れに対して「どうして遅れてしまったのか、一緒に原因を探りましょう」とアプローチするのは一つの方法です。
2. 言葉の持つ変革力
(1)ビジョンとミッションの具現化
言葉は、組織の目的や方向性を具現化する役割を果たします。明確なミッションステートメントは、メンバーが共通の方向を持つ手助けとなります。例えば、ある製品開発チームが「ユーザーの生活を豊かにする」というミッションを持っている場合、その言葉が製品の品質向上や機能追加のモチベーションとなり得ます。
(2)自己変革の契機として
ある一言や本からの引用によって、自らのキャリアや人生観が大きく変わる人は多い。これは、言葉が私たちの心や考え方に強烈な影響を与える証拠です。例として、あるセミナーでの講師の言葉が、参加者のキャリア選択の方向を変えたという事例があります。
3. オンボーディングと人材育成における言葉の役割
(1)オリエンテーションの重要性
オリエンテーションでの上層部のメッセージや先輩からのアドバイスは、新人の企業やチームに対する第一印象を形成する重要な要素です。言葉選びの工夫により、新人が安心感を得て積極的に活動に参加するきっかけを作れるでしょう。
(2)継続的なトレーニングの実施
継続的なコミュニケーションスキルのトレーニングは、チームの結束を強め、プロジェクトの効率を上げることが期待されます。例えば、定期的なロールプレイやケーススタディを活用して、現場の実際のシチュエーションを模倣することで、効果的なコミュニケーションスキルの習得が促進されるでしょう。
まとめ:言葉の力を最大限に活用しよう
言葉は単なるコミュニケーションの道具ではありません。それは、人の心を動かし、組織の文化を形成する強力なツールです。リーダーとして、野村克也氏の教えを胸に、日々の経営や人材育成の現場で的確な言葉を選ぶことの重要性を再認識し、実践していきましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
