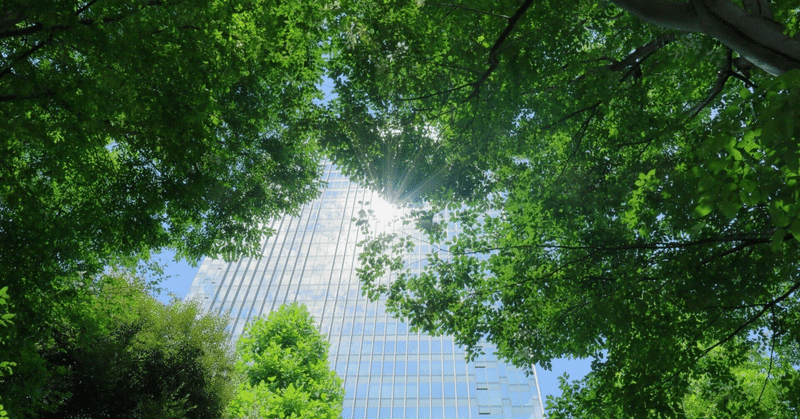
経営理念は赤字会社を救わない
鹿児島で社労士をしています原田です。
企業の根幹となる考え方や方向性を定めるものとして、
企業理念・経営理念・企業目標・経営指針 等様々なものがあります。
混同して使っている場合もあります。また、企業や個人で異なる解釈をしている場合もあります。文書化し、言葉にすることで伝えるためのものとしてそれぞれを確固たるものとして作成して、周知実行しているのであれば、混同していても特に問題はありません。
それぞれの役割と考えられているもの
①企業理念
企業の社会における存在意義を示すもの。何のために存在し、何のために事業を行っているかを示すものです。一般的にはあまり変わるものではありません。
②経営理念
企業の活動を行う上で、大切にする価値観や考え方のことです。①企業理念と合わせて「経営理念」という人もいます。
③経営方針
②経営理念を基に、企業の基本方針を定めたものです。②経営理念より具体的になり、様々な経営判断を行う場合の基本的な考え方になります。
④経営戦略
経営方針で定めたものを基準として、どの方向に向かって企業を進めるのかを具体的に定めたものです。掲げる目標が意味する理由や、行う行動の理由付けになるものとなります。③経営方針と④経営戦略を合わせて経営方針と言う場合もあります。
⑤経営計画
②経営理念、③経営方針、④経営戦略を基盤として、具体的な目標になるものです。基本的には数値目標であり、行動目標まで定める場合もあります。各部署の目標まで定めることもあります。
⑥経営指針
②経営理念、③経営方針、④経営戦略、⑤経営計画をまとめて経営指針と言います。経営ビジョンや単純にビジョンと呼ぶ場合もあります。一般に全て又は一部を公開している場合もあります。経営指針書として文書かしている場合もあります。
3年~5年の期間で成長するための具体的道筋を定めた経営指針書を、中期経営計画と呼ぶ場合もあります(3年~5年⑤経営計画の計画を中期経営計画と呼んでいる場合もあります)。
⑦社是
①企業理念や②経営理念を言語化したもの。そもそも企業理念も経営理念も言語化するので、社是自体が企業理念や経営理念だったりする場合があります。会社の◯箇条とか行動規範等の名称で社是を掲げる場合もあります。
⑧社訓
社是が理念であることに対して社訓は方針や行動規範を指す場合が多く、②経営方針と同様に使われる場合が多いです。
⑨クレド
ジョンソン・エンド・ジョンソンが考案導入したと言われ、リッツカールトンが使っていることで有名になった言葉で、②経営理念や⑥経営指針を従業員に浸透するようにしたものをクレドと読んだりします。単純に浸透まで考慮せずに②経営理念=クレドだと解釈している場合もあります。先に言いうリッツカールトンの場合は、従業員が共有している理念・価値観のことを意味します。
必要とされる理由
解釈はいろいろあるのですが、本来必要なのは
・定めて
・周知して
・全員が理解する
ことまでが本当はセットです。そのため多くの企業では、唱和したり覚えさせたり、文書や手帳を配布したりしています。何のためにやっているかを理解しないと、「カルト宗教のようだ」と揶揄されるので、そのメリットを理解しなければなりません。
最も重要なのは、経営判断として重要視されることです。
例1)身体や精神にも危険性が無く、利用者に著しい不利益が生じるものでもない些細な不良品が発生した場合に、企業の判断としては
1.どんな些細なものでも一般に公表して回収する
2.次のロットから修正し、一般に公表はしない
3.クレームマニュアルを作成して、修正もしない
4.その程度の発生リスクぐらいはありえるとして何もしない
といった判断が行われます。
例2)新分野進出で、売れて儲かる分野と言われているが、倫理観を損なう恐れが高い分野である場合に、
1.企業価値や利益を優先して進出する
2.企業倫理を優先して進出しない
3.子会社を使って本体はやっていない素振りで進出する
といったような、様々な判断を行う場合があります。多くの判断において、理念が浸透している組織であれば、どこが判断してもそれが理念に基づく判断であるなら、組織のほとんどが納得できるものでなければなりません。(理念に書いてない分野の判断には対処できませんが)
こうした経営判断が現場で行っても上席で行っても同じような結論になるのであれば、現場で判断する裁量が増加し、意思決定がスピーディーにできる利点があります。
また、理念に合わない人は採用できませんし、理念に合った人材しか昇進できないので、強固な組織作りが可能になります。これは退職者を減らし、同時に不要な人を排除することができます。
更に、方向性が定まっているので、それに沿った人材育成も可能ですし、従業員のモチベーションアップや統一されたコンプライアンスの認識も可能となります。
タイトルと話が違うぞ
良い話ばかりで、タイトルと違うと思う方もいるでしょう。
メリットを並べてみると気付くことができます。
・意思決定がスピーディーにできる
・強固な組織作りが可能
・退職者を減らす
・不要な人を排除する
・人材育成も可能
・従業員のモチベーションアップ
・統一されたコンプライアンスの認識
これらには、赤字企業を黒字化させるポイントが希薄なのです。
そもそも赤字企業は、ビジネスモデルが成長軌道から外れており、従業員がモチベーションが上がらない最大の理由は、低い給料とそれが上がる見込みが無いことだったりします。
企業の持つビジネスモデルで黒字を出せなければ、従業員全員が経営理念を理解できても業績は上がりません。
衰退産業を機関産業とする企業では、従業員の退職率を減らすどころではなくリストラが必要な状態で、本業ではない別の産業を基軸に再構築しなければ、存続すら困難な場合も多数あります。
業績悪化も「理念を変化させることで対応できる」と言われる方もいます。しかし基軸になる成長産業を既に持っていた上で、それに沿った理念への変化でなければ、理念をまた変えることになります。
そもそも、事業が長期的に低迷しているということは、企業理念たるその企業の市場における存在意義が乏しくなっている可能性が高いのです。
経営がうまくいく万能な武器などありません。そのそれぞれが合った形で、優先順位を定めながら、必要な手法を採択できることが重要です。
面白いとか、役に立ったとか、つまらないとか思って頂けたら、ハートをお願いします。ツイートやFBで拡散して頂けると、とってもうれしいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

