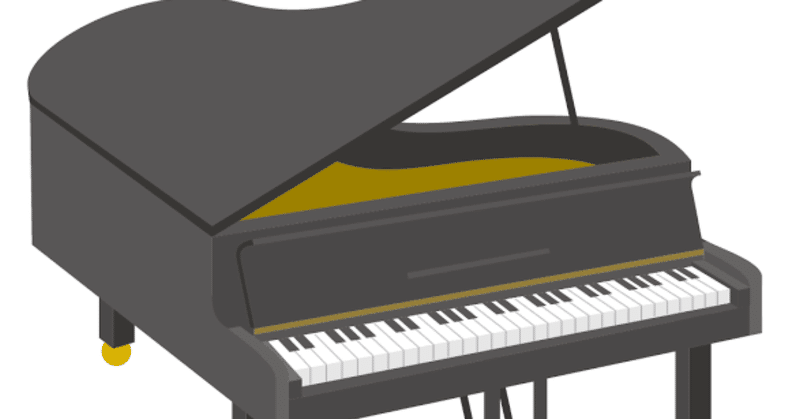
ピアノのバッハ2: イギリス組曲に寄せて
ピアノで弾かれるバッハ、ピアノでバッハを弾くことが大好きです。
KAWADE夢ムックというムック本があるのですが、そのムック本にグレングールドのために編まれた一冊があります。
発売が2000年四月なので古い本です。
グルードの録音を聴いたりするときに、いまだに時折、本棚に手を伸ばしたりしています。

1982年に五十歳で亡くなった、生きながら伝説となったカナダのピアニストを教祖のように崇める音楽愛好家には、とても興味深い本です。そうでなくとも、いろんなグールド評の詰まった、非常にマニアックな勉強になる本。
グレン・グールドの名前はクラシック音楽を普段から聞かない人にさえ、文化的アイコンとして、彼の名前だけは聞いたことがあるのでは。
そして彼の遺した録音、全くいわゆる「クラシックオンガク」的ではないので、クラシック音楽愛好家には異端的で、大好きな人は大好きなけれども、ピアノ専門家で蛇蠍の如くに嫌う人も少なくありません。
特に音楽の先生はグレン・グールドを生徒さんに聞きなさいとは言わない、聞いても真似しちゃダメよと釘を支える始末。
さて何をもって正統な音楽を信奉するクラシック音楽教信者たちをして、グルードを異端と言わしめるのか。
ムックからの引用
上記のムック本に面白い引用がありましたので引用してみます。
明石政紀さんという音楽評論家が寄せられた「小プレリュードと小フーガ集: または小さなグレン隊」というエッセイ。
バッハが小さな子供たちのために書いたFugetta (小さなフーガ)の曲集がありますが、あまり有名ではありません。ピアノ初学者が弾かされてバッハ嫌いになるインベンションとシンフォニアなどよりもずっとステキなメロディに溢れていて、それでいて正真正銘の立派なフーガなのですが、技術的にかなり易しいので、全く子供向き。
でもこの子供の手習いのための作品は、異才グルードの手にかかると、平均律曲集のフーガ並みに面白い音楽になるのです。
このホ長調、とてもリズミカルで楽しいですね。
ニ長調。個人的にこれ、大好きです
オモチャの軍楽隊のようなへ長調。
ドラマチックなニ短調、BWV935。
そこで引用です。
サラ・トゥーストラ (八歳) へのインタヴュー(ベルリン、1999年)
ー「サラちゃん、グレン・グールドの《小フーガと小プレリュード》を愛聴しているんだって?」
ー「うん」
ー「どうして?」
ー「だって音のツブツブが気持ちいいじゃん」
原文はドイツ語のはずですが、「音のツブツブ」はまさに言い得て妙。
音のツブツブ感、ただスタッカートなだけでは音楽は「気持ち良く」なりません。
音楽の快感は、リスナーの音楽的嗜好に左右されますが、まず音楽の三要素のどの部分をより愛するかで変わってくるように思えます。
音楽の三要素、バッハのリズム
ビート音楽が強調する、一定間隔で繰り返されるリズム
ヒーリング音楽などで強調される、陶酔的な快感に通じる深いハーモニー
カラオケなどで好まれる、いわゆる歌いやすい抒情的なメロディー
クラシック音楽の世界では、バッハはリズムに、ベートーヴェンはハーモニーに、そしてメロディーにおいてはモーツァルトが傑出しているとよく言われます。
バッハのリズムですが、何がバッハのリズム的要素をバッハ足らしめているといえば、舞曲であることです。
舞曲はバッハの生きていた時代のバロック音楽全盛時代に後の世につながる音楽形式として器楽曲に取り入れられましたが、舞曲は文字通りに「踊る」ための楽曲。
その踊る音楽を器楽的に複雑化して芸術的に完成させたのがヨハン・セバスチャン・バッハでした。
バッハと同時代のヘンデルやクープランの器楽的舞曲も素晴らしい。
でも音楽一族バッハ家の家長であるヨハン・セバスチャンは、家業を受け継ぐ子供たちに「舞曲とは何か」を徹底的に教え込むために、「フランス組曲」「イギリス組曲」そして「パルティータ」を、子供たちの鍵盤音楽学習の練習曲として書いたのです。
超高度な教則本!
「小前奏曲と小フーガ」もそんな練習曲集の一部。
そこで「音のツブツブ」なのですが、西洋音楽の基本は拍にあります。
世界の民族音楽の中には拍を重んじない音楽もたくさんあるのですが、西洋音楽は二拍子とか四拍子とか、拍のある音楽にこだわり続けた音楽でした。
拍とは繰り返されるリズムパターンのこと。ビートは刻まれるリズムのひとつひとつ。つまりツブツブ。
でもツブツブの刻み方に工夫が必要。
四拍子ならば、1234 | 1234 | 1234 etc. という具合。大事なのは拍の区切りである冒頭の1の拍のリズムを強調すること。
1234| 1234 | 1234 etc.
という風に演奏することで、強拍と弱拍が生まれます。
アクセントのある言語の英語やドイツ語と同じです。フランス語や日本語のように全ての音を平板には奏でないのです。
応用として二拍目、いわゆる裏拍を強調する音楽も出てきますが、これがまず基本。

三拍子で二拍目を強調するポーランドのマズルカとかも、一拍目を強調する普通のサラバントやメヌエット、ワルツがあるからこそ意味深いのです。
でもですね、器楽音楽において、舞曲を舞曲らしく演奏するのはなかなか難しい。
音符が複雑になればなるほど、強拍をしっかり鳴らして舞曲らしさを表現するのが大変です。いや弱拍とのコントラストを表現するのが大変でしょうか。
ショパン国際ピアノコンクールでは一等賞二等賞とは別に、マズルカ賞という特別賞がありますが、あれはショパンのマズルカを最も舞曲のマズルカらしく奏でた人に贈られます。
一等の優勝者が必ずしももらえるわけでもないのは、それだけ舞曲を奏でるのが難しいから。マズルカはショパンの音楽の魂と呼ばれるだけあって、本当に表現が難しい。
さてバッハですが、グレングールドの奏でるバッハの舞曲が快感を感じるほどに素晴らしいのは、グールドはどんな音楽を奏でても、拍を重んじた繰り返されるリズムの躍動を強調することにあります。
メンデルスゾーンを弾こうがショパンを弾こうが、グールドか全く同じ姿勢で奏でることは賛否両論ですが、ことバッハに関しては文句なしに素晴らしい。
バッハはまさにそういう音楽を想定して作曲したからです。
どんなに複雑なフーガでもリズム感を失わせないグレン・グールドのバッハ。
ゆったりとしたテンポでも息の長い拍が常に生きていて、いつだってグレン・グールドには、音楽とは舞曲なのです。
そしてスタッカート気味の規則正しい機械的なタッチは、バッハの音楽を弾くためにあるようなもの。(グールドにはフルペダルでルバートするブラームスのインテルメッツォのような録音もありますが、スタッカートが好きなのがグールドです)。
バッハはピアノのために鍵盤音楽を作曲しませんでしたが、歌う打楽器であるピアノと相性が良いのは、歌いながら踊ることが想定されているから。
ヘンデルにもたくさん鍵盤楽器のための舞曲はありますが、彼のステキな鍵盤音楽音楽は非常に器楽的。
でもバッハではそれが渾然一体と融合しているのです。
ヘンデルの場合
歌いながら踊り、踊りながら歌うのが、バッハ。
オペラ作曲家ヘンデルは歌劇場の歌と器楽音楽の舞曲を分けて考えていたきらいがあります。
需要が違いますからね。バッハの練習曲の演奏難易度が高いのは、歌って踊るから。だから芸術的。後年のクレメンティやチェルニーとは雲泥の差があるわけです。
例えば「愉快な鍛冶屋」。ヘンデルの名作。
これはチェンバロ組曲第五番ホ長調の一部ですが、変奏曲部分は、既存の型にはまりすぎていてイマイチです。指の運動の技巧を披露するには良いので、かのラフマニノフが録音を残したほどに非常に楽しい名品なのですが。
歌って踊りながら演奏するグールドがバッハを得意としたことは当然ですね (グールドはヘンデルをほとんど演奏しませんでした。ヘンデルがグールドにとって面白くないのは当然でしょう。そういう音楽なのですから)。
二拍子のガヴォット
先日、コンサートホールのアンコールで、バッハのヴァイオリンのための「ロンドのガボット」を聴きましたが、
それ以来、イギリス組曲のト短調のガヴォットにハマり、二分の二拍子である舞曲「ガヴォット」が面白くてなりません。
バッハ以外で最も有名なガヴォットはやはりフランスのゴセックでしょうか。近代の新古典主義のプロコフィエフのガヴォットも素晴らしい。
二拍子の音の強弱をしっかりと強調すると、この単純な音楽が文字通り踊り出すのです。
聴くよりも、演奏する方が楽しい。踊るとさらに楽しい。
バッハの舞曲集
イギリス組曲はイギリス風舞曲のジーグなどばかりで構成されている訳ではありませんが、フランス組曲にはない、長大な前奏曲が冒頭に置かれていて、弾き通すのはフランス組曲よりも技術的に難しいのですが、今回、第三番ト短調のガヴォットに親しんだので、全曲弾き通しましたが、やはり良い音楽です。
全六曲の組曲中、多くのピアニストに録音される最も有名な大傑作は第二番なのですが、第三番も負けず劣らず素晴らしい。
「音のツブツブ」
さてサラちゃんがツブツブと表現したのは、バッハの音楽ではいつだって規則正しく八分音符なとか刻まれて、ビート音楽のように長い音符が奏でられていても、音楽が細かいリズムを刻んでゆくからでした。

モーツァルトなどを奏でると長い音符では演奏者が拍を数えて音を伸ばしますが、バッハでは細かいビートが絶えず刻まれます。
これが音のツブツブ!
ジャズのリズムセクションのように、ピアノは細かい音符を刻んで、でもアクセントのある音符とアクセントの弱い音符を弾き分けるピアニスト。バッハの場合はビート担当は左手だけでなく右手と絶えず入れ替わる。
演奏は慣れるまで大変ですが、出来るようになると快感なのです。
そんな弾き分けの超天才が、グレングールド。
でも誰もがグールドのように弾かなくてもいいし、いろんなバッハがあってもいい。
バッハは、音楽の超基本の、「強く弱く強く弱く」の拍子感のある音楽を誰よりも忠実に守り続けたのでした。
弱起で「アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ!」
これが基本。バッハを聴くと、意識していなくても、音楽のアクセントとビートの上がり下がりを体感出来るのです(イタリアオペラの長大なアリアには美声に対する陶酔感はあってもリズムの快感を感じることは少ないのです)。
だからジャズミュージシャンにも尊敬されるし、クラシック音楽なんて古臭いと見下すような音楽家にまで、バッハは一目置かれるのです。
音楽の基本、それは音のツブツブを体感できること。バッハはビート音楽なのです。
ガヴォットの二分の二拍子の音楽のアクセントのない空間には、弱い拍のツブツブがある。それを体感できる時、ああ音楽って素晴らしいとわたしは心から思うのです。
イギリス組曲、フランス組曲ほどに弾きやすくなくて、メロディーのチャーミングさに欠けますが、ビートを体感できる舞曲性はこちらの方が上。
イギリス組曲にフランス組曲、どちらも素晴らしいけれども、わたしはイギリス組曲を聴いて弾いて幸せになれました。良い日曜日をお過ごし下さい。
ほんの小さなサポートでも、とても嬉しいです。わたしにとって遠い異国からの励ましほどに嬉しいものはないのですから。
