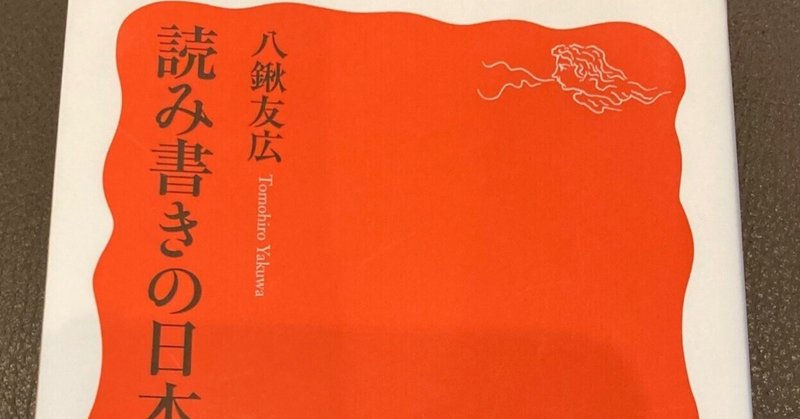
江戸時代:市井のリテラシー
八鍬友広 著『読み書きの日本史』岩波新書.2023.6.を読んで
1. 近況
月6か所ほど読書会に参加するようになってきた。意見交換が活発になる時、参加者間の解釈と、進行役の座の取り回しで思いがけない共鳴作用のようなものが生じることがあり、読書会沼は深い。30年継続して運営している会もあり、課題本選定作法が独特。顔見知りができてくると(あの方はどう読み解かれるか。)を心待ちにする。同時に、読みが浅い自分を振り返って反省する。
2.読了感
往来物を軸に、動くテクストから固定のテクスト(教科書の指定)への移行について、教育の歴史社会学的な観点で表された貴重な本として読みました。
公私文書作成および読解は難易度が高く,ひらがなを知っているだけで、公文書の読み書きと直結しなかった。仕事で師弟制を通じ、初心者は周辺的な作業に従事しながら、これらを熟練者に学んでいった。その過程は、レイヴとウェンガーによる「状況に埋め込まれた学習」、正統的周辺参加1)を表すとの指摘が興味深い。読み書きの学びは実践知として社会的な背景(身分制の世襲)や文脈のなかに埋め込まれ、おのおのの学びが積まれて熟達者となっていくうち,共同体を形にしていく。
「読み書きの習熟度にはグラデーションの層がある(p.149)」より
・近世でいう花押文様化された署名を記すことが出来る識字者。筆子碑の風習や、門人帳、軒付帳の詳細から、当時の教育実情が伝わった。
・公私文書を読解し作成しうることと、教養として読み書きができる層。この層が市井で無数に広がった点について、少し埋もれている女性の実態を知りたいと思った。
・江戸時代瓦版や読み本のような市井の文書で娯楽文化が広がった2)傾向は、外国人が日本人の識字率が高いと驚いたきっかけとなった。つまり、ひらがなを知っていれば(公文書ではない)瓦版を読める人達を見て、読み書き能力が普及していると。
3.私見
江戸時代の民間塾リテラシーを、丸谷才一氏による情報リテラシーのコツに紐づけて考えてみる。米澤誠氏の書評3)によると丸谷氏は、「目次や索引を活用して必要な情報だけを仕入れる,インデックス・リーディングという手法を推奨する。また、多様なものを要約,概括して,そこから一つの型をとりだす。それがものを考えるときに非常に大事」と述べている。このコツを実践知で活かしたのが、下記の庄屋民間塾の事例と考えられる。
江戸時代の唐津では庄屋塾が盛んだった。『知行合一(ちこうごういつ)』を目指す(儒学の一派)陽明学に限りなく近いスタンスをとった。陽明学は、凶作の時に庶民の救済を求めるなど実学志向で、幕府の統制の対象だったが、同塾では農民対象に自由な討論も行われていた。全国3千件あった一揆の成功例はほんのわずかだが、「虹の松原一揆」成功の背景に民間塾で鍛えられた指導力があったと指摘4)される。つまり、米澤氏が丸谷氏から学ばれた「自分の得意とする分野をホーム・グラウンドとして,他分野のあらゆることがらについて,自分のホーム・グラウンドで考えることも重要なコツ」を当時の唐津藩の民は寺子屋リテラシーから学び取っていたともいえる。
情報過多の現代。リテラシーは、紙でも電子媒体でも「そこに記載されている情報は本当かな。」と信頼おける人や媒体(二次資料)で確認すること。そして、よい本を読んで文章で表現されることを内に取り込み、外に発信することかもしれない。
4.つぶやき
p.6「漢字をこれほどまでに自家薬籠中のものとした国は他にないとも言われている。」
他国の文化を取り込んでのアレンジは、日本人の特性かと思う。文字のみならず料理もそう。中国人は華僑となっても自国の料理を作って広める。日本ほど日常的に(軽食中食外食で)和洋折衷の料理を作り味わう国は珍しいのではないか。
孤独な読者p.218については、少々消化不良気味。読書会までに再考できればと思う。
5.引用・参考文献
1)正統的周辺参加
人間の学習を状況に埋め込まれた活動とみなす状況的学習論において,レイヴ(Lave, J.)とウェンガー(Wenger, E.)が提示した。学校以前からの徒弟制において、熟達者から新入りに技が伝承していく様子を観察した研究がもとになっている。
正統的周辺参加と足場づくり - 教授システム学専攻 - 熊本大学
https://www.gsis.kumamoto-u.ac.jp/opencourses/pf/3Block/09/09-1_text.html
2)江戸時代における化粧文化と書籍文化 ―往来物・教訓書と玉屋景物本から探る―
星野, 菜々子 中京大学文学会論叢 9 69-90, 2023-03-15
https://chukyo-u.repo.nii.ac.jp/records/18999
3) 米澤誠著.「丸谷才一が語る情報リテラシーのコツ」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/52/1/52_1_57/_pdf/-char/ja
4) 唐津藩・庄屋の民間塾盛ん 実学志向120年間で30ヵ所 一揆の成功例も導く
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/418859/
参考文献
島村直己著「近代日本のリテラシー研究序説 」
https://repository.ninjal.ac.jp/records/1151
これまでの港区史(資料グループ)新修港区史(目録)新修港区史(1) 学制発布前の教育(テキスト)
https://adeac.jp/minato-city/text-list/d100010/ht101850
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
