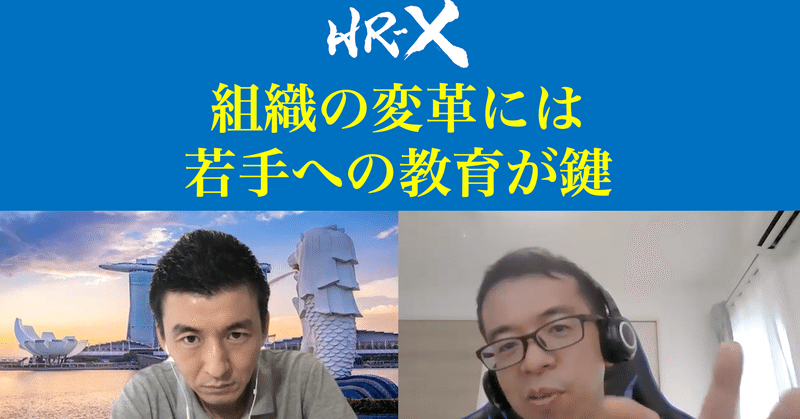
組織の変革には若手への教育が鍵/高山久さん(横河電機株式会社 人財開発部)
高山久さん プロフィール
横河電機株式会社 人財総務本部 国内人財統括部 人財開発部 ラーニング&ディベロップメント課長
立教大学経済学部を卒業後、株式会社オカムラに新卒で入社し、法人営業を経験後、人事部門に異動し、人事管理業務に従事。SCSK株式会社に転職後、人財開発(グローバル人財育成等)、人事制度企画・運用(シニア関連、副業解禁等)を幅広く経験し、2019年11月より横河電機に入社。今後大きな変革にチャレンジしていく同社にて人財育成、教育領域のマネージャーとして変革を目指して育成施策の企画全般に従事。
(四方)
こんにちは!スパイスアップ・ジャパンの四方健太郎です。
「人事」のHRと「トランスフォーメーション」のXを掛け合わせて「HR-X」と名付けた当番組は、「トランスフォーメーション人材で組織を変革する」をスローガンに、「人事」と「トランスフォーメーション」、つまり「変革」というキーワードで様々な取り組みをしているゲストをお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。
今回のゲストMr.Xには、横河電機株式会社人財開発部の高山久(ひさし)さんをお迎えしました!
高山さん、こんにちは!
(高山さん)
こんにちは!
よろしくお願いします。
(四方)
よろしくお願いします。
高山さんとは以前に所属されていた会社でも海外研修をやらせていただいたり、最近でもいろいろグローバル人材育成に関してのご相談をいただいたりとしていますが、実は同い年だったり、サッカーが大好きだったりという共通点があって個人的には勝手にすごく親近感を持ってお付き合いをさせていただいておりますが、今日はビジネスパーソンの働き方や人事マンとしての革新的な変革というテーマで色々お聞きしたいなーと思っているんですが、まずは自己紹介をお願いできますか?
(高山さん)
高山久と申します。
今、横河電機の人事の方で働かせてもらっていて、横河電機は3社目で1年半くらいお世話になっています。
主に人材育成のマネージャーをしておりまして、新人教育から始まって選抜、マネージャーの教育というところの企画、実施をコーディネートしています。
プライベートとしては四方さんとの共通の趣味のサッカーで、最近やるのはご無沙汰ですけど、Jリーグの清水エスパルスを熱狂的に応援しておりまして、盛り上がれないシーズンが10年くらい続いているんですが、粘り強く応援しております。
そんなところです、よろしくお願いします。
(四方)
よろしくお願いします。
横河電機さんといえば、サッカーチームをお持ちでクラブチーム化したというところで、僕もサッカーチームをやってますので、エスパルスのところに向かって行っていますので応援して欲しいなと思っております。
さて、今日は組織の変革というキーワードなんですけど、これは永遠のテーマといいますか、各社さん色々悩まれていると思いますが、高山さんならではのユニークなお考えがあると伺っているんですが、ご紹介いただけますでしょうか?
(高山さん)
私ならでははちょっと大袈裟な話ですけども、横河電機のビジネスを簡単にお話しすると、いわゆる制御と計測をビジネスの強みにしている会社です。
具体的には石油プラントとかガスプラントみたいなところの精製や材料の制御などに色々な機器を導入して、そこに強みを持ってグローバルカンパニーともやりとりをしている会社です。
ただ一方で石油とガスって、サスティナビリティや気候変動というワードでいくとともすると悪者になってしまいますし、これからESGみたいな形で考えていくと、シュリンクしていったり、ジリ貧みたいな表現をしてしまっている業界ではあります。
なので今はまだビジネスとして成り立っていて、お客様にも重宝されているんですけど、今後はシュリンクしてしまって、じゃあ次どうするかというところを模索している状態です。
その中でいくと今年から新しい中期経営計画を出しているんですけど、社会課題を解決する会社になるんだ!というのを一言で打ち出していて、社会課題に対して社員はどうマインドチェンジして、どういう方向でどういうビジネスをしていくんだというのを考えなければいけない。
そういう意味では会社もそうですし、社員も変革していかなければいけないというバックグラウンドが今あります。
その中で私が今やっているところは、教育全般を見てはいるんですけど、特に若手の教育に力を入れてやっています。
組織の変革には若手への教育が鍵
(高山さん)
具体的にはもちろん基礎教育もやりながら若手、特に新人から3年間くらいのところの情報のアンテナ、外への興味を喚起するための取り組みということを年次に合わせてやっています。
新人とか若手なので、ビジネスに大きなインパクトをすぐ与えられるかというと、日系企業ならではというところで、そこまでできることではないんですけど、一方で組織が大きくなればなるほど、上に行けば行くほど外の情報を取りにいくというアクションが起こりにくいですし、実際情報を取りにいってもそれを社内で展開しようというのはやりにくかったりすると思います。
なので若手に外の情報を入れることによって、職場の変革の火種になり、そういう情報が入ることによって、職場でまずは話題になって、それってうちのビジネスと繋がっているのかな?とかそういう新しい展開に持っていけるんじゃないかなって思って、色々な情報提供をしているところです。
それは研修だったり、それこそ四方さんや豊田さんに講演してもらったりとかそういうもので刺激を与えたりしています。
(四方)
会社にはヒエラルキーといいますか、色々な年次がある中で会社自身が変わらなきゃいけない!と恐らく中計にもあるようにトップマネジメントがそういう意識があるとは思うんですが、それをトップからじわじわと落とすのではなく、むしろ1年目から3年目という若手に経営資源をフォーカスさせようというのはどんなところからなんですか?
マネジャーよりも若手にフォーカスする理由は
(高山さん)
そうですね、もちろん上の方にいくとビジネスへのインパクトが大きいので、そこの方々がマインドチェンジをすると大きな変化になると思います。
ただ一方で変化をする感度は年次が上がれば上がるほど、なかなか変え難いものが出てきてしまっていますし、人事としては本来、何か施策をする時は上からやるのがセオリーなんですけど、そのセオリーが通用しなくなってきているなっていう側面も感じところもあるんですね。
下からやることがメインストリームになるというわけではないかもしれないけど、全社一律に何か大きな方向を示して、ヒエラルキーの中で展開されるっていうことがなかなか機能しなくなっているんじゃないかなって感じるところはあります。
(四方)
ある意味予測ができない、先が見えないVUCA時代だからこそ、経験が邪魔をしてしまうこともあるので、経験が浅い方が革新的なアイディアが生まれてきたりするってことがあるんじゃないかってことですよね。
この取り組みをされてて、仰っていたような若手が外から情報を引っ張ってくるとかマインドが変わって組織に与えた良い事例は何かありますか?
若手が組織の変革に影響を与えた事例
(高山さん)
私が直接やっていることではないのですが、若手メンバーをプロジェクト化して未来のシナリオを描くとかっていうのをHRが仕掛けているプロジェクトがあります。
実はそれも中計の考え方の1つに入っているというところもあって、そのプロジェクトのメンバーは我々ともコミュニケーションを取っているのですけど、そこで面白い話が結構あって、1つは2035年の横河電機を考えるプロジェクトなんですけど、じゃあ2035年の話を部のミーテイングで話をしたところ、トップの反応としては「2035年のことは分かったから、今は目の前の仕事をしろ!」ということでした。
もっとひどい話でいくと、「飯の種にもならないから、そんな話を部の中でしないでくれ!」ぐらいのことを言ってしまったりということが、初期の頃はあったようです。
それが実はうちのビジネスに繋がっていくという話を徐々に出すと、そこから部長陣の反応が変わってきて、「どういうことなんだ、意味分かんないわけにはいかないから教えてくれ」と部長の方から聞きに来たりという話も出てきてるらしいんですね。
そこは私が仕掛けているわけではないので受け売りのところがありますけど、そういうことって今後も起こり得るかなって思っています。
(四方)
それ無茶苦茶良い話ですね。
HR側もそうかもしれないですけど、初めに一定の抵抗ってあると思うんですよね。
それを気にしないといいますか、愚直に今の信じるやり方を突き進んだ結果、部長陣が聞く耳を持ってくれるところまで持っていけているということですよね。
仕掛けるにあたり、変革を起こしやすい組織と起こしにくい組織、どんなところに違いがあるんですか?
変革を起こしやすい組織・起こしにくい組織
(高山さん)
なかなか一言でってなると難しいかなと思うんですけど、気に入って最近色々なところで喋っている話としては、「組織のサイロ」というワードって結構あると思うんですね。
サイロ化する、要は内側に篭ってしまうというような形で使われるんですけども、それってリレーショナルアナリティクスという関係性の分析みたいな話の中でいくと、日々のメールやチャットのやりとりの比率が、内部が5に対して外部が1を切ってしまうとサイロになりやすくなります。
それがメールでもなんでもいいんですけど、内側の人たちとだけやりとりしている組織はサイロ化してしまうし、変革を起こしにくい体質になってしまうかなと思うので、外との関係性を定常的に持っている組織は変革を起こしやすいんじゃないかなと思います。
(四方)
なるほど、でもこれはそうですよね。
それこそ高山さんとは仕事の中でお付き合いもありますけど、HRないしはそれをも飛び越える異業種交流会みたいな中でも共通の仲間がたくさんいたり、ああいうところに人事部の方自身がある意味サイロに陥りやすいので、どれだけ外と接点を持っていて、越境学習なんて言い方もしますけど、そういうものの価値観が良いなって思ってる人が人事であれラインの上長であれ、そういう人がいないと変化って起きにくいでしょうから、もうはなからどんな大企業であっても当たり前なんだということを、若手の頃からマインドとして身に付けてしまえば、これがグーって上がっていっても良い変革しやすい組織になるんじゃないかということですね。
ちなみに先ほど若手は変わりやすい、ないしはちょっと上に上がってくるとなかなか変われないというお話がありましたが、高山さんが個人的にチャレンジしていることをよかったら教えていただけないでしょうか。
いまチャレンジしていること
(高山さん)
今、組織を見させてもらっていて、教育の部門でも外の情報を取りに行くということがなかなかできてなかったりするんですよね。
なのでそれを取りに行こうぜ!っていうことで勉強会もそうですし、自分が外で学んできたことを社内にシェアするってことは積極的にやっています。
まだまだ結果に結び付くというところはこれからですけど、まずは自分が学んでいる姿を見せるというところが必要になってくると思っています。
(四方)
コロナの前でしたら、異業種交流会とかビジネススクールなど色々あったと思うんですけど、オンラインなってからはどうやってやってるんですか?
(高山さん)
そうですね、やっぱりどういうことを学ぶかって結構難しかったりもすると思います。
仰る通り、MBAに行くと教材が全部あって、それを学んでいけばいいと思うんですけど、最近感じるのはちょっと尖った学びをしている人を知っているかがキーなんじゃないかなって思っていて、そういう人がこういうの面白いよとか、この本面白いよとかで引っかかってくるのが、リモート環境下でいくと本屋で手に取ることが難しかったりするんですよね。
そういう意味でいくとSNSでもなんでもそうですけど、尖った人を知っていることは結構重要かなっていう気がしますね。
(四方)
コロナの前から掲げていたアンテナがあってこそというのもあるし、今のこの状態になってもなんらかの掲げ方があったり、逆に自分から発信することでキャッチしてもらったりとかってことですよね。
(高山さん)
そうですね。
(四方)
でもHRの中の人が外に向いていかないと、当たり前っちゃ当たり前ですけど、そういう人を周りは見ていて、やってないじゃないかと、若手が変わっていくって言うのは簡単ですけど。
今日は示唆に富むお話、ありがとうございました。
僕らもそういう機会を作れるんじゃないかとか、我々はある意味横串で繋がりやすいですし、自分自身もそうでありたいですけど、そういう尖った人を人事の方にご紹介できていけたらなと思いました。
そんなことがひょっとしたらビジネスチャンスになるんじゃないかなっていう風に高山さんのお話から思いましたし、僕自身が勉強させていただきました。
さて、HR-Xではこれからも「人事」と「トランスフォーメーション」というキーワードで、様々なゲストをお呼びしてお届けしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
それでは今回はこの辺でーー―!
高山さん、どうもありがとうございました!
(高山さん)
ありがとうございました!
四方健太郎(株式会社スパイスアップ・ジャパン取締役/ Spice Up Singapore PTE LTD Managing Director)
立教大学を卒業後、アクセンチュア株式会社の東京事務所にて、主に通信・ハイテク産業の業務改革・ITシステム構築に従事。2006年より中国(大連・上海)に業務拠点を移し、台湾・香港を含む大中華圏の日系企業に対するコンサルティング業務にあたる。2009年にフリーランスのコンサルタントとして独立。独立後、1年かけてサッカーワールドカップ2010年大会に出場する32カ国を巡る「世界一蹴の旅」を遂行し、経済界社より『世界はジャパンをどう見たか?』を上梓。
現在、東南アジアやインドでグローバル人材育成のための海外研修事業に従事。株式会社スパイスアップ・ジャパン取締役。シンガポール在住。
株式会社スパイスアップ・ジャパン
公式ウェブサイト https://spiceup.jp/
公式フェイスブック https://www.facebook.com/SpiceUpJP/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
