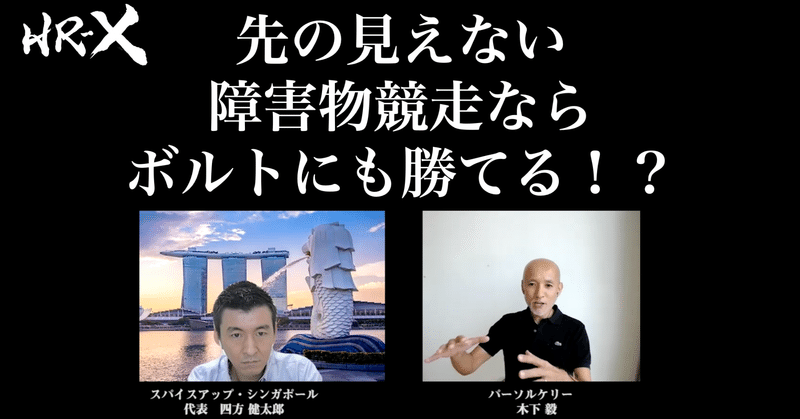
先の見えない障害物競走ならボルトにも勝てる!?/木下毅さん(パーソルケリー・ジャパンデスク責任者)
木下毅さん プロフィール
PERSOLKELLY PTE. Japan Desk ASEAN Sales Director
NTTデータ入社3年目より海外子会社の経営支援、米国企業との業務提携支援など海外事業支援を数多く担当。1997年、マレーシア支店立ち上げに伴い、クアラルンプールにて経営基盤を整備。
帰国後、ヘイコンサルティンググループに参画。日本企業、外資系企業向け各種人事制度構築を数多く担当。2006年、ジャパンデスク立ち上げに伴い、中国上海へ赴任。人事戦略策定、育成体系整備、各種人事制度構築、組織風土改革、事業戦略策定支援、研修講師、ファシリテーションまで幅広く担当。
2010年、エーオンヒューイットチャイナに参画。2013年からは南アジアも担当し、タイ、シンガポール、マレーシアでのプロジェクト実績を多数有する。
2016年、IWNC中国に経営として参画。ローカル人材を対象とした経営塾の立ち上げ、組織変革をリード。
2018年11月、パーソル総合研究所入所。同年12月マレーシア着任。
現在は、クアラルンプールをベースに、アセアン域内でTalent Acquisitions、人事制度構築、構造改革支援、人材育成まで広範囲に及ぶサービスを提供。
(四方)
こんにちは!スパイスアップ・シンガポールの四方健太郎です。
「人事」のHRと「トランスフォーメーション」のXを掛け合わせて「HR-X」と名付けた当番組は、「トランスフォーメーション人材で組織を変革する」をスローガンに、「人事」と「トランスフォーメーション」、つまり「変革」というキーワードで様々な取り組みをしているゲストをお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。
今回のゲスト「Mr.X」には、マレーシア・クアラルンプールをベースにしながら、アジアの日系企業を中心にHRコンサルティングサービスを提供する、パーソルケリー・ジャパンデスクの木下毅(つよし)さんをお迎えしました!
木下さん、こんにちは!
(木下さん)
こんにちは!
お招き、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
(四方)
木下さんとは、10年前、僕がアクセンチュア中国でコンサルの仕事をしていたときのお付き合いで、あのときはコンサルという業種は同じですが、どっちかと言うと上海で奮闘するビジネスマン仲間というか、ただの飲み仲間というか・・・(笑) それから僕はひょんなことからHRの業界にやってきたことになるわけですが、木下さんはもう20年くらいこの業界にいらっしゃる大先輩。
ということで、まずは自己紹介をお願いできますか?
(木下さん)
ご紹介いただきました木下と申します。
現在マレーシア・クアラルンプールをベースに東アジアを含むアセアンで事業活動されている日本企業を人と組織という文脈でサポートさせていただいています。
個人的にはマレーシアは2回目の赴任で、新卒で入った日本企業でもマレーシアに駐在していた経験があるので、20数年ぶりにマレーシアに駐在しています。
その後、四方さんと出会った上海には12年、干支も1周したということで、そろそろ次なる地へということでマレーシアに縁があって来ていますけど、海外生活は今年で25年目に入りました。
順番でいくと、アメリカ、マレーシア、中国、マレーシアとなります。
見た目はこんな感じなのですが、謎のアジア人でパスポートの色は無色という事で、この地で色々な形で日本企業を支援させていただいております。
(四方)
なるほど、ありがとうございました。
パスポートの色は日本だったら赤か紺色だったり緑色を持っている人がいたりしますけど、無色というのは新しいですね!
アメリカや中国、そして東南アジアを見られていて、マレーシアに居ながらも色々な国に行かれたりすると思うのですが、海外から企業を見られている立場から、海外に居るからこそ気付く日本企業が変わらなきゃという点はありますか?
海外から見える、日本企業が変わらなきゃ!という点
(木下さん)
僕は人事制度や育成をやっていますけど、一番最初、中国に渡ったのが2006年の10月で、そこ以降ずっと海外で日本企業を人と組織という領域から見てますけど、2006年当初に課題や問題だと思ったことと、コロナの前後で課題、問題の本質はそんなに大きくは変わっていないんですね。
古くて新しいという表現する方もいますけど、例えば2006年の中国にある日本企業ですと給与や評価制度の考え方とか。
それは今でもこのマレーシアに移って、アセアンの国々で日本企業を見ていますけど、基本的には大きく変わっていないです。
もう少し分かりやすく言うと、日本のものをポンと持ってきて、それを取り敢えず導入して運用をしているのですが、そもそもこれイケてないよなということもあります。
日本の型を持ち込むと言ったらいいんですかね、もうそろそろというか遥か前に変わってくれなきゃ困っちゃうんですけど、どうも日本人は「型にはめる」ことが好きなんだとすごく感じます。
日本は製造業を中心として成り立ってきたわけですが、例えばアメリカをターゲットとして追い抜け追い越せという時代がずっと続いてきている中でいくと、明確なターゲットがあって、効率化をしようとすると型化が必ず出てきます。
製造現場では必要だと思いますが、どうも非製造の部門にもどんどん入っていって、考え方はこうだ!これじゃなければいけない!
且つ決めたことは絶対曲げない、とにかく愚直にやり続ける、それで結果が出てきました日本企業!みたいなものが海外では相変わらず綿々と続いていて、ローカルから見るとこの人たち何言っているのかな、ついていけません、みたいなことが特にコロナになってよく感じるようになりましたね。
(四方)
型にはめてきた「勝利の方程式」みたいなものがあったがゆえに、マネジメントも含め、慣らされちゃっていて、それがゆえに変われないとかビジネス環境が違う海外なのに同じやり方をしてしまうことに疑問を持たないということでしょうか。
(木下さん)
そうですね、そういう人たちで圧倒的に多いと思います。
普段接する日本企業の駐在の方はだいたい新卒で入社され、ずっと同じ釜の飯を同じ会社の仲間と食べ続けて、気が付くと色々な型にはめられているんですね。
日本でその組織にいるのであれば良いと思いますが、海外って全く違う価値観があるので、そこにポンと持ってきて、これでやりなさいと言われても現場の人たちは付いていけないんじゃないかなと思います。
(四方)
冒頭に仰っていたコロナだから、というわけではなく、元々そういう傾向があるというお話だったのですが、まさに今VUCA Worldという、先が読めない不確実な時代、コロナがやってきて急激に価値観や働き方が変わってきている中で、組織や個人には何が求められているんですかね?
VUCAワールドな今、組織や個人には何が求められているのか
(木下さん)
表現的に許されるか分かりませんけど、平たく言うともっとみんなバカになったらいいと思うんですよ。
日本人の皆さんはかなり真面目なんですよね。
昔からやってきたことを一度リセットして何もなかったようにアホな顔してワァーって何かをすることを日本人はなかなかできないんですよね。
染み込んじゃっているってところがあると思います、僕も含めて。
だけど今みたいに世の中が大きくパラダイムシフトを起こして、変わっていく中では過去はこうだったからとか成功体験や型がこの先果たして意味を持っていくのかというと、ほとんど意味の無い物になってしまうのではないかなと思っています。
無価値化するなんて言う人もいますけど、そういう世界に入ってきていると先ほど言ったバカってどういうことかと言うと、昔のことを忘れてもっと楽しくおかしく今できることをとにかくやってみる、ダメだったら違うことをやっていこうよという感じで今に適応する道を探していくって言うんでしょうかね。
(四方)
ゼロベースと言うか、アンラーニングと言うか過去のしがらみを一旦外して考えてみようよと。
(木下さん)
そうそうそう、「脱・型化」を含めてね。
(四方)
そうかそうか、型とか、ないと。
今この状況にどういうのが一番フィットするのかをゼロベースで考えてみようよ!ということですね。
(木下さん)
それを製造業がやってしまうと品質や安全性はどうなんだという話になってしまうので、全業界やりましょう!なんて言うつもりはないですが、少なくとも企業の経営に携わる方々は一度リセットする必要があるのではないかなという気はします。
(四方)
僕らは伝統的な企業とお仕事をすることもあれば、革新的な企業、大きく分けて2種類のタイプがあるのですけど、変革できる組織と変革できない組織、ゼロベースで考えられる組織とそうではない組織の違いってどんなところにあるんですか?
変革できる組織と変革できない組織の違い
(木下さん)
僕の答えは1つしかなくて皆さんご理解いただけると思うのですが、基本は全部リーダーだと思います。
組織のリーダーがどういう行動や発言をしているのかだと思います。
やっぱりいくらボトムアップでやろうっていっても上がそれを抑制したらおしまいになるので、上が変わるぞって意識を持っていただいて、自ら行動していくことで下に落としていくということ。
当たり前なことなのですが、その当たり前がなかなかできないんじゃないかなーと。
できている企業はオーナー企業ですよね、ファーストリテイリングの柳井さんなんて分かりやすい例じゃないですか。
日本電産さんも。
あれだけの規模の会社でもオーナーシップでバリバリ上から改革していくと下も変わらざるを得ないし、やっていかないといけないので。
他方、トラディショナルな日本の会社はどうかというと、表現が適切かは別として皆さんサラリーマン社長ですよ。
社内政治で上がった人がいれば、そうじゃない人もいるのですが、やっぱりそういう人たちに変革を求めること自体に限界が来ているんでしょうね。
(四方)
型にはまることである意味出世された方もいらっしゃるかもしれませんが、ひょっとしたら悪気があるのではなくて、会社のシステムがそうだったから、ご本人もそうなってしまっているのかもしれないですね。
一番難しいところかもしれませんが、そのような会社って少なくないと思っていて、その会社が変わっていかなきゃいけない場合はどういう風に変えていくことが良いのでしょうか?
(木下さん)
僕が人事担当者や人事担当役員に掛け合ったところで変わらないでしょうね。
インパクトを与えられるとすれば社外取締役だと思うのですが、基本的にお友達クラブですよね。
(四方)
イエスマンしか入れたくないでしょうからね。
(木下さん)
社外取締役っていらっしゃいますけど、そこに改革を迫るような人たちってあんまりいらっしゃらないですよね。
四方さんの質問の答えになってないんだろうけど、根本的には想いとして中期経営計画に変わりたい!って掲げているけど、そこに座っている人が心の底から変革をするぞ!と思っていないリーダーがいる会社は無くなるんですよ、きっと。
時間を掛けて衰退していくんだと思います。
そういう時代なんじゃないですかね。
(四方)
生物学的にも環境変化に耐えられなければ、種としては絶滅するしかないですしね。
(木下さん)
自分たちを変えられない人は淘汰されていくんだと思います。
(四方)
僕たちは50年とか、実体験に紐付く100年くらいの歴史しか見られてないけど、本来はもっと長いですし、体感としては10年は長いですけど、企業の歴史の中からいうと10年なんて一瞬でしかないですが、このタイミングで衰退、無くなる会社もありますよね。
(木下さん)
今、企業の寿命が短くなっていますよね。
日本には100年企業はたくさんありますけど、とはいえ短くなってきているので、まさに変化に付いていけない企業が多いということなんだろうなと思います。
今みたいな時期だから加速度的にギュッと短くなっているということが起きているんですね。
(四方)
氷河期なのか隕石が落ちてきたのか分かりませんけど、素早く変化できる企業が強いのかもしれないですね。
(木下さん)
僕が昔勤務していた某外資HRのコンサルティング会社でもラーニングアジリティって言ってましたけど、本当にそうだと思っていて、今までは100mを9秒、10秒で早く走ることが求められていたのですが、でも今は障害物競走で、しかもどんな障害物が降ってくるのか分からないけど早く駆け抜けないといけないという世界なんですよ。
(四方)
それは良い表現ですね!
今は100m走ではなく、障害物競走になっていて、スタート時点ではその先に何が出てくるのか分からないということですね。
何が来ても変化できる引き出しを持っておけということでしょうか。
(木下さん)
そうですね、昔の100m走はラクでしたよ。
ボルトが活躍していましたけども、さすがのボルトでも無理だよという世界ですね。
(四方)
ボルトも障害物競走だったら勝てるか分からないですからね。
(木下さん)
パン食い競争だったら、彼勝てないんじゃないかって話ですよ。
(四方)
障害物競走ならボルトに勝てるかもしれないという捉え方もできるわけですよね。
(木下さん)
この間、あるところに寄稿したのですが、コロナが全世界で起こったことによって経済がボロボロになり、どこの国でも変革しないと!と言っているのですが、日本のイケていた企業、イケていなかった企業もスタートラインはどの企業も同じになったのかもしれないですよね。
それでヨーイドンで障害物競走が始まってみんなで一気に行くぞ!と。
ですので、この先どの国が出てくるのか、どの企業が勝つのかはまだまだ分からないですよね。
(四方)
いやー本当新しい時代というか、スタートラインに立たされた、ないしは既に差がついてしまっているのかもしれないですが、これも分からない中で暗中模索をしているというところですかね。
(木下さん)
中国はなんとなく先を行っているような感じはありますね。
(四方)
あー、そういう風に見ますか!なるほど。
本日は僕ら、組織の話にフォーカスしましたけど、恐らく個人も同じで組織を構築しているのは個人だったりもしますし、我々個人が生き延びていくのはまた別の話ですからね。
ただ結局のところ、このような変化によって会社が潰れても自分は他の会社でやっていける、他の国でやっていけるようになっていかないといけないし、そういう人たちが集合している組織は一見バラバラに見えても実は強いんじゃないかと。
ダイバーシティマネジメントの話に繋がっていくのではないかなと思います。
(木下さん)
本当その通りだと思います。
まさに個が強くないと、これから先はしんどい世の中になっていくんだろうなと思います。
そうなると別に正社員じゃなくても良いんじゃないかなとここ何年か思っているところです。
あるプロジェクトがあって、こういうスペックの人材が必要ですと。
だったらそういうスペックの人材を外から買ってきて編成を組んだ方が結果として物凄い物が出るんじゃないかなと思います。
そこを正社員だけで編成を組もうとすると社内のロジックにみんな引っ張られてしまって、期待する成果が出ないんじゃないかなと最近感じています。
(四方)
外資系のファームにいると、割とそれを愚直にやっているところがあったと思っていて、日本の制度上、どうしても正社員にしないといけないとかあるのかもしれないですが、もっとフレキシブルな業務の進め方もあるのではないかなと感じますね。
この辺を伝統的な大企業でもそういった形を入れていけると変わっていけるんじゃないかなと思います。
(木下さん)
いや、本当にそうですよね。
他流試合とか人材交流を大手企業もやっていますけど、その背景にはもっと色々な価値観を取り込もうとしてるんだと思うんですよ。
だけど大前提が正社員であるべきだとかというところも崩していかないと変わらないですよね。
我々の母体は人材紹介をやっているので、あんまり言うと怒られちゃうんですけど、そういうところも変えるべきだと僕個人としては思います。
(四方)
あっという間のお時間でしたが、今日は色々と勉強になるお話をありがとうございました。
型にはめないとか、先の見えない障害物競走というキーワードが出たかと思いますが、まさにそんな時代かなと思います。
今日はありがとうございました!
(木下さん)
とんでもないです、ありがとうございました!
(四方)
さて、HR-Xではこれからも「人事」と「トランスフォーメーション」というキーワードで、様々なゲストをお呼びしてお届けしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
それでは今回はこの辺でーー―!木下さん、今日はありがとうございました!
四方健太郎(株式会社スパイスアップ・ジャパン取締役/ Spice Up Singapore PTE LTD Managing Director)
立教大学を卒業後、アクセンチュア株式会社の東京事務所にて、主に通信・ハイテク産業の業務改革・ITシステム構築に従事。2006年より中国(大連・上海)に業務拠点を移し、台湾・香港を含む大中華圏の日系企業に対するコンサルティング業務にあたる。2009年にフリーランスのコンサルタントとして独立。独立後、1年かけてサッカーワールドカップ2010年大会に出場する32カ国を巡る「世界一蹴の旅」を遂行し、経済界社より『世界はジャパンをどう見たか?』を上梓。
現在、東南アジアやインドでグローバル人材育成のための海外研修事業に従事。株式会社スパイスアップ・ジャパン取締役。シンガポール在住。
株式会社スパイスアップ・ジャパン
公式ウェブサイト https://spiceup.jp/
公式フェイスブック https://www.facebook.com/SpiceUpJP/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
