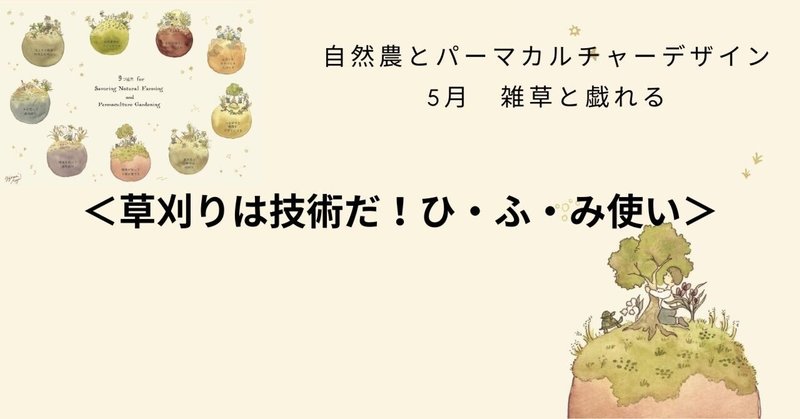
草刈りは技術だ!ひ・ふ・み使い

<草刈りは技術だ!ひ・ふ・み使い>
自然農がなかなかうまくいかない人たちに共通して勘違いしていることが「不除草」である。畑を見て「これ、草刈りしたら問題なく育つよ」とアドバイスすることも多い。
「不除草」ほど自然農で誤解されていることはないだろう。言葉のイメージが一人歩きしている。実際、自然農の職人たちはこまめに草刈りをするが、ただ草刈りするわけではなく季節や天気、野菜に応じて草刈りを使い分けている。草刈り一つで野菜が成長を早めたり、病気がおさまるところを何度も見てきた。だから「自然農の作業は何か?」と聞かれたら「草刈りがすべてだよ」といつも答えている。
江戸時代の農書には雑草という文字は数回しか出てこないが、草刈りの方法はよく出てくる。『農業全書』には「上農は草を見ずに草を取り、中農は草が見えてから草を取り、下農は見えても取らない。」(上農とは才ある農民、老功の農民、老農のこと)とあるように、昔から草取り一つで農家としてののレベルが測ることができた。草毟りの「毟」という漢字は中国にはない日本独自の国字である。草が多く生えてくる日本ならではで、日本人が昔からずっと草と向き合ってきた証だろう。
私が受けた研修先では来る日も来る日も草刈りばかりしていたことがある。そんな研修先が一番学びが多かったのも事実だ。そこでは草刈りの仕方をたくさん教わったが、私が講座で教えているのは主に以下の3つである。
一つ目は草削り。鎌の刃先を少し土の中に入れて、土を削るようにザクザクと草の根を残しながら刈っていく。決して根のすべては取り除かない。魚の三枚おろしのように、大地から草を丁寧に剥がしていく。
いきなり「不除草」のイメージと真逆かもしれないが、すべての草に対して行うわけではない。野菜の自立根圏内にある草を刈っていくタネを播くときや苗を定植するときに事前に自立根圏内を地際刈りをしておき、草マルチなどでむやみに草を生やさないように工夫する。
二つ目は高刈り。これは高さ約20~30cm程度の高さで草を刈る方法である。これは主に自立根圏外や畝肩、通路の草に対して行う。これは草を生かして、刈る。少し大人しくしておいてもらうイメージだ。
この理由は二つある。一つは地際刈りをしてしまうと、成長点が高い双子葉類の草が居なくなり、成長点が低い夏草(イネ科の植物)ばかりが生えてきやすくなる。夏草は生命力旺盛でかつ回復力に富んでいるので一度生えてくると草刈りの回数が多くなってしまう。双子葉類は夏草に比べて、とても大人しいため草刈りの回数が減る。
植物の種類によって成長点の位置は違うため、職人たちはそこの生えている草に応じて高さを変えていく。大地の再生の方々は風の草刈りといって、茎葉が風に揺られて曲がるところをノコギリ鎌でスパスパと刈っていくので、それを参考にすると良い。もしまだよく分からないときは、高さ20~30cm程度に合わせて、その後の草の勢いを観察してみよう。天候や季節、風の強さによって草の生え方は異なるため、観察を通じて一番草の勢いが減るところを見極めたい。そうすれば、草刈りの頻度も少なく済むようになる。
もう一つの理由は側根を増やして、微生物を増やすためだ。双子葉類は主茎を刈るとそれに対応している主根の成長をやめて、代わりに側根を伸ばすことで脇芽を伸ばしていく。この側根は菌根菌などの微生物と共生関係を結ぶ根である。つまり、高刈りをすると植物の側根が増えて、土中内の菌根菌も増える。
初心者の畑でよくあるコンパニオンプランツの失敗例がトマトが全然育たずにバジルばかり育つパターンだ。これはバジルが養分と水分を他の植物よりも早く吸収する性質があり、畝の養分・水分を独占してしまうから起きる。そこで行いたいのが三つ目の根切りである。
これは主に高刈りをした草がメインの作物の自立根圏内に入ってくる根に対して行う。特にコンパニオンプランツで混植しているハーブ類には必須である。ハーブ類の根が自立根圏内に入ってくると養水分をメインの作物よりも先に吸収してしまう。そうなるとメインの作物は育たないが、ハーブ類は育つ状況になる。これもまた初心者にありがちな失敗例だ。それを防ぐためにノコギリ鎌や移植ゴテなどで根を切って、メインの作物が育つように手助けをしよう。
また畝の肩で根切りをすることで残していた雑草の勢いを減らすこともできる。特に梅雨入りから夏至にかけての雑草の生育の速さは野菜よりも格段に早い。少し大人しくてもらうことにもなるし、畝の水はけを良くしてくれる。
このように自然農の草刈りでは根は必ず土に残す。残った根は土中生物の餌となり、団粒構造の土になる。自然界のように土は植物の根が耕し、団粒構造の土は土中生物が作る。
3種類の草刈りをすることで、土の上で得られることは光合成・呼吸・水分の3つである。
言うまでもないが、すべての植物にとって光合成ができるかどうかが肝だ。特に自然農では菌根菌との共生関係を結ぶことが重要であるため、その菌根菌に提供する糖分を作り出す光合成が十分に行われなければならない。そのため光合成の邪魔をしているようならば草を刈る。また光合成の邪魔になっていると徒長やツルボケの原因にもなってしまう。
さらにトマトなどのように光が当たることで熟す果菜類では10~14時の間に太陽光が実にしっかり当たるように葉を落としていく。特にまだ気温が上がらない梅雨時に有効だ。梅雨時は湿気の多さから熟す前に実割れを起こしてしまうから、青いうちに収穫するかこの剪定を行って防ぎたい。
次に呼吸だ。私たち人間などの動物は肺という臓器を持っているおかげでマスクをしても空気を吸うことができるが、植物には葉の裏に多い気孔を開閉することしかできないため、風が呼吸の助けとなる。葉に切れ込みがある植物は風の通り道を作ることで呼吸をスムーズに行い成長のスピードを速めている。風の強さは強すぎると倒れないようにするためエネルギーを茎を太くするために使ってしまうし、逆に風通しが悪い(風が弱い)とカビ菌が発生しやすくなるばかりか害虫にとっても居心地が良くなり集まってしまう。虫は全般的に風を嫌うため、風のないところに集まる習性がある。こうして草刈りによって、畝の上に「そよ風」が通るようにコントロールする。畝を横から見て、畝の肩と上の植物の形がかカマボコ型になるようにすると、草の勢いが弱まる。大地の再生の方々は「風の草刈り」と言って、そのように刈り込む。
最後に水分は根を伸ばす範囲とマルチで決まる。側根は菌根菌と共生関係を結び、菌糸ネットワークで養分だけではなく水分も根圏以上の範囲から集めてくれる。そのおかげで夏場の乾燥が強い時期でも水やりが必要ない。また乾燥があまりにも強い時期は光合成の邪魔にならない程度でかつ、そよ風が通るほどのに高刈りをして、他の植物を残しておくことで畝の上に日陰が生まれて過乾燥を防ぐ。また水分が好きな野菜には最初からそうしておく。逆に雨が多い年は地際刈りをして乾燥をうながすこともする。こうしてそのときの季節や野菜の性質に合わせて草刈りも変えていく。
この光合成、呼吸、水は日本語の数の数え方の「ひ・ふ・み」である。
自然農の作業は草刈り以外にもあるが、そのほとんどがこの3つをコントロールしている。「ひ・ふ・み」をコントロールすることで「世(よ)」の中に「命(い)」が宿る。
つまり草刈りとは、野菜がイキイキと育つために必要な「ひ・ふ・み」の環境を作り出す技術なのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
