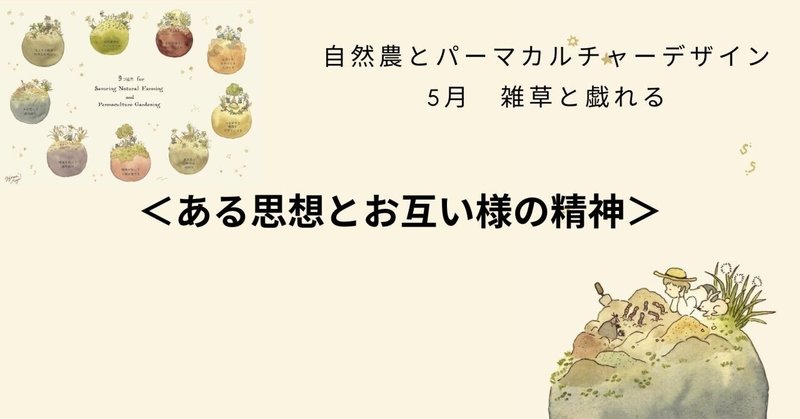
ある思想とお互い様の世界

<ある思想とお互い様の世界>
「ない」ということが「ある」ということ
「ある」思想は「ない」を無視するわけでも悪いこととするわけでもない。
たとえば、トマトは湿気が苦手だ。
日本の梅雨のように雨がたくさん降る環境ではよく病気になったり、弱った時に虫がついてしまう。
このとき、「ない」思想だとトマトのこの湿気が苦手な特徴は欠点だ。
だから、ビニールマルチを使うし、ビニールで屋根もつける。
さらには病気が発生するようなら、仕方ない仕方ないといって農薬も使う。
極め付けは大きなビニールハウスを作って、土の中に大量に砂を入れたり資材を入れたり、土の中に排水システムを導入して、給水システムも作って水やりも徹底的に管理することになるだろう。
「ない」から外から持ってくるのだ。
では、「ある」思想ではどうするのか?分かりやすい方法がコンパニオンプランツだ。同じ畝で違う野菜やハーブなどを一緒に育てることで、お互いにメリットを生む作物のことで、共栄作物と訳されている。
トマトのコンパニオンプランツとして有名なのが、シソ科植物であるバジルだ。バジルの特徴は水さえあれば育つと言われるほど、水が好きなのだ。バジルは他の植物よりも水をどんどん吸い上げてしまう。そのためにバジルを植えた畝は乾燥気味になる。
そう、バジルの利点である水をたくさん水吸い込む性質はトマトの欠点である水が苦手の性質を補ってくれる。トマトの利点は太陽光をあまり必要としない点だ。その証拠に葉が小葉の集まりである複葉で、切れ込みが多く太陽光をめいいっぱい受け取らない。これは根元にしっかり太陽を当てて、乾燥を促す意味もある。その利点のおかげで、バジルはしっかり太陽光を浴びて大きく育つことができる。バジルは水をたくさん吸って大きく育つために、光合成が重要な役割を持つ。水がたくさん必要な植物は光合成をたくさんしなくてはいけない欠点を持つ。こうして、トマトの利点はバジルの欠点を補う。
さらに、バジルの欠点はどんどん大きくなるために、周りの植物があまり育ちづらくなってしまう点だ。家庭菜園初心者にありがちな、コンパニオンプランツが育ちすぎてしまい、メインの夏野菜が育たないことを防ぐためにもバジルを積極的に摘む必要がある(それ以外にも工夫は必要だよ)さらにバジルが繁殖しすぎると、風通しが悪くなってしまいバジル自身も弱ってしまう。
その欠点を補うのが人間だ。人間はバジルを様々な料理に使うことができる。(これはシソ科全体に言えること)しかも、夏の間に必要な栄養分や薬効を持っているので、毎日のようにバジルを摘むことになるだろう。ここでもまた、人間の欠点をバジルが補い、バジルの欠点を人間の利点が補う。
人間がバジルを摘むことで、バジルからは独特な香りが畑全体を覆う。その香りはカメムシなど害虫などを忌避してくれる効果もある。どうしても、湿気がちになってしまう日本の畑を人間の利点とバジルの利点が、このようにして補う。
「ある」思想は植物や動物が持つ利点を活かすことを考える。そのために「ない」ことを無視してはいけないのだ。「ない」ということを「ある」と認めることが始まりだ。農学者ハワードは言う。「すべての生物は生まれながらにして健康である」と。
西洋の世界観(二元論)では「ある」と「ない」は分離してしまう。
しかし、東洋の世界観では分離しない。むしろ「ある」のなかに「ない」が含まれている。
そうすれば「ない」は欠点や悪いことではなくなる。「ある」思想では欠点も利点も『接点』となる。そして、お互いの特徴が最大限に活かすことができれば、そこには美しい個性しかない。つまり、外から何かを持ってくるのではなく内にあるものを磨く。
現代の教育では個性を重要視することが増えた。しかし、欠点を無視したり、仕方がないものとしてしまうことが多い。すると、凸と凸ばかりのコミュニティが生まれる。それでは競争や衝突ばかり生まれてしまう。
昔は平均的な人間を作るために欠点を解消することばかり考えていたので、□と□ばかりだった。衝突が生まれない代わりに個性も生まれなかった。
深いつながりによって多様性が育まれている美しい自然界は凸と凹によってデザインされている。凸と凹だからこそ、深くつながるのだ。美しいデザインや解決法を思いつく人は、自然界は面白いパズルだと考える人がほとんどだ。だから、ひとつひとつのモノやひとりひとりの個性を観察し、ありのままに理解することからはじめる。決して先入観やレッテルで理解したつもりにならない。
「ある」思想は欠点を無視して、利点を叫ぶことではない。「ない(欠点)」をありのままに認めることで、接点に変える魔法である。
自然農法はそれを「自然界の摂理を活用する」と呼び、パーマカルチャーの原則ではそれを「多様性」「つながりの良い配置」「多機能性」「生物資源の活用」などでデザインしている。
単に種類が多いだけでは多種類であって多様性ではない。生物多様性は凸凹がパズルのようにつながることで、調和が生まれる。お互い様はそれぞれが「違う(たがう)」ことに御と様をつけて尊ぶ思想である。違うことは素晴らしいのだ。「みんな違って、みんないい」とは「みんな違うからこそ、みんないい」。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
