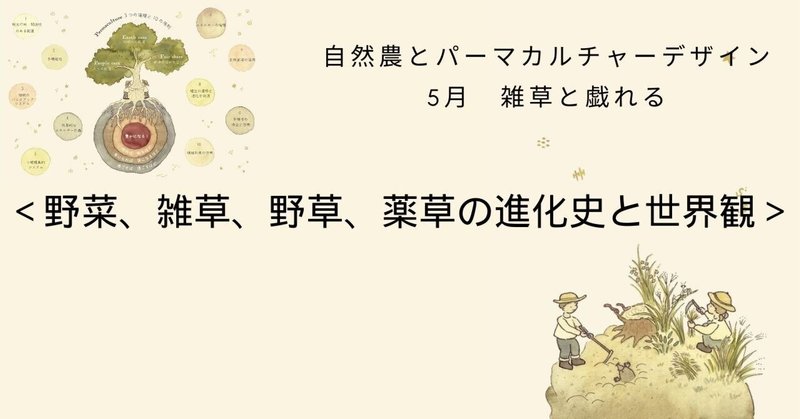
野菜、雑草、野草、薬草の進化史と世界観

<野菜、雑草、野草、薬草の進化史と世界観>
ある農家の元で研修を受けているとき、ちょうど春先だったこともあって家のおばあさんとともに雑草摘みにでかけた。おばあさんは次から次へと私に植物を指差し、名前とどう食べたら美味しいのかを教えてくれた。ときどき、おばあさんが無視をする植物があることに気がついた私は「これは何ていう雑草ですか?」と聞くと「それは・・・草だ、草。」とそっけなく答えてくれた。
「雑草という名の植物はない」と日本の植物学の父と謳われる牧野富富太郎は言うのを思い出す。
雑草という言葉は江戸時代の農書300書のうち、たったの2回しか出てこない。江戸時代後半に記された植物図鑑『本草図譜』に出ててくる雑草という言葉は「役に立たない邪魔な植物」としてではなく「効用や症状がはっきりしない植物」として使われている。
「どんな植物でも、みな名前があって、それぞれ好きな場所で生を営んでいる。人間の一方的な考えでこれを雑草として決めつけてしまうのではいけない」というのは昭和天皇の言葉だ。
雑草という言葉がいつから悪いイメージを持つようになったのかははっきりとは分からない。しかし、文明開化とともに西洋の価値感が入ってきてからではないかと思える節がある。
1910年札幌農学校の半澤洵博士が専門書「雑草学」を記し、そこに「雑草とは人類の使用する土地に発生し、人類に直接或いは間接に損害を与ふる植物を云ふ」とあるように、英語のweedの翻訳として「雑草」という言葉を当てたのだろう。現在のアメリカ雑草学会では「雑草とは人類の活動と幸福・繁栄に対して、これに逆らったり、これを妨害したりするすべての植物」と定義づけ、weedを邪魔者扱いしているのが分かる。
しかし、雑草が好きな人たちからすれば、この定義に違和感どころか反発したくなるに違いない。雑草の中には食べられるものもあるし、お茶や薬になるものある。衣服や日常品の繊維や染料にもなる。雑草でアートを楽しむことも、花の鑑賞を楽しむことも、その姿形で遊ぶこともできる。雑草は多くの農家にとっては邪魔者かもしれないが、雑草愛好家にとっては愛すべき存在である。
weedの形容詞形「weedy」という単語には「ひょろひょろとした、弱い」という意味がある。もし「You ara a weedy man」(お前は雑草みたいな奴だな)と言えば、それは「ひょろひょろとした弱っちい奴」という意味になる。これは雑草魂という言葉がある日本とはまるで違う意味だ。元メジャーリーガーの上原浩治さんがアメリカで記者会見した時に「雑草魂で頑張ります」と発言した時に、記者が鼻で笑っという話がある。
この雑草に対する価値観の違いはそのまま自然に対する世界観の違いである。文明が崩壊すると荒地・砂漠になる西洋では雑草もひょろひょろとしたものがまばらに生えている。逆に文明が崩壊すると草木に覆われる東洋では雑草はジャングルのように視界を遮るほど繁盛する。
真夏にイスラエルから友人家族が遊びに来たとき、彼らは草刈りをして燃やしている農家を見て非常に驚いていた。草を燃やすなんてありえないと。また私の庭の端で野生化して蔓延っているミントを見て「よしき、ミントにはどんな肥料とあげているんだ?」と聞いてきたので、「Nothing,Only rain.」と答えると笑っていた。それくらい西洋と東洋では世界観が違うのである。
私が海外からやってきた人たちに雑草を説明するとき「ジャパニーズハーブ」つまり「和ハーブ」だと説明している。herbは薬草や香草という意味で、usuful plants(有用植物)の中に含まれる。ハーブはヨーロッパの貧弱な環境でも育つ、強くて役に立つ良い奴というイメージだ。実は有用植物の種類は北半球の温帯に属する国では日本が圧倒的に多い。
西洋の文明と価値観が入ってきたことで生まれた日本語や日常でも使われるようになった日本語はたくさんある。雑草もおそらくその一つのようだ。こういうとき言葉の選定を間違えると、誤解があとあとまで私たちを洗脳してまう。
植物が本来持っている性質ではなく、人間側の価値観や生活スタイルの違いによって、雑草とか薬草とか呼ばれるだけ。レッテルはいつだって客観と装った偏見的な主観である。
野菜の多くは原産地ではハーブのように振る舞う。誰かに水や肥料をもらうわけでもなく、農薬をかけてもらうこともなく、勝手に生育し、現地の人々は必要な時にやって収穫していく。実は野菜の祖先が雑草である。
日本を代表する植物学者に中尾佐助(私の親戚ではない)は当時知られていた野菜(穀物も含む)の先祖が雑草であることについて、一つの疑問を感じていた。「では、雑草はどこから来たのだろうか?」と。
博士は野菜と雑草のルーツを探すためにヒマラヤ山脈の山奥やアフリカの砂漠地帯へと足を運び、昔ながらの暮らしを営む民族とその植物を観察した。そこで生物学において非常に大きな発見をすることになる。
狩猟採集や小規模な農耕を営む民族たちは1年に一度、ある季節になると集落から少し離れたところまで、旬の恵みを採集しにでかけていく。
その恵みが我々現代人が栽培してる雑草と非常によく似ているのだ。その旬の恵みとは現代で言うところの、山菜などの野草の感覚に近い。人間が管理や栽培をしているわけでないのにも関わらず、毎年同じ時期に同じだけの食物を恵んでくれる彼らだ。もちろん雑草に似ているということは野菜(穀物)とも似ていることを意味している。
そして、博士はもう一つ重要な発見をする。野菜の原種と呼ばれる雑草はその民族が住む集落の端っこに今でも簡単に発見することができるのだ。その端っことは人間のゴミ捨て場である。実は野菜も雑草もゴミ箱から生まれた可能性が高い!集落のゴミ捨て場とはつまり集落の周縁である。エッジ効果おそるべし、だ。人間の作った新しい環境に突然変異によって変異して適応した植物群が雑草で、そこからさらに野菜(栽培種)へ進化したのだ。
ここで博士は植物の分類をこう定義する。
野生種(山菜などの野草)、雑草種、栽培種(現代の野菜や穀物)。そして、その生態や姿形から雑草種が原種、野生種が原原種であると見抜いた。つまり、博士は観察を通してこう仮説を立てた。「野生種→雑草種→栽培種」で進化してきた植物であると。この仮説は現代の遺伝子工学によってほぼ結論づけられているから驚きだ。
人間の農業の歴史が1万年ということは野菜の歴史も1万年前からで、雑草の歴史も同様だ。私たちの近くに雑草がいるのも、野菜の近くに雑草がいるのも頷ける。つまり、彼らは進化の最先端を行く植物である。そして彼らの祖先をずっと辿っていくと氷河期の生き残り高山植物にたどり着くのも面白い。
これらは近縁種であるために容易に自然交配をし、種子を残すことができる。パンコムギの起源に関して面白い話がある。過去によく栽培されていた二粒系コムギと雑草のタルホコムギが交雑することで、その子孫の中からパンコムギが現れてくることが分かったのだ。つまり雑草が畑に生えていなければ現在のふっくらしたパンは生まれなかった。
現在栽培されている植物はずべて雑種起源である。日本で流通している野菜は約150種ほどで、そのうち90%超が海外原産地。この驚異的な適応力が野菜の特徴。つまり突然変異による進化と、ヒトによる自然淘汰に適応してきた。それと同様に雑草もまたヒトにくっついて世界中を旅し、世界中のヒトによる自然淘汰に適応してきた。
ナタネ、コンフリー、イタリアンライグラス、ナガミヒナゲシ、ナギナタガヤなど本来日本には作物や園芸種、牧草として輸入・栽培されていたものが、人間の手から離れて雑草化した植物で逸脱雑草と呼ばれる。
意図的に栽培されてきた雑草もある。それがなんとヒエだ。イネに対して強害草とも呼ばれるほど嫌われる雑草だが、無農薬で田んぼをすると向き合わざる得ない植物である。
しかし、昔から飢饉に対する備えとして救荒作物が栽培されており、その代表的な植物で、ヒエは冷害に非常に強い。過去の飢饉の原因はほぼ間違いなく冷害で、夏に寒くなりやすい東北では重要な作物として考えられていた。
昔、お世話になった自然農法家の家族は頻繁に雑草や野草を採取して暮らしていた。彼は「もし自給自足を目指したいなら、野草の知識は絶対必要だよ。なぜなら野菜が採れない時に食べられる野草が旬だから。」と話してくれた。そのときは確かにその通りだと思ったが、人間の歴史は逆である。狩猟採集民族だった頃のヒトは野草ばかりを食べていた。そして、食べられる野草が少なくなる真夏と真冬に食べることができる野菜をわざわざ海外から運んできて、わざわざ畑を作って栽培したのだ。
雑草には牧草としての役割もあった。牛や馬などの餌となるため、彼らにとっての毒草は人間がひとつずつ除去していった。
こういった雑草は資源であるにも関わらず、経済的・文化的な理由で間違った評価をしている。それは虫や獣に対しても言えることで、駆逐されるよりもむしろ利用されるべき自然の余剰(生物資源)である。
農業の現場からは高い収量をあげられるが、労働と管理にがたくさん必要になる。それに比べて野生たちは収量は低いが、収穫以外に作業は必要ない。この二つ間の緊張とバランス関係が大事になるのは間違いない。自身の好みや暮らしに合わせた最適なバランスを目指したい。
エッジから生まれる山菜などの収穫物は貧しい人々だけではなく、食糧不足の時は多くの百姓や農民が生き残るために頼ってきた。そしてヒトを生かしてきた植物だ。雑草や野草がいなければヒトはとっくに絶滅していただろう(食糧としても防災としても)。野生を無視したり過小評価する偏見から生まれるレッテルは、いざという時に命を奪いかねない。
遺伝子組み換え作物を不耕起栽培して、なおかつ雑草をグリホサートで枯らせば、雑草防除問題も土壌流亡問題も解決できる。これが環境保全型農業と呼ばれるもの。はじめは高い収量と栽培管理の簡単さから普及が進み、注目を浴びた。しかし、グリホサートで枯れない雑草が報告され始める。その雑草の中にグリホサートを不活化させるために作物に導入した遺伝子が雑草に移っていることがわかった。作物の祖先が雑草であったことを考えれば当たり前の話だろう。遺伝子組み換え技術が遠からず破綻するのも当然のことかもしれない。遺伝子組み換え技術は作物を進化させたが、雑草も進化させることになったようだ。
最後にアメリカ神学者エマーソンの言葉を紹介したい。
「雑草とは何か?それはあなたが、まだその価値(美点)を発見していない植物である」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
