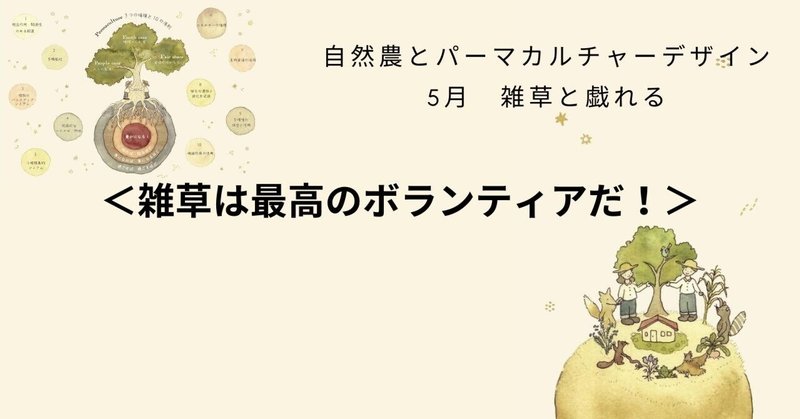
雑草は最高のボランティアだ!

<雑草は最高のボランティアだ!>
自然農の先駆者・川口由一さんは「草を敵としない」と後輩たちを諭した。とはいえ、日本では雑草は敵として考える人が多く
自然農をしている人でも「雑草=厄介なもの」という印象が強いのも確かである。アメリカ雑草協会の雑草の定義はズバリ「雑草とは人類の活動と幸福・繁栄に対してこれに逆らったりこれを妨害したりするすべての植物」だという。
では、雑草はいったい何をしにこの世の生まれてきたのだろうか?
「きみはこの地球に何をしにやってきたの?」
自然農とはそれを雑草に、野菜に問いかけるところから始まる。
1日講座でも連続講座でも、雑草を学ぶ時間がある。
畑の講座でその時間を取るのはきっと私だけだろう。
その理由は決して雑草が食べられるからではない。雑草がこの地球を豊かにするために才能を備えて、この地球にやってきたからだ。雑草はオンリーワンの性質とナンバーワンの性質を持った進化の最先端をゆく植物。そして、それは人間との共生で進化した野菜にも同じことが言える。
多くの植物に関する書籍には植物には適した土質や気候があると紹介されている。そのために畑や気候の性質を理解する上でも雑草観察は役に立つ。ある特定の雑草がその土地に生えているということは、その土地の性質を表す環境指標となる。もし何かしら環境を整える必要があれば、それをもとに何をすれば良いのかがわかるのだ。しかし、雑草を長い目で観察しているとその知識では不具合が生じることがある。
ある雑草が蔓延ってしまったために、その雑草が生きられなくなってしまうのだ。この現象は一般的にアレロパシーを持つ植物の話として有名だが、決して一部の植物だけではない。かといって、異常なことでも珍しいことでもない。
自然遷移の法則ではたとえ何かの種が繁栄したとしてもと必ず衰退を迎える。自分自身の積み重ねが次のステージの植物にとって栄養となり、自身にとっての毒となる。子孫のために住みやすい環境を整える力も持つが、その力ゆえに繁栄し、衰退する。
自然遷移における雑草の役割を一言で言うと、彼らは「人間が破壊した大地を森林に戻すにために土台を築いている」ということ。条件さえ整っていればどの土地も雑草を通じて森林になろうとしている。そのためのベースとなる土を作るのが雑草たちの仕事なのである。
さまざまな条件のもと、雑草はそれぞれが持った才能を生かして土地を整えていく。大地を耕す雑草、窒素を固定する雑草、土を中性に戻す雑草、汚染された土壌を浄化する雑草、水分を蓄える雑草、虫を集める雑草など。雑草たちは誰かに頼まれたわけでも肥料をもらうわけでもなく、自然に土壌を整えてしまう。
スギナは酸性に偏っていた土を中性にし、弱アルカリ性になるとツクシを伸ばし、胞子を飛ばしてまたどこかへ旅に行く。セイタカアワダチソウは化学物質で汚染された土地を浄化し終えると勝手に自滅して土に帰る。などなど、例えをあげ出せばきりがないほど、人間ではまだ解明できていないことばかりの才能を発揮して私たちの足元で雑草はこの地球を豊かにしていく。そして、自分の役割を終えると次の植物にバトンタッチをする。その間にたくさんのタネを土の中に残し、何か大きな破壊があったときのために備えておく。
彼らはその才能を惜しみなく発揮して、今もみんなの知らないところで
この世のために尽くしていると聞いて、あなたは信じられるだろうか?
しかし、それは科学的にも解明されている事実なのだ。それがまさに「自然遷移の本質」である。
つまり、雑草と言ってもそれはそれは個性的なやつらがたくさん居て、
彼ら一つ一つに、必ず意味があり、役割があり、そして才能がある。
もちろん雑草という草はなく、すべてに名前がある。
家庭菜園や農業をやる上で、全て覚える必要はないけれども、その知識を得た上で、土を、雑草を見てみるとパーマカルチャーのある有名な言葉にたどり着く。
Problem is solution.問題は解決策である。
そう、雑草はあなたの畑のの欠点や弱点を補うために、そこにいるのだ。雑草に任せておけば、どんな荒地でも3年でいくつかの野菜が栽培できるようになり、7年も経てばほとんどの野菜が育つ。そして雑草が蓄えた栄養分を元に低木類が育ち、高木類が育ち、森林が形成されていく。文字通り雑草は森林の土台を作っている。雑草なくして森林なし。雑草なくして自然農なし。雑草を草マルチとして利用するのは、「雑草が栄養を奪う存在」だからではなく「栄養を蓄えてくれている存在」だからだ。自然農を始めるには耕作放棄地のほうが適していると言われるのだ。雑草がすでに働いてくれているからに他ならない。
また人間の発達した文明が生み出した重金属(銅や鉛、カドミウムなど)や石油などで汚染された土地にも誰かに頼まれたわけでもないにも関わらず生えてきて、土壌を修復していく。これをもとに植物によって汚染土壌を修復することを目的とした研究がファイトレメディエーションと呼ばれる。
しかも、彼ら肥料も要らなければ、農薬も要らない。種を蒔く必要もない。勝手にどこからともなくやってきて、勝手に住み着き、働いている。それこそ「ボランティア精神」のたまもの。誰から賞賛されることもなく、表彰されることもないのに働き続ける。
たとえ無知な人間たちに酷い言葉を浴びせられたり、ときには酷い仕打ちをされたとしても、彼らはイキイキと生きる。雑草は荒れている適した場所で才能を発揮する。才能は適材適所で自ずと輝くものなのだ。
とはいえ、やっぱり野菜を育てる上で厄介になる雑草もいる。だから雑草を見て、土壌診断をして、彼らの役割を理解し尊重することで人間が何をしたら良いのかがわかる。そこで野菜やハーブでその代用を託すこともあるし、畝のデザインや資材の投入で解決することもあるし、彼らの役目を早く終わらせてあげることもある。それを人間の手で早めてあげる。それが大地を整えるということである。これをパーマカルチャーの「自然遷移の加速」といい、自然農では野良仕事という。
人間の手入れが彼らと調和すれば、彼らは安心して役割を終えて、自ずと姿を消していく。自然農ができる頃になると雑草は野菜たちと共生できるものばかりになる。雑草を尊重せずに本に書いてある方法だけを真似すると、草刈りの回数は増えるばかりか、野菜が育ってくれないことも多い。
自然農では「草を敵としない」と言うが、もうすでに味方なのだ。あなたが勝手に人間の目線で雑草を敵だとか厄介なやつだとかレッテルを貼ってしまうから悲劇は起こる。敵だと思っていた、意見が違う人だと思っていた人がよくよく話してみると同じ価値観だったり、同じ目標に向かっている同志だったりする。これは人間関係でもよくある話だろう。
まずは目の前の命を理解しよう。そして、尊重をしよう。畑にいるすべての生命を理解し、尊重し、信じること。つまり、地球を愛すること。そうすると、あなたの畑で面白いことが起きる。
私はこの世界にあるものには必ず意味があり、役割があり、そのための才能が備わっていると考えている。個性があるということは才能があるということなのだ。そして、どんな生命も才能が発揮されるときにイキイキと輝く。
同じように野菜にもこの地球を豊かにするための才能が備わっている。
その才能を理解し、尊重し、その環境を整えてあげると野菜はほとんど手をかけなくてもすくすく育つのだ。ときに時間がかかることがある。
しかし、植物は与えられた環境で、生き抜こうと適応し始める。タネの中に環境の情報を残そうとする。そうすれば、次の世代がこの土地で生きやすくなるからだ。「草深い」という言葉は農村の代名詞であり、豊かな植生の、生物多様性の証だった。
だから、信じて待つことが大切なのだ。
ときに雑草たちは人間をよく観察している。そして、こちらの動きに合わせてくれる。耕作放棄地から自然農に切り替える過程でそれがよく分かる。私たちが雑草たちの仕事を理解し、尊重し、少し手助けをしてあげるとびっくりするくらい、いきなり植生が変わる。去年まで生えていなかった雑草たちが芽吹くのだ。やっかいな雑草たちが勢いを弱め、そして居なくなるのだ。雑草と仲良くなるためにまずは観察から初めて、そしてその蓄えてくれた栄養分を大地に還元するか、食べて飲んで自身の栄養にしよう。雑草を排除するために草刈りをするのではなく、土を育てるために、野菜をそ立てるために、畑を育てるために、そして自分自身を育てるために草を刈っていく。草刈りのための草刈りをしないように。
雑草だけではない。昆虫たちも、野生動物たちも動きを変えていく。誰もが豊かな森林を目指して、手を入れていく。生物多様性という調和に向かっていく。
人間がその流れを無理やり早めようとすれば、それにストップをかけようとする。逆にその流れと全然違うことをすれば、それにもストップをかけようとする。自然界に生きる生き物たちは誰もが超素直で、超ワガママだ。
自然農とは自然遷移のコントロール。何かしらの理由で荒れてしまった大地を人間の手によって生物多様性の豊かな大地にすることである。
それは決して畝の上だけの話でもなく、畑の中だけの話でもなく、里山全体で整えていく。
無為自然とは自ら然り、作為がないこと。つまり自分の内側に存在している力でそうなっていく(そうなってしまう)ことである。
歯をくいしばる必要もなく、心を折る必要もない。内側にあるものに気がつ、尊重し、信じることができれば、自ずと天の采配(助け)が起こりあらゆるものがつながると、あるべき調和の世界におさまる。その姿勢が道(タオ)と呼ばれるものだった。
これを読んでいる
きみはいったいこの地球に何をしにやってきたのだろうか?
そして、われわれ
人類はいったいこの地球に何をしにやってきたのだろうか?
その答えは自然農をやりながら考えてもらいたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
