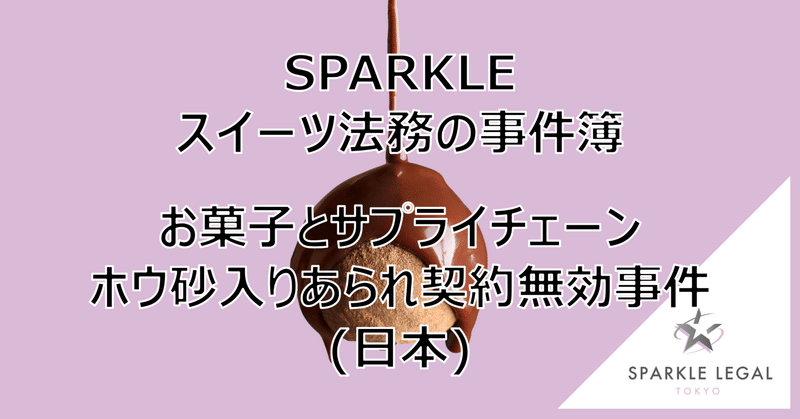
【スイーツ法務の事件簿】お菓子とサプライチェーン-ホウ砂入りあられ契約無効事件
みなさん、はじめまして。スパーくまです!本連載は、スパークル法律事務所の非公式マスコットのスパーくまがスイーツに関する古今東西の興味深い事件を取り上げるコラムです。

今回は、昭和30年代に起きた「あられ」についての事件(最判昭和39年1月23日民集第18巻1号37頁)を紹介します。あられ製造を行う原告(X)が、販売業者(卸売)である被告(Y)との売買契約における代金の支払を請求したという事件です(※為替手形支払金請求ですが、手形法の論点は省略)。
製造業者であるXは、「あられ」に有毒のホウ砂を使用していたため、「あられ」の製造、販売禁止、製品の回収廃棄等の行政処分が行われました。その後、Xは、卸売業者であるYに対し「あられ」の販売代金を回収しようとしましたが、Yは、(旧)瑕疵担保責任を理由とする売買契約の解除の主張の他、上記契約が公序良俗(民法90条)に反し無効である等と主張しました。最高裁は、Yによる契約無効についての主張を認めました。
1.今回のスイーツ

そもそも、皆さんは、「あられ」というと、どのようなお菓子をイメージするでしょうか。地域によって、醤油味のものから甘いものまで様々な種類があります。
また、似たような米菓が存在しますが、大まかにいえば、今回のスイーツである「あられ」は、原料と大きさによって定義されるようです。
・煎餅:うるち米を原料として焼くか揚げた米菓
・おかき:もち米を原料として焼くか揚げた米菓のうち、大きなもの
・あられ:もち米を原料として焼くか揚げた米菓のうち、小さなもの
2.事件の背景・経緯

Xは、製造したあられに、ホウ砂(四ホウ酸ナトリウム)を混入していました。ホウ砂は、コンタクトレンズの清浄液や目の消毒薬、害虫駆除等で用いられる他、もっとも親しまれているのは、小学校の理科の実験等で用いる「スライム」づくりの一材料としてかもしれません。
しかし、経口摂取すると人体に有害な物質であり、子供であれば2~3g程度、成人でも15g程度が致死量とされています。そのため、ホウ砂は食品衛生法4条2号(現6条2号)の「有毒な……物質」に当たり、製造、販売等が禁止されていました(当事者間に争いなし)。
食品衛生法
第6条(旧4条2項)※抜粋
次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
XとYは、昭和32(1957)年1月頃より、あられを継続的に売買しており、Xは、当初、ホウ砂が有毒物質であることを知らずに使用(混入)していました。ところが、同年10月頃、ホウ砂の毒性が各地で問題となり、新聞報道でホウ砂入りのあられが禁止されていることを知りました。そこで、Xは、Yに対し、あられの売却を中止したい旨の連絡を行いました。
しかし、Yは、Xに対し、以下のように述べて、混入の事実を知った上で、送品の継続を強く要請し、売買は継続されました。
「今はアラレの売れる時期だからどんどん送つて貰いたい、自分も保健所に出入りしているが、こちらの保健所ではそんなことは何も云つておらぬ、君には迷惑をかけぬからどんどん送つてほしい」
翌昭和33年(1958年)2月、行政(県)は、ホウ砂の混入を理由にあられ原料の製造並びに製品の販売禁止、製品の回収廃棄等の行政処分を行いました。
小売店からの売買代金を回収できなくなったYは、(旧)瑕疵担保責任を理由とする売買契約の解除の主張の他、売買契約の公序良俗違反(民法90条)による無効等を主張して、Xに対する支払いを拒絶しました。
民法
(公序良俗)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
3.法的論点・判示
1審・控訴審は、以下の理由でYの契約無効についての主張を認めませんでした。
1審(松山地判昭和33年2月25日)
「……食品衛生法の規定は、専ら行政上の取締を目的とするものであつて、これに違背する取引をしたものには同法所定の制裁を科するに止り、その取引自体を当然無効とする法意ではないから、本件取引に基き生じた債権関係も有効なものというべきである。」
控訴審(高松高判昭和35年10月27日)
「控訴人は行政上の取締だけを目的とした法令違反の場合でも、契約当事者が違反者の可罰性を認識しつつ通謀したり若しくはその違反行為を勧誘助長するなど双方の行為に違法を伴う場合には民法第90条の適用があり、本件はこの場合に該当すると主張する。しかし、そのような場合でも、契約が公序良俗に反して無効だというためには、ただ単に動機等に不法があるというのにとどまらず、その不法性が強度であつて、これを無効とする必要が当事者の私的な利益や更には当事者間の具体的衡平をも度外視しうる程の場合であることを要するのであつて、右の主張をそのままには採ることができない。」
これに対して、最高裁は、以下のように述べて、Yの契約無効についての主張を認めました。
「思うに、有毒性物質である硼砂の混入したアラレを販売すれば、食品衛生法4条2号に抵触し、処罰を免れないことは多弁を要しないところであるが、その理由だけで、右アラレの販売は民法90条に反し無効のものとなるものではない。
しかしながら、前示のように、アラレの製造販売を業とする者が硼砂の有毒性物質であり、これを混入したアラレを販売することが食品衛生法の禁止しているものであることを知りながら、敢えてこれを製造の上、同じ販売業者である者の要請に応じて売り渡し、その取引を継続したという場合には、一般大衆の購買のルートに乗せたものと認められ、その結果公衆衛生を害するに至るであろうことはみやすき道理であるから、そのような取引は民法90条に抵触し無効のものと解するを相当とする。」
公衆衛生を害すると知ってホウ砂入り「あられ」を販売する旨の売買契約である点が重視され、公序良俗に反して同契約は無効とされました。
4.さいごに
事件当時とは異なり、現在、食品の製造では、栄養表示の義務化や加工・流通・販売のサプライチェーン全体を通じた衛生管理(HACCPに沿った衛生管理)がなされており、安心して「あられ」を食べることができるようになっています。
奈良・平安時代には既に存在していたという「あられ」。皆さんも「あられ」を召し上がる際には、「あられ」と食品衛生、そして民法90条の歴史に想いを馳せてみてはいかがでしょうか。


文責:スパークル法律事務所
連絡先:TEL 03-6260-7155/info@sparkle.legal
本記事は、個別案件について法的助言を目的とするものではありません。
具体的案件については、当該案件の個別の状況に応じて、弁護士にご相談いただきますようお願い申し上げます。
取り上げてほしいテーマなど、皆様の忌憚ないご意見・ご要望をお寄せください。
