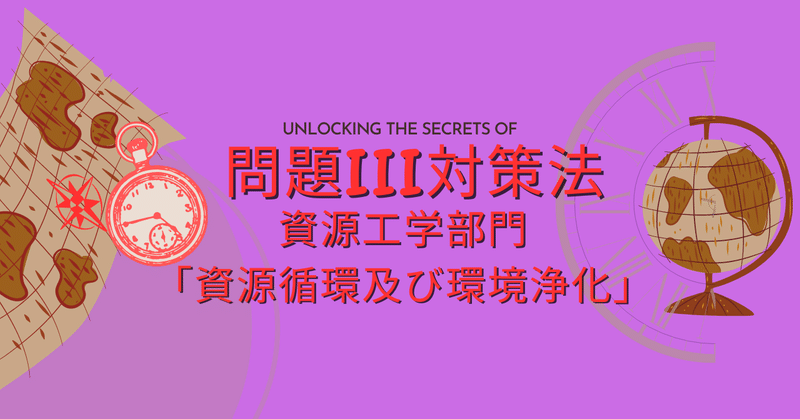
問題Ⅲの対策法:資源工学部門「資源循環及び環境浄化」~技術士第二次試験~
有料記事としていますが、95%無料で読めます(^^♪
最後の5%分は、添削を受けたい方向けの記事です。
本記事では、技術士第二次試験「選択問題Ⅲ」の対策法について、資源工学部門の「資源循環及び環境浄化」科目を対象として、以下に私見を述べます。
【1】 注意事項
・100点の答えにはなりません
・60点を目指すヒントとして捉えてください
★あくまでも、自力で考えることを忘れないでください。
【2】 問題Ⅲの過去問
「日本技術士会」HPに公表されていますので、上記リンクより参照してください。
【3】 過去問の傾向
3.1 過去問題の「テーマ」(△△△を○○○する)
過去問題の「テーマ」(△△△を○○○する)は、非常に多岐にわたっている。H25年~R05年の問題Ⅲの各テーマを以下に記載する。なお、R01年の試験制度改正前後で各問題のテーマの整理を区分する。
★H25~H30年(試験制度改正前)
1)我が国に存在する様々な使用済製品の中には、原材料として使用した有用な金属資源(地上資源)が多く含まれている。独立行政法人物質・材料研究機構の推計結果によれば、我が国に蓄積されている地上資源としての金属資源量は、鉄12億トン、銅3,800万トン、銀6万トン、金6,800トン、レアメタルであるタンタル4,400トン、リチウム15万トンとなっている。これを、世界全体の現埋蔵量に占める割合で考えると、鉄1.62%、銅8.06%、 銀22.42%、金16.36%、タンタル 10.41%、リチウム 3.83 %となる。この数値には、現在まだ使用中の製品、使われないまま家庭で保管 (退蔵)されている製品、廃棄物として埋められたものなど、直ちに資源を回収することができないものも多く含まれていることに留意する必要があるが、総量として、我が国に眠っている地上資源は、海外の大鉱山に匹敵する大きなポテンシャルを有しているといえる。この様な状況を考慮して、我が国に眠っている地上資源としての金属資源の活用を図る。
2)鉄くず、非鉄金属くず等の金属系廃棄物等の我が国の輸出量は、平成12年から平成22年までの10年間で、約2倍以上に大きく増加している。また、平成22年に輸出された中古製品は、自動車80万台、 PC等のモニター460万台、 テレビ260万台となっている。国内で発生した循環資源が海外で再使用(リユース)されたり、 リサイクルされたりするのは、グローバルな視点からの資源循環に資するものである。 しかしながら、開発途上国では、循環資源中の有害物質の処理を適切に行っていないが故に、環境汚染や作業員の健康被害を引き起こしているとの研究報告がなされている。 この様な国際資源循環における資源性と有害性の関係を考慮し、開発途上国で行われている 環境汚染や作業員の健康被害を引き起こす循環資源の再使用(リユース)、 リサイクル処理上の問題点を解決する。
3)小型家電(携帯電話、デジタルカメラなど)には、レアメタル(希少金属)や貴金属が多く含まれているが、使用済みとなった製品のうち、使われないまま家庭で保管(退蔵)されている割合の調査結果(環境省調べ)をみると、携帯電話(約5割)、ビデオ・DVDプレイヤー (約3割)、携帯音楽プレイヤー (約4割) といったように高いことがわかる。これを踏まえ、いまだ不十分な状況にある使用済製品からの有用金属の回収を加速化させるため、小型家電を対象とした新たなリサイクル制度(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律) が、平成25年4月からスタートした。 このような状況を考慮し、小型家電のリサイクルに関する諸問題を解決する。
4)経済のグローバル化に伴い、国境を越えて移動する循環資源(廃棄物等のうち有用なもの)の量が増加している。日本政府は2006年の使用済み家電のおよそ30%が中古品として輸出されたと推計している。また、使用済みPETボトルについても、2000年を過ぎた頃から中国の経済発展に伴い合成樹脂の需要が増大し、中国・香港への輸出が盛んになった。経済発展の著しい国や発展途上国では、不足する資源を越境してきた廃棄物から回収し補っており、国際資源循環が行われている。しかし、 循環資源中の有害物質の処理が適切でないと、環境汚染や作業員の健康被害などの問題を引き起こす。これらの背景を踏まえ、有害廃棄物の不適切な越境移動を抑制しながら、適正な国際資源循環を進める。
5)我が国の第三次循環型社会形成推進基本計画では、「質」にも着目した循環型社会形成の取組として「2R(リデュース・リユース) の取組がより進む社会経済システムの構築」、「水平リサイクル等の高度なリサイクルの推進」などが挙げられている。ここで水平リサイクルとは、使用済製品を原料として用いて同一種類の製品を製造するリサイクルを指す。この背景を踏まえ、2R(リデュース・リユース) 及び水平リサイクル等の高度なリサイクルを推進する。
6)2011年3月の東日本大震災では、膨大な量の災害廃棄物(岩手、宮城、福島の3県で、津波堆積物も含めて合計2,802万トン)が発生した。 岩手県の災害廃棄物についての調査報告によれば、 主な構成物(割合)はコンクリートがら (37.7%)、不燃物(18.7%)、可燃物(10.1%)、金属くず(3.1%)、柱材角材(1.3%)、その他(1.5%)、及び津波堆積物(27.6%)であった。地震以外にも、台風、噴火、豪雨などの自然災害に伴い被害が生じ、多量の廃棄物が排出される。これらの背景を踏まえ、被災地の住民の生活や経済活動の一刻も早い復興のために、災害廃棄物を迅速に、かつ適切に処理する。
7)レアメタルは、鉱業審議会において、地球上の存在量が稀であるか、技術的・経済的な理由で抽出困難な金属のうち、工業需要が現に存在する(今後見込まれる。)ため、安定供給の確保が政策的に重要であるものと定義され、現在31鉱種(レアアースは17元素を1鉱種として数える。)が対象となっている。この背景を踏まえ、レアメタルリサイクルを経済的に成り立たせる。
8)自然由来の重金属等含有土壌の対応については、平成22年4月1日に改正土壌汚染対策法が施行され、自然由来の土壌汚染も同法の対象になるとともに埋め立てに起因する土壌汚染は人為的原因による土壌汚染として扱われることとなった。しかし、自然由来の重金属等含有岩石(ズリ)は、原則として同法の対象外である。今後も大規模公共工事等にともなって、自然由来の重金属等含有岩石(ズリ)が大量に発生することが予想される。この背景を負雨、自然由来の重金属等含有岩石(ズリ)の対策を講じる。
9)我が国に存在するさまざまな使用済製品の中には、原材料として使用した有用な金属資源が多く含まれている。そこから、金属資源を回収し、リサイクルを行う。
10)静脈産業をはじめとする環境関連のビジネス、いわゆるエコビジネスと言われる産業は、急速に成長している。鉄鋼や非鉄金属から流通大手もエコビジネスに参入し、国も積極的にこの流れを促進しようとしている。静脈経済の大規模化、成熟化、いわゆる静脈メジャーあるいはリサイクルメジャーの育成を政策として打ち出している。これらの背景を踏まえ、成長途上にある静脈ビジネスをより促進させる。
11)平成29年版環境・循環型社会・生物多様性白書(環境省)において、国内の、「質」にも着目した循環型社会の形成に向けての取組の中に、次の①~③が含まれている。 ①2R(リデュース・リユース)の取組がより進む社会経済システムの構築、②使用済製品からの有用金属の回収、③有害物質を含む廃棄物等の適正処理システムの推進。これらの3つそれぞれの取組を進展させる。
12)ブラウンフィールドとは、国や地域により定義は異なるが、一般には 「土壌汚染の存在若しくはその存在する可能性に起因して再利用ができずに遊休化した土地」を指すことが多い。1990年代より欧米の工業都市を中心にブラウンフィールドの増加が社会問題なってきた。この背景を踏まえ、ブラウンフィールドの発生防止対策を行う。
★R01~R05年(試験制度改正後)
1)水銀及びその化合物の人為的な排出及び放出から人の健康及び環境を保護することを目的とし、2017年8月16日に「水銀に関する水俣条約」が発効された。当条約を踏まえつつ、 水銀の採掘から貿易、使用、排出、放出、廃棄等に至るライフサイクルにわたり適正な管理と排出の削減を行う。
2)平成30年6月22日に公布された「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の一部を改正する法律(改正海岸漂着物処理推進法)」では、海岸漂流物等の多くが、国民生活からのプラスチックごみが多くを占めることや、海域におけるマイクロプラスチックによる生態系への影響など、プラスチックごみに起因する問題が、その成立の背景となっている。この背景を踏まえて、プラスチックごみに関する問題に対処する。
3)最終処分場の枯渇や資源の有限性などから、これまでの大量消費・大量廃棄から廃棄物のリサイクル等による循環型社会の構築が推進されている。廃棄物のリサイクルの推進においては、動脈物流に比較して静脈物流の輸送コストは高水準である。その輸送コストを低減するために、静脈物流の効率化及びそれに寄与する静脈物流システムを構築する。
4)国内の産業活動に伴って生じた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)に基づき、生活環境の保全に配慮した産業廃棄物処理業によって、適正処理及びリサイクル等が行われることによって廃棄物の排出抑制及び循環型社会の維持がされており、今後も社会には不可欠な業種である。また、産業廃棄物処理業は、取り扱う産業廃棄物の特性により、より多くの労働力を必要する業界であるが、他産業と比較して労働災害が多く、厳しい労働環境下にある。これらの背景を踏まえ、産業廃棄物処理業での従事者を維持するために、従事者に対する安全を維持・改善する。なお、参考までに表1~表3に、産業廃棄物処理業における労働災害の推移を示す。


5)新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の感染拡大により、従事者へのマスクの着用、密集・密接・密閉を避けるための換気の追加や従事者同士との距離の確保などの職場における感染防止対策が新たに必要となった。国民生活に伴って生じた廃棄物の処理では、従事者の廃棄物や他人と直接的な接触をする機会が多く、かつ多くの従事者を必要としている。これらの状況を踏まえ、今後、新しい感染症が感染拡大する中であっても、国民生活を維持するために廃棄物の処理を継続する。
6)レアメタルは、物理的・化学的特性や市場規模・価格・主要生産国等は多様である。またレアメタルは、xEV (電動車)やAI・IoT等の脱炭素社会における先端産業において、製品の高機能化を実現する上で重要な電池・モーター・半導体等の部品の生産に不可欠なものとなっている。しかし、今後、先進国や新興国との間で資源獲得競争の激化が見込まれるため、レアメタルの安定供給を確保するためにサプライチェーンを構築する。
7)フッ素は、半導体の洗浄・エッチング、 液晶ガラスのスリミング、リチウムイオン電池の電解質、冷媒・エアゾール、有機合成触媒、各種フッ素樹脂などに用いられる。我が国は、その原料であるフッ化カルシウム(CaF2)を主成分とする蛍石やフッ素化合物の主な出発原料となるフッ化水素(HF)を、数か国からの輸入に依存している。また、人体への有害性から環境への排出が厳しく規制される中でも、フッ素を含んだ産業廃棄物が生じている。また近年では、フロン類や有機フッ素化合物(PFAS)による環境や人体への悪影響が顕在化し、これらの物質については適正な処理(破壊)が求められている。カントリーリスクが存在し、今後もその需要の増加が見込まれるフッ素について、日本国内で再資源化が維持できる仕組みを構築する。
8)令和4年4月1日に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「法」という)」では、製品のライフサイクルの全般(設計・製造・販売・提供・排出・回収・リサイクル) に関わる、プラスチックの資源循環の取組、3R+Renewableを促進するための措置が講じられている。その実現に向けて、各関係主体(事業者・消費者・国・市区町村・都道府県)が参画し、相互に連携し相乗効果を高める。
9)令和4年版 環境・循環型社会・生物多様性白書では、持続可能な経済社会を目指し、地域資源を活用して環境・経済・社会の統合的向上を実現する事業を生み出し続けるとともに、都市と農村のように地域の個性を活かして地域同士で支え合うネットワークを形成する「地域循環共生圏」の拡大と深化を重要としている。最近では、脱炭素化や災害時のレジリエンス強化を目的とし、 廃棄物処理に伴い生じた電力や熱の有効利用及び地域内における資源循環が進められている。 これらの状況を踏まえ、地域循環共生圏の拡大と深化を進める。
10)2022年10月に国際民間航空機関(ICAO)で採択された「国際航空分野で2050年までに二酸化炭素(CO2)の排出を実質ゼロにする長期目標」では、持続可能な航空燃料SAF(Sustainable Aviation Fuel) の開発・増産の加速化を掲げているが、2021年のSAF生産量は、世界の航空燃料需要に対して0.03%にとどまっているというデータもある。SAFは、主に植物などの有機物を原料として人工的に生成され、その製造方法は2022年時点で、国際規格「ASTM D7566」において、7種類の製造方法が承認されている。これらの製造方法の中で最も普及している方法は、使用済み食用油や植物油などを原料とした水素化処理である。この製造方法に関する国内状況としては、商業化された製造施設はなく、主な原料となる廃食用油は、飲食店等から約38万トンが回収・処理され、再資源化された廃食用油は、家畜飼料として約20万トン、工業向けの原料として約5万トンの需要がある。一方で、約10万トンが国外に輸出されており、その量は家庭から回収されずに焼却処理されている量とほぼ同じである。このような状況を踏まえて、SAFを日本国内で普及させる。
3.2 設問(1)の傾向・対策
R01年以降、設問(1)~(3)の問題文は、部門・科目により違いがあるものの、おおむね統一されている。また、「資源循環及び環境浄化」科目のR01年以降の設問(1)は、問題文が年々変化しているものの、大局的にほぼ共通である。ここでは、直近のR05年の問いかけを参照として、設問(1)の標準問題文を以下のとおり設定する。
設問(1)では、この問題文がR06年以降の想定問題に引用できると考える。
3.3 設問(2)の傾向・対策
R01以降、「資源循環及び環境浄化」科目の設問(2)問題文は、問題文が年々変化しているものの、大局的にほぼ共通である。ここでは、直近のR05年の問いかけを参照として、設問(2)の標準問題文を以下のとおり設定する。
R06年以降の設問(2)は、上記の問題文に類似した問いかけで出題されると考える。
3.4 設問(3)の傾向・対策
R01以降、「資源循環及び環境浄化」科目の設問(3)問題文は以下の問いかけでほぼ共通である。
★
R06年以降の設問(3)は、上記の問題文に類似した問いかけで出題されると考える。
【4】 問題Ⅲ対策
「資源循環及び環境浄化」科目の問題Ⅲ対策は、前述した内容を踏まえ、以下に示す3つのレベルに対応する想定問題を作成し、その問題への解答論文を作ることを提案する。さらに、本対策は、既技術士等に添削を受けることで、解答の質を上げられると考える。
なお、各レベルの課題文{設問(1)より手前の問題文}は、受験生各自で設定してください。
4.1 レベル1
「テーマ」として、H25~H30年過去問題の課題文のいずれかを選択し、以下の(1)~(3)の各設問に解答せよ。
(2)前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対して資源循環及び環境浄化の技術者として関与し、実現すべき複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
4.2 レベル2
「テーマ」として、R01~R05年過去問題の課題文のいずれかを選択し、以下の(1)~(3)の各設問に解答せよ。
(2)前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対して資源循環及び環境浄化の技術者として関与し、実現すべき複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
4.3 レベル3
「テーマ」として、各受験生の「資源循環及び環境浄化に関する経験業務」または「資源循環及び環境浄化に関する最近のトピック」を1つ挙げ、以下の(1)~(3)の各設問に解答せよ。
(1)「テーマ」の実現に向けた課題を、技術者として多面的かつ異なる観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
(2)前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対して資源循環及び環境浄化の技術者として関与し、実現すべき複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
【5】 添削
ここから先は
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
