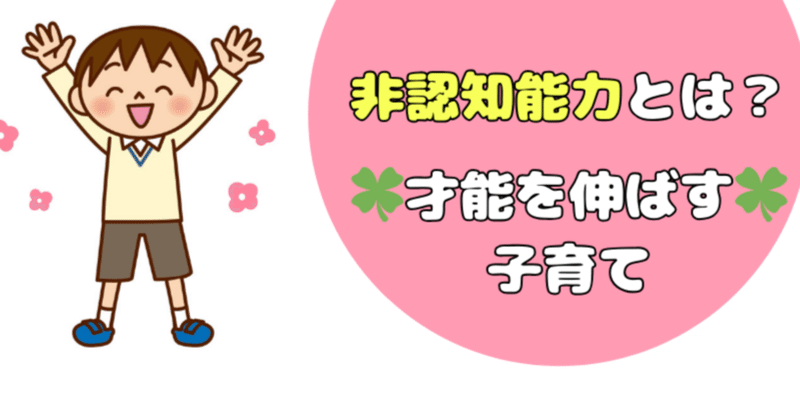
『非認知能力』とは?🍀才能を伸ばす子育て🍀
『非認知能力』とは、
『認知能力』(IQや言語・計算能力など)以外の力全てを指す総称です。
特に教育関連機関では、『非認知能力』を社会生活を歩むスキルという側面で捉え
『社会情動的スキル』
と表現しています。
ではなぜ『非認知能力』の向上が、子育てには大切なのでしょうか。
大きな理由の一つは、社会が『非認知能力』を求めているからではないでしょうか。
AI(人工知能)の発達により、知識や計算はこれからもどんどんと、AIを使用さえれることが多くなっていくと思います。
事実、GoogleやAmazonといった大企業が最も重要するスキルとして学力などの『認知能力』ではなく、知的好奇心などの『非認知能力』を挙げています。
今回は、『非認知能力』を高めるにはどのような環境・関わりが大切なのか、以下の書籍を参考に一緒に学んでいきましょう💪
【参考文献】
『非認知能力』を構成する力とは?
『非認知能力』とは、
『認知能力』(IQや言語・計算能力など)以外の力全てを指す総称です。
具体的に、どのような力があるのか例を挙げていきましょう。
① 自己認識
(能力についての自己概念、自己肯定感)
② 意欲
(マインドセット、内発的動機づけ)
③ 忍耐力
(やり抜く力)
④ 自制心
(自分の行動を自分でコントロールする力)
⑤ メタ認知
(自分の認知を認知する力)
⑥ 社会的コンピテンス
(リーダーシップ・ソーシャルスキル)
⑦ レジリエンスと対処能力
(ストレスや失敗をしても、そこから立ち直り再びチャレンジする力)
⑧ 創造性
⑨ 性格的・特性
いずれの能力も先天的なものだけではなく、生活習慣や学びによって獲得していくものだと考えられています🌱
日本の子どもは『非認知能力』が育ちにくい?
『非認知能力』の一つに自己肯定感(自己認識)があります。
自己肯定感とは、ありのままの自分を肯定する感覚のことで
「自分はこのままでいいんだ』
「自分にはこんな良いところがある』
『私ならできる(できるようになる)』
などのように、自分自身を信じられる感覚のことです。
しかし日本の子どもたちは、他の先進国に比べて自己肯定感が低い傾向にあります。
内閣府の調査『自分に満足している子どもの割合』では
日本 → 45.8%
韓国 → 71.5%
アメリカ → 86.0%
ドイツ → 80.9%
スウェーデン → 74.4%
というデータがあり、日本が圧倒的に低水準であることがわかります💧
自己肯定感は全ての能力向上のエネルギー源のようなものです
つまり日本の子どもは、非認知能力が育ちにくい心理や考え方になっているということがわかります😅
背景要因には、様々なことが考えられますが、
教師として感じている要因の一つは、同じ年齢集団でみんなが同じ学習をする、という日本の学校教育システムにあると個人的には思います。
「同年齢の子と比べてどうか」
というものさしで測ってしまい、どうしても劣等感を感じやすい環境です…しかし、学校教育システムは、すぐに変えられるものではありません…
(将来的には変わってくる、教師として変えたいと熱望しています)
そこで鍵になるのが、家庭での関わりです。
家庭での関わり方はすぐにでも変えていくことができると思います🔥
『非認知能力』を養う、家庭環境とは?
一家は習慣の学校なり、父母は習慣の教師なり
福沢諭吉が言及していた家庭教育の重要性の通り、近年の研究によっても、子どもたちの育ちは家庭環境に大きく左右されることが明らかになっています。
アメリカで開発された家庭環境の質の高さをチェックリスト『HOME(Home Observation for Measurement of Environment)』を参考に、いくつかの項目をピックアップしました。
家庭環境を客観的にチェックしてみましょう💪
□ 家事などをしながら、子どもに話しかける
⇨ 家事や仕事をしている間にも、子どもを気にしている様子がわかるように接する。
□ 子どもに本を読んだり、絵を見せたりする
⇨ 子どもとの関わりを深め、新たな世界や知識を広げる
□ 父・母とも育児に参加している
⇨ 複数の大人と関わる機会が大切
□ 子どもの言動にすぐに反応する
⇨ 親がすぐに反応することで、子どもの情緒的な発達を促す
□ 子どもに対して、肯定的に関わる
⇨ にらんだり、しかめっつらしたり、舌打ちしたりなどの否定的な関わりは、子どものストレスになります。
□ 子どもの表情や感情を言語化する
⇨ 「楽しいね」「おいしいね」など、感情を言語化してコミュニケーション力の発達を促す
□ 子どもに対し、笑顔など豊かな表情を見せる
⇨ 親の豊かな表情で、子どもの表情も豊かになり、表情を理解する力も向上する
□ 毎日1回以上抱く
⇨ 特に乳幼児期はスキンシップを通して、親の愛情を感じ、愛着の形成が進む
□ 子どもの行為に、過度な干渉や禁止をしない
⇨ 適度なルールを設定し、自制心を育む
□ 自分だけの本がある
□ 散歩や公園、買い物に子どもと一緒に行く
⇨ 様々な刺激とふれ、人との出会いやお金の仕組みについての素地を養う
□ 親・教師以外の大人との交流機会をもつ
⇨ 親戚や地域活動など、普段外の人との関わりをもつことで、社会性を養う
□ 家の中が整頓されている
⇨ 自由遊びが制限されず、適度に整頓されていて、安全が保たれている
□ 保護者が外出する時、子どもの面倒を見てくれる人がいる
□ 園や学校の先生と情報共有している
⇨ 園・学校と家庭での関わりに一貫性をもたせ、子どもの混乱を防ぎ、成長を促す。
まとめ
『非認知能力』はこれからの時代を生きていく子どもたちにとって、より重要視される力です💪
日本の教育システムでは、知識・技能の向上を目指すプログラムが圧倒的に多いですが、
そ身につけた力活用し
創造し
失敗を繰り返しながら何度でも立ち直ってチャレンジ
できるようなエネルギー(自己肯定感・自己有用感)🔥を
ご家庭でも高めていこうと意識していくことが大切ですね🍀
最後までお読みいただき、ありがとうございました✨
いつも、記事を読んでくださり本当にありがとうございます。
スキ・フォローとても励みになっています🍀
この記事を読まれた方が、
少しでも『非認知能力』について理解を深めていただき、少しでも参考になれば嬉しいです🌈
今後もできる限り有益な記事を書いていきますので、よろしくお願いします✨
【参考文献】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
