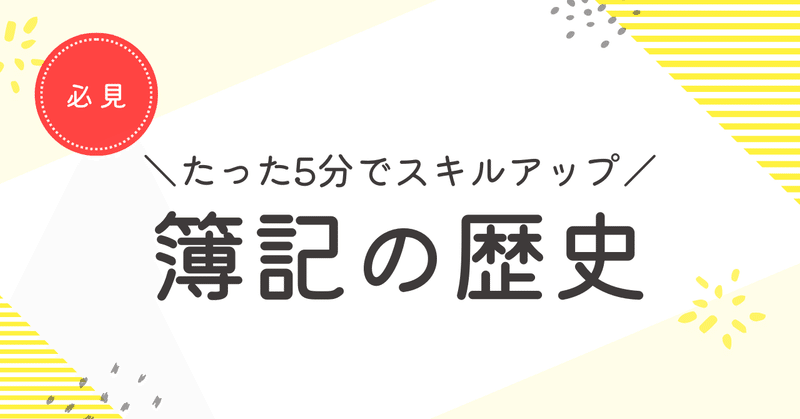
【たった5分でスキルアップ】簿記の歴史をサクッと理解
こんにちは!WEBライターのsora(そら)です。
みなさんのスキマ時間でスキルアップできる記事を定期的にアップしていきます。
日々仕事に追われて時間のないビジネスパーソンに向けて、5分程度で見て理解できるような記事にしていきますので、興味を持った方はぜひフォローしてくださいね。
簿記はビジネスパーソンの必須スキル
簿記はビジネスパーソンの必須スキルです。
簿記を知っている世界と知らない世界では雲泥の差があります。
企業活動となる企業会計の基礎である「簿記」を知っていることは、あなたにとってメリットしかないはず!
全世界共通の「簿記」の知識について、これから一つひとつあなたに伝わるように解説していきますね。
「簿記」をただの資格としてみるのではなく、社会を上手に生きていくためのテクニックと活用してもらいたいからこそ、わかりやすく発信いたします。
今回は「簿記の歴史」を調べてみました。
簿記は人類最高の発明である
18世紀の後半から19世紀の前半位かけて活躍した、ドイツを代表する文豪「ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ」。
彼の小説に出てくる主人公の親友のセリフで「複式簿記は人類最大の発明のひとつであった」とあります。
この言葉はゲーテが言ったのではないかと誤解されがちですが、あくまで小説の中の一節です。
ただし、ゲーテが複式簿記に精通していたことは事実であり、高く評価していた可能性はあります。ゲーテは非常に多彩な人です。政治家であり、小説家であり戯曲家です。
ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ(Johann Wolfgang von Goethe、1749年8月28日 - 1832年3月22日)は、ドイツの詩人、劇作家、小説家、自然科学者(色彩論、形態学、生物学、地質学、自然哲学、汎神論)、政治家、法律家。ドイツを代表する文豪であり、小説『若きウェルテルの悩み』『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』、叙事詩『ヘルマンとドロテーア』、詩劇『ファウスト』など広い分野で重要な作品を残した。
ゲーテといえば、何をしたかはわからなくても名前くらいはわかると思います。
そんな偉大な歴史上の人物が「簿記」について「人類最高の発明である」と感じていたことは事実です。
簿記は4,000年前に発明された
人類の歴史上、簿記を最初に使用したのは古代バビロニアの人々で、ハンムラビ法典の商法に記載された記述が起源といわれています。
年代は紀元前2,000年〜紀元前1,700年頃とされてますから、簿記は約4,000年以上の歴史を持つことになります。
最初に発明された簿記の手法は「単式簿記」といわれ、いまではあまり使用される機会が少なくなっています。
そして「簿記」のスタンダード、メジャーな方法として活用されている「複式簿記」はいまから約600年前のイタリアで発明されました。
この「複式簿記」こそゲーテが人類最高の発明と呼んだものです。
単式簿記と複式簿記の違い
単式簿記とは
単式簿記は、1つの取引に対し1つの勘定科目で記録する記帳方法です。
どういう記帳方法か?
例えば「4月1日に100円の商品を現金で仕入れし、4月2日にその商品を200円で現金で販売した場合」
4月1日 仕入 100円
4月2日 売上 200円 と記帳します。
これにより、売上200円ー仕入100円で取引後の残高は100円となりますよね。
これが単式簿記の記帳方法です。
日付・内容・金額を記入するだけのシンプルな記帳方法。
家計簿に近い簿記手法です。
複式簿記とは
複式簿記は、1つの取引に対し2つ(借方・貸方)に分けて記録する記帳方法です。
借方・貸方ってなんだろう?って思われる方が多数派だと思います。
経理や財務諸表の作成をされている方なら、この用語を聞いたことがあると思いますが一般人には馴染みの少ない用語です。
先ほどの例を複式簿記で記帳すると
「4月1日に100円の商品を現金で仕入れし、4月2日にその商品を200円で現金で販売した場合」
4月1日 (借方)仕入 100円 (貸方)現金 100円
4月2日 (借方)現金 200円 (貸方)売上 200円 と記帳します。
単式簿記ではあれだけシンプルだったのに、なぜこんな複雑になるんだ!と思われる方もいらっしゃると思いますが、それは別の機会にご説明しますので安心してください。
これが複式簿記です。
複式簿記は中世のイタリアで発明された
諸説ありますが「複式簿記」は1,400年代のイタリアで発明され、仕組みが出来上がったといわれています。
しかも発明されたのはイタリアのベネツィアです。
ローマじゃないの!と思われる方もいらっしゃいますが、ベネツィアで生まれたのにはちゃんと理由があるんです。
航海職人の商売のために発明された
ベネツィアといえば「水の都」ですよね。
「水の都」で商売をするには「航海」が最適。商人たちは航海(船旅)でも儲けを計算するために「複式簿記」という「帳簿の記帳方法」を発明したのです。
この時代、いまの「会社」のようなものは存在しません。
初めて「株式会社」が設立されたのは17世紀のオランダの「東インド会社」。
そのため1回の商売(航海)でチームメンバーを募集し、航海終了時にはチームは解散。
チームメンバーにきちんと利益を分配しなければ、今後2回目、3回目の航海でひとは集まりません。
そのためにお金の出入りを明確にし、利益(給料)を支払う仕組みとして、この「複式簿記」という記帳方法が発明されたのです。
ではどうやって航海して商売していたか?
プロセスを簡単に説明すると
❶チームメンバーでお金を出し合って船を購入
❷商売品となる商品を仕入れ、船を出航
❸船で各地をまわりながら商品を販売
❹商売が終わったら船を売却
❺チームメンバーの給料となる利益を配分
この一連のお金を流れをきちんと記帳するために使われた手法が「複式簿記」でした。
日本の簿記の歴史は江戸時代から
日本で商人が活躍しはじめたのは江戸時代。その頃にはすでに「簿記会計」の考え方は定着していました。
しかし、取引の原因と結果を正確に記帳する複式簿記の導入は、明治時代まで待つことになります。
明治時代に複式簿記を広めたのは福沢諭吉
明治時代に世に複式簿記を広めたのは、1万円札で有名な「福沢諭吉」さんです。
福沢諭吉は、経済発展と社会改革の重要性を世に知らしめた偉人です。
彼は経済の自由化や資本主義の導入を支持し、日本の近代経済の発展に大きく寄与しました。また身分制度の廃止や社会制度の改革を提唱し、日本の社会構造の変革に影響を与えた「現在の日本の資本主義社会の礎」を築いた方なんです。
資本主義の導入・発展に寄与した福沢さんならごもっとも。
「複式簿記」を導入したことも納得です!さすが福沢諭吉大先生です!
彼は1873年(明治6年)にアメリカの商業学校で使用されていた簿記教材を翻訳し「帳合之書」というタイトルで書物が発行されました。
そしてこの書物を使って講義を行ったことで日本に「複式簿記」が広まったのです。
そして「複式簿記」の基本ともなる『借方・貸方』の用語も福沢さんによる翻訳から現代までずっと使用されています。
そして同じ頃、日本政府は明治9年に大蔵省(現在の財務省)に「簿記法取調掛」を設置します。
明治11年に「太政官第42号通達」を出して複式簿記を正式採用を決定しました。この通達に基づき、明治政府は地方の予算執行にあたり、全面的に複式簿記による記帳作業をはじめました。
ところが、明治14年日本銀行が設立されたことにより、中央銀行が国庫金を集中管理する仕組みへと移行。これを契機に国の収支管理は官庁会計となり、現在もその流れが続いています。
簿記の歴史|まとめ
4,000年前に発明され現在まで続く簿記。その歴史はいかがでしたか?
中国4,000年の歴史とよくいわれますが、簿記も同様の歴史を経て、現代でもそのテクニックは活用されています。
簿記は学問の域を超えて、ビジネスにおけるテクニックだと考えています。そして簿記を学ぶことは、ビジネスパーソンとしての重要な装備を獲得することに直結すると思います。
本記事を読んでいただき簿記に興味を持っていただけたらうれしいです。
これからも簿記に関する情報を定期的に発信していきます。
ご覧いただきありがとうございました。
WEBライターsora(そら)|ポートフォリオ
ぜひご覧になっていただけるとうれしいです。
現在、案件を募集しています。よろしくお願いいたします。
連絡先|お仕事の依頼等
メールアドレス|sora.writing@gmail.com
X(旧twitter)|https://twitter.com/sora_writing_ao
*もしも記事が気に入っていただけましたらXをフォローしていただけるとうれしいです!
ご依頼・ご相談への返信は迅速にいたします。
何かございましたら、いつでもご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
