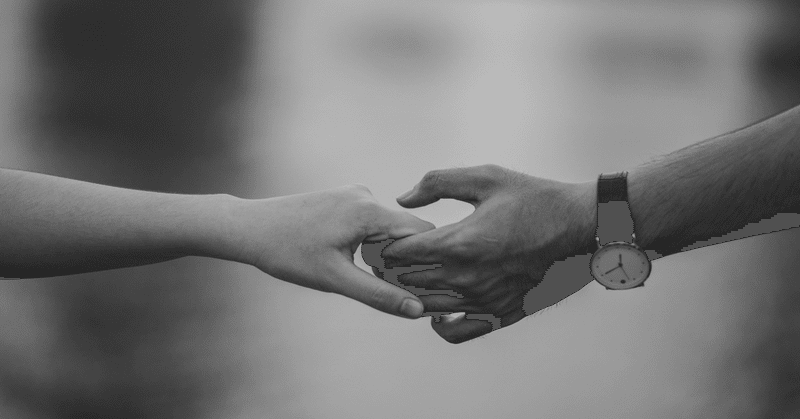
【エッセイ】恋に恨みと恍惚を ①
それは、青春が実らせた甘くて酸っぱい果実の恋ではなく、
首にはめた枷が少しずつ皮膚を擦り切らせるような恋でした。
◆
大学への通学路、講義の教室、学生たちのおしゃべりが響いているだだっぴろい食堂。
こっそりと教科書の山に頭を埋めた眠りに、駅前に霧散していく学生たちの陰った背中と話し声。
真っ赤な太陽が溶ける夕空。
目にする光景が、ふだんのように流れてはゆかず、私の視線だけ不審に彷徨います。
『あいつはいないの?』
どの景色を見ても、そこに彼の姿が穿たれた空洞を見つけてしまう。
視線が彼のかたちの空洞に吸い込まれてゆく。
そして生気や情熱だけでなく、自分の肌のぬくもりさえも、吸い取られる。
その頃の私はなにもかも抜き取られて枯れた流木みたいに、同じ毎日を漂流するだけのひとになっていました。
◆◯
彼は絵描きです。
私は、高校生の頃から絵画や陶芸作品などが好きで、自称・芸術好きを名乗っていました。
たくさんの良いものを見ていると、無名の作品でも、これはいいとか悪いとかの判断がつくようになります。
そして彼の生み出す作品は、これまで美術館でもインターネットでもSNSでも見たことがない独特なものでした。
暖色と寒色の氾濫。
皮膚が切られ、生気と感情が流れ落ち滴るようなドローイングに、絶望を宿すことも忘れた、うつろな瞳が浮かんでいます。
反発し合うはずの性質をもつ色同士が、彼の手にかかると、一枚の紙の上で見事に調和し新しく生きている。
センスと才能の塊。
私の片思いは、才能の目新しさに惹かれたところから始まりました。自分が知らずにいた世界が、彼の瞳の奥には潜んでいたのです。
そんな彼とは同じ講義を取るようになり、過ごす時間が重なることが多かったので、
帰宅の時間が重なれば一緒に最寄り駅まで歩いていました。その間、講義の課題の話をしたり、お互いが作っている作品の話題をしたり、お互いの生き方やひとに対する振る舞い方の話をしたり。
絵描きと物書きという違いはあるけれど、手からものを作り出している者同士、話題には困らなかったのかもしれません。
けど、彼は私より才能があるだけでなく、圧倒的な知性の持ち主でもありました。
「あのな、もっとちゃんと考えてから意見を言ってくれよ。俺の友だちは、顎を指で支えて考えてから反論するんだぞ。」
彼は頑固で、自分が嫌だと思った考え方や言い方をすると、それのどこが悪いのかをいちいち指摘するのです。
「お前よりも俺のほうが才能あるよなあ?」
平気な顔で、そういうことも聞いてきます。
『なんでそんなことに同意を求めるんだろう。』
そう思いつつ私は、「そうだねえ。」と笑っていました。
当時、私は物書きとしての自覚が確立できていなかったのです。
「俺がこんなにいろんな気づきを与えてるのに、お前はなにも気づきを与えてくれないな。」
また、彼は気づきという言葉が好きでした。
人生の新しい見方や考え方を知ることが、気づき。
気づきを与えてやる、というのが彼が最も口に出すことの多い言葉で、気づきを与えたら気づきを返す、というのが彼のルールでした。
彼よりも頭の悪い私に、彼に人生の気づきを与えることなんてできませんでしたが、彼はしつこく私にせびりつづけました。
気がつくと、
彼の言葉をまるで孔子の言葉のごとく拝聴するようになりました。
反論の余地がない彼の弁舌に巻かれ、私への痛烈な否定や非難を噛み締め、落ち込みながら家に帰る灰色の日々を送りながら。
それでも、そんな「愚鈍で」「馬鹿な」私よりも彼はいつでも美しくて、
自分を嫌悪すればするほど好きになっていきました。
大学からの帰宅前に私から頻繁に連絡するようになり、一緒に帰れなければ気を揉んで泣いて、
「もう死ぬしかないのかも」と自宅から三時間かかる海まで歩いて行ったりしました。
あるいは彼を忘れるように、仲良くしたくもない同級生とつるんでみたり。
辛かった。
でも、彼に呼ばれたら、求められたら、
会うのをどうしても自制できない。
恋の枷は首にはまったまま、彼のもとへと引っ張られてしまうのです。
出会ってから四年が経ち、大学卒業を迎えました。
私も彼も内定が決まり、お互いの地元で働くことになりました。
大学最後の日、ふたりでビジネスホテルに泊まって一晩明かすと、
どこに行くこともなく、卒業してしまった私たちにはこの街に行き場もないので、
適当にぶらぶらしてから、別方向に向かう電車に乗って別れました。
さようなら、ありがとう、の言葉もなく。
あれだけの苦しい年月が嘘かのような、それはあっけない別れ方でした。
◆◯◆
大学を卒業して一年が経ち、退職すると、私は一人暮らしをしました。
東京でウェブライターをしながら、多摩川のほとりを歩いたり、夜にひとりで缶チューハイを飲んでみたり、初めての一人暮らしの時間を満喫しました。
しばらくすると北海道に飛んで、かぼちゃの収穫やじゃがいもの選別をしながら小説を書く生活を送りました。
いま思い出しても、それは輝く一年間。
東京で出会った短い恋人、北海道で出会ったおじいちゃんやおばさん。出会いは自分を育みます。それに、なにもかもが「自分ひとり」という一単位で、なんでもできる自由がありました。
私は自分らしさをあたり構わず放出し、幸せや苦しさを吸収しながら、あくせく働いて暮らしていました。
北海道から帰り、二ヶ月ほど経った春。
「会わないか。」
彼から久しぶりに、連絡が入りました。
辛すぎた仕事。ストレスで抜けた頭髪。
弱々しいメッセージ、元気のない声。
「仕事辞めたんだ。それで会いたくなった。」
大学生の私だったら、泣くほど喜んで会いに行ったでしょう。
でも、いまの私にとって彼は昔のひとでした。
『いまさら、あいつに会うメリットってあるかな・・・』
思い出されるのは、投げかけられた厳しい言葉たちの残骸。
いまなら分かる、彼の傍若無人さ。
「俺は正しいことを言ってるのに、なんで誰も聞かないんだ。これを聞いたら成長できるのに。」
「俺が気づかせてやったのに、感謝がないなんて。」
わざわざ気づきを得たくて友だちを作るわけではない。
そしておそらく彼との触れ合いで気づきを得ようと思うひとがいないことにさえ気がつかない、盲目。
卒業から月日が経つとともに膿の固まってきた、こころの古傷を見つめます。
その膿をまたほじくることはしたくない。
あのときにまた戻りたくない。
だから、会うことを決めました。
彼が、大学生の頃の私に会いたがっていることは明らかでした。
あの頃の私に会って、言いたいことを聞いてくれる私に、傷を慰めてもらいたがっている。
そういう彼に、この一年間がどれだけ私を変えて進化させてくれたのかを深く刻み込んでやろう。
慰めなんてくれてやらない。大学時代の彼が、私に辛言を与えつづけたのと同じように。
あの頃の苦しみや辛さを追体験させてやるのだ。
彼が私に刻みつけたこころの傷と同じくらい深く深く。
「久しぶりだね!もちろん会いたい」
別れて二年が経ってようやく私は、
彼に人生の気づきを返すことができそうでした。
(恋に恨みと恍惚を ②につづく)
次回は、恋の決着か?
それとも新しい展開か?
不定期に更新するので気長にお待ちください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
