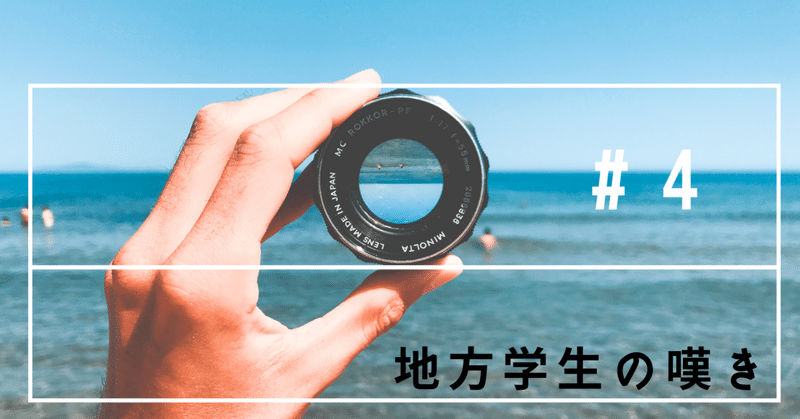
地方学生の嘆き(答えはまだ分かりません)
今日は私が就職活動で感じたモヤモヤを話していきたいと思います。
みなさん”地方就活”という言葉を聞いたことがあると思います。
その言葉からどんなイメージが浮かびますか?
地方大学に通う大学生による就職活動。情報が少ない。就活にコストがかかる。学歴が低い。などその多くはあまりポジティブではないかもしれません。僕も地方就活という部類なので、そのような言葉を聞きながらそして感じながら就職活動を行ってきました。
ただ私はその”地方就活”という言葉はあまり好きではありません。
なぜなら「地方だから大手有名企業は無理だ」とか「地方の大学は地元就職には強いから就職はここでする」とか、地方という言葉に、そして感覚としてネガティブで否定的な捉え方をしがちだからです。
ただそう思ってしまうのも無理はありません。私も実体験を通して感じました。私は1か月ほど東京に宿を借り、就職活動を行いました。そこで様々なインターンシップや他大学の学生と対話する機会を多く作りました。
そこで一番感じたことは、「ここまで学生のレベルが違うか」ということでした。
コミュニケーション能力、論理的思考力、経験のレベル。なんといってもその主体性や積極性に感心しました。私自身、少し覚悟はしていたものの想像以上でした。
そこで私が思ったのは、なぜ地方の大学の学生は都会の学生と比べて、主体的な学生が少ないのか。能力値が低いのか。という問いです。未だ明確な答えはありませんが、そこには大きく2つの理由があると思います。
①そもそも機会がない
正直、情報格差はどんどん縮んでいると思いますが、機会格差はまだまだ大きいのではないかと思います。
長期のインターンを経験できる機会や活き活きした社会人に会う機会、働くことについて考えるセミナーなど、やはり地方よりも首都圏の方がそのチャンスは未だに多いなと強く感じます。
情報よりも実際に肌で触れる機会、対話をする機会の方が、学びや影響度は高いと思います。
ただコロナウイルスによるオンライン化によって機会格差はより平等に近づいているとも言えます。そこに少し期待したいところです。
②挑戦者を否定する文化
この部分は大きく影響していると思います。地方の学生に限ったことではないと思いますが、私の実感として、地方の方がより
「出る釘は打たれる文化」があるのではないかと思います。
これは①の意見と関連性はあると思いますが、そもそも地方に主体的に挑戦する人、少数派の行動をする人がいないことに要因があると思います。
地方の学生は未だに、いい意味でも悪い意味でも安定的です。
「公務員のキャリアが最も安定している」や「去年の先輩がここに入ったからここを第一志望にする」など、先人と同じレールを歩むこと、習うことが最も善いキャリアだと考える人が未だに多いと感じます。よって少数派を生きる挑戦者を嫌う。知らないものは叩く。だから主体的な挑戦者が生まれないのだと思います。
正直この課題はとても大きく、様々なアプローチが必要だと思いますが、地方に生きる身として何かしていきたい。そう思います。
まずは、今、自分にできることとして、従事している就職支援活動を通して、
「主体的なキャリア選択ができる人を1人でも多く」
そんな目的意識を持ちながら全力で頑張りたいと思います。
本日もここまで読んで頂きありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
