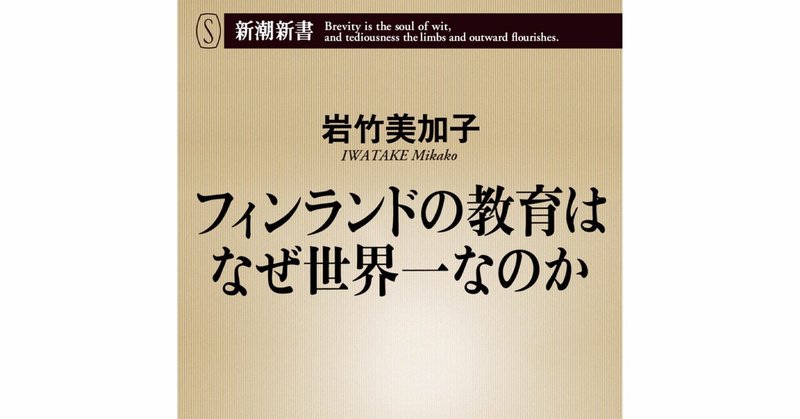
「ウェルビーイング」を主体に考えるフィンランドの教育
フィンランドで、ウェルビーイングは権利と並ぶ教育の柱であるが、その意味は幅広い。健康。体に不調がなく心地よい。日々の生活の快適さ。生き生きとしている。気分が晴れやか。自尊心を持てる。自己肯定感がある。他人も尊重できる。人と心地よく繫がっている。性的充足。不安がない。脅かされていない。差別やいじめ、虐待がない。障がいがあっても、支援や保護を受けられる。諸権利が侵害されておらず、護られている。経済的、精神的に安全で安心して暮らしていける。貧困、紛争、戦争からの自由。
ウェルビーイングは、フィンランド語で「ヒュヴィンヴォインティ(hyvinvointi)」である。それは、「ヒュヴィン(良く)」という副詞と、「ヴォインティ(状態、コンディション)」という名詞の複合語で、「良くあること」「良い状態」のような意味である。
2019年刊行の『フィンランドの教育はなぜ世界一なのか』からの引用。著者の岩竹美加子氏は、1955(昭和30)年、東京都生まれ。早稲田大学客員准教授、ヘルシンキ大学教授を経て2019年6月現在、同大学非常勤教授(Dosentti)。ペンシルベニア大学大学院民俗学部博士課程修了。著書に『PTAという国家装置』、編訳書に『民俗学の政治性』等。
人口約550万人、小国ながらもPISA(一五歳児童の学習到達度国際比較)で、多分野において一位を獲得、近年は幸福度も世界一となったフィンランドについての一冊である。著者はフィンランドで子育てをした経験から、フィンランド人の教育における価値観や考え方を紹介している。フィランドの教育は、入学式も、運動会も、テストも、制服も、部活も、偏差値もない。小学校から大学まで無償、シンプルで合理的な制度、人生観を育む独特の授業がある。その教育のあり方を貫く価値観とはどのようなものか。
その一つが「個人のウェルビーイングの重視」である。フィンランドでは「ウェルビーイング」(フィンランド語では、ヒュヴィンヴォインティ(hyvinvointi))があらゆるところで語られるという。そして、実に幅広い意味で使われている。健康、心地よい、快適である、気分が晴れやかであるということに加え、自尊心・自己肯定感があり、他人も尊重できる。人と心地よく繫がっている。さらには、差別やいじめ、虐待がないこと。諸権利が侵害されておらず、護られていること。そして、貧困、紛争、戦争からの自由、などなど。
フィンランドの教育では、この個人のウェルビーイングを主体にして教育が組み立てられている。つまりは平等であり、権利が保証されており、個人のウェルビーイングが侵されない教育である。フィンランドの教育の良さは、何よりもそのシンプルさにある。入学式や始業式、終業式、運動会などの学校行事がない。授業時間は少なく、学力テストも受験も塾も偏差値もない。統一テストは、高校卒業時だけ。服装や髪型に関する校則も制服もない。部活も教員の長時間労働もない。そうしたシンプルな教育を支えるのが、徹底した教育無償化と平等、子どもの権利やウェルビーイング、子どもたち自身の教育への参加などの理念なのだという。
さらに興味深いのが教育(学校)と地域のかかわりである。日本では、「学校、家庭、地域」と言うが、フィンランドには教育に関して地域という考えはなく、さまざまな連絡協議会、青少年育成委員会など、学校を取り巻く煩雑な組織がないという。こうしたことも、子どもたちのウェルビーイングを第一に考え、大人や周囲が干渉する形で教育を考えるのではないという姿勢を示したものだろう。こうしたさまざまな仕組みはすべて日本に導入すれば良いというわけではないだろうが、「ウェルビーイング」を主体に考えるフィンランドの教育のあり方は、教師も生徒もともにどこか疲弊していくような日本の教育の現状に対して、さまざまな示唆を与えてくれるのではないだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
