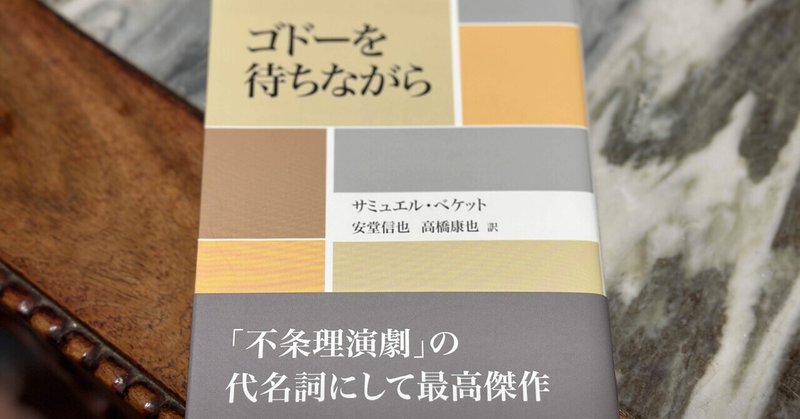
われ苦しむ、ゆえにわれ在り——ベケット『ゴドーを待ちながら』を読む
ヴラジーミル:……そうだ、この広大なる混沌の中で明らかなことはただ一つ、すなわち、われわれはゴドーの来るのを待っているということだ。
エストラゴン:そりゃそうだ。
ヴラジーミル:でなければ、夜になるのを。(間)われわれは待ち合わせをしている。それだけだ。われわれは別に聖人でもなんでもない、しかし、待ち合わせの約束は守っているんだ。いったい、そう言いきれる人がどれくらいいるだろうか?
エストラゴン:数かぎりないね。
ヴラジーミル:そうかな?
エストラゴン:よくはわからないけどな。
ヴラジーミル:そうかもしれない。
ポッツォ:助けてくれ!
ヴラジーミル:いずれにしろ、確かなことは、こうした状態では、時間のたつのがまことに長く、したがって、われわれは暇をつぶすのに、なんといったらいいか、一見合理的に見えるがすでに習慣となっている挙動を行なわざるを得ない。それは、われわれの理性が沈没するのを妨げるためだというかもしれない。それはたしかにいうまでもない。しかし、すでに久しく理性は大海原の底深く、永劫の闇のうちをさまよっているのではなかろうか。わたしがときに考えるのは、そこだ。わたしの推論が、わかるかい?
エストラゴン:うん、人はみな生まれたときは気違いよ。そのまま変わらぬばかもある。
サミュエル・ベケット(Samuel Beckett, 1906 - 1989)は、アイルランド出身の劇作家、小説家、詩人。不条理演劇を代表する作家の一人であり、小説においても20世紀の重要作家の一人とされる。1945年以降おもにフランス語で執筆した。ウジェーヌ・イヨネスコと同様に、20世紀フランスを代表する劇作家としても知られている。1969年にノーベル文学賞を受賞。
1952年、現代演劇に多大な影響を及ぼすことになる戯曲『ゴドーを待ちながら』を発表。同戯曲は翌年、ロジェ・ブランの演出によって、パリの小さな前衛演劇の劇場であるテアトル・ド・バビロン(Thétre de Babylone)で初演された。批評は九分の無視ないし敵視に抗して、一分の熱狂的称賛に分かれたが、いわゆる「醜聞ゆえの成功(シュクセ・ド・スキャンダル)」を収め、百回を越える公演を記録した。彼自身は「三部作を書く苦闘の中での息抜き」として書いたと述べていたが、その新しさと普遍性によって彼の作品の中でもっとも著名なものとなった。
この芝居は現代演劇最大の傑作(あるいは問題作)であると言われる。訳者の一人高橋康也氏は、あとがきで、この作品が偉大であるのは、この作品についての解釈が確定しておらず、「いまだに新たな解釈を生成しては吸収してしまう巨大なブラックホール」であるからと述べている。そして、それに匹敵する作品は『ハムレット』ただ一つであろうとも述べる。
物語はヴラジーミルとエストラゴンという2人の浮浪者が、ゴドーという人物を待ち続けているところから始まる。2人はゴドーに会ったことはなく、たわいもないゲームをしたり、滑稽で実りのない会話を交わし続ける。そこにポッツォと従者・ラッキーがやってくる。ラッキーは首にロープを付けられており、市場に売りに行く途中だとポッツォは言う。ラッキーはポッツォの命ずるまま踊ったりするが、「考えろ!」と命令されて突然、哲学的な演説を始めたりする。はたして、ゴドーはやってくるのか……。
2人が待ち続けるゴドー(Godot)の名は英語の神(God)を意味するという説もあるが、ゴドーが実際に何者であるかは劇中で明言されず、解釈はそれぞれの観客に委ねられる。木一本だけの背景は空虚感を表し、似たような展開が二度繰り返されることで永遠の繰り返しが暗示される。それはまるで、無為な日々を毎日くり返す私たちの人生のようである。
「不条理劇」の傑作とされるが、ベケットははたして世界の不条理について描きたかったのかも定かではない。高橋康也氏は、作者の劇作意図はその内容よりも「形式・表層」のほうにあったかもしれないと述べる。作品は奇妙な対称性や二重性に満ちている。第一幕と第二幕(一幕のポッツォは二幕で盲人となっている)、キリストと共に磔刑に処せられた二人の泥棒(一人は救われ、一人は地獄に堕ちる)、ウラジーミルとエストラゴンという対称をなす二人の浮浪者……。作者は摂理の不可知や世界の不条理に頭を悩ましているが、その思想的「内容」の深さよりは、対称的な「形」の美しさに魅せられているかのようである。
また、問われているのは不条理性だけではなく、西欧的理性・合理性でもある。物語は矛盾に満ちている。論理的矛盾、非連続、逆説に満ちている。話の中では「考える」ということがテーマとなっている。しかし人間たちは考えない。従者・奴隷であるラッキーに考えさせる。明らかにラッキーは人間以下の存在(動物)として描かれており、その存在に「考えさせる」という矛盾。「考える」という合理性は、物語の中では完膚なきまでに嘲笑される。「われ考える(思う)、ゆえにわれ在り」というデカルト的合理性は、作品の中では崩壊しているのである。
もう一つ、この作品の特徴として「身体性」が挙げられる。「台詞がこれほど身体性に貫かれている芝居も少ないだろう」と高橋氏は述べる。人物たちの身体的苦痛は、視覚的に明示されるばかりでなく、たえず言語としても滲み出る。エストラゴンの靴の痛みや殴られた身体、彼らの息や足の悪臭、空腹感、ラッキーの赤むけした首筋……。ほとんど「われ苦しむ、ゆえにわれ在り」の感がある。そして、演劇と受苦(パトス)とは切っても切れぬ関係がある、と高橋氏はいう。この作品では、受苦の末に磔刑に処せられたキリストのメタファーがいたるところに現れる。奴隷として苛まれるラッキー、二人の浮浪者に支えられる盲人となったポッツォ。何よりゴドーを待ち続けながらこの世の受苦に苛まれる浮浪者の二人が、キリストのようでもある。この作品のテーマは「われ苦しむ、ゆえにわれ在り」という、受苦の現実性・身体性というところにあるのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
