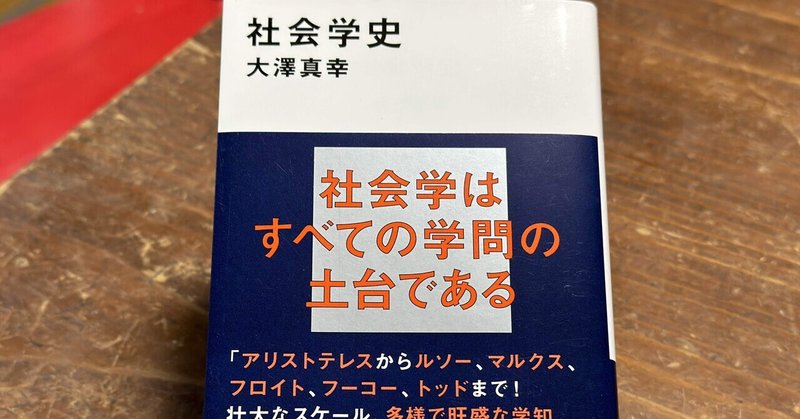
社交とは「演じる」という形式の相互行為である——ジンメルの相互行為論より
ジンメルの社会学の重要な用語をひとつだけ取り出すとすれば、「相互行為(独 Wechselwirkung, 英 interaction)です。そして、相互行為には必ず内容と形式があるということが、ジンメルの着眼点です。(中略)
このようにコミュニケーションには、内容のアスペクトと形式のアスペクトがある。それが相互行為の二つの側面です。そして、この二つが独立しているというところが、ジンメルの非常に重要な着眼点です。独立していることの証拠として、二つ挙げています。一つは遊戯、もう一つは社交です。(中略)
[遊戯と]同様のことを、大人がやるのが社交です。つまり社交においては、お互いがどんな目的や意図をもっているのかは別として、お互い嫌いだと思っていても仲良くして見せたり、礼儀正しくしたりする。社交とは、相互行為を内容から切り離して、形式だけを楽しむことです。社交という現象は、相互行為に内容とは別に形式のアスペクトがあるということを照らし出しているのです。(中略)社会を社会たらしめているのは、内容ではなく形式のほうだというのがジンメルの論点です。
社会学者の大澤真幸さんの本『社会学史』より、社会学者のゲオルク・ジンメル(Georg Simmel, 1858 - 1918)についての解説を抜粋。ジンメルは、デュルケームやヴェーバーに比べると「こういうことを言いました」という要点を取り出しにくい社会学者である。しかし、デュルケームと同様に、やはり「社会」を見出したのがジンメルであり、ジンメルの社会学のキーワードを取り出すならば「社会圏」や「相互行為」という用語が挙げられる。
社会圏(social sphere)とは、ジンメルの独特の用語で、境界線やメンバーシップがはっきりしていなくても、それとなく利害とか目指すところが共有されているという意識がある人間の集団全体を「社会圏」と呼んだ。彼は、近代化が進むにつれて、個人の社会圏が拡大していくと考えた。つまり農村共同体のような限定された社会圏から、都市生活を送る個人がもつ多様で広範な社会圏への移行である。結果として社会圏が拡大するほど、つまり「都市化」するほど、個人が自立することになる。個人の自立の程度が高まると、社会圏の内部の分化が、つまり分業や、あるいはより小さな下位集団の形成が促進されるという。こうした変化は、「責任」や「罪」といった概念にも劇的な影響を与える。前近代社会では、責任とは原則的に集団的責任(部族全体など)だったものが、社会圏が拡大し個人が自立すると、責任は個人に帰せられるようになっていく。(昭和の時代にミスをすると連帯責任でケツバットを受けていた野球部は前近代社会的な社会か…)
もう一つのジンメルの重要概念である「相互行為(独 Wechselwirkung, 英 interaction)」は、英語で言えばインタラクション、つまりコミュニケーションや人間のやりとりのことである。これには「内容」と「形式」がある。これだけ言えば当たり前のように聞こえるが、ジンメルのすごいところは、この二つが独立していて、さらには内容よりも「形式」が重視されるのが社会における相互行為(=社交)であると喝破したことだ。内容とは、相互行為の目的や動機のこと。そして、形式とは、さまざまなコミュニケーションの振る舞いのことで、助け合うとか、協力するとか、分担するとか、競争するとか、服従するとか、模倣するとか、そのような形式のことである。例えば「遊戯」(ごっこ遊び、ままごと)を考えてみると、子どもたちは特に目的もなく、形式を楽しんでいるように見える。それと同じことを、大人がやるのが「社交(独 Geseligkeit)」である。社交においては、目的(お互いの絆を構築する)とは独立して、形式(礼儀的にふるまう、おべっかを使う)を重視しているように見える(まあ、そこにもそうすることで保身をするという隠れた動機があるわけだが)。目的とは独立して、形式を重視するということが社交(相互行為)の本質であるというのが、ジンメルの理論である。つまり、社会を社会たらしめているのは、内容ではなく形式のほうである。ジンメルは、相互行為の形式としてのアスペクトに、個人の目的や動機といった内容には解消できない、社会の独特のリアリティを見ようとしたわけだ。(ジンメルの社会学を「形式社会学」という用語でくくることがあるが、これも社会学という学問において「形式」を重視したジンメルの考えを強調したものだ。)
「演じる」という形式のアスペクトが重視されるのが社交であるとしたら、演じることは嘘をつくということではなく、人間同士の相互作用を円滑に進めるポジティブなものとして捉えられるのではないか。同じことを、劇作家の菅原直樹さんが言っている。菅原さんは劇団OiBokkeShiの主宰で、演じること、演技をすることが認知症や高齢者のケアにもつながるとして、演劇ワークショップなどを全国各地で開催している方である。菅原直樹さんが脚本を担当した映画「うちげでいきたい」の解説で、菅原さんは「演じる」ことの本質に相手を思いやることがあり、演じることをきっかけにして本音が言えることもあると語っている。
今回の家族では、最後、珠美と雅文が演じるじゃないですか。最初はしてあげるための演技だったけれど、途中で特に雅文と民代のやりとりは本音が出ている。演技だったものが真実になっているわけですよね。役を演じてお母さんにある台詞を言うと、お母さんはそれに応えるわけですよね。これはお母さんにとって、もしかしたらずっと言いたかった台詞かもしれない。で、さらにそれに息子が返事をする。これももしかしたら、ずっと言いたかったけど言えなかった台詞かもしれない。なので演技はきっかけなんだけれども、そこで本当に言いたいことは言えたっていうね。
演じるというパフォーマンスは私たちは日常生活の中で思いのほか、頻繁に行なっているものである。そして、ジンメルに言わせれば、その演じるという「形式」こそが社会を社会たらしめている、つまり「社交」の本質である、というわけである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
