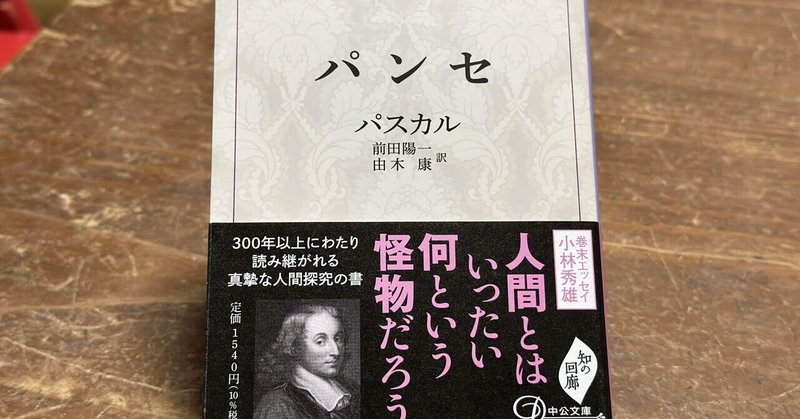
すべてのことについて少しずつ知ること——パスカル『パンセ』を読む
三七
すべてを少しずつ。
人は普遍的であるとともに、すべてのことについて知りうるすべてを知ることができない以上は、すべてのことについて少し知らなければならない。なぜなら、すべてのことについて何かを知るのは、一つのものについてすべてを知るよりずっと美しいからである。このような普遍性こそ、最も美しい。もしも両方を兼ね備えられるならばもっとよいが、もしもどちらかを選ばなければならないのだったら、このほうを選ぶべきである。世間は、それを知っており、それを行なっている。なぜなら、世間は、しばしばよい判定者だから。
ブレーズ・パスカル(Blaise Pascal、1623 - 1662)は、フランスの哲学者、自然哲学者、物理学者、思想家、数学者、キリスト教神学者、デカルト主義者、発明家、実業家である。神童として数多くのエピソードを残した早熟の天才で、その才能は多分野に及んだが、39歳にして早逝した。その遺稿は死後『パンセ』として出版されることになった。「パスカルの定理」「パスカルの原理」など幾何学・物理学でも名を残すが、哲学者としても著書「パンセ」は、没後300年以上経つ現在まで読み継がれている。
『パンセ』はもともとパスカルの意図としては、護教書(キリスト教の信仰の正しさを示す書)の執筆構想があり、その材料となる断片を書きためていたようだ。『パンセ』全体の構成としては、前半で「神なき人間」の悲惨と偉大さの両面を指摘し、「考える葦」の本質的矛盾を指摘する。後半で、その本質的矛盾を解き、人間を至福に導くものはキリスト教に他ならないと結論している。もっとも、それを踏まえたとしても『パンセ』はその思索・思想の奥深さと、つきつけてくるテーマの多様性と鋭さなどにより、単なる護教書に留まるものではない。人間の欲望の構造、個人と共同体の問題、他者の存在によって想像的な自我が生ずること、認識と視点・言語との関係、テキスト解釈と暗号の問題、等々の重要で深遠なテーマが扱われており、特定の思想的・宗教的な立場を超えており、現代でもそのテーマの重要性は変わっていない。
小林秀雄は1941年に著した文章で『パンセ』の主題は以下の文章にあると喝破している。「人間とは、一体、何んという怪物であるか。」当初、数学や幾何学の研究に長い年月を費やしたパスカルは、その後「人間の研究」に向かい始める。そして、数学の方法が人間の研究に適していないことに気づく。「数学を知らない人より、数学に深入りした私の方が、遥かに自分の状態について迷っている事を覚った」のである。そして、『パンセ』には人間の抱えるさまざまな矛盾やその本性について、鋭い洞察が綴られている。
断章三七は「すべてを少しずつ」知ることについてである。「普遍的であること」あるいは「普遍的な人」についての考察が、断章三四でなされている。「普遍的な人たちは、詩人とも、幾何学者とも、その他のものとも呼ばれない。しかし、彼らは、それらのすべてであり、すべての判定者である」と。詩人と幾何学者は対置されている。詩人とは「繊細な精神の人々」のことであり、目に見えない微妙なものを感じとることができる人々のことである。しかし、彼らは幾何学者のように秩序だってそれらを証明することはできない。一方、幾何学者(数学者)は、原理のほうに慣れていて、原理によって推理するので、目の前にあるものを見ないことが多い。原理では扱えない繊細な事物にぶつかると途方にくれてしまう。
それでは、詩人でも幾何学者でもない「普遍的な人」は、どのようにものごとを知るのであろうか。それは「すべてのことを少しずつ知る」のである。人は、すべてのことについてすべてを知ることはできない。一つのことについて深く知る人は幾何学者であり、すべてのことを感じとることができるのが詩人であるとすれば、普遍的な人は、すべてのことについて少しずつ知る者である。パスカルがここでいう「普遍的な人々」とはどのような存在なのだろうか。
おそらくパスカルとしてはキリスト者を想定していたに違いない。しかし、私たちは神なき時代に生きているし、信仰を人間の指針にするだけでは満足できないであろう。私にはそれは「哲学する人」であるように思える。哲学する人は、演繹的な思考だけに頼ることもせず、目の前の現象をただ感じとるだけで満足することもない。哲学する人とは、すべてのことについて少しずつ知り、世界と人間について洞察する者である。数学者のような厳密さと、詩人のような繊細な感覚を同時に持ち合わせている。しかし「哲学する人」と「哲学者」を混同してはいけない。真に哲学する人は、哲学者であることに甘んじず、哲学という学問にもこだわらないからである。パスカルは断章四で次のように言っている。「哲学をばかにすることこそ、真に哲学することである」と。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
