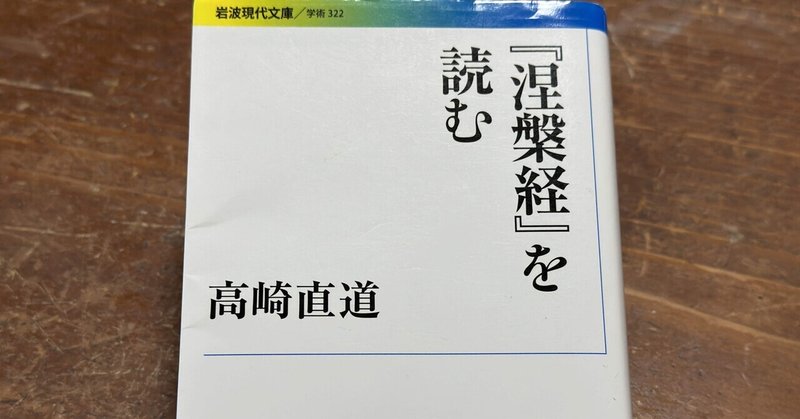
仏性を見るための「中道」——高崎直道『『涅槃経』を読む』を読む
いろいろな例をあげながら「仏の本性」、つまり仏性を得るにはどうすべきかを説いているわけです。そこに中道の考え方・ものの見方が述べられています。(中略)
仏の教えは苦と楽の両極端を離れた道であるというのが、もともとお釈迦さまが説いた中道の教えです。それが大乗仏教になりますと、『般若経』あたりから「空」という教えを説きます。この空の教えは「有る」ということと「無い」ということの両極端を離れた中道であるというように変わってきます。これが大乗の空の教えで、空とは何もないという意味ではありません。有と無の両極端を離れた中道という意味なのです。
『涅槃経』ではまた少し変わった言い方をします。仏は常住でありまた無常である。あるいは有我(うが)であり無我であり、苦でもあり楽でもある。その両方であって、見方によってそのどちらにも偏らないことがここでいう中道です。特に無常とか無我に対して、ここでは如来は常住である。そして如来の仏性が真実の我であると強調してきまして、その教えが決して有我とか常住ということだけをいおうとしているのではなく、仏教の従来の教えである無常とか無我という教えを踏まえた上で、しかも如来が常住であり我であると説くのが、この『涅槃経』の説く中道の特色であると説明しています。
『涅槃経』(ねはんぎょう、梵: ニルヴァーナ・スートラ)は、釈尊の入滅されるその日の最後の説法を通して、仏教の根本思想を伝える経典である。クシナーラーの沙羅双樹の中で釈尊が、「仏の永遠性」「一切衆生悉有仏性」などの真理を語る。仏は永遠であり、全ての人間には、仏のさとりを得られる「仏性」が備わっていることが明らかにされる。日本仏教に大きな影響を与えた。本書『『涅槃経』を読む』は、仏教学の第一人者である高崎直道氏が、NHKのラジオ第二放送「こころの時代~宗教・人生~」で放送された講義録を元にしたものである。
「一切衆生悉有仏性(一切衆生悉く仏性有り)」とは、命あるものは、すべて仏となる性質(可能性)を内にもっている。 つまり、すべての人が仏に成るべき仏性を生まれながらに具えているという意味である。まず、仏性とは何かというと、「仏性は真金(しんごん)の蔵のごとし」という。そういう無上の宝物を衆生はみな持っている。しかし皆それには気づいていない。なぜ気づかないかといえば、いろいろな欲望とか無知、怒りなどの煩悩に覆われてがんじがらめになっているために、本来自分が仏と同じ仏性という宝物を持っていることを知らないのだという。
私たちはいろいろな煩悩の殻に覆われているために仏性を見るのが難しい。それでは、仏性を見るためにはどうするべきか。それが「中道」だという。例えば、大乗仏教の「空」という考え方も中道である。空とは無ということではない。空とは有るとも無いとも異なる。その両極端の見方を離れた中道が「空」のものの見方である。同様に、仏性は常住であり、また無常である。仏性は有我であり無我であり、苦でもあり楽でもある。その両方であって、どちらにも偏らない見方が中道である。仏性を見るためには中道のものの見方が重要だというわけである。
凡人はすべてが無常であるとか、すべてが苦であると聞くと、それ以外に苦でないもの、無常でないものがないように思う。しかし智者は自分の身にある法身の種子、つまり仏となる種があることを知って、一切が無常だとはいわないものだという。結局、ことばの上で「有」であるとか「無」であるというとき、いかなる場合に「有」といい、いかなる場合に「無」であるのかを、正しく真実を知ることが中道であると、この『涅槃経』では説明しているように思われる。
解説で仏教学者の下田正弘氏が「悉有仏性(悉く仏性有り)」とは「仏の呼びかけ」であると説明している。自分たちのうちに仏性がありながら、それに気づかない衆生は、苦悩の輪廻の世界に囚われつづけている。このとき、さとりに至った仏(如来)が「すべての衆生に仏性がある」と宣言するとき、衆生はその仏の声を聞き、それを受容することで輪廻から涅槃へと意識を転換する。この如来による仏性の存在の宣言は、仏の発話として自立した主張であるとか、普遍的に妥当する真理ということではない。この言明は、仏の内から外に向けて発され、衆生の内へとまっすぐに向かう「仏の呼びかけ」なのだという。そして、この「仏の呼びかけ」を聞き、仏性を見るために必要とされるのが「中道」なのであろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
