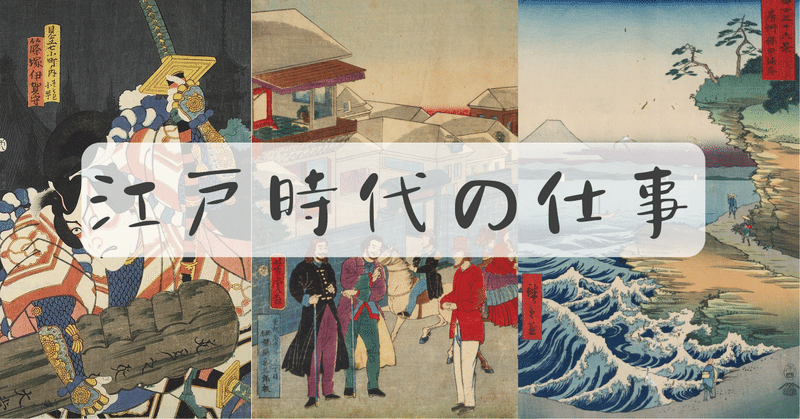
【読書記録】『仕事と江戸時代』
『仕事と江戸時代』を読みました。
今年に入ってから、労働の歴史(『働き方全史』)について学びました。
そんな中で、日本人にフォーカスされている箇所がありませんでした。なので、「じゃあ、日本はどうだったの?」って思ったのが読んだきっかけです。
学校で日本史を習ってからさっぱりだったので、なんとなく聞き覚えのある言葉も見ながら読みました。
身分の違い
当たり前のことかもしれませんが、まず身分の武士・町人・百姓があった上で職業があることをよく理解していませんでした。また、その身分の中でも位があることも知りませんでした。全て別物という認識でした。
例えば、旗本・御家人と呼ばれる人たちは、武士の中の位の違い。具体的には、将軍に面会できるかどうか。
本百姓と水呑百姓は土地を持つかどうかの違い。
武士
江戸時代くらいまでは武士が多くいるイメージですが、人口では6%ほどしかいなかったそうです。この時代に学校はありませんが、クラスの1~2人くらいが武士でそれ以外はほとんど町民・百姓と考えると少なさが分かります。
武士には、士分、徒士(准士分)、足軽層、武家奉公人と位が分けられていました。私たちがイメージする武士は士分・徒士にあたり、全体の半分程度でした。つまり、人口の3%くらいしかいなかったのです。
ちなみに士分と徒士の違いは武士の権利を子どもに引き継げられるかどうかで、徒士は必ずとはいかなかったようだ。
武士は領地を支配することが仕事で土地を守るのはもちろん、行政も管理していた。食べ物は農民の年貢があったため食べるには困らなかった。いわゆるベーシックインカムが保証されていた。
士分と徒士、足軽層と武家奉公人の身分による違いは現代でいうところの正社員と非正規雇用にあたる。しかし、正社員は現代よりは厳しい。士分は辞めることが許されず、忠誠心が求められた。辞める際には、男性の、主に親族や親戚に譲渡することで辞めることができた。
このように職は世襲だったので、学校などは存在せず、親から子へと仕事は直接引き継がれた。しかし、現代のマニュアルのように引き継がれていたため、解決できない問題も多かった。
江戸時代は学問も発展し、江戸中期にはこの問題を百姓を起用して解決していった。二宮尊徳も活躍した内の一人だった。この頃から、世襲(身分制度)による行政は崩壊していく。
そんな中でも、以前のやり方に固執する武士もいた。しかし、彼らをクビにすることはできず小普請と呼ばれた。旗本の4割はこれにあたり、恩恵を受けているにも関わらず全く働いていない。現代の働かないおじさんとも言える。
こうした人が働く現場はほとんどがルーティンワークでやりがいがなく、いじめが横行していたという。
では、非正規雇用はどうだったのか?
武家奉公人について書かれていたのは、派遣のような1年以下の短期雇用で働いていたそうだ。
具体的には、大名家の門番や傭兵として働いていた。
しかし、給料が少ないことや、すし詰めのような集団生活で逃げ出す人も多かった。人手不足になると、仲介人を通して地方からも雇っていた。だが、待遇の悪さが広まり時間が経つにつれ、人が集まりにくくなっていたようだ。
町人
主に江戸、大阪、京都で働いていた。本書では江戸に焦点を当てている。
まず、武士と同じく、位がある。家持、地借、店借の3つ。
家持は土地を持っている人のこと。地借は土地を借りて、店を建てて商売する人。店借は建物を借りる人を指す。
土地は表通りに対して細長く分割されている。基本的にお店は表通りに面した表店に出す。その奥の裏店にはアパートがある。

家持は地借への土地の貸出料と店借のアパート代金を受け取ることができた。
店借は振売で生計を立てていた。振売とは、市場から新鮮な食材を仕入れて得意先にある仕事である。
他にも、子ども向けの玩具の製作、花や植木、生活道具の修理などをして生計を立てていた。
いわゆる店借は独立自営業者が多かった。
*
町人の中にも武士のような正社員にあたる人たちがいた。大店の奉公人である。
大店は表店に店を出している中でも大きい店舗。店の入口の広さで決まる。一般的な店が10mなのに対して、30-70mある。
大店として有名なのは、三井越後屋、白木屋がある。三井越後屋は現在の三越伊勢丹のルーツに当たる。
これらの店のルーツは江戸になく、上方(京都、近江、伊勢)にある。そのため、江戸には支店を出店していた。それは、江戸幕府を開いた徳川家康は豊臣秀吉の命によって江戸へと領地を移されたからである。
では、奉公人はどんな生活をしていたのか。
まず奉公人となるのは、経理や営業にあたる人だけであり、食事を作ったり、雑用をする人は短期雇用だった。
採用は11〜12歳で、男のみだった。それから、丁稚として5年ほど働く。昼間は働き、夜はそろばんを習う。この間の給金は出ないが、衣食住は用意されている。
とは言っても、生活は寮の集団生活、雑魚寝、ご飯が少ないなどストレスが多いものだった。中には、お使いの最中に買い食いをしたり、お店の物を盗んで食費に充てるものもいた。また、階級が上がらないと娯楽(将棋、囲碁)や読書、おしゃべりも禁止されていた。この生活に耐えられず逃げるものもいた。
この期間をすぎると、若衆として出世し、給金が出た。それからも年功序列と実績を評価され続けた。40歳までに昇進できないものは退店を余儀なくされた。
40歳くらいになると、企業の中でも出世ルートに乗る人と、そうでない人が別れ始めると聞いたことがあります。そういう点から、企業にとって見込みの無い人を切るのは合理的なやり方なのかもしれません。
しかし、ある程度の期間を働いた者には退職金が出た。これを使って、自分でお店を開いたりする者いた。位が高く退店した人は暖簾分けを許された。また、奉公期間は結婚が許されなかったので、所帯を持つ者もいた。
退店を機に第2の人生を歩み始めることができた。
百性
百性とは、「村」に住民登録されている者を指している。
農業だけをしているイメージがあるが、他にも輸送業、土木、漁業、鉱山に携わっていた。
農業
米だけではなく、麦や大豆、野菜なども育てていた。また、衣服を作るための綿や麻も植えていた。
作った作物は年貢や自分で食べるもの以外は売ってお金にした。
年貢は土地の面積、条件によって決められた。年によっては豊作・凶作もあり、収穫前にその年の年貢が決められた。土地の検地は一度しか行われなかったため、農業技術の進歩は加味されなかった。そのため、検地に入らなかった小道や空き地も使って作物を育てた。
江戸中期以降は、年貢を金銭で納めるようになった。このことから農民が余った作物を使って自分で付加価値をつけたり、湯屋、髪結、居酒屋といったサービス業を始めるものもいた。
また、農地作業ができない期間に働く(農間余業)者もいた。しかし、原則として、百性が農地を捨てて商人になることは許されていなかった。あくまでも余力として農業以外に取り組めた。
輸送
戦国時代の道路を引き継いで行われた。宿場町を作り輸送を行っていた。そこでは、馬を飼い、輸送を行う馬士という職業も生まれた。百姓が宿場町を運営しながら輸送を行うことは不可能だからだ。
宿駅を使った輸送にはお金も時間もかかる。というのも、10km-20kmおきに馬を交代させる必要があり、その都度お金を取られる。また、荷物の移動により商品が傷ついたりもする。
そのため、宿駅を使わず個人間の取り決めで安く早く輸送を行うものも現れた。宿駅は幕府の機関であり、問題だった。たびたび裁判が行われたが、減らなかった。現代で言えば、タクシー会社ではなく、Uberで運んでもらうようなものである。
土木・漁業・鉱山
土木は治水事業。洪水によって氾濫した河川の堤防を修理した。誰がどこまで払うのか、やるのか(材料費は誰が払うのか?人件費は誰が払うのか?計画は誰が行うのか?)によって、色々な方式が取られたようだ。
本書において漁業は網漁に絞って書かれている。基本的に網元-網子の支配的関係であった。網元は船や網を持っている人であり、網子は平漁師。漁を行うのは網子であり、分前は網元が決めた(現物支給)。
鉱山業は佐渡で行われた。武士は鉱山の治安活動や上納金の分配をするだけで、採掘や製錬は商人に任された。労働環境は酷く、油煙や粉塵まみれになった。そのため、30歳前後までしか生きられなかった。また、数倍の給金をもらっていたが、酒、性、食に使い潰していた。
書かなかったが、労働者の法律、勤務時間、女性の働き方についても書いておく。
・労働者を守る法律は無かった。あるのは、労働者を罰するものだけだった。それも労働者には不利なものばかりで、主従関係は絶対。雇い主に歯向かうことは許されなかった。歯向かうことは最高刑の丨磔《はりつけ》だった。これは全く無関係の人を殺すことよりも重い刑だった。
・勤務時間による縛りは意外と緩く、大体10〜15時だった。だが、しっかりと勤務記録は残された。
・女性の権利はそこまで蔑ろにされていなかった。結婚しても財産権があったり、妻の両親が夫に滅亡して離婚を促したりもした。2-3ヶ月で離婚することもあったという。娘が親の元へ帰ってきて暮らすことはなんも不思議ではなかったようだ。
最後に、武士にも副業が許されていた。
百性は農間余業で働いていたが、武士も傘張り、提灯張り、版木彫、植木作り、虫の養殖などをしていた。というのも、給料は固定給だっちめ、上下はしないが、冠婚葬祭など突然の出費には耐えられない場面があった。
そういう事情が背景もあって、ベーシックインカムが無くなった明治でも副業をしていた武士は上手く立ち回れたのではないかと言われている。
*
本当に最後に感想を。
この本は江戸時代の職業を現代に当てはめると?という視点でも書かれていて理解しやすかったです。
身分が分かれていて、その上に職業があるので、確かに管理しやすいと言えば管理しやすいのかな〜って思いました。システム化されているので、「あーなれば、こう」みたいなのが分かりやすい構造なのかと。
サラッと流しましたが、治水事業では誰がどこまで払うとかやるとかがキッチリ決められていて、現代の仕事に近いのかな〜と。
図書館の新刊でたまたま目について手に取った本でしたが、江戸時代の仕事を押さえるという点では良書でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
