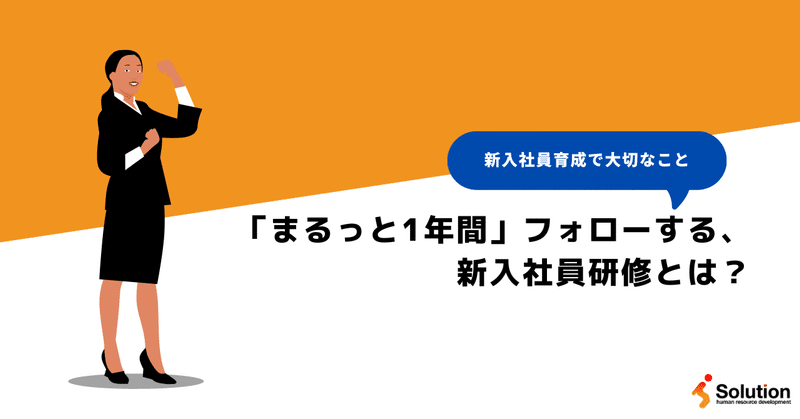
「まるっと1年間」フォローする、新入社員研修とは?
2月がスタートし、新卒採用をされている企業様にとっては、
内定者フォローや、受け入れ準備を進めている時期かと思います。
そんな皆様に、お役立ちできる情報をお届けすべく、
毎週月曜日に「新入社員を成長させるためのおすすめコラム」を
配信させていただきます。
「新入社員を成長させるためのおすすめコラム」4週目です。
本日も目を通していただき、誠にありがとうございます。
先週2月20日の配信では、
「新卒1年目が成長する!「5つの成長ステップ」とは?」
をテーマにお伝えいたしました。
どんな内容だっけ?という方は、こちらからご確認ください。
本日は、そんな5つのステップを提唱する我々が、新入社員の方を成長させるために拘っている「研修プログラム」についてお伝えいたします!
多くの企業様では、新入社員研修期間を、
数日、長くて1 か月ほど実施することが多いかと思いますが、
我々が、クライアント様に実施する
新入社員研修の期間は【まるっと1年間】です。
なぜなら、社会人になって1年目の皆様には、
学生時代には経験してこなかった“壁”がたくさん訪れます。
だからこそ、適切なタイミングを逃すことなく関わることが必要であり、
それが【社会人1年目としての成長】に繋がると考えているためです。
では、どのようなタイミングに、どのような研修を実施しているのか、
ここからはその内容についてお伝えしていきます。
最後に、研修で活用しているワークシートの
プレゼントもありますので、ぜひお読みいただけると幸いです!
弊社では、1年間で合計5回の研修を実施します。
第1回目の研修は【4月】です。
ご想像いただける通り、
学生から社会人に切り替わるタイミングとして、
ここはとても大切な場となります。
「社会人になる」とはどういうことなのか、
「働く」とはどういうことなのか、
「会社が新入社員を迎え入れる」とはどういうことなのか、
一つひとつ丁寧に考え、議論することで
“今自分たちが求められていること”を確認していきます。
現実に向き合うことや、葛藤することに慣れていない方が多いですが、
だからこそ4月のこの時期に、しっかりと基礎をつくっていきます。
第2回目の研修は、入社から3か月が経過した【7月】です。
「7月」に設定している理由は、
8月に長期休みがあることが関係しています。
長期休みには、実家に帰省する方が多く、
家族や友達と様々な話をする機会があります。
うちの職場はこうだ、上司がどうだと話す中で、
良くも悪くも影響を受けやすく、
「本当に今の職場でいいのかな」
「あの子の職場は働きやすそうでいいな」
など、隣の芝が青く見えてしまうこともあるのです。
そのため、長期休みに入る前の「7月」に時間をとり、「入社してから3か月間の振り返り」や、「長期休みに取り組むこと」などを決めていきます。
そうすることで、休み期間でもブレることなく過ごすことができますし、上司も「休み中の課題はどうだった?」と、共通の話題をもって休み明けのコミュニケーションを取ることができます。
第3回目は、入社をして半年となる【10月】です。
半年後には、次の後輩が入ってくるタイミングであり、
「もう後輩が入ってくるのか・・・」と
プレッシャーに感じる新入社員の方もいるでしょう。
「育成されていた側」から「育成する側」になる日も近く、“視座を上げる”必要がある時期です。
この時期は、新入社員の方の間にも“成長の差”が顕著に表れています。
自信をなくしてしまっている方もいれば、仕事の面白さを感じている方など様々な方がいますが、必ず“この半年感”で得たものや成長できたことはあります。
それらを、一度立ち止まって振り返り、「来年には先輩になる」ということも視野にいれつつ、残りの半年間の過ごし方を考えていく場になります。
その際に使用するワークに「GROWシート」というものがあります。
GROWとはコーチングで使用されている目標達成のフレームワークで、目指すべき場所と自分自身の現状、そのギャップを埋めるために必要な行動を
把握することができます。
本日は、特別に「GROWシート」のテンプレートをプレゼントします!
ご興味のある方はこちらからお申込みいただけます。
さて、丸1年間の新入社員研修としては、あと2回、1月と3月に場を設けています。続きは、来週<3月6日>の配信でお伝えできればと思います!
「来週まで待てない・・・!」という方は、簡単な内容が記載してある、弊社のホームぺージをご確認ください。
それでは、本日もお読みいただきありがとうございました!
よろしければ、サポートをお願いします。いただいたサポートはコンテンツ発信の充実に使わせていただきます。
